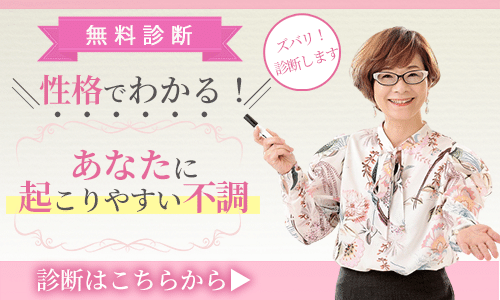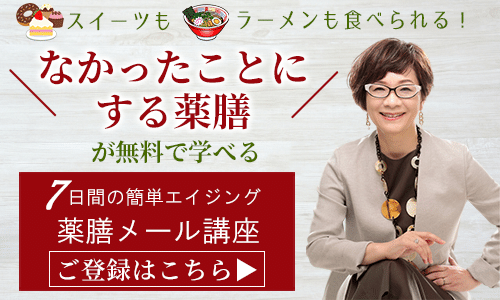秋の一品!れんこんの超簡単ステーキ
れんこんは煮物や辛子れんこん、天ぷらくらいしか思い浮かばない人もいるかもしれません。
あと一品欲しいという時に、3ステップ(洗う・切る・焼く)でできて超美味しい(←自分で言う(笑)でもホント。)れんこんステーキレシピのご紹介です。
組み合わせるもので同じような薬膳の効果のあるものもご紹介しますので、
乾燥が気になるアラフィフ世代、秋の一品にぜひ加えてくださいね。
潤わせるれんこんステーキレシピ
潤わせるれんこんステーキ
材料(4人分/
れんこん10㎝程度(直径5~6㎝)、ロースハム2枚、オリーブオイル大さじ1、青のり適宜、塩少々
作り方/
1. れんこんはよく洗って、皮を剥かずにそのまま1㎝厚さに切る。
2. フライパンにオリーブオイルを熱し、両面をこんがり焼く
3. 空いているフライパンで1枚を四等分に切ったハムを両面焼く。
※ ハムは焦げやすいので早めに皿に移すか、れんこんの上に載せておくと
冷めにくい。軽く塩を振り、更に盛ったら青のりをかけて完成。
二面性のあるれんこんの性質
薬膳では、どんな食材にも性質と効果(効能)があると考えます。
性質とは、それを食べたら体が温められる、冷える、どちらでもないの3つ。さらに細かく分けて5つあって五性と言われます。
れんこんは、生の時と調理をした時では性質が変わる珍しい野菜です。
他にも大根が生と調理時で変わります。この記事の下に大根のことを書いた記事を貼っておきますので、合わせてお読みください。
では、生の時、調理した時のそれぞれを説明して行きます。
生の時の体への影響
生のれんこんは体にこもった熱を冷ます性質を持ちます。
そして五臓の「肺」を潤わせ、のどの乾燥、渇きを鎮める働きを持つとされる秋の薬膳食材の代表ですね。
れんこんの絞り汁は鼻血や不正出血に効果があると言われています。
また、血めぐり効果もあるとされますし、胃腸機能を保つ効果も言われています。
生でれんこんは食べない!と思われるかもしれませんが、シャキシャキ感を残しさっと熱湯にくぐらせる(30秒くらい)のは生と考えてください。
お正月に酢れんこんを食べるのもお正月のご馳走で胃が疲れるのを緩和させるなかったことにする薬膳の一つです。
加熱した時の体への影響
加熱により冷やす性質が緩和されます。冷やしも温めもしない平性と考えて良いでしょう。
消化力をアップさせる効果が高まり五臓(肝心脾肺腎)全てを整える効果があるのは、切った時に糸を引くような水溶性たんぱく質のムチンの効果です。
れんこんはあく抜きして使いたくなりますが、水溶性の栄養素が水に溶けだしてしまうので、水にさらさずに使うこともポイントです。
(色を白く仕上げたい時は、あく抜きのため一度水にさらすと良いですが、焼いてしまうので色を気にして水にさらす必要はないですね。)
一緒に潤わせる食材を使う
秋は空気が乾燥して、アラフィフ世代は気をつけたい季節の始まりです。
夏に大量の汗をかいたままだったり、秋晴れの日に屋外で太陽を浴びたりすると知らずに体の潤い不足になっています。
夏が大好きで、夏の間スポーツなどで大汗をかいた後の秋、急に体調が崩れたり気持ちが落ち込んでしまう人がいます。
五臓の「肺」は乾燥が苦手で、夏に失った潤いが補給されないままに乾燥の季節になったことが原因ですね。
「肺」の不調は悲しい・憂鬱という感情と繋がります。
急に悲しい感情や、落ち込むのを感じたら「肺」の潤い不足だと思ってください。
しっかり潤わせる食材でリカバリーしましょう。
れんこんと一緒に使ったハムは豚肉に変えても良いです。
豚肉は潤わせる肉の代表!
れんこん単独より、豚肉を合わせてさらに潤いを意識したメニューとなります。
豚肉の他には、帆立やイカ、タコなどの魚介類のソテーを添えても豚肉同様潤いアップになります。
乾燥からの不調は潤わせる食材で!
季節は確実に陽から陰へ移行しています。
気温の下がり方はまだそれほどでもありませんが、空気の乾燥がはじまっている初秋。
暑さが残るので真夏同様の暮らしをしがちですが、乾燥対策は食べ物で内側から。化粧品で外側から。
アラフィフ以上はしっかりケアして過ごしましょう!
【関連記事】
性格からわかる、起こりやすい不調とおすすめ食材を無料でお知らせします。
下のバナーからお答えください。
なかったことにする薬膳が学べる7日間の無料メール講座を配信中です。下のバナーをクリックしてお申込みください。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?