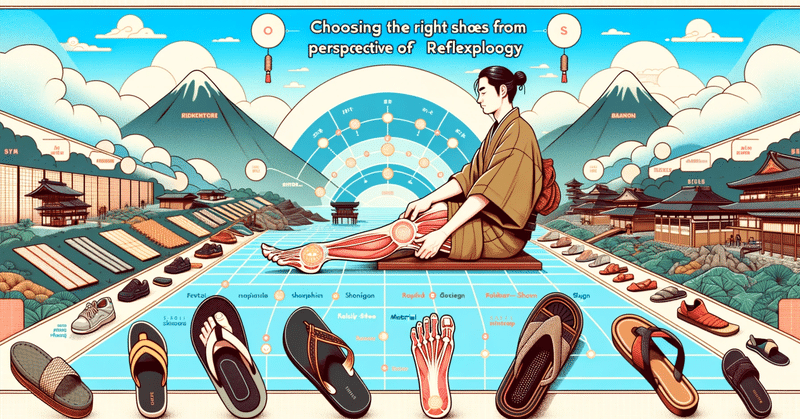
『上手な靴の選び方』
こんにちは、皆さん!
4日間にかけて、履き物と足の関係について投稿してきました。
いくら靴が健康に悪いといっても二十一世紀に生きる私たちは裸足で生活する訳にはいきません。そのため靴で痛めつけられた足をもむことは欠かせませんが、血行を助ける靴を選ぶことも大切なことです。
今日は足心反応療法の視点から見た「上手な靴の選び方」についてお話ししたいと思います。
足心反応療法って何?
まず、足心反応療法について簡単に説明しましょう。足心反応療法は、足の裏にある反射区を刺激することで、体全体の健康を促進する方法です。足の裏には全身の臓器や器官に対応する反射区がたくさんあります。この療法では、足裏をマッサージすることで、血行を良くし、自然治癒力を高めることができます。
昔の人たちの靴は?
その昔、ヨーロッパの靴職人は一人一人の足の木型を作り、それに合わせて革をはり、少しでも足の健康を守る努力をしていました。
日本では、上手な靴職人こそいませんでしたが、わらじという素晴しいはきものがありました。足底に地面に知覚を感じられ、それでいてワラの感触が直接の刺激を和らげてくれる。 足首も自由に動かせ、つま先も完全に動く理想的なジャパニーズシューズです
1. 靴選びのポイント わらじ
靴を選ぶときは、このわらじをおもいうかべて欲しいと思います。
つまり、足をしめつけず、指先の一本一本が伸ばせ、動かせる靴です。サイズを合わせるだけではなく幅、つま先、足の甲、土ふまず、かかとの各部分を入念にチェックしてください。
2. 靴選びのポイント 形
足の形は人それぞれ違います。
扁平足やハイアーチなど、自分の足の特徴を理解して、それに合った靴を選びましょう。例えば、私はハイアーチなので、アーチをサポートしてくれるインソールが入った靴を選ぶようにしています。これにより、長時間歩いても足が疲れにくくなりました。
3. 靴選びのポイント 素材とデザイン
靴の素材とデザインも見逃せません。
通気性の良い素材を選ぶことで、足の蒸れを防ぎ、快適に過ごせます。また、足心反応療法の視点から見ると、足の裏全体に均等に圧力がかかるデザインの靴が理想的です。私も、デザインにこだわりつつも健康を意識した靴を選ぶようにしています。
4. 靴選びのポイント 横幅
また、23cmとか24cmとか足の縦のサイズは知っていても、横幅の寸法には意外と無頓着です。C、D、E、EEと表示されていますが、これは足囲といって、指のつけ根部分の足まわりを計ったものです。足囲がきついとここでしめつかられ指先まで血が流れず疲労の大きな原因となります。
5. 靴選びのポイントその3 夕方
夕方の足がむくんでいるときをみはからって靴選びをしましょう。
必ず両足で履き、実際に歩いてみて、足がむくんでいても楽にはいていられる靴を選んで決めることです。足を生かす靴を選び、なるべく第二の心臓である足裏の機能をいかすようにしてこそ健康な生活がおくれるのです。
まとめ
靴選びは足の健康に直結する大切なポイントです。
足心反応療法の視点からも、自分に合った靴を選ぶことは、体全体の健康を守ることにつながります。皆さんも、今日から少しずつ靴選びに気を付けて、快適で健康的な毎日を過ごしてみませんか?では、また次回の記事でお会いしましょう!
ー 筆者紹介 ー
こんにちは!
私は宮崎県で足心反応療法をしております神宮司裕と申します。
足心反応療法とは、足の裏、足の甲、足首、ふくらはぎにある反射区を刺激し、体全体の健康を促進する自然療法です。この反射区は身体の諸器官と繋がっています。
私はこの治療を通して、多くの方の身体の不具合を改善してきました。
「頭痛で苦しんだ過去」
30年以上前、私も頭痛で苦しんだ時期がありました。突然の痛みに耐えきれず、病院でCTスキャン・MRIを受けましたが、結局「原因不明」、診断は「片頭痛」でした。処方されたボルタレンという痛み止めを手にして思いました。
「私は一生、この薬と付き合わなければならないのか…?」
しかし、足心反応療法に出会ってからはスッキリ痛みが取れ、 身体も軽くなり、目の前も明るくなったように感じます。
私の所にいらっしゃる方たちはこんな悩みも抱えています。
天気の悪い日は特にあたまが痛い
何も覚えがないのに突然腰が、、、
最近、肩が痛くて腕が上がらない
何だか食欲がないぁ、胃が悪いのかなぁ
頭、腰、肩、胃などが痛いと思った時、実はそこが原因ではないかも?しっかりと原因を突き止めないと改善したとは限りません。
もし、宮崎県宮崎市までお越しいただける方は、 お気軽にご相談ください。 ただ、遠方の方もいらっしゃるとは思います。 そういった方のために、オンラインで自宅で実践できるガイドブックを作成しました。
〈ガイドの内容〉
ガイドブックは、「片頭痛の原因となる仕組み」を基礎編として「具体的な実践方法」「知っておきたい知識」で構成されています。
具体的には以下の通りです。
基礎知識として片頭痛の発生原因の特定方法
ストレス軽減と効果的なリラクゼーション技術
頭の血流の大切さと改善方法
女性特有のホルモンバランスと片頭痛の関係
日常生活で片頭痛の予防法
根本的な解決策を解説しつつ、突然の痛みに対する対処もご提供しています。

※このサイトから購入して頂いた方に限り、特典を10個差し上げます。
ぜひ、この機会に購入を検討されてみて下さい。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
