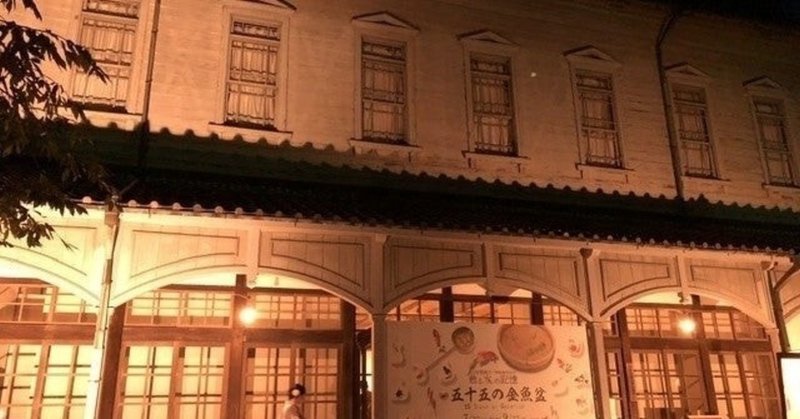
超人たちの物語。『英語達人列伝』斎藤兆史
斎藤先生は東大の助教授(執筆当時)。日本の英学の歴史を調べていたとき、かつて日本にいながら英米人も舌を巻くほどの英語を身につけ、西洋にかぶれことなく、日本と外国の橋渡し的な役割を演じた達人たちがいることを知ったとのこと。
新渡戸稲造、岡倉天心、斉藤秀三郎、鈴木大拙、幣原喜重郎、野口英世、斉藤博、岩崎民平、白州次郎、西脇順三郎。
彼らの活躍ぶりをみれば、日本人は基本的に英語が苦手だという通念は信じられなくなると著者はいう。そして、「従来の文法・訳文中心の英語では役に立たないから、今後はコミュニケーション重視にしよう……」などといった、失敗から学ぶ英語教育ではなく、成功から学ぶ英語教育を考えよう、外国人の教育法の輸入ではなく、日本人ならではの学習方法を考えようとうったえる。
斎藤先生の言うことは確かにもっともだと思うけれど、本書で語られる10人の英語の達人たちは、一般人とはかけ離れた人たちばかり。おかげで、英語への興味のあるなしに関わらず、普通の伝記読みものとして、本書はとてもおもしろかった。
例えば、紙幣に肖像がのることで話題になった野口英世。
TVでは、彼が手の障害を乗り超えて医学を志し、アフリカの人々を救うために赴いた現地で黄熱病かかって殉職した物語ばかり放送していた。でも、実際の野口は執念ともいえるほどの出世欲に駆りたてられた人物で、英語の勉強は立身出世のための猛烈な努力の一環にすぎないらしい。でも、昔の彼の伝記には、彼の「礼節」無視の部分がきれいに取り除かれているそうだ。そして、出世欲の一環である英語への猛烈な野口の努力は半端なく、奇行に近い。
圧倒させられるような英語への偏愛をみせる人物、尋常でない英語の読書量を誇る人物たち。もちろん良識の範囲で尊敬できそうな人たちも含めて、とにかく10人の達人たちはすごい。
江戸末期、かかりつけの医者から英語や科学の初歩を教わり、東京外国語入学後は、眼病を誘発するまで英語の著書を多読した新渡戸稲造。天才が努力するとこうまでなれる、という見本のような人。
美術思想家として名高い岡倉天心は貿易商の子供として生まれ、幼少から英語教育を受け、9才で英米人と同じ程度の会話力を身につけていた。英語を覚えれば漢字を忘れる。ある漢字が読めなかったことをきっかけに、自分を恥じた岡倉は国語国文の本格的な勉強を始めた。彼の場合は妻に卒論を焼き捨てられ(女性問題でやきもちを焼かれたからとか)、やむを得ず残り2週間で書きあげた英語論文で、岡倉のその後の人生と日本美術史が変わった話など、おもしろい逸話に事欠かない。
斉藤秀三郎は英国人役者たちに、「おまえらの英語はなっちゃいない!」とまでいえた人。わずか5才で仙台藩の英語学校に入学し、大学時代の3年間で図書館の英語著書は全部読破した英語の達人は、結局一生に一度も海外に出かけたことがなかった。吉原での放蕩ぶりが目にあまって大学を退学させられるが、英語学校を開いて大繁盛し、つみあげると3Mにもなるほどの膨大な著書を執筆した。しかもその内容は、コロンビア大学の教授が感激したほどの内容だとか。ただし、彼に協調性など全くない。業績に注目した東京帝国大学からも声がかかったが、その他の学校と同じように喧嘩して辞めている……などなど。
こんな達人たちの英語経歴と並外れた逸話の数々は、著者の文章のうまさも含めて、一読の価値あり。
同じ著者の本:『英語襲来と日本人』斎藤兆史
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
