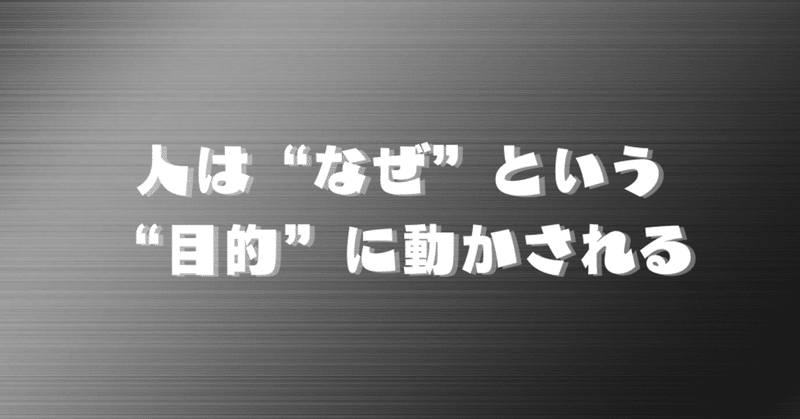
人は“なぜ”という“目的”に動かされる
はじめに(いつも書いてること)
このnoteでは、「仕事でも私生活でも心をラクにする(ワークライフハック)」をテーマに文章を書いています。
※「ラクする」というのは、「心身に苦痛などがなく快く安らかに過ごす」という意味で使っている言葉であり、シンプルに「サボる」という意味ではありません。
今回の内容
自身のライフログ(Evernote)で『目的』『対話』という言葉を検索して、過去から遡ってノートを見ていたら、『目的の重要性』についてnoteで取り上げたいことを見つけました。
約7年前のメルマガです。
私たちが意識的に取る行動には、自分自身への質問によって引き出されているものが多くあります。
「明日の商談は何時からだったか?」
と、出かける時間を決めたり、
「何を準備すればうまくいくのか?」
と、資料を作成したりしているのです。
準備について自分に質問するから、準備という行動を取ります。
その質問がなければ、準備しないかもしれません。
つまり、どのような行動をするかは、自分自身に対する質問の内容次第なのです。
では、仕事においてはどうでしょうか。
自分自身への質問に最も大きな影響を与えているのは、その仕事をする「目的」です。
たとえば、「世界一安全な車をつくること」を目的に仕事をしている人がいるとします。
その人は、さまざまな場面で「この方法で世界一安全な車になるだろうか?」「そのためには、自分はどのような能力を高めれば良いだろうか?」など、「目的」に向かうための質問を自分自身に投げかけるでしょう。
一方、仕事の「目的」が不明確な人は、「目的」に向かうための質問を自分に投げかけることはありません。
指示に従ってうまく仕事を進めることはできるかもしれませんが、目的に向かって「主体的に動く」ようにはならないでしょう。
その結果、両者の仕事の仕方や言動、会議への参加姿勢、勤務態度などに違いが生じ、最終的には仕事の「成果」に影響を与えてしまいます。
TEDのプレゼンテーションで人気が出たサイモン・シネックは、「優れたリーダーや優れた企業に共通しているのは“なぜ”、すなわち“目的”が明確であることだと分かりました。人は“なぜ”という“目的”に動かされるのです」と話しています。(※1)
また、コロンビア大学ビジネススクール・モチベーションサイエンスセンターのハイディ・グラント・ハルバーソン副所長は、著書の中で、「“なぜ”という視点で捉えると、日々の小さな行動にも、意義を感じやすくなります。理由が明確になることで、小さな行動が、大きな行動を達成するための一歩に変わるのです」と述べており、人は「“なぜ”を考えるとやる気が出る」と語っています。(※2)
仕事の「目的」が明確であることは、自分自身への「質問」を生み、それによって「行動」を引き出し、やがて「成果」につながっていくと考えられるのです。
しかし、「目的」が明確でさえあれば成果につながるかというと、そうではありません。
一人ひとりが仕事をする「目的」は、その人の能力や経験、やりたいことなどによって異なります。
しかし、その「目的」は、所属する組織が目指す方向性や理念に合致していることが望ましいのではないでしょうか。
一人ひとりの仕事の「目的」と、組織の方向性や理念がどのくらい合致しているかを正確に測ることは難しいですが、私が担当している複数の組織に対して、コーチ・エィとコーチング研究所が調査したところ、組織の方向性や理念を「理解」していても、そこに向けて「行動」している、と答える人の割合が50%を超える組織はほとんどありませんでした。
こうした結果から考えられるのは、組織の方向性や理念に沿った「目的」を設定し、それに向けて自分に「質問」している人は 少ないのではないか、ということです。
そこで、みなさんから次のような質問を用いて、メンバーに問いかけてみてはいかがでしょうか。
「この仕事を通じて、あなたは何を実現しようとしているのですか?」
答えにくい質問かもしれませんが、これは極めて重要な問いです。
この質問から明らかにしたいことは2つあります。
1) 仕事の「目的」が明確かどうか。
2) その「目的」が、組織の方向性や理念に合致しているかどうか。
これらに明快に答えられるメンバーが多い組織は、組織自体が理想とする状態へと成長していけるはずです。
組織の「目的」を指し示すことができる企業理念はCSRのためだけでなく、「業績を向上させるため」でもあるのです。
・自分自身が責任を持つ組織の「目的」を明確にする。
・そして、メンバーの仕事の「目的」が、組織の「目的」に合致しているかどうかを知る。
対話がきっかけとなり、「目的」に向けた問いが一人ひとりの中に生まれれば主体的な行動につながります。
組織の中で対話を起こす。
そうした活動こそが、組織の成長を加速させられるはずなのです。
【参考資料】
※1 サイモン シネック「優れたリーダーはどうやって行動を促すか」から要約。Japanese translation by Natsuhiko Mizutani,reviewed by Yasushi Aoki. More talks in Japanese
※2 『やってのける ~意志力を使わずに自分を動かす~』ハイディ・グラント・ハルバーソン (著)、児島 修 (翻訳)
「仕事の『目的』を明確にする」 粟津恭一郎
このメルマガを受け取ってEvernoteに転送したのは、2014年6月12日午前12時46分のようです。
僕はこのメルマガを受け取って、ライフログとして残しておくことを決めたんですけど、この時の僕は、前職で2年目を迎えて2ヶ月が過ぎたくらいのタイミングでした。
1年間の施工管理職を経て、建築構造設計職として本配属になり、目まぐるしい毎日を過ごしていた頃です。
当時の僕は、「働く目的は?」とか「この会社にいる意味と自分の働く目的を結びつけてる?」という問いの意義を理解して、自分では考えていましたけど、それらの要素を仕事にしている未来(それが今)があるなんて、思ってもいませんでした。
不思議です、過去に残していたライフログを今読んで、「やっぱこれだよな」と今の自分が頷く感じ。
◆目的があるから決意できる。
◆目的があるから熱中できる。
◆目的があるから元気になる。
※元気とは、自身の元から沸き起こる(溢れ出てくる)気を発揮している状態。
どんな小さな言動にも、その背景には何かしらの目的があるはずなのに、「それってなんでやってるの?」「それをやる目的は?」と問われると、「・・・」と答えられなかったりする。
上記の引用部分(「人は“なぜ”という“目的”に動かされるのです」「“なぜ”を考えるとやる気が出る」)にもあるように、「なぜやるのか?」を考えるからこそ、自分が主体的になって行動を起こせるのですが、「なぜやるのか?」を考えないで行動を起こしているということは、誰かからやらされている状態を脱することができません。
自分で選んだ会社なのに、自分で選んだ仕事なのに、働いていると、気づいたら「やらされている」になっている人がいる。
そういう人に「なんでこの会社でその仕事をやってるんですか?」と聞くと、「なんででしょうね」とか「働き始めてなかなか辞められなくて」という答えが返ってくる。・・・非常に悲しい状態です。
理念やビジョンを理解して共感して入社を決める人は多いのは、採用時に理念やビジョンと向き合わせて、理解と共感を求めているから・・・という背景もあるでしょう。
候補者自らが主体的に理念やビジョンへ共感することもありますが、理念やビジョンを理解して共感しているとを感じられなければ内定を出しにくいという理由もあるので、候補者は半ば強引に「理解している、共感している」という言葉を出すしかない状況になっている可能性もあるわけです。・・・これは、採用時に候補者と対峙する人が向き合わないといけない課題だと思います。
自分の目的は自分で決めるしかないのに、目的を考えずになんとなく組織に所属して、なんとなく仕事をしている人も多い。
組織の方向性や理念を「理解」していても、そこに向けて「行動」している、と答える人の割合が50%を超える組織はほとんどありませんでした。
こうした結果から考えられるのは、組織の方向性や理念に沿った「目的」を設定し、それに向けて自分に「質問」している人は 少ないのではないか、ということです。
入社時には入社理由を考えて、「入社理由は?」と問うことがあっても、入社してからは『ここで働いている状態』を前提にマネジメントが進んでいったり、研修が実施されたりする。・・・僕がこれに違和感を感じました。
ライフステージやライフロールが変化していく中で、仕事観や人生観が変わっていくはずで、入社理由はあったとしても、それがイコール『働き続ける理由』『ここで頑張り続ける理由』にはならないからです。
なので、僕は面談のたびに「なんでここで頑張ってるの?」という問いを立ててますし、新卒向けに実施してる入社後3年間の研修では、研修のたびにこの問いと向き合う機会をつくっています。

「なんでここで頑張るんだ?」という問いに対する回答を自分で考えられるようになることこそ、ビジネスパーソンとしての自立力と自律力が高い状態であるといえます。
「個人の成長と企業の成長をすり合わせていくことが大切だ」と言っている新・社会人基礎力のスライドが経済産業省から出ていますが(以下)、これこそ、「個人の目的を明確にして組織の目的とすり合わせていく」という部分に通ずる話です。・・・働く全ての人が考えるべきこと。

目的の大切さはこれまでも書いてきましたが、上記の引用部分の切り口は非常にわかりやすかったので、noteで紹介しました。
感謝
今回も、読んでいただきありがとうございました。
他のnoteも読んでいただけると嬉しいです。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
