
成果の基礎にあるのはチームのコミュニケーションだ 〜リモコミ開発よもやま話〜
「わたし・みらい・創造センター(企業教育総合研究所)」では、リモートスタッフのパフォーマンスが向上するeラーニングプログラム「リモート・コミュニケーション」をリリースしました。
今回は「リモコミ」が生まれた背景について、開発担当でもある研究員 頼木(よりき)と副センター長 加井(かい)の対談をお届けします。
リモートになった瞬間、情報の制約が生まれて
かい コロナ渦になって2年。私たちが今研究しているリモート・コミュニケーションについてビデオラーニングで考え方をリリースしましたが、どんなきっかけがあって開発スタートしたんでしたっけ?
よりき コロナ渦によってリモートによる働き方の多様化が進みました。同じ部署の上司と部下、気心知れた仲間でやり取りしていたのが、リモートになった瞬間、情報の制約が生まれたわけです。
これによりリモートがストレスになったり、業務効率が下がったりする人が増えた。そんなリモートの悩みを少しでも解消するためにeラーニングコンテンツを開発しようと思ったのがきっかけです。
うちの社内を想像しながら作ってました
かい ちなみになんですけど、ウチの社内でもリモートのストレスって感じてましたか?
よりき そうですね、ウチの社内を想像しながら作ってましたね。お客さんの状況ってリアルに見ることができないので、自分たちにも共通する点から考えていきました。
私たちの中で起こっていることは他の組織の中でも起こっているんじゃないかと思って。そこをヒントに開発しましたね。
かい 具体的にどんな課題が浮き彫りになっていると感じましたか?
よりき やっぱり情報の齟齬ですかね。情報って言葉以外の要素があってはじめて判断ができるんだけど、リモートってそこが測りづらくて。伝えたつもりが、じつはなかなか伝わってない。
リモートではテキストコミュニケーションの比重が大きくならざるをえません。自分でもやってみて感じたのは、文字でコミュニケーション取る限界と
それによる弊害。
だからできるだけリアルはリアルで、文字は文字でと使い分ける必要があるなとに思ってます。その点の課題意識は強かったですね。
現場でリアルに起こってる課題って何なんだろうか
かい コンテンツを制作するとき苦労したこと、困ったことはありましたか?
よりき リモートワークが半ば強引に始まったことで、現場でリアルに起こってる課題って何なんだろうか。まずはそこを徹底的に追求しなくてはいけません。リアルな声を聞いたり、資料や文献を集めたりといった情報収集が一番大変でした。
わたしたちは良かれと思って作ってるんだけど、どうしても主観的になりがちです。第三者からの「これちょっとわかりづらい」ってフィードバックでわかることもあるし。
自分たちが「いい」と思うだけじゃなく、現場の人が活用できる、実践できるものを作りたい思いがあって、そこどうやって入れていくかが一番難易度が高かったですね。
リモートで重要な3つのこと

かい そんな課題もありながら、「リモート・コミュニケーション」のチャプターが5つできあがりました。
よりき 5つのチャプターにはテーマが3つあります。リモートをするときに重要なのは何か。私が考えるものは3つあって、
一つは、チームの仕事環境を整えること。
二つ目は、メンバー間で情報共有の仕組みを持つこと。
三つ目は、メンバーの互いの知恵を引き出す場を作ること。
そのコンセプトをベースに、より具体的なテーマに落としこんでいったんですね。
縦割りで与えられた役割をこなすだけではダメ
かい 今回の開発を見ていて、頼木さんのこだわりというか、ここは譲れないみたいなものをちょっと垣間見たと言うか。開発者魂みたいなものを感じました。
よりき 作るにしてもただリモートの状況をイメージするだけでは難しかったから、いろんなことを考えました。市場にある情報、世の中で発信されているものから徹底的に情報を集めて。
私自身、職場はメンバー同士の信頼関係がなければ成り立たないって言う、モットーがあるので、そこは外せなかったですね。
たとえば心理的安全性をどうやって作っていくかっていう部分。Googleが自社の数百のチームを分析して、どんなチームがより生産性の高い働き方をしてるかというレポートを出しています。
これも参考にしながら考えたのは、メンバーが縦割りで与えられた自分の役割をこなすだけではダメだということ。
それぞれがチームとして成果を上げるためにどうするかを考え、個人ができること実践する必要がある。組織って団体スポーツと同じと思っているので、そういった考え方で中身を詰めていきました。
情報占有から情報共有へ
かい チャプター3、情報共有のパート。あれもなかなかマニアックというか、大事な部分ですよね
よりき あの部分は、じつはもっと深めたかったんですけど、世の中に出ているデータや事例がまだ少なくて。透明性を担保するための考え方はまだまだ深められるテーマです。引き続き研究テーマとして深めていきたいと思っています。
キーコンセプトは「属人的な情報占有からオープンな情報共有へ」。
情報占有とは情報を独り占めすること。これをやめてメンバーが簡単に情報にアクセスできる状態をいかにして作るのか。これからも突き詰めていきたい内容です。
かい バージョン2みたいなものが出てくるのが楽しみですね。
成果の基礎にあるのはチームのコミュニケーション
かい 「リモコミ」はどういう組織の方々に取り入れてもらったら一番いいですか?
よりき 今までコミュニケーションがうまくいってるつもりだったんだけど
、じつはうまくいってなかった。本当にお互いのことを理解し合えていなかったり共有できていなかったりに気づいてしまった、という組織の方ですね。
部下の気持ちがわからないと言ってる上司や、上司の気持ちがわからないという部下がいる場合には、リモートコミュニケーションの特徴を理解してそれを少しでも良いから実践してみようとする。
上司であろうが部下であろうが関係がなくて、メンバーがお互いに意見や
アイディアを出し合えるような、そういうチーム作りに使ってほしいな
と思ってます。
当たり前といわれることこそ、案外できていないものなので。コロナ禍をきっかけにいま一度、組織のコミュニケーションをチェックしていただければと思います。
成果の基礎にあるのは、いつも「チームのコミュニケーション」です。
【リモコミ資料DLできます】
「リモート・コミュニケーション」に少しでも興味を持たれた方は、下記のリンクより資料をダウンロードしてください。
↓ ↓ ↓
【わたみそ通信配信中】
「わたし・みらい・創造センター(企業教育総合研究所)」では、メルマガ「わたみそ通信」を配信しています。人材、組織開発に関する情報やイベント情報をお届けするものです。ぜひご登録ください。
この記事を書いた人
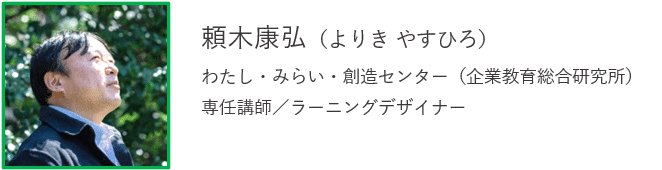

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?

