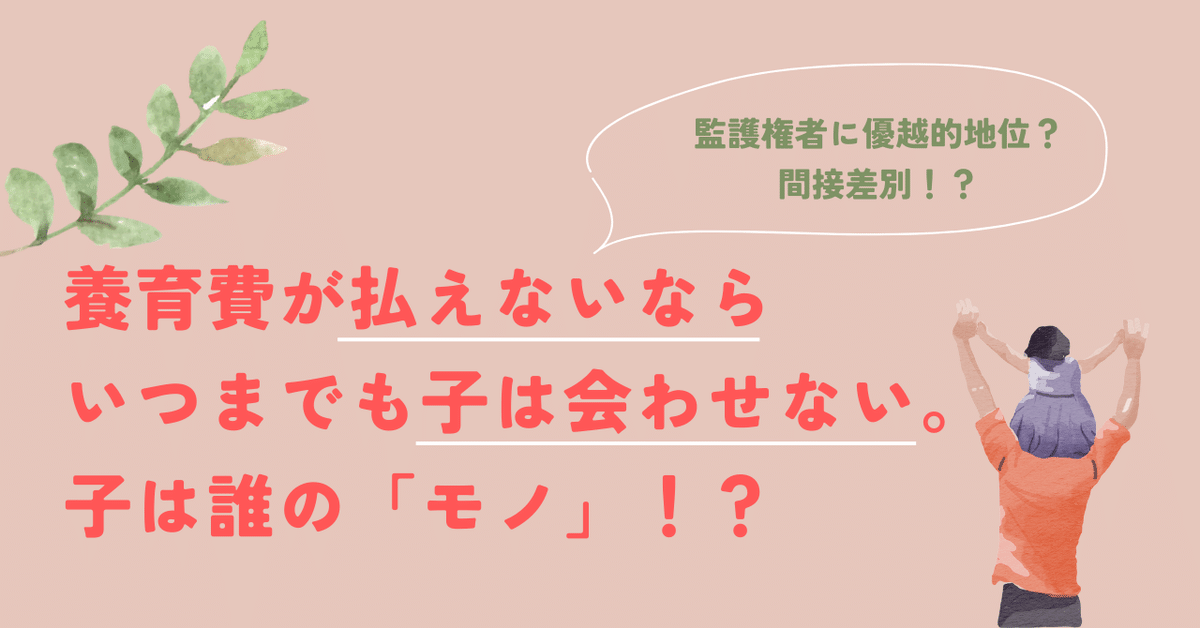
養育費を払えない場合、「子は」親に会えない?子は、誰の「モノ」?
親の利益、子の利益の区別
親の請求権と子の請求権を分ける必要があります。なぜ弁護士は、養育費から成功報酬を徴収するのか、それは養育費が「親の利益」だからです。監護権の分属、分掌が行われた際に、民法766条において「子の監護についての必要な事項として」を定められてきました。
民法第766条(2011年改正)適用の場合
1,父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者その他監護について必要な事項は、その協議で定める。協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、これを定める。
2,子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子の監護をすべき者を変更し、その他監護について相当な処分を命ずることができる。
3,前二項の規定によっては、監護の範囲外では、父母の権利義務に変更を生じない。
これは法改正されても、裁判所で変更されない限り有効。
1,法の不遡及(ふそきゅう)の原則
法令は施行と同時にその効力を生じますが、原則として将来に向かって適用され、法令施行前の出来事には効力が及びません。人がある行為を行った後に、その後の法令によって予期したものとは異なる結果となるのでは、法律関係を混乱させ社会生活が不安定になるからです。
2,既判力(きはんりょく)
裁判で確定した判決には「既判力」というものがあり、その判決内容は同じ当事者間で後の訴訟において争うことができなくなります。これは、判決が確定した時点でその効力が固定されることを意味します。
法改正の影響
過去の行為や事件に対する影響:
通常、法改正は将来に向けて適用されるため、過去の行為や事件には適用されません。このため、確定した判決に対しても通常は影響を及ぼしません。例えば、法改正後に新たに同じ行為が違法とされても、過去にその行為が合法であった場合、その当時の判決の効力は変わりません。
特別法による遡及適用:
ただし、特定の法改正が遡及的に適用されることが法律に明記されている場合や、特別法が制定されて過去の行為にも適用されることが定められている場合は、過去の判決に影響を与える可能性があります。このような場合、具体的な法改正の内容とその適用範囲によります
親権喪失した親の親権復活は特別法により可能
改正民法第819条
1,父母が協議上の離婚をした場合には、その協議で父母の一方をその子の親権者と定めなければならない。
2,父母が協議しても親権者の指定をすることができないときは、家庭裁判所がこれを定める。
3,前二項の規定により親権者と定められた父又は母が死亡し、又は親権を行うことができない場合において、その子が未成年であるときは、家庭裁判所は、子の親族その他の利害関係人の請求により、子の利益のために、他の一方の父又は母を親権者と定めることができる。
4,第1項又は第2項の規定により親権者と定められなかった父又は母は、その後の状況の変化により子の利益に適うと認められる場合には、家庭裁判所に対し親権者の変更を請求することができる。
5,家庭裁判所は、前項の請求を認める場合には、親権者の変更を命じることができる。
※ 2024年の改正民法では、改正民法第819条4条及び5条において、親権を失った親が状況の変化に応じて親権を回復する手続きが明確に規定されています。
民法第766条(2024年改正)適用の場合
① 父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者又は子の監護の分掌、父又は母と子との交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。
② 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、同項の事項を定める
「子の監護に要する費用の分担」とは「監護権者が負担すべき費用の分担」ですから、監護権を有しないものに履行義務はなく、監護権の分属、分掌により監護権が認められた時に履行義務が発生するものと解釈しています(扶養義務は子の請求権)。
監護の分掌については、子を監護を担当する期間を父と母で分担したり、監護に関する事項の一部(例えば教育に関する事項)を切り取ってそれを父母の一方に委ねたりといった決め方が考えられます。あくまでも身上監護権に属する事項で、財産管理、法定代理権の行使は親権に属します。(要綱案の取りまとめに向けた議論のための補足説明資料より)
「父母の協議による監護の費用を含む監護について必要な事項」、「子の監護に要する費用の分担」と「面会交流の関係」
受働債権とは
「子の監護に要する費用の分担」を受働債権として相殺することが原則として禁止されています(民法510条)。子の監護に要する費用の分担の法的手続において,親が子のために行うというところは面会交流調停の目的と共通しているものの,法律上は直接的に関係性が生じない別の事情であって,制度の根拠も,その方法,手続きも,異なる全く別のものです。
利益相反行為とは
親権を行う父又は母とその子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。
2 親権を行う者が数人の子に対して親権を行う場合において、その一人と他の子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その一方のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。
その行為が、一方の当事者にとっては利益となるものの他方の当事者にとっては不利益となる行為となることは禁止されています(民法108条1項)。
第826条の趣旨は親権の濫用から子を守ることです。親と未成年の子の間で利益相反が生じる可能性があり、監護権親が内心でどう思っているかという動機・意図を考慮すべきではないと考えているためです。
形式的判断説(判例)
利益相反行為に該当するかどうかは、親権者が子を代理してした行為自体を外形的・客観的に考察して判定すべきであって、親権者の動機・意図をもって判定すべきでない(最判昭和42年4月18日民集21巻3号671頁)
実質的判断説
ある行為が一方において親権者に利益をもたらし、他方において未成年者の子に不利益をもたらす場合には、それが行為の外形から認識されるか否かを問わず、利益相反行為となる。
少し話が外れますが,離婚に伴う単独親権者の決定は、単独に親権者となる親の「単独利益」を認めることであり「子の利益」の観点からすれば「親の利益」が「子の利益」を害する「利益相反」の関係となるなどの議論もあります。
子の監護に要する費用の分担や両親双方に生じている債権債務が、どこまで面会交流調停に影響を受けるのか。これらを面会交流調停の場で弁明の機会が付与されること,また,その求めは違います。両親が,それぞれに利益を求めたとしても,面会交流調停という協議の場が,お互いが求める様々な事情のすべてを,一度に解決させうる場ではありません。子のために必要な事項を個別に解決していくことが家族法,家事事件手続法,それら制度として手続きが分かれているという事です。面会交流調停という協議の場で多くの事を同時に解決することが可能な制度であるとすれば,家庭裁判所の家事事件解決において面会交流調停の手続の1つでよくなり不合理です。そのうえ面会交流調停の場で親の利益に関して協議和解を求めることは,利益相反を思料することから,子の監護に要する費用の分担が支払えないことで,信頼関係が再構築出来ないという主張は,一様に認められません。
そして債権者として親権者、監護権者が金銭的要求を求めることは,面会交流調停で行う和解の「交換条件」に交渉しようと目論むことになり,利益相反であり一切出来ません。ましてや未成年者の人身を担保,留保したうえで交渉することは,子らを拘束していることに相当し,違法行為を助長するものです。
令和6年4月2日第213回 衆議院 法務委員会で法務省・民事局長・竹内努氏は「離婚後の父母双方が親権者である場合には,親子交流の機会を通じて,別居親が子の様子を適切に把握する事が,円滑で適切な親権行使のために有益である事もひとつの視点として,考慮される事になると考えられますが,いずれにしましても,適切な親子交流のあり方は,親権行使のあり方とは別に,子の利益の観点から,個別具体的な事情の下で検討されるべきものと考えられます。」と大口議員の質疑で回答しています。
離婚中は共同親権でありながら離婚したという理由で一方親の親権を喪失させる強制的な制度は法改正されますが,「親権行使のあり方とは別に」とありますとおり,現行法上も,親子交流が「親の利益の観点から検討されるべきもの」ではありません。面会交流調停で,親の利益に沿う実務運用があれば,親権者、監護権者の親権濫用や利益相反を裁判所が助長することにもなりかねないということですから、まずもってあり得ないのです。
非監護権者には監護権は認められていない。
判例1
「被監護親の子に対する面会交流は,基本的には,子の健全育成に有益なものということが出来る。(大阪高決平成18年2月3日家月58巻11号47頁)」とあるように,親子交流(面会交流)が子の健全育成に有益と示されているが,親の権利性や利益には触れていない。
判例2
「監護に関する処分の一環(平成8年4月30日横浜家審:家月49巻3号75頁)。」
判例3
「子の監護の一内容であるということができる(平成12年5月1日最高裁判決:民集第54巻5号1607頁」
とあるように,面会交流調停で決定する債務は親権者,監護権者に与えられた処分です。監護は監護権者に認められますので、監護権の分属や分掌がなければ、非監護権者は監護に関わることが出来ません。逆に、監護の一内容に係る処分を課せられることはなく、監護権者の責務を負いません。
判例4
「面会交流の法的性質や権利性自体について議論があり,別居親が面会交流の権利を有していることが明らかであるとは認められないから,控訴人らの主張する別居親の面会交流権が憲法上の権利として保障されているとはいえない(東京高裁令和2年8月13日判決・判例時報2485号27頁)。」
ともあるように,被親権者,被監護権者は,監護権や面会権,訪問権を自身に有する権利として請求出来るものではありません。
判例5
「調停条項が,当事者の給付意思を表現した給付条項であるか,権利義務の確認にとどまる確認条項であるかは,当事者の内心の意思によって決まるものではなく,調停条項全体の記載内容をも参酌しつつ,当該調停条項の文言から客観的に判断すべきものである(高松高裁平成14年11月15日決定)。」
このとおり「当事者の給付意思を表現した給付条項であるか,権利義務の確認にとどまる確認条項であるか」は,相手方の「内心の意思」によって決まるものではありません。そもそも本来,債務者に課せられた給付の決定が「債務者自身の内心に沿うか,沿わないか」という債権者の主体で判断してよいというものではないことから,債務者ではない子らと債権者に対して,裁判所が恰も,何らの措置が講じたかの如く,債権者は調停条項,面会交流実施要領を恣意的に歪めることなど,あってはなりません。
つまり、子に対して「別居親と会ってはいけないと裁判所で決まっている」、また別居親に「面会交流の取り決めを守れ、会っていい時間は裁判所が決めたとおりだ」など、恰も優越的地位にあるように指示しますが、不当です。これは面会交流の取り決めが大事?誰が?を参考にして頂けたらと思いますが、子や債権者である別居親に何ら裁判所は命令していません。
要するに、面会交流制度とは、監護権者に対して、被監護者が「子どもの監護に、子どもを別居親と会わせるという「監護の一内容」を含める必要があるから、裁判所は監護権者に適正な措置を課してほしい」と、求める制度なのです。そして調停条項や面会交流実施要領で決定するのは監護権者に限定して監護の一内容を債務(給付)として決定し、適正な措置を処分するものですから債権者である別居親や子どもは債務の履行義務など求められることは不当となります。
面会交流実施要領で定められた適正な措置(給付)は,監護権者の監護上その一部において,被監護親との「共有の時間」を監護に含めることが「子への有益な影響」があることを示しています。つまり子の利益の為に適正な措置を講じられる監護権者の課せられた監護の一内容,債務(給付)である監護に関する処分(措置)の一環であり,非親権者,被監護者の監護の権利性は肯定されていません。したがいまして被親権者,被監護権者が子らと時間を共有することは,単独親権,単独監護権の制度上,監護権者の監護において被監護権者による見守り,子どもたちの安心,安全への配慮を共有時間とするものであり,被親権者,被監護権者の監護に要する時間としては採用されません。
最高裁調査官の判例解説
「面接交渉の内容は監護者の監護教育内容と調和する方法と形式において決定されるべきものであり,面接交渉権といわれているものは,面接交渉を求める請求権ではなく,子の監護のため適正な措置を求める権利である」
という解説があります。民法766条に基づき非親権者が面会交流調停を求める意義は「監護権者が,子を被監護親に会わせることが,子の利益に資することであり,監護権者の監護の一内容に必要であることの認容」を裁判所に求める制度であって,監護権者に対して監護にあたり子への寛容性や善意を求めるものです。
子どもが自立的に被監護親と交流する際の自然的交流権は,自由権であり,子と親に認められうる双方に有する基本的人権であることは思料されますが,被監護親は監護権が認められてない以上,面会交流を実施する監護の権利は債務者にのみ認められるものです。したがいまして面会交流調停とは,子と非親権者との「共有する時間」に認められる利益(権利性)は,子らを主体に運用される制度設計なのです。
被監護親に親権があるか否かを問わず(事実婚を含む)「監護の意義とは子が両親に求めうる,そして確保しうる(両親から適切に監護される)子の利益(権利)性が明確化」されたもの,それを認めうる理念が明確化したものとして,子の利益に資すべき,家族法の運用(面会交流調停を含)が「利益の主体性を,子に焦点に当てるべき」と明確化したものと解せます。
子どもは親権者、監護権者の所有物ではない。
令和6年4月5日第213回 衆議院 法務委員会で法務省・民事局長・竹内努氏は「別居親と一切交流させないというような場合は,個別の事情にもよるものの,これにより心身に有害な影響を及ぼした,と認められる場合には,DVに該当する可能性もあり得る,と考えられます。」と三谷英弘議員の質疑で回答しています。
このことを鑑みれば,結果として,子どもの意思に反して,直接的な親子交流(面会交流)に同意せず妨げて,子の利益を侵害する事情は,親権者、監護権者が「故意に作為してきた悪質な言動」として明確に露呈することになり,親権者、監護権者に不法性の根拠が明白となると考察できます。
判例6
「社会人として成長した暁には人格として備わっていなくてはならない二つの特性,すなわち,人間の母性原理の他,父性原理を一郎(子)自身が学習すべき絶好の機会を被告自らが摘み取っている態度というべく,決して讃められた態度ではない。子供は産まれたときから二親とは別個独立の人格を有し,その者固有の精神的世界を有し,固有の人生を歩むというべく,決して,母親たる被告の所有物ではないのである(静岡地裁浜松支部平成11年12月21日判決 判例時報1713号92頁)。」
という判例があります。
ですから面会交流調停の趣旨や目的の異なる債権債務など、様々な理由で子どもを別居親に会わせようとしないこと、つまり子の監護に要する費用の分担を面会交流調停の協議、和解に含めて、子を会わせる、会わせないといった「力の支配(DV)」で衡量させることは、恰も親権を所有権と勘違いした優越的地位の濫用であり、親権の濫用的行使にあたります。
親権者と被親権者を間接的に差別する裁判所
親権者、監護権者の優越的地位を裁判所が認容し、「力の支配(DV)」を憂慮すれば、明らかに間接差別です。子にとって両親は平等であり、監護権者が優位に立つという差別などあってはなりません。非監護権者が、監護者の善意に媚びへつらう必要があるなど、通常、裁判所は認めません。相手弁が有能で、裁判官に、そのように心証を持たせることがあっても、それは自弁が無能だということです。
そもそも親権者、監護権者の利益を協議に含めることは親権者、監護権者の満足のためであって,葛藤により係争を高葛藤にするだけではなく,子らに「有用な影響」が及ぶなど一切ありません。殊更,この面会交流調停で審理すべき最重要課題,特段な事情とは言い難く,面会交流調停での手続上で齟齬が生じうることの懸念,監護権者と子の利益とが相反するといった懸念が生じるということになります。
総括
両親が,それぞれに利益を求めたとしても,面会交流調停という協議の場が,お互いが求める様々な事情のすべてを,一度に解決させうる場ではありません。いくら信頼関係が大切だとしても,子のために必要な事項を個別に解決していくことが家族法,家事事件手続法,それら制度として手続きが分かれているという事です。
面会交流調停という協議の場で多くの事を同時に解決することが可能な制度であるとすれば,家庭裁判所の家事事件解決において面会交流調停の手続の1つでよくなり不合理です。そのうえ面会交流調停の場で親の利益に関して協議和解を求めることは,利益相反を思料することから,親権者、監護権者の望む,信頼関係の再構築の在り方は,一様に認められません。
面会交流調停という適正な措置を審理する趣旨や目的は,一義的に子の最善の利益の確保であり子の権利(利益)性ですから,「子の監護に要する費用の分担」を面会交流調停の協議の場で解決を求めること,また和解の「交換条件」にしようと目論むことは,一切出来ないことは明らかです。ましてや未成年者の人身を担保,留保したうえで交渉することは違法行為を助長するものです。
くれぐれも裁判所には「親の権利性(子の代理権や同意権)」に主体を置かず「子の権利や利益」に主体を置いて頂くよう、主張しておく必要があります。
子の監護に要する費用の分担の和解に向けた協議(調停の趣旨)を面会交流調停で行うにあたり,恰も両親のお互いに抱えている葛藤が強いものとして債権債務の問題に焦点を当てさせ,介入させて,異なる両親の事情の和解を求めることは,面会交流調停の意義が「子の権利や利益の主体性」から「親の権利(利益)性」に歪められ妥当性を欠くものと思料します。
親子交流(面会交流)の和解に向けた協議を実施するうえで,監護が監護権者の権利あることから,親が子の利益ために行うという観点で見られることに間違いはありませんが,制度設計としては「子が,親から適切な監護を受けることに,子の利益の観点から重要」とされる制度ですので,主語は「子が」となるものです。ですから「親の権利(利益)性」は関係がないわけではないものの,事あるごとに「高葛藤」を理由として,親子交流(面会交流)の制限を求めることは,「子の権利(利益)性」を主体にすれば,子の考えや子の意思,子の意見がないがしろになるということであって,親権者、監護権者の内心(利益)を尊重することになります。親権者、監護権者が自身の利益を目的とすれば問題がない,とはなりません。
「不平の百日より感謝の1日を」河野進さんの詩の一節ですが,当たり前ではない今の幸せに気づき,感謝することは,とても大切なことです。どの家庭の両親であっても,それは婚姻中でも離婚後も当然,お互いに不平が生じます。それは,子を有する両親であれば,子が幸せと感じることに感謝すべきであり,子の幸せを議論の中心とすべきであって,この点から解決の糸口を探すことが建設的な議論ということになろうかと思うところです。
したがいまして面会交流調停で,親権者、監護権者が別の事情(個人的な不平)として
子の監護に要する費用の分担
を介入させて高葛藤を作為することは,子らを巻き込みうる大きな影響が想定されますので避けなければならないと主張しましょう。
子らの年齢相応による理解や,その能力を鑑みれば,仮に,子らが受ける影響が「悪影響」ではないと審理がなされたとしても,少なからず「有用な影響」を子らが受けるとは言い難いことは,否定させません。したがいまして「子の権利や利益の主体性」を中心に面会交流調停では審理に望むべきと言えるでしょう。
最後に
裁判官は、材料の中で判断します。材料とは、双方の証拠や主張です。全く何もない材料を、いきなり持ち出せば、裁判官の越権行為です。高裁への公訴理由になります。ですから、しっかり書面に材料を入れ込むことを忘れてはなりません。「普通、一般人なら分かるだろう」とか、「ここまでのストーリーを読めば理解できるだろう」は通用しません。採用してほしい材料は、必ず、書面にして提出しておくことを忘れないように、頑張りましょう。
私たちの活動について
https://note.com/welwel
サポートして頂ける皆様に感謝しております。この費用はプロジェクトとは別に、子どもたちの支援活動に充てて頂いております。今後とも、どうぞよろしくお願いします。
