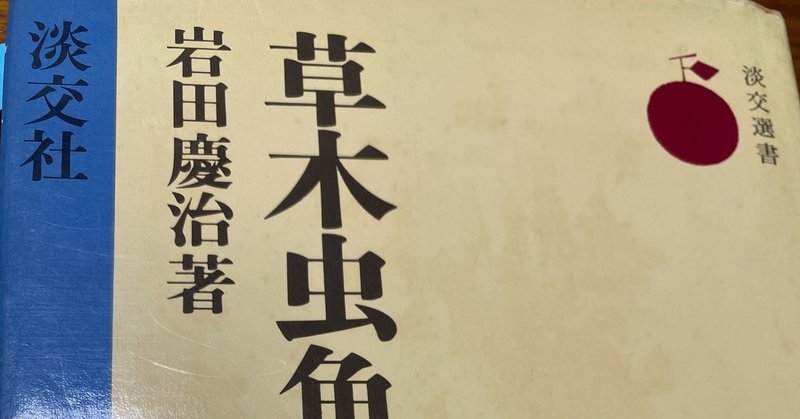
区別の仕方をメタモルフォーゼさせる ー岩田慶治著『草木虫魚の人類学』を読む
(この記事は有料に設定していますが、おわりまで無料で読めます)
◇
人類学、人類つまり「人間」について考えるはずなのに、草、木、虫、魚、と来る。草は人類なのだろうか?木は?虫は?魚は人類だろうか?
駅前で100人に聞けば、おそらく多くの人は、草は人類ではない、木も虫も魚も人類ではない、と当然のように答えるのではないか。私たちの日常の常識は、人間と人間ではない動物や植物を区別している。人間と自然を区別しているといってもいい。
岩田慶治氏がこの『草木虫魚の人類学』で考えるのは、まさにこの「区別している」ということ、その素朴で具体的で生々しい経験を、いかにして現代を生きる私たちの意識の表層に浮かび上がらせるかである。
※ちなみに本noteに示す同書からの引用ページ数は淡交社の昭和51年版を参照している。
区別することと、その手前
私たちの日常の意識にとって人間と草木虫魚が別々であるのは、最初から別々であるからではなくて、そのように区別をするからである。
この「区別をする」ことは、中沢新一氏の『レンマ学』の言葉を借りて言えば”脳、中枢神経系のニューラルネットワークで作用するロゴス的知性の働き”と言える。ロゴス的知性とは事物を区別して並べる働きであり、これが私たちの意識できる意識の経験を形作っている。
ここで考えたいのは「区別をする」前はどうなっているのか、ということである。
区別の手前では、”未だ区別がない”のだろうか。
無分別で、どうにかして自他を区別し続けようとするあらゆる生命体の営みを飲み込むように、あらゆる境界を溶かしてしまう動きが充満しているのだろうか?
あるいはそれとも人間のロゴス的知性の働きとは無関係に様々な差異が至る所で生じては消えていると、言うべきか?
どちらにしても、そのようなことを私たちが言葉で記述しようとした瞬間に、それはロゴス的知性が作り出した区別の体系の中に結ばれた像になる。なってしまう。
「区別以前」について考え語ろうとしても、それを意識によって、言葉によって、区別することによって生み出された互いに区別され対立関係にある事物の配列を通して行わざるを得ないところが「人間」の宿命というか業のようなものである。
とはいえ、区別を、対立関係の配列の網の目を通さざるを得ないということは、人間の知性の欠陥ではない。
他ではない人でありながら、区別以前を志向することとは
もちろん区別以前に直接入り込みたいと望む者にとっては、意識と言葉は聳え立つ壁のように見えるかもしれない。
が、一人一人の人間もまた一つの生命体として、絶えず自他の境界膜を再生産し続けることで自を他とは異なる存在として区切りだし持続させているのだとすれば、それを止めるということは死、あるいは生死の区別を超えた非生命への流出ということである。その先では区別以前を「望む」その望みあるいは欲望ないし執着もまた雲散霧消するのかもしれない。
人間があくまでも一人一人「ひとつ」の生命体であり、つまり自他を区別することを本分とするシステムであり、生死の区別を引き受けざるを得ない存在であり、その存在がある一つの知性として生きることでもある、とすれば、何よりも区別することを徹底的に引き受け、対立関係の配列の網の目に映る世界を意識し引き受けることが生きるということに他ならない。
重要なのは、この区別することの引き受け方である。
区別することを引き受けた上で、たまたま成育過程で贈与された他者達の言葉の区別の仕方を機械的に反復し、他の区別の可能性など「あり得ない」という顔をして生きる=死に向かって突っ走るのか…、それとも区別の仕方を自在にすることができるのか。
区別の仕方を自在にする
岩田慶治氏がこの『草木虫魚の人類学』で問うているのは、まさにこの区別の仕方を自在に組み替える可能性である。
どうすれば、現代の、生身の、一人一人の人間が、区別の仕方を自在に組み替えるという営みに自らを開くことができるのか?
人間もまた、他の動植物や細菌のようなものと同じようにタンパク質の合成と分解のプロセスの連鎖としての生命である。が、それと同時に人間はシンボルとシンボルの関係を合成したり分解したりする言語によって拡張された意識を持つ存在でもある。丸山圭三郎氏の言葉を借りるなら「身分け構造」と「言分け構造」が重なっているのである。
シンボルとシンボルの関係の体系としての「意味」の世界に掴み取られていることが、私たちがある区別の仕方を疑うことを可能にもするし、区別以前を希求する事を可能にもするし、また区別せざるを得ないことを引き受けながら区別の多様な可能性を試すことをも可能にする。
動物や植物にはそういうことはできないと思われているが、果たしてどうなのか。人間である私には皆目見当がつかないが、少なくとも私たちと同じような言語という外部のテクノロジーを用いて思考を拡張しているようには見えない。あるいは動物や植物は人間にとっての言語のようなシンボルの体系をそれぞれ環境の中に見出している可能性もある。いずれにしても私たちが動物や植物それぞれの「シンボル」を知ろうとするなら、人間の言語の体系に変換せざるを得ない。私たちはまずは徹底的に、自分たちの言語、言葉、シンボルとシンボルの配列と置き換えの関係のパターン化したコードを、徹底的に自覚し意識し、その他の配列の可能性を感覚し、思考することから初めてみよう。
<対応>の場
ここで岩田慶治氏は「<対応>の場」という概念を持ってくる。
<対応>の場とは、「時間と空間の出所であり、メタモルフォーゼ(変身)の場」であるという(p.I)。
どういうことか?
まず、時間と空間の出所。
時間とは、事物を互いに他とは異なるものとして区別して、そして並べたものである。空間もまた同じく、事物を他から区別して並べたものである。時間と空間のちがいはといえば、その区別した事物達の並べ方、順序の置き方のちがいである。
そして実は「時間」とひとことで言っても、時間が行う区別と配列のやり方にもいくつものバリエーションがある(例えば「反復する時間」、「反復しない時間」、「振り子運動としての時間」、「相似のペアが共有する時間」。詳しくは『草木虫魚の人類学』の249ページから250ページを参照)
<対応>の場が時間と場所の出所であるということは、<対応>の場が、そこで区別が生じる場所だということになる。
<対応>の場の「<対応>」とは、人間と草木との対応であり、人間と虫との対応であり、人間と魚の対応であり、人間と<もの>の対応であり、人間と人間の対応であり、自己と自己との対応であり、我々の築き上げた世界と別の世界の対応であり、二つの事柄の対応である。
では、二つの事柄が<対応>するとはどういうことか。岩田慶治氏は次のように書いている。
「二つの世界の間には壁がある。しかし、時としてーそれが時の誕生なのであるがーそこに対応という窓があくことがある。いや、実は、窓が開いたとき、対応のところにおいて、二つの世界が互いに見えてくるのである。そのとき、そのところにおいて、向こうの世界が誕生し、こちらの世界が誕生するのである。そこが創造の原点である。わがいのちの出所である。…二つの世界は、そこにおいて、いや、ここにおいて、実は、ひとつの世界なのであった。」(『草木虫魚の人類学』p.253)
対応のとき、ところにおいて、「向こうの世界が誕生し、こちらの世界が誕生する」とある。ここには非常に重要なことが書かれている。
対応は、誕生のとき・ところである。
何が誕生するか。「向こう」と「こちら」が誕生する。
向こうとこちら、互いに他とは異なるものと区別されるふたつの事柄は、<対応>において誕生する。
<対応>に先行して向こうが向こうとしてそれ自体としてすでにあったわけではなく、こちらもこちらとしてそれ自体として既に有ったわけでもない。向こうとこちらは元々あったものではなく、あるとき・ところで誕生する。その誕生の場、ある事柄が他との関係において他とは異なるものとして区切り出され区別され境界面が形成され並べられる場が<対応>の場である。
この対応の場は、二者が区別される瞬間である。この瞬間において、二者はまだ二者ではなく一であり、しかし同時にあくまでも二である。二にして一、一にして二。
そしてこの二にして一、一にして二の<対応>の場は、メタモルフォーゼ(変身)の場でもある。
人間がカミになりカミが人間になる。人間が草になり草が人間になる。人間が木になり木が人間になる。人間が虫になり、虫が人間になる。人間が魚になり魚が人間になる。
この「なる」=変身は双方向的であり、同時的でもある。草木は草木のままで人間であり、同時にまた人間ではない。虫や魚も虫や魚のままで人間であるとともに人間ではない。対応する両者は二でもなく、一でもなく、二にして一、一にして二である。メタモルフォーゼとはこういうことである。
メタモルフォーゼの場としての<対応>の場は、区別をすると同時に区別をせず、区別をしないと同時に区別をする。それは区別が「あるのかないのか」と問い、「ある」または「ない」、イエスかノーかのどちらか一方で答えることを要求するような思考を超えた感覚と経験の場である。
その場所は『レンマ学』の言葉を借りるなら、ロゴス的知性がレンマ的知性によって貫かれることによって、区別を行い互いに区別された事物を配列しながらも他の区別の区切り方を試行し、他の配列の可能性を試し続けることに相当しようか。そこで人は、あらゆる事物が一つにつながる「縁起」の網の目に溶け込むことなく、あくまでも一人の生命体として束の間生きながらも、ロゴス的知性が区切り並べる事物の網の目を通して、その「ゆらぎ」の向こうに、全てが他の全てと繋がりながら全体として運動する運動体のレンマ的な「知性」の働きの影というか、影響というか、気配のようなものを感じとる。
※
草は人類なのだろうか?木は?虫は?魚は人類だろうか?
この問いに言葉でもって答えるとすれば、確かに草は人類とは異なるものとして人類から区別されるものであるが、同時にこの区別がなされる瞬間のとき・ところにおいては、未だ人類と不可分でもある、といえる。
この区別されながら、区別されていない、という「宙ぶらりん」の曖昧な領域を開くことで、私たちは自分自身がどういう区別を疑い得ないものとして受け入れしまって、そこからはじめてしまっているのかを言語によって意識する可能性に開かれる。そこではさらに区別のやり方を組み替えることを試し、新たな言葉を、言葉と言葉の組み合わせ方を試す猶予と余地を与えられる。メタモルフォーゼをしながら、区別の仕方を自在に組み替えることを試すのである。
このnoteは有料に設定していますが、全文無料で公開しています。
気に入っていただけましたら、ぜひお気軽にサポートをお願いいたします。
文献調達の原資として有効活用させていただきます。
m(_ _)m
関連note
ここから先は
¥ 150
最後まで読んでいただき、ありがとうございます。 いただいたサポートは、次なる読書のため、文献の購入にあてさせていただきます。
