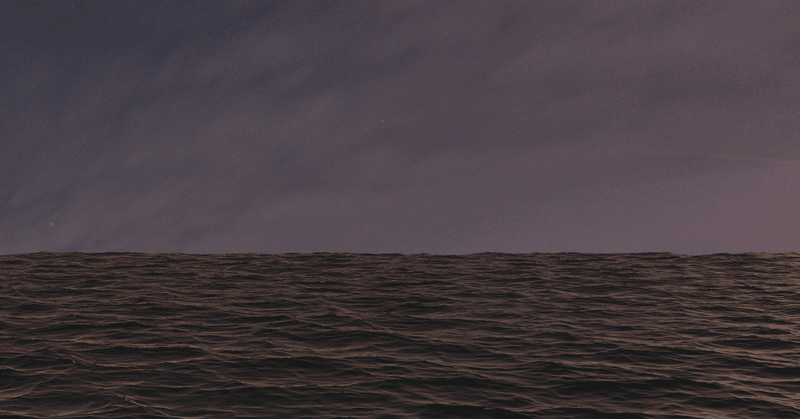
悲しい動物、双子葉としての世界。
忙しい日々が続いている。6月というのに真夏日をやすやすと超えて、朝な夕なに感じる風が、コンクリートの上をたいそう苦労して通ってきたのだろうと思わせるほどに傷だらけであるのを知る。風は、常に同じ温度ではない。ひと吹きするなかにも、一種の緩急があり、温度の波がある。紫陽花の横を通り過ぎたのだろうか、と思いきや、ああこれは労しいと思うほど熱い瞬間があったりする。どこをどう走ってきたのだろうか。足跡として——文章と風は、似ている。ひとつの連続体の中に、それまで踊ってきたリズムの確かな痕跡があり、作者や恣意者の確かな歴史を感じる。確かに紡ぎ出された文章には、その紡績行為にあっただろう逡巡や確信までもが痛々しいほどに明瞭に浮かび上がる。
今日死ぬには、あまりにも天気がいい。
死と、生と、その境界線が夏に近づくにつれて、いつも曖昧になる。ガラスのコップに水垢がついて、透明性を低下させていくように、しかしそれよりもっと緩慢なやり方で、曖昧さという水面が迫り上がってくる。コントラストが強まる季節には、生者の確かさというものが揺らぐ。陽炎のように、それがそれであるべくして在った輪郭や臨界点や境界線が何重にも暈され、影が真下に落ちる。真下に落ちた影を拾おうとかがめば、そこに在ったはずの影が真円に近いことを知る。光が強ければ強いほど、私の内在的な実存がくっきりと映し出されるかと思いきや、実際にはそうではない。むしろ、その周囲にまとわりついている雑多な思念や肉体がより色濃くコントラストを作り出して、私の実在の所在を見えなくさせてしまう。木々のざわめき、潮騒の冗長さ、土の湿り気、粘度をもった空気、エアコンの排出する生ぬるい不愉快な匂い、あまりに直裁すぎる日光の促す発汗。見えないからといって、無理に自分の現在地を探り出そうとすれば、骨の継ぎ目さえもわからなくなってしまうので、ただただ、暑さにうだりながら、強烈な可視光線の過ぎ去るのを待つしかない。地球は律儀で、おおよそ日の出から14時間も経てば光線は弱まり、ゆるやかな自殺に適した時間がやってくる。それでも完全に光は潰えず、道路に閉じ込められていた熱気や仄明るい光の粒子が行き場を失って、蛍光灯の周りに滞留したりする。それぞれの物が存在している境界線の周りに、あたかもその存在を助け舟とするかのようにか弱くまとわりつく光の粒子を、ひとつひとつ確かめながら、アスファルトの上を歩く。川に架かっている橋に近づくと、やおら下水の匂いと、その中に混じる原始的な循環の匂いがする。下生えが刈り取られ、魚は産卵し、水が泥を巻き上げる、その匂い。橋脚にぶつかりながら軽い対流を巻き起こす水は、所在なげな光の粒子を食みながら、薄く桃色のハイライトを孕みつつおおよそ群青として存在する。三叉路の直進方面の坂道も同じくて、自動販売機の放つ粒子を吸収して夏としての情景を編み出そうとしている。
そんな苦しみを、より正確には、あまりにも「そうでありすぎる」ことの絶え間ない反復性と緩慢な論理循環の冗長性を、いつまで経っても飲み込めないまま、いつも6月にいる。むしろ、その絶え間ない反復と論理矛盾の苦しみの渦中でこそ、言葉が紡ぎ出されるのだし、洗濯機の中で脱水される洗濯物が常に外側を指向しながら常にあるのは「何もない中心」であるようなものだ。そう、脱水される洗濯物たちを眺めながらいつも、この子達は真ん中に行きたいのね、と思う。ジャスミンティーをコップに勢いよく注ぎながら、その黄金色の液体は光を受けながら半ば艶やかに、死の匂いをまとわりつかせて中央を指向する。けれど、中央にぶつかった液体はその勢いでコップの内側を駆け巡り、増えていく水嵩に比例してその回転は高まって、いよいよ外へ溢れ出てしまう。一度外へ溢れ出、重力にしたがって落ちるべきところへ落ちて仕舞えばあとは沈黙するだけの存在になる。中央を目指して、精一杯の運動を繰り返し、いつの間にか外側をぐるぐると回り続けている。お互いの繊維を絡めあい、ほぐしあい、体液を絞り出し、重さから自由になろうともがきながら、目玉だけを中央に向けて、その外側——つまるところ洗濯槽——にひしゃげた身体をくっつけている。彼らは・彼女たちは、ある所定の時間になればその運動を中断させられて、清潔さと引き換えに個別具体的な存在となるが、私たちにはそれは許されないのだろう。地球がその運動をやめ、火星や土星もそれをやめたなら、ゆっくりと中央に引き寄せられて、哄笑しながら破裂していくだろうか。というより、そもそも中央への引力それ自体がなくなることに等しいなら、それは舞台の暗転というべきか、秩序系の崩壊に従う自由の到来ということになるかもしれない。皮肉なことに、演者は舞台の明転中より暗転後の方がより自由なのだ、本質的に——。私たちも洗濯槽の内側で、いつまでも中央を指向しながら(そこにはいつまで経っても到達できないまま)自らの体液を外側へ逃しているのだとしたら、その回転系から脱落することを希みつつ、私たちは祈り続けていることになる。祈ることに似た時間が増えれば増えるほど、私は幼くなっていく。というより、幼くあるために、祈っている時間がある。何かに対してそうであって欲しいと期待することで、未来という形がまだ自分の延長線上にあると信じているのだろう。つくづく、期待とは無責任な行為であると思う。期待をしなければ、未来も飛び方を忘れた鳥のように潰えてしまうのに、期待は常に惨めである。こんなに惨めな行為を何度も繰り返しながら、自己欺瞞と分かったつもりになっている世界の諸々の構成要素と——、ぬか喜びを重ねて、鈍感になっていく。現実と期待の乖離に対して慣れてしまうことを「大人になった」という言葉で押し込めて、痛みに対して知らないふりをする。いつしか、痛みを覚えることすら朧げになってしまうのだろうか。深夜の東名高速下りのSAで深呼吸をすること、そのたびに萎縮していた肺が空気の自由さを知り、息をすることの痛みを知ること、その瞬間を、その瞬間に対して、私は真摯に向き合いたい。痛みから逃げないでいたい。
食事を適当に済ませ、皿を洗い、シンクを綺麗に磨き上げ、フローリングを拭き、エアコンを付ける。冷たさをスライスしたような風が部屋を充満し、粘ついた空気から軽やかな人工的空気へと移行していく。食後の満腹感もやおら倦怠感に移行する途中の気分の悪さ。それでも、と零す。それでも、その気分の悪さにこそ、生きている実感があったりする、と思う。何もリストカットを擁護するわけじゃない。内臓が内臓として働き、血液がそれぞれの粒子のうちに生きるべき犠牲を把持し、奥底から水分が体液に変わっていく感覚の中で、生きていることは何も快楽なんかじゃないと痛感する。その時は決まって、どこか空虚な眼差しを無理にでも睨みに変えて、精一杯堪えている。視線は武装であり、同時に、視線の着地点たる服もまた、それゆえに武装たりえるのだろう。私は睨む、そことなく。時に、嫌われてきた過去を思い出したりする。体育館の倉庫でバスケットボールや雑多な掃除道具の放つ独特の匂いに包まれながら、私に向けられていた嫌悪感を知るとき、疼く内臓の運動を思い出す。そのときの内臓の正しさは、食後の倦怠感に似ているのだと思う。疎まれ、蔑まれ、妬まれ、出来ることが他者との分断線になっていく。嫌われるにつれ、嫌われるべきであるようになった。他者より優位であることがその理由ならば、その理由から逃げるわけにはいかない。かくて、優位性を吐き捨てることもできないまま、自己卑下と異常なほどのねじれた尊厳が綯い交ぜになった皮膚を守ってきた。電気を消して、しばらく横になる。消え去った音の残響が脳内に反響して、反響の中心地を想起させる。痛みこそが正しい、と何度も思う。
私の周りには、誰がいるのだろうか。私は、どうしても私を好きにはなれない。どうしたところで、人間の機能として感覚がひとつ欠落しているのであり、それが善であれ悪であれ、事実として存在している。それゆえに受けてきた寵愛もあれば、それゆえに受けてきた苦しみもあった。それを今更否定することも望まない。ただ、私は私を無条件に許容できないだけなのだろう。例えば海沿いで、そのまま波に呑まれたいと感じても、機械として成立した聴覚がそれを拒絶する、「塩分を含んだ水に浸されれば錆びます」。どこかに、そこらじゅうに、薄く立ち入り禁止区域が張り巡らされていて、私を制限する。それを超えるとき、私は社会的な私を脱ぎ捨てなければならない。聴覚や視覚や……感覚はその意味でひどく社会的なのだ。意識するにせよ、しないにせよ、そこには必ず社会的制約が含まれていて、私はそれを超えるとき、ひとつの悲しい動物になる。私は悲しくなんかない。けれど、状態として、存在として、原理として、悲しいのだ。悲しみを私ひとりで具現するつもりもないし、そんな覚悟もない。けれど、確かな実感として、私は悲しい。I do not feel sadness, but I am sadness. ひとつの感情を背負いつつ、同時に、私はそれゆえ、Hence, 私たり得ているのだと思う。葉がざわめくことで、風が高速道路を吹き抜けていくことで、光が青くなることで、初夏が初夏としてあるように、私は、周囲のそれら社会的視線を受けて、私であるのだ。実在など、なくていい。視線や同情や共感や、そうした一切が織りなす反射や結び目が、私としての境界線を織りなしていく。その中に私がいようといまいと、それはそういうことなのだろう。スプリンクラーのような愛が、土壌を満たそうとも、それは本質的に満たされはしないことを知っているから。諦めないことが愛ならば、私は私を諦めない。満ち足りるとか、与えるとか、そうしたことから解き放たれて、それがそれであるための心地よい運動系のリズムをこそ、匂いをこそ、イメージをこそ——聞こえること以外のすべて——を、信じ抜く。涙が溢れようとも、蔑まれようとも、妬まれ、嫉まれようとも、むしろ、嫌われるたびに、そのたびに、反射のプリズムは強くなるのだから。
こうしたことを紡いでいける言葉を獲得したことは、私にとって唯一、世界から与えられた大いなる〈災厄=幸福〉だと思う。生まれてこなければよかった、という明確なアンチテーゼに対して、もはや取り返しのつかない幸福としてその誕生を振り返り、生き直す権利はまだ私たちの方にある。忘却もまた同じくて、それをそれとして、そこに再び運動を与えることができる。何度も繰り返される偽善に、ひとつの時間軸を与えることができるのは、それ自体忘却のパラダイムに組み込まれているからだ。忘却無くして想起もない。おおよその事柄は、あれがあればこれがある。その二項対立的な=双子葉的世界のなかで、その根源たる「ひとつの種」を探り出したとき、大きな融合が見えてくる——母と父と——、そのレイヤーで私を肯定したい。道はきらめき、指が透明になっていく、その季節まであとどれ程かかるだろう。透明になった指がそれを名指すとき、つまりは世界の根源たる何ものかに触れるとき、私は私を救い出す、自らの手で、言葉を翼にしながら。
クィアな眼差しで、中性的でもなく、ゲイでもノンケでもバイでもレズでもなく、その花弁的レイヤーのもうひとつ上あるいは下、すなわち「それではない」場所で、睨み続けたい。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
