
ユカイ工学代表・青木俊介と縁ある人との「ユカイ予想図」対談企画。第5回目は小野直紀さんと
みなさんこんにちは。デザイナーの はらだ です。
ユカイ工学代表の青木俊介が、その道々で活躍し世の中へ向けて様々な提案をしている縁のある人物を訪ね、「ちょっと最近どうですか?」というざっくばらんな会話から、今をどう捉え、未来についてまで、様々に語り合う対談企画「ユカイ予想図」をお届けします。
第5回目の縁ある人は、博報堂monom代表の小野直紀さん。
今回は、デザイン視点からのものづくりについて語っていただきました!どうぞお楽しみください!
▼これまでの「ユカイ予想図」記事はこちら
第1回目:猪子寿之さんと片桐孝憲さん
第2回目:根津孝太さん
第3回目:遠藤諭さん
第4回目:大杉信雄さん
ーーー
プロフィール
小野 直紀(おの なおき)
博報堂monom代表。クリエイティブディレクター/プロダクトデザイナー。
2008年博報堂に入社後、空間デザイナー、コピーライターを経てプロダクト開発に特化したクリエイティブチーム「monom(モノム)」を設立。社外では家具や照明、インテリアのデザインを行うデザインスタジオ「YOY(ヨイ)」を主宰。文化庁メディア芸術祭 優秀賞、グッドデザイン賞 グッドデザイン・ベスト100、日本空間デザイン賞 金賞ほか受賞多数。2015年より武蔵野美術大学非常勤講師。2019年より博報堂が発行する雑誌『広告』の編集長を務める。
著書『会社を使い倒せ!』
ユカイな未来ってなんだろう?
青木
今日は博報堂のmonomの代表をしていらっしゃる小野さんをお迎えして、お話を聞きたいと思います。よろしくお願いします。
小野
よろしくお願いします。
青木
小野さんとはQooboの誕生からですね。

今はPetit Qooboという新しいモデルもご一緒させていただいております。クラウドファンディングもありがたいことに大幅達成で終わりました。本当にありがとうございます。
小野
いやいや、おめでとうございます。
青木
良かったです。ちょっとほっとしました。
Petit Qooboは声に反応するようなマイクがついたり、ずっと一緒にいれるよっていうのがテーマで、子供っぽい動きの感じのアクチュエーターがついたりしています。
小野さんは最近どんなことをやられてるんですか。
小野
最近は、博報堂が出してる雑誌『広告』で編集長ををやっていて、それが5〜6割くらいですね。
それと「Pechat(ペチャット)」という、ぬいぐるみをおしゃべりさせるボタンの販売・開発も引き続きやっています。
あと、博報堂の新規事業をいくつか進めているのと、会社とは別で「YOY」というデザインスタジオも引き続きやっています。
このなかだと、雑誌の仕事が一番大変ですね。編集者ではないので、さぐりさぐりという感じです。
青木
雑誌読ませてもらいました!これ、次のテーマは?
小野
ありがとうございます!次は「流通」です。
青木
流通ですか!え、面白いですね。今めっちゃ興味あります。
小野
流通、めちゃくちゃ面白いですね!
ビジネス視点の流通については扱う本がいっぱいあるので、そういう視点だけじゃない流通を深ぼっています。
博報堂って広告会社じゃないですか。
「広告」と「流通」って、立ち位置で言うと近いんですよ。広告も流通も、商品ができた後にやることで、広告は情報を、流通は商品を生活者に届けるという感じで。
でも、広告会社の人って流通の仕組みに疎いんですよ。
青木
なんか店頭のプロモーションとか別の会社がやったりしますもんね。
小野
そうですね。
まだその店頭プロモーションとかお店作りぐらいはやったりするんでわかるんですけど、その裏側がどうなってるか、デパートの在庫置き場がどうなってるかとか、卸がどういう仕組みなのかとか…全く知らないし、全くタッチしてこなかった。
でも、ものづくりと広告は切っても切り離されないものだし、ものづくりと流通も切っても切り離せないものだから。それが分断されてるっていうのが良くないなと思ったんで、勉強しながら作っています。
青木
そうなんですね。
今、D2Cっていうキーワードはすごいホットじゃないですか。
それもやっぱり新しい流通のひとつですよね。
小野
そうですね。
個人でも小規模の会社でも、簡単に直接商品を届けられるようになったのと、直接自分たちでブランディングやプロモーションをやれるようになったという背景があります。
SNSを使ったり、共感する人たちを集めたり…D2Cみたいな形っていうのも当たり前になっていますよね。「バズワード」になっているから、プレスリリースにD2Cって書かれているのをよく目にします。
青木
不思議ですよね。
小野
Qooboもクラウドファンディングをやったり、ファンミーティングやったり、購入者やファンのコミュニティがあったりしますよね。
つまり直接コミュニケーションや販売をしていくみたいなことをやってると思うんですけど、そういうのが普通になっているという印象です。
そこから、より規模を広げてくってなったときに、既存の小売や卸との連携っていうのは、まだまだ必要だなっていうのはPechatをやっていて思います。
青木
そうですよね。
直接ファンとの強いコミュニティがあると、改善とか意見が聞けたり。それに応援してくれたりとか。
最初のベクトル・指標みたいなのを作るのにめちゃくちゃいいなと思っていて。そういうものと、Amazonみたいな今ある大きいプラットフォームみたいなものが、いろいろ掛け合わせてやっていくのかなって。
僕がすごく面白いなと思うのは、ロフトさんがQooboを扱ってくれたりしたこと。他にも、「ふなっしー」を掘り出したのは、実はロフトの船橋店だったとか。
小野
それ面白いですね。
青木
まず「ふなっしー」って船橋市公認キャラクターじゃないじゃないですか。
僕も地元船橋なんですけど。
「変わった着ぐるみ着て頑張ってる人がいるんでちょっとお店に置いてみようか」みたいな感じで、ロフトの船橋店でそういうのを置き始めて。
小野
でも全国区の人気になりましたよね。
青木
全国区になりましたし、中国でもキーホルダー売ってましたからね。
すごいですよね。
そういう、流通って一口で言っても、メーカーとユーザーと割と距離が近くて役割もオーバーラップしてるような、そういうのはすごく面白いなあと思うんですよね。
小野
なるほど。たしかにそうですね。
流通とメーカーが一緒にものづくりするケースが増えてる。
プライベートブランドとか、わかりやすくそうなんでしょうけど。
百貨店や家電量販とかも一緒に作ったり。小売とメーカーが結びつくみたいなのがあるんでしょうけど、それは最適化・効率化のためにやってるみたいな印象があって…。
「ふなっしー」みたいなことってそれとは違うし、そういう方が面白いなと思います。
青木
そうですよね。
そういう人が一緒になって面白がってるみたいなパターンって、新しいものが生まれる環境なんじゃないかなあって思いますね。
小野
そうですね。
あとバイヤーさんっていうんですかね。
新しいものを本当に探して世界中飛び回ってる人とかもいるし。
僕も海外のバイヤーさんとよくやりとりするんですけど、彼らはミラノサローネなど展示会に足を運ぶから、毎年「久しぶり!」って現地挨拶したりしますね。そうやって面白いものを発掘する目利きというか。そういう人たちの存在と作り手って、また全然価値が違うと思っています。
メディアもある種、目利きが大事じゃないですか。
例えば、インテリア雑誌「ELLE DECOR(エル・デコ)」の編集者が、新しいデザイナーや新しいインテリア、プロダクトを見つけて紹介するのと同じように、新しい何かを見つけてそれをお店に仕入れるみたいな。
流通というか小売の役割で新しく文化を作るみたいなことはずっとやられてきていて。それが今どう変わってきているのかな、みたいなことにちょっと興味があります。
青木
草間彌生のスケボーとか、MoMAであるじゃないですか。
あれってMoMAの方が企画しているんですかね。
小野
どうなんすかね。
でも割とMoMA Design Storeに置かれるものって、めちゃくちゃ王道のデザイン品か、普通よりちょっと高いくらいの価格で売りやすいものっていう印象です。
YOYの商品もいくつか置いてもらっています。Qooboも置いてます?
青木
Qooboは日本だけOKが出たんですよ。
僕がアメリカに営業行った時は、「まだちょっとアメリカ人にはわかんないな」って感じで。
小野
たしかにマーケットによって、合う合わないがありますよね。
YOYでデザインしたコースターも売っているんですけど、これはめちゃくちゃシンプルなんで、10年ぐらい世界中で売り続けてくれています。これは仕入れではなく、MoMAとして作っているんです。
青木
へぇ〜!これは「Design by YOY」みたいな感じになっているんですか?
小野
「Design by Naoki Ono Yuki Yamamoto」ですね。
あとこれとかも今は売ってないけど、過去に日本・海外のMoMAで扱ってもらっていて。

あとはリリックスピーカーのセカンドモデルも扱ってもらっています。
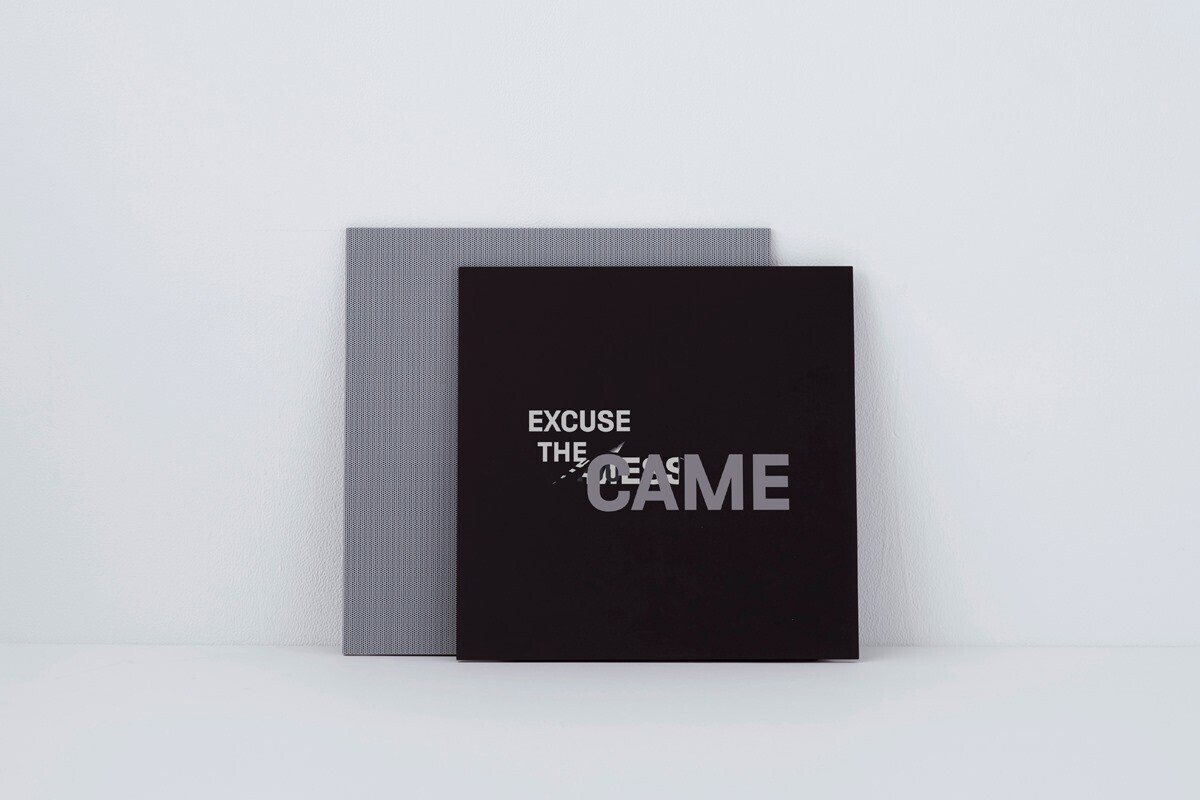
青木
日本だと、僕が仲良くさせてもらっているのは、アシストオンさんっていう雑貨屋さんなんですけど。
大杉さんって方が店主で、商品は全部自分が普通に使って気に入ったものを置くスタイルなんですよね。
クリエイターの方が売り込みに来たり、駆け込み寺になっていたりして。
「BALMUDA(バルミューダ)」は創業のとき、「これどうですかね」って感じで商品持ち込んでいたみたいです。
僕は大杉さんとすごく仲良くさせてもらって、色々教えてもらってるんで、そういう届け手の方ってすごく重要っていうか。
小野
そうですね。個人や小規模で意志を持ってやられてる人たちとかは増えてきてるし、良いなと思っていますが、もう少し大きい規模のところ、それこそロフトとか、そういう会社の中でどういう人たちがどういうビジョンを持ってやってるのかなっていうのはちょっと気になりますね。
会社の中にいる人たちってあんま見えてこないなって。
青木
あ、そういう方々にインタビューを。
小野
行きたいんですよね。
あとは、小売以外にも、物流とか、倉庫がどうなってるのかって話だったりも扱おうとしてます。
青木
倉庫によっては、家電の修理をチーム持ってるとこもありますよね。
小野
なるほど。
倉庫ってただ物を置いとくだけじゃなくて、加工がそこに加わったりとか。
予想も含めて全体で設計されるというか。それ面白そうだなって。
すごい大事なパートだけど、デザイナーだとそこにあんま関わらないですよねやっぱり。
ものを作るところのデザインをする、プロダクトのデザインするっていうところは関わるんだけど、じゃあLogisticsはどうするんだとか、倉庫はどうなってんのかっていうのは、考えたこともないっていうか。
僕の場合はPechatやるようになって考えるようになりました。
それまでは、そういうところを無視してるわけじゃないんだけど、あんまり自分の関与度がなかったなっていう反省しています。
ものを作る人たちが、「ものを作ってる」って自分で思っているんだけど、作る過程とか届ける過程を取り巻くものごとに対して関与度が低いっていう状態は、僕自身も含めて良くないなと思っていて。
そうした過程に、商品や受け手・使い手に対してより良い影響を与えるアイデアや考える余地がたくさんあると思っています。
広告会社って縦割りの極みの会社なんですよね。
要するに広告をするっていう部署が企業の中にあって、そこから広告会社に発注がくるわけですよね。企業が大きくなっていくと、そうなっちゃうんですけど…結局、効率化みたいなことになって「つまんないな」って思ったりもします。
何か新しいものって、もっとごちゃごちゃしているところから生まれると思うんです。
効率的ということは、最適化はされていくんだろうけど、なんかものすごいものが生まれたりしない。
必要のないものとかがどんどん削ぎ落とされていく。
だから、なかなかそういう場所では、Qooboとか生まれないわけですよ。
青木
生まれないですよね。
小野
QooboとかPechatもそういう側面があって、僕は「いらないもの」が好きなんですよね。
いらないものっていうのは生きていくために必要ないものっていうか。
そういうものだけれども、でも欲しい!みたいな人の気持ちをくすぐるみたいなものです。
何かの効率を良くしたりとか、世界を救ったりとか、環境問題を解決したりとかっていうことも、大事だから意識はするんですけど。
でもそこだけにコミットするよりは、一見無駄だと思われるものを作るってことにコミットしたいって思うんです。
雑誌も特集としてはちょっとマニアックっていうか。
それも「『著作』とか『流通』とか誰買うの?」みたいなやつじゃないですか。
青木さんはもの作りやってるから流通とかって言ったらちょっとピクッてなると思うんですけど、一般の人や広告関連の人からすると…。
青木
対極の世界ですよね。
小野
そうそう。
流通って言われても、自分と関係があると思えないと誰も買わないじゃないですか。著作だったらギリギリ気にするかもしれないけど、なんかちょっとカタい。
青木
そうそう、結構カタいテーマ選ぶんだなって。
小野
直接的に必要じゃないなと思われるものの方が、僕は興味があるんだなと思っていて。
「世の中の鏡である」とか「これみんな好きでしょ」みたいな商品じゃない方が僕は好きっていうか。鏡に映ってない何か別の世の中のあり方みたいなものを提示してる方が、なんか良いなと思ってるんですよね。
青木
なるほど。面白い。
小野
Qooboとか絶対そんなんじゃないですか。
そんなみんな期待してないじゃないですか。
青木
そうですね。妄想の産物ですもんね。
小野
そうそう。でもなんかみんな気になるっていう。
そういうドンピシャな感じ。
最初ユカイでQooboのプロトタイプ見たとき「これ絶対面白い」って言った記憶があるんですけど。

青木
いやぁ、あのときに小野さんが応援してくれたからこその製品だと思います。
小野
いえいえ。でもなんて言うか…Qooboデザイナー高岡さんの偏執的な想いみたいなのがね。めちゃくちゃピュアな想いから生まれたものが世に存在できる方がいいなと思ったんですよね。
それが「一部の変わった人たちがちょっと興味を持つもの」っていうものよりは、もう少し広がった方がいいなと思ったんですよね。
青木
似たような事例だと、マウンテンバイクとかすごい好きで。
YouTubeでも歴史の話があがっていたりするんですけど、最初は「山走ったら面白いじゃん」みたいな話で。
カリフォルニアの数人の元ロードレーサーが自分たちで太いパイプを溶接してバイクを作って、山を走り始めたのがきっかけで。
そうしたら、「なんかそれ面白そう」って人がどんどん集まり始めて、その最初にやりだした何人かが作った会社が、マウンテンバイクの初期のブランドになったんですよね。
小野
そういうのがいいなと思います。
「こういうものを世の中が求めているから、こういうものを作りましょう」みたいな作り方よりも、自分が面白いと信じられるものと、世の中もそれを面白いと思うんじゃないかっていうギリギリのところでやりたいっていうか。
「自分が面白いのは世の中も絶対これ欲しいはず」とまでは信じ切れなくても、ギリギリ世の中喜ぶんじゃないかっていう、そこの接点があると。
「世の中の人はこれが欲しいんじゃないか、これを作ろう」みたいな感じの作り方するのは、皆さんやってくださいっていう気持ちがすごいあって。
別にそれはできる人いっぱいいるし、みんなでやればいいじゃんと思う。
青木
「売れそう・儲かりそう」だと、もう大企業がやってますよね。
小野
そう。やってたり、そういうスタンスでやる人たちはみんなやってるわけで。
そういういう作り方をする人たちが多数なのであれば、そうじゃないアプローチでものを作った方が、もの作りの多様性とが生まれるような気がして。
僕はそっちはやらないみたいな気持ちが強いっていうか。
やらないっていうか、できないのかもしれないですけど。
青木
そう、できないんですよね。
小野
青木さんそういうのしなそうですよね。
したくないわけじゃないと思いますけど。
青木
したくないわけじゃないんですけどね。
僕らがD2Cやるとしたら…どういうふうにやってたらいいと思いますか?
小野
ユカイのロゴ作ったじゃないですか。
僕はあのロゴ本当に好きで。
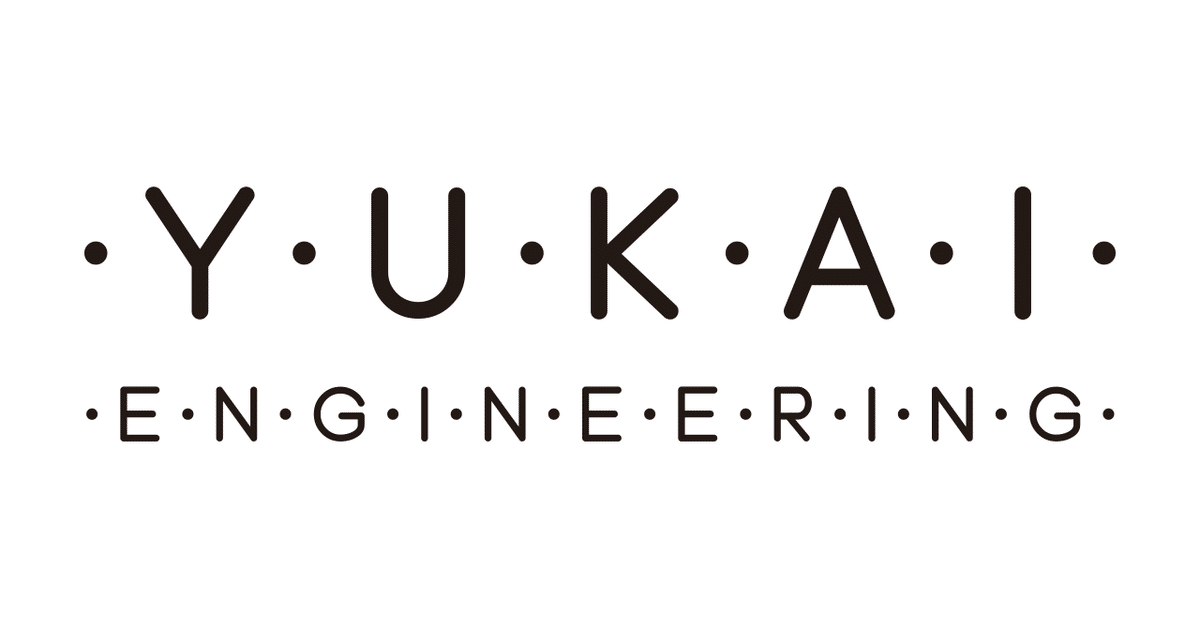
青木
僕も大好きです。
小野
本当にあれいいなって思ってて。
「名は体」じゃないですか、ユカイって。
ロゴはいろんなアルファベットが顔に見えるというもので、ユカイな仲間が世の中に増えく状態をイメージしています。
ものって擬人化されることがあるじゃないですか。
それこそ今話してた例だと、バイクや車に名前付けてる人とか。
要するに自分にとってパートナー的存在に思うようなものの、拡張をしていくんだなあと。
車も「便利だから車乗ってるんです」っていうことだけでもないんじゃないですか。
青木
たしかに、愛車に名前つけたりとかしますもんね。
小野
そう。だから、その感覚に近いものを作ろうとしてるんだなと。
それって愛着じゃないですか。
名前つけなくても、ずっと使ってたらコップとかでも愛着湧くわけじゃないですか。
そういう、ものとの関係性みたいなものって、ユカイの場合はもう少し生き物というか、動くものというかロボットっていう形で、それをやろうとしているなと思って。
世の中がそういうのを欲しがるかどうか以前に、そういうものをたちが世の中に増えたらいいなっていうイメージに、僕はすごい共感してるんです。
青木
たしかに、そうですね。
小野
ある種、漫画みたいな感じ。
漫画や映画って、なくてもいいもじゃないですか。
生きていけるっていうか。
音楽もそうだけど、好きなものもとことんハマって、ファンになって。
アニメとかだったら「このセリフを覚えてる」みたいな。
僕の中ではそういう愛着みたいな「ものと人の関係」って、アニメとの関係に近くて。
そういうものの方が、「便利です」みたいなことより良いなって思ってる。
もちろん便利なものも大事なんで、便利なものを考えるのも楽しいんですけど。そっちよりは、不便で役に立たないけど…みたいな方が好き。
本当に売るってことだけを考えたら、役に立つとか、便利、安さ、効率…そういうのが大事だったりするので、そこを無視するわけではなく、両面必要だなと思っていて。
世の中が求めるものの中に、世の中が求めてないかもしれないけどあった方がいいものを混ぜ込んでいくっていうか、そういうのができると良いんだなあと思っています。

Qooboもギリギリそうなってると思ったんですよね、最初見たとき。
「温かくする機能は無くしましょう」とか言った気がするんですけど。
それは否定したわけじゃなくて、単純にそれで価格が高くなるのは、その存在と人々が手に入れたいと思うギリギリのラインをちょっとだけ超えちゃいそうだなと思ったので、なるべくそぎ落とした方が手に届きやすくなると思ったんです。
ものの価値って「すごく良いけど高い」ってなったら、結局その価値があるかどうかわかんない状態で終わっちゃうんですよね。
やっぱり使ってもらうことで、初めて価値が発揮されると思うから。価値の発揮の総量みたいなものも増やしていこうと思うと、諦める部分が必要と思います。
Pechatも加速度センサをつけるとか、音に反応させてピカピカ光らせるみたいな企画を一切潰して、音だけにしようって絞ったんです。
それは「iDoll(アイドール)」の経験があったからですね。

iDollは本当に良かったと思うんですけど、価値発揮が結果的にできなかったわけじゃないですか。価値はあったんですよ。
ただ、価格の難しさがあって、それを発揮する場があの時点では1回失われたから、すごいいい経験だったなと思って。
青木
届けたいですね。
小野
「世の中がこれを求めている」っていうところを完全に無視することはできないじゃないですか。かと言って「世の中がみんなこういうの好きだからそれを作る」みたいなことではないというか。
なんか流行ったからそれを真似して作る、みたいなこともまあいいんだけど…「BALMUDAで高いトースターが売れてるらしいぞ」って言って各種メーカーが高いトースターを本家よりちょっと安くして出すみたいな。
ああいうのはしてもいいけど、なんかそれは僕はしない。
それになかなか手が届かなかった人に届くわけだから、あれはあれで価値ある。ただ、僕はそっちの価値作りよりは、想定しきれない価値作りの方が。
これは悪く言ってるわけではなくて、そういう作り方ではないアプローチも世の中にはすごい大事だなと思っているんです。
あと僕の場合は、そっちの方が単純に楽しい。
青木
やっぱり小さい組織でやる方は、みんながやらないアプローチでやるということに価値があるとは思っていて。
小野
そう。まあ、そう思いたいだけかもしれませんけど…。
本当は全くそんなのやらずに、もっと効率的に働いて金稼いだ方が、博報堂的にも全然いいから「小野もっと稼げるものを作れ」って言われるような気はするし。笑
「普通に広告の仕事した方が多分稼げるから広告やれよ」っていうこともあるかもしれないけど…とはいえ、雑誌は最も利益を出さないし。
それをやらせてもらってるってことは、そういう遊びというか、余剰の部分っていうのがギリギリ許されてて。
そういう余剰の部分を積極的に博報堂とか広告会社、経済の真ん中の会社でやるっていうのがやっぱ面白いなと思ってて。
青木
やっぱ生活に入り込む方が面白いなって思います。
小野
そう、僕もそっちの方が。
YOYでやってるやつとかも、照明や椅子とかだから「もう無印でいいじゃんIKEAでいいじゃん」「名作のものいっぱいあるじゃん」みたいなものを作ってるんですけど。
でも「まだこれは見たことないんじゃないか」ってものを作って、ギリギリそれが世の中の人が欲しいと思ったり、実際に買える状態っていうのを目指していて。
愛着が湧くみたいな、ものと人の関係性って、ものを見て面白いなと思ったときに築けるんだけど…ただそれだけだとイベント的すぎるっていうか。
やっぱりプロダクトはイベント的な時間や体験の消費じゃない方がいいなと思っています。
青木
そうですよね。見て終わりじゃなくて。
小野
そういうものも必要だとは思うんですけど。
青木
やっぱり寝起きでも見るし、プロダクトによっては時間帯によって役割が違ったりしますよね。
小野
そうそう。
最近料理を始めて、キッチングッズを徐々に増やしてるんですけど。
たまたま柳宗理のスプーンを買ったんですよ。
実は僕、そんなにものに頓着してないから、もともと無印のスプーンを持ってたんですけど。笑
柳宗理のスプーンってちょっとだけ逆三角形みたいな感じになっていて、形が変わってるんですけど…なんかもうそれだけでも。
無印って、あえて無味乾燥にしていて、王道で誰もが使いやすくて、なるべくシンプルなものですよね。誰が使っても自然な形というか、そういうものを作っていて。
もともとそういうのが好きだったんですけど。
柳宗理のを使い出すと、ちょっと歪というか…崩れてるから、逆三角形で。それだけでなんか愛着沸いたんですよね。「なんだこれ」と思って。
誰もが「スプーンはこうあるべきだよね」とか、それすら思わないものよりも、少し違和感や想像と違ったずれがあった方が好きになるのかなと思ったりして。
でもそういうものって、効率化の中では削ぎ落とされるわけじゃないですか。嗜好性が出ちゃうから、「そういうのは要らない」と思う人が出ちゃう。
無印だとあんまりそういうのは作らないと思うんですけど。
でもそういう要素っていうのはすごい大事だなと思ったりしますね。

Qooboの時もそうだし…Petit QooboのやりとりはいまだにCDOの巽さんとしてますけど、骨の部分とか中のところも割と細かく「ここもっと骨っぽくしたい」って言ったりしていて。
やっぱり普通は見ないけど、見る人が見たときに、少しでもそういう愛着が湧く要素っていうのを入れていきたいなと思っています。
やらなくても、ほとんどの人が見ないし、そんなに気にしないんだけど。でも、やりたいんですよね。
青木
ものと人の関係がちゃんと作れるようなっていうのは、何か魅力がないと…というか。自分もやっぱそういうものが好きだからですね。
小野
そうなんじゃないですか。
自分が燃えないと青木さんやらない気がするけど。
青木
それがあると思います。
乗り物とか靴とか、なんか特別な愛着があった気がしますね。文房具とか。
小野
バランスですけどね。全ての身の回りのものに対して愛着を持つっていうのは相当大変じゃないですか。
これも、これも、これも…ってこだわって部屋ができているタイプの人もいると思うけど、僕は比較的ものへの関与度が低かったんですよ。
めちゃくちゃ考えてというより「まぁ無印でいっか」みたいな感じで買うタイプだったんですけど。
でもなんか、何個がやっぱ好きで買ってるものとかはやっぱあるから。
青木
お気に入りのものはそうそうないのかもしれないですよね。
小野
そうそうそう、結局はね。
全部に対して関与度高く持って、こだわりの選んだものだけでまとめていくっていうのは、それはやってる人いると思うんですけど、結構精神力いるっていうか。
「ファッション好きな人が大量に服を買ってこだわってる」みたいなことを、他のいろんなものに対してやるっていうことだと思うんで、それはお金も時間もそこにかかるから。
僕はもの作るのは好きだけど、ものを買うのは別にそんなに今まで興味なかったから。車も持ってないし、自転車も持ってないし。
ちょっと矛盾してるんですけどね。
青木
やっぱり愛情を注げる存在はそんなに多くはないんですかね。
小野
そうですね。
でも自分が生み出すものはそういう対象になってほしいって思いはあります。
青木
ものづくりのお話をお聞きできて良かったです!
ありがとうございます。
次の雑誌『広告』楽しみにしてます!
ーーー
世の中に求められるものと、必要ないけれど欲しくなるギリギリのラインへの追求。
そして、「ものと人の関係性」と「愛着」は大変興味深いものでした!
素敵なお話をありがとうございました!
マガジン更新中
そのほかの対談noteは是非マガジンからご覧ください。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
