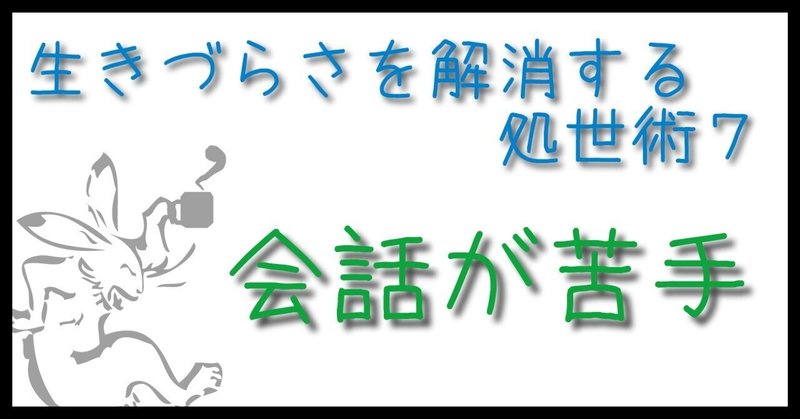
苦手な会話の克服方法
自分に理解できない人はちょっと怖い
堂々と生きている人がちょっと怖い
自分は堂々と生きることができないから
流れるように話しかけてくる人がちょっと怖い
自分にはできない芸当だから
昔はなんともなかったのに、苦手意識が強くなった
学生の頃は会話に対して対して抵抗がなかったのに、社会人になってからなんか会話に苦手意識を持つようになりました。
小中学生の同学年は、同じ年に同じ地域に生まれたという共通点だけで集められた集団です。気の合わない人は相手にしなくても良い。気の合う人とだけ人付き合いをしていればいいという選択の自由が与えられます。
高校に入ると同じぐらいの学力の人間が集められます。そして生まれ育った地域もそこまで遠くないので、価値観が近い人間関係を築きやすいです。
大学に入ると、地域性こそ違えど同じぐらいの年代、同じぐらいの学力の人の集団です。そして人数が多いので、ここでも気の合う人とだけ付き合うという選択自由を与えられます。
ところが社会人になった途端、全然年齢も違う価値観も違う人が上司になって共通点は同じ会社に属しているということだけで、付き合う人間を自由に選ぶ権利は奪われてしまう訳です。
そうなると起きるのが会話の選択です。これまで特段気にせずしていた会話が突然気を遣って行わなければならなくなるわけです。
職場の同期も同じ年代に入社した新人というくくりだけで出身大学も違えば専攻してきた学問も違っていたりします。
定型発達の人は器用に会話をすることが出来ますが、我々は頭をフル回転で会話をしなければなりません。そして失敗が多いです。そして、会話で失敗をする度に自信がなくなっていきだんだん苦手意識が芽生えてきます。
社会人になると多種多様な人達と会話をする場面が増え、その度に失礼のないようにとか嫌われないようにとか意識しなければならず、会話の難易度は段違いに上がります。
そこで、人間関係を築く上で使える会話のコツをまとめてみました。
雑談が苦手。立食パーティーとか地獄
街でばったり同僚に出会った時、懇親会や職場の飲み会など、何話したら良いか分からずオドオドしてしまう。ありますよね。
私は職場の飲み会が苦手で仕方なかったです。何話していいか全然わかりませんでした。
セミナーみたいな集まりで、『では、お互いが仲良くなるために今からフリータイムです。みんなでご歓談ください。』とか、地獄でしか無いです。
公務員の内定者の懇親会パーティにお呼ばれしたけど、誰とも話できず会場の隅っこで気配を消して、黙々と食事を楽しんでいた私です。
気の合う知り合いが会場内に居れば、もうその人から離れたくないなんてこともありますよね。
社会人を何年かやって、身についた克服方法は「挨拶を笑顔で大声て愛想よくやる」「定型文でなんとか乗り切る」です。
挨拶なら堂々とすることができますよね。
街で同僚にばったり出会ってしまった場合も、相手に嫌な思いをさせないために挨拶は元気よく笑顔ですることをお勧めします。それさえしておけば、その後会話が続かなかったとしても、相手に嫌な印象を残すことはありません。大丈夫です。
「おはよーございます!!じゃっ、ちょっと用事があるんで!」と颯爽と逃げるだけでも、好印象を与えることができます。
職場の飲み会では「お疲れ様です!最近どうっすか?」で乗り切れます。後は相手が勝手に喋ってくれます。
そしたら聞き役に徹しましょう。
そして合間合間で定型文をはさみます。
「流石ですね〜」「勉強になります」「それはお疲れ様でした」「グラスが空いてますね、次何飲みますか?」「私なら耐えれないですね〜」「私?私はぼちぼちってところですね、特筆するような事起きてないですね〜」
こんな感じでいくつか定型文を覚えておくと良いです。
職場の飲み会で真剣に議論する人はほぼいません。だいたいは「昨日は楽しかったな」で内容はほとんど忘れてます。内容なんてどうでもいいのです。
そんな無意味なことに時間とお金を割くのは嫌だと考える人も多いと思いますが、ここで聞き役に徹しているだけで普段の仕事も何故かスムーズに進んだりするので、通過儀礼と思って耐えましょう。
定型文は使える場面、使えない場面あるので、色んなシチュエーションを想定してイメトレするのがお勧めです。
距離感がわからない
仲良くなりたいあまり、つい踏み込んだ事を聞いてしまったり、いきなり二人で飲みに行こうとか誘ってしまったりして引かれたことはありませんか。
どんなにかわいい猫も突然ふところに飛び込んできたらびっくりして掴んでぽいっと投げてしまいます。
人間も一緒です。
あなたがどんなに魅力的な人間だろうと距離感は大事です。
まずは、簡単な会話から、仲良くなってきたら踏み込んだことにと順を追う必要があります。
しかしその順番がいまいち分からないのが我々、発達民。
私が見つけた法則は「聞かれたことは聞いても良い」「自分が聞かれたらちょっと嫌な気がすることは聞かない」この2つです。
ご出身はどこですか?と聞かれた場合、相手は地理に関心があり、自分も聞いて欲しいと思っている可能性が高いです。
自分の出身地を答えた後に、そちらは?と聞くだけで会話が成立します。
もし相手の出身地について知識があれば、〇〇な場所だよね?と会話を続けることができます。
こういった、お互いのパーソナリティな部分を共有しあってから、踏み込んだことを聞くことが出来るようになります。
いまいち踏み込むタイミングが掴めない時の攻略法は、こちらの秘密を打ち明けることです。
「ちょっと相談があるんやけど・・・」とこちらの踏み込んだ話を先にすることで、相手との距離感はぐっと縮まります。
注意点としては相手が口が軽いかもしれないので相談事の内容は周知されても構わないことにしましょう。
一対一ならなんとか。大人数だと黙る。
一対一なら会話のテンポもつかみやすく、話を振られるのは自分しかいないのでそれなりに返すことができるけど、大人数で話するとなるといつが自分が喋る番なのか、話の流れは今どうなっているのか、把握するだけで頭の容量を使ってしまいついていくことができず、結果黙り込んでしまうことってあると思います。
大人数で話する時は、特に気の利いた言葉を発する必要は無いと思います。
いくつかの定型文を覚えておいて、それをところどころで挟んでいくだけで話に参加している雰囲気が出ます。
「えっ、かわいい」「これ美味しいね」「楽しそう」「そうなんだー」「何処で買ったの?」「分かるわ〜」「私もそうだよ」
こんな感じの定型文を挟むだけで、なんとなく自分のテンポも周囲のテンポも乱すこと無く、なんとなく話の流れを把握することができます。
後は聞き役に徹することが良いと思います。
話を振られた時に備えて、話の流れだけは見失わないようにしましょう。
そこで少しズレたことを発しても問題ありません。
案外みんなそんなに気にしていないからです。
とにかく参加するぞという気合だけで十分です。
まとめ
会話は普通に生きていると避けて通ることが出来ないものだと思います。
無人島で1人で自給自足で生きていくなら別ですけど、そんな人でさえ(だからこそ?)インタビューとかが来てしまうと思います。
当たり前にあり、これだけ多くの人が居るからこそ、絶対的な正解はないと思います。少しのコツと気配りで下手なりにも嫌われない会話は出来るようになると思います。
まずは苦手意識を無くすことが、会話上達への第一歩だと思うので、少し意識して会話の練習をしてみてはいかがでしょうか。
とは言え、慣れないことは疲れます。
ほどほどに自分に合った距離感を掴むことも大事です。
といったところで今回はここまで。
ありがとうございました。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
