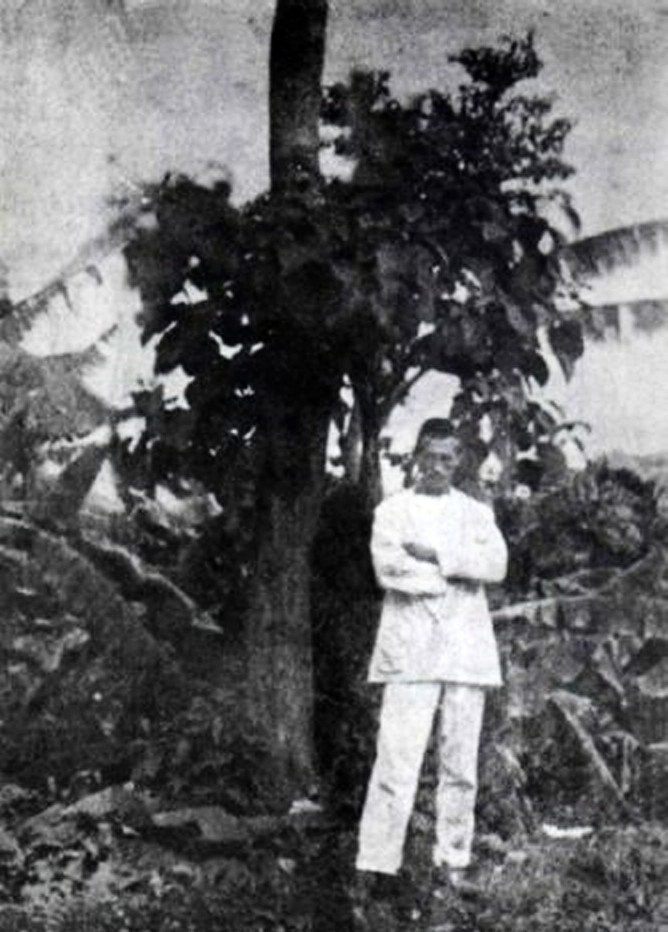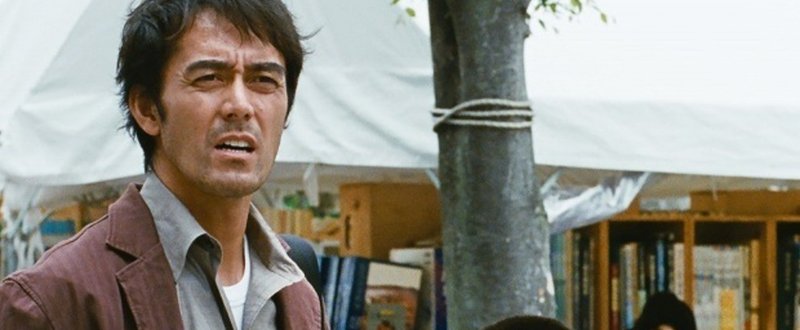#澁澤龍彦
シブサワがいたところ(五)
(五)追記「寺」
志多町の古いたばこ店と今はもうない古い町工場は、いずれも町の旧家である甲斐野さんによって営まれているものであった。そうなると、何となく気にかかってくるのが、そこからすぐ目と鼻の先の東明寺橋を渡って信号を右折すると見えてくる、新河岸川の対岸の宮元町にある真行寺のことである。真行寺は、浄土真宗大谷派の寺院であり、正式には至誠山成就院真行寺という。至誠が成就して真行となるとは、なかな
シブサワがいたところ(四)
(四)追記「工場」
坂の上のよろず屋のところから志多町の坂を下ってくると、東明寺の門前の参道とぶつかる角のところに古いたばこ店がある。よろず屋(梅原商店)の脇の壁には付近の商店の場所が(トタン板に)書き込まれた簡易的な案内地図が掲げられている。その地図を見てみると、古いタバコ店を営んでいるのが甲斐野さんであることが分かる。そして、その名前がキッカケとなって昔の記憶がいろいろと蘇ってきた。まず、あ
シブサワがいたところ(三)
(三)追記「石」
志多町の工場跡の敷地とその隣りの家のちょうど境界のあたりに古い境の石(らしきもの)が残されている。今では道路と歩道の端から20センチほど少し入ったところに立っているが、かつては道端のよく見える位置に何らかのことを示す標として立てられていたのであろう。裏面を見ると、それが明治10年代に立てられてものであることが刻字されている(石の下の方は工場を建てるときに土を盛ったのであろうか地
シブサワがいたところ(二)
(二)志多町探索
志多町の坂の上の店の工事が始まった(旧梅原菓子店(かどみせ)修理事業)。小さい頃から「坂上」とか「角店」とか単に「よろず屋」などと呼んでいた、佇まいからしてとても古くからあるに違いない、ちょうど坂を登ったところの角にある店が、鉄骨の足場などに囲まれてシート類で覆われていた。
いつの頃からか、車道に面した店の南側の前方部分はいつも大きく開け放たれてはいるものの、中はとても薄暗く、
シブサワがいたところ(一)
(一)志多町界隈と弁天横丁
先ほど、SNSで見かけた遊郭跡に関する記事を読んだりしていて、いくつか思い出したことがある。
遊郭の歴史は古く、古代より人の交通や交流のあるところには郭の原型ともいえる場所が存在した。それは、人間の歴史とともにあったものだといっても過言ではないだろう。また、特に江戸時代の風俗を描いた小説、芝居、落語、時代劇といった作品の中には、町人や武士たちの遊び場として頻繁に登場