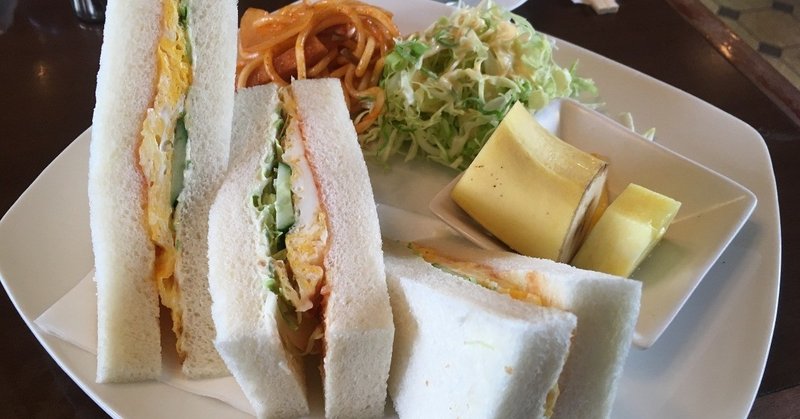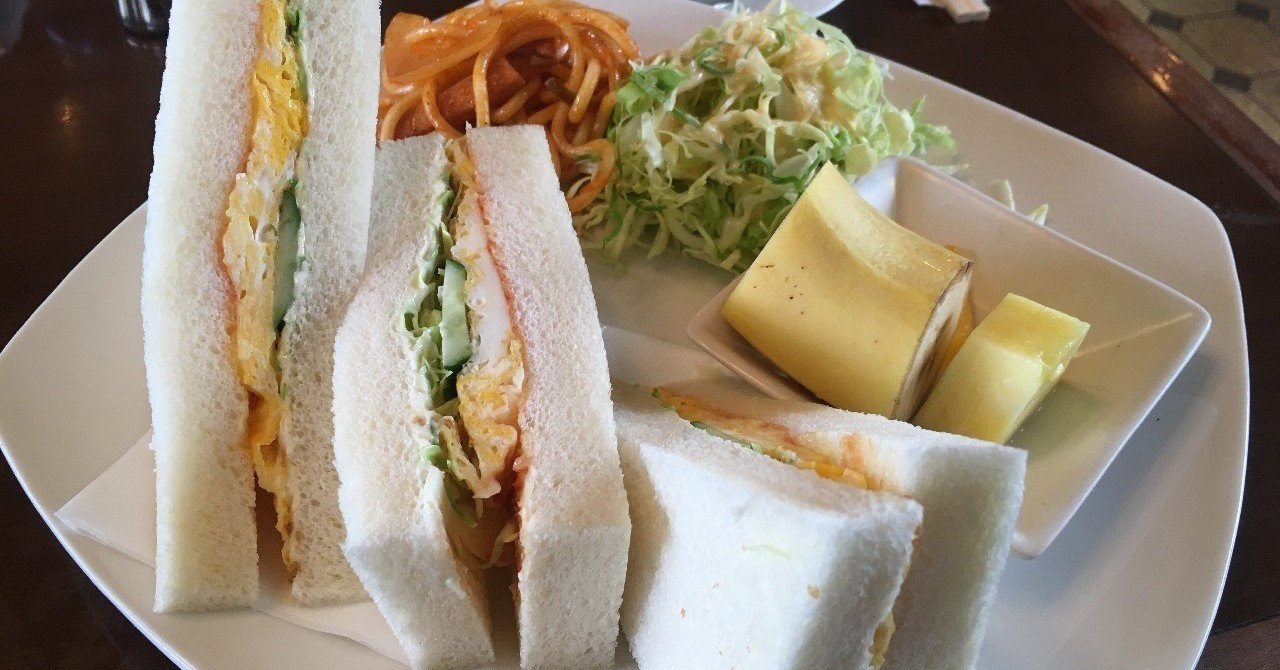最近の記事
- 固定された記事
- 固定された記事
マガジン
記事

書評=ガート・ビースタ(上野正道、藤井佳世、中村(新井)清二訳)『民主主義を学習する 教育・生涯学習・シティズンシップ』勁草書房、2014年。
キャリア教育や学び直しが昨今喧伝されていますし、学び直しや、生涯学習は人間が人間らしくなっていくためには、必要な契機と考えていますから、その内実を精査することが僕は必要だと考えています。 そうした新しい教育の在り方を根本的に考え直していきたいときに、まず紐解きたいのがガート・ビースタ(上野正道、藤井佳世、中村(新井)清二訳)『民主主義を学習する 教育・生涯学習・シティズンシップ』(勁草書房、2014年)ではないでしょうか。 「民主主義の学習とは、政治における主体化である。