
短編小説『ドロップ』
小説2作品目です。
縦読みと横読みのバージョンがあります。
読みやすい方で読んでください。
縦読みバージョン
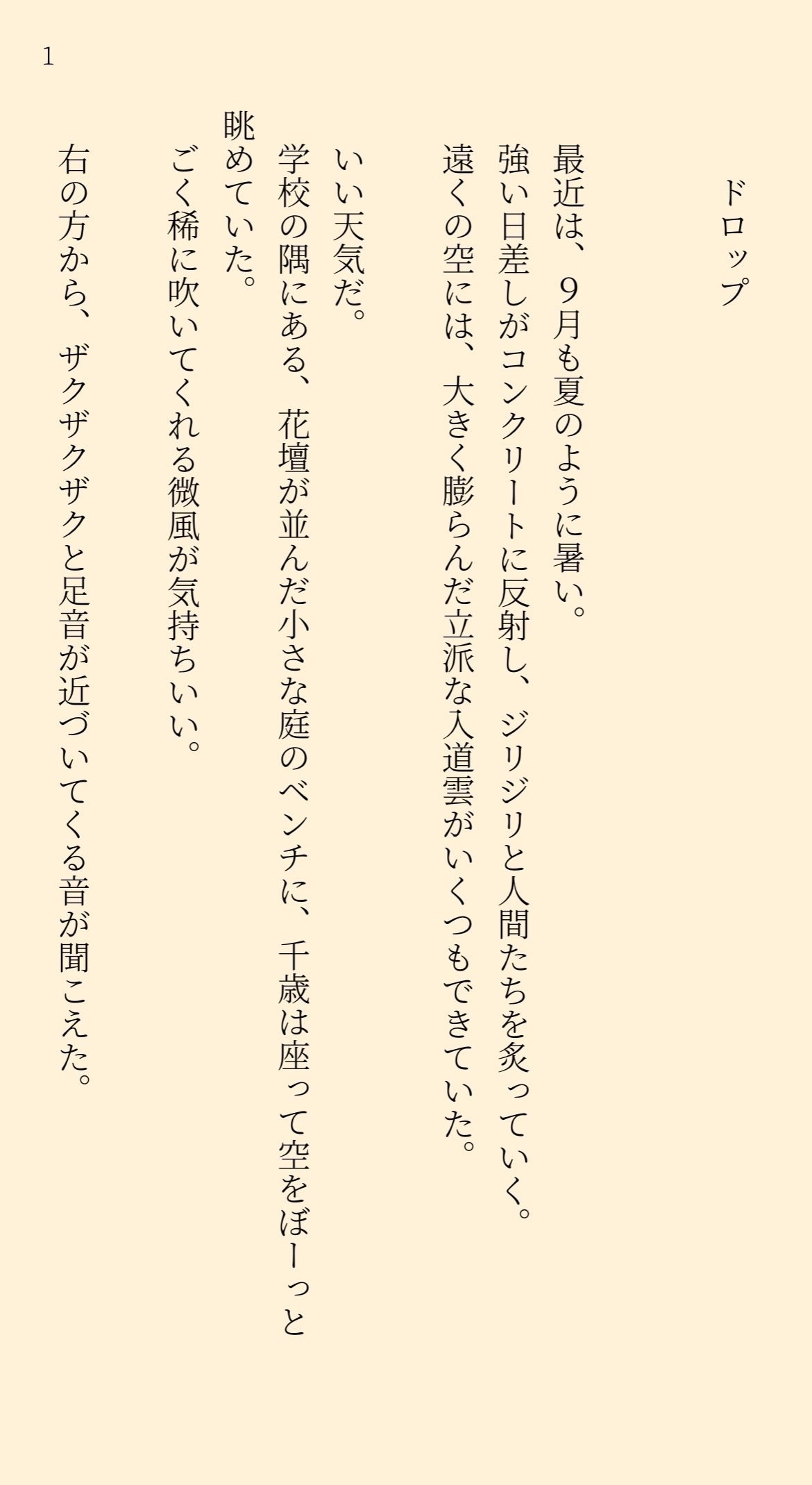
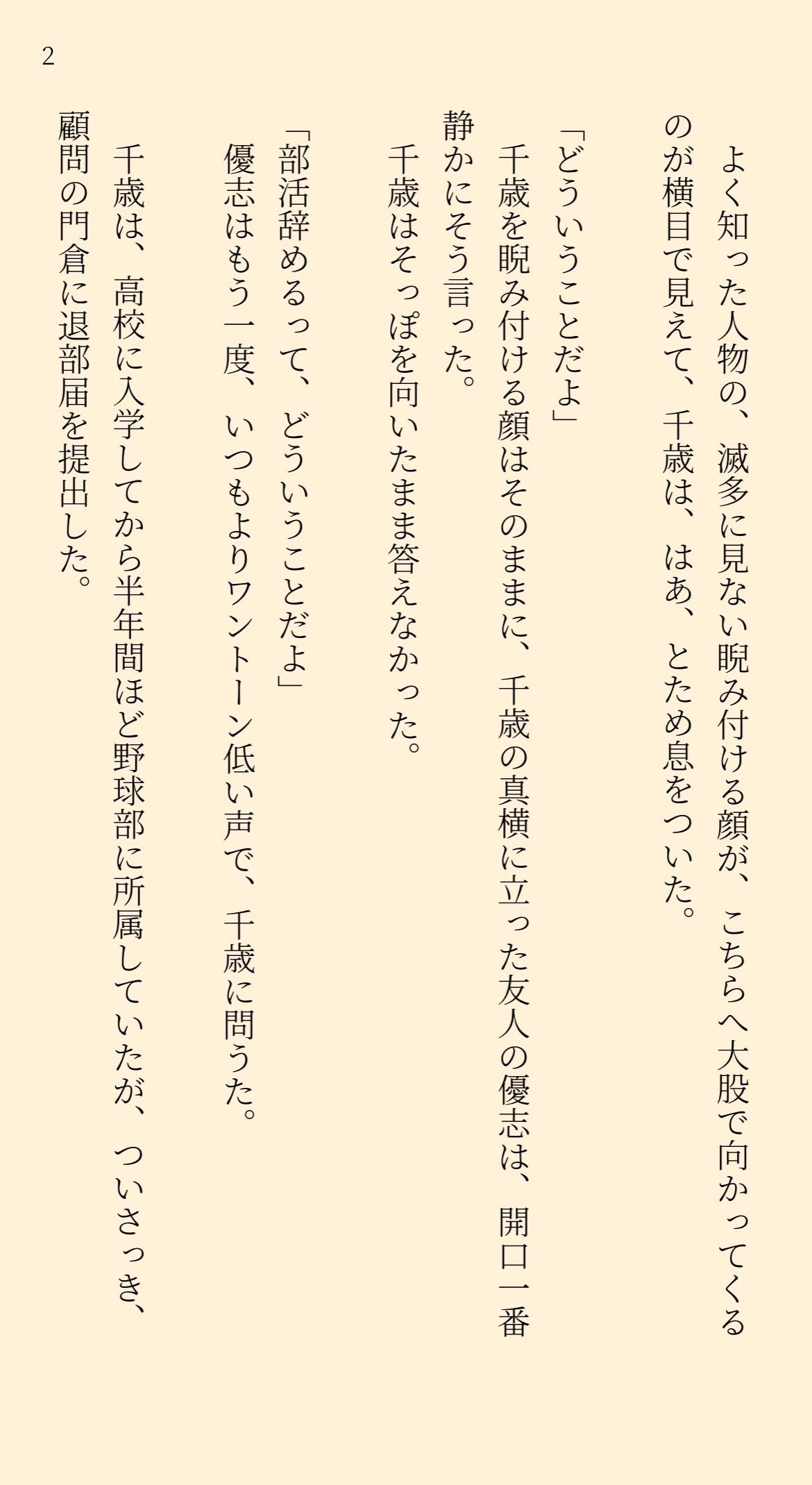



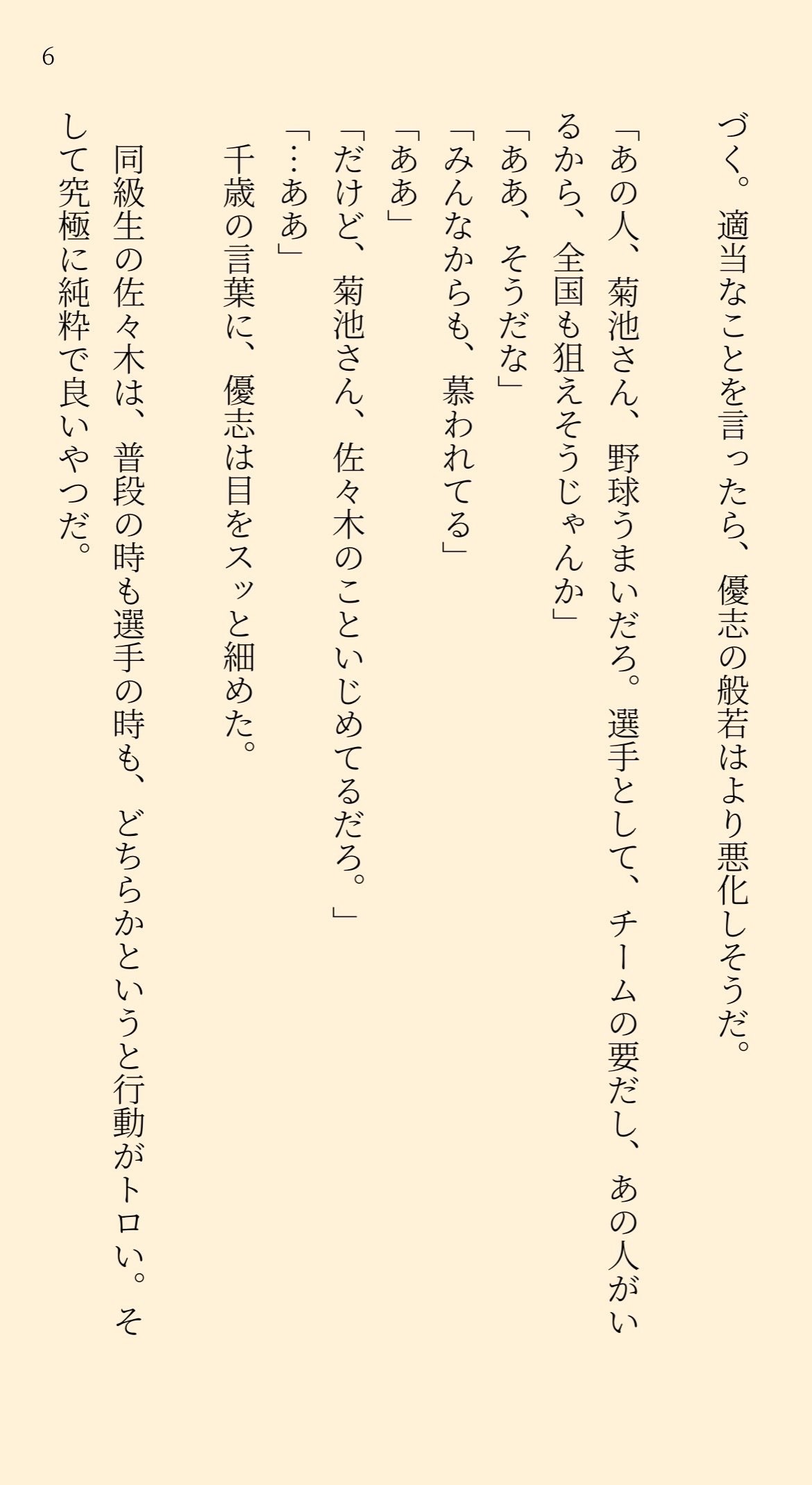
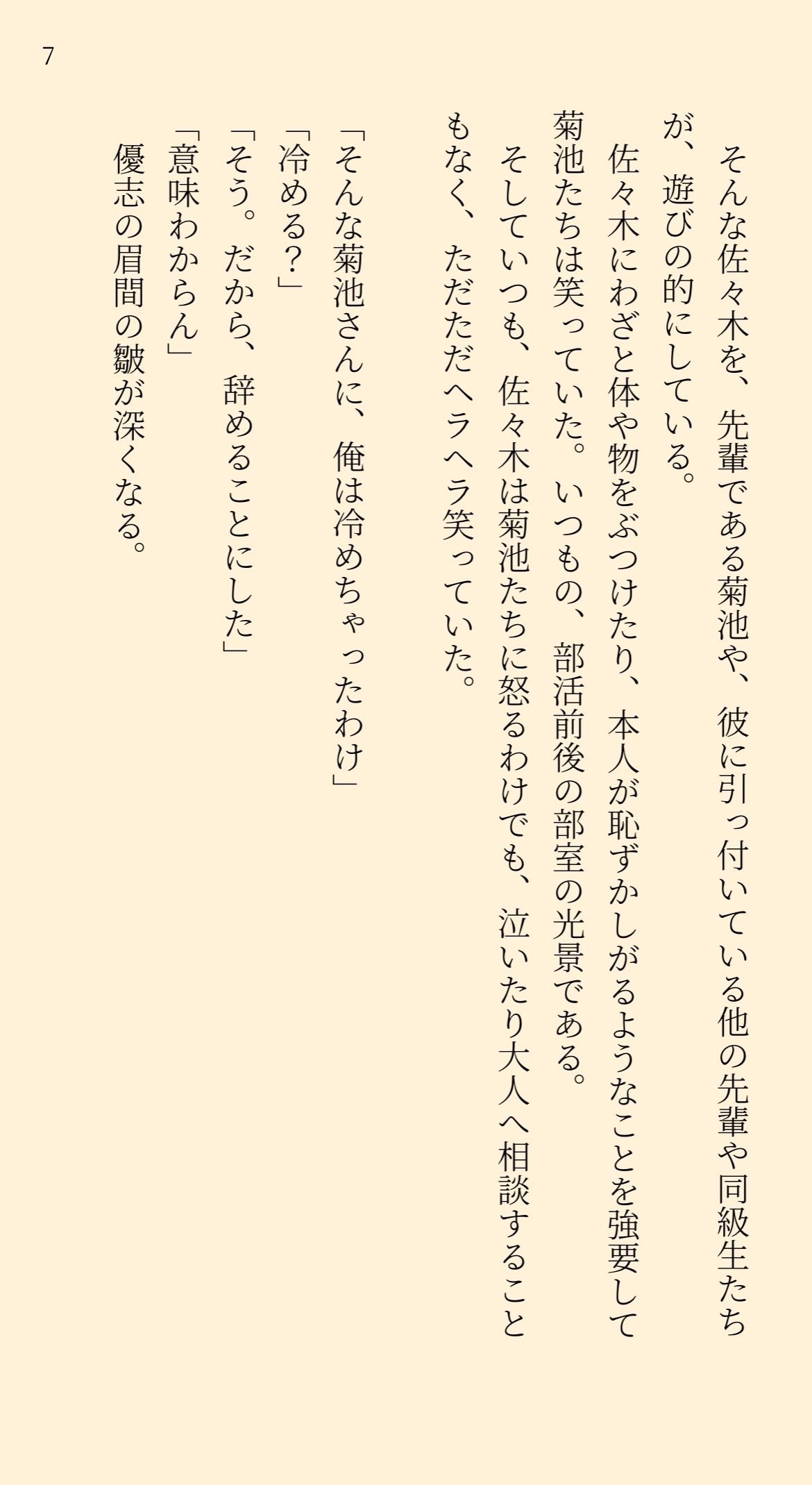











横読みバージョン
ドロップ
最近は、9月も夏のように暑い。
強い日差しがコンクリートに反射し、ジリジリと人間たちを炙っていく。
遠くの空には、大きく膨らんだ立派な入道雲がいくつもできていた。
いい天気だ。
学校の隅にある、花壇が並んだ小さな庭のベンチに、千歳は座って空をぼーっと眺めていた。
ごく稀に吹いてくれる微風が気持ちいい。
右の方から、ザクザクザクと足音が近づいてくる音が聞こえた。
よく知った人物の、滅多に見ない睨み付ける顔が、こちらへ大股で向かってくるのが横目で見えて、千歳は、はあ、とため息をついた。
「どういうことだよ」
千歳を睨み付ける顔はそのままに、千歳の真横に立った友人の優志は、開口一番静かにそう言った。
千歳はそっぽを向いたまま答えなかった。
「部活辞めるって、どういうことだよ」
優志はもう一度、いつもよりワントーン低い声で、千歳に問うた。
千歳は、高校に入学してから半年間ほど野球部に所属していたが、ついさっき、顧問の門倉に退部届を提出した。
今日から千歳は帰宅部メンバーである。
そのことを、幼馴染の優志をはじめ、今日まで誰にも伝えていなかった。
だから、優志の般若のような顔も、一応は想定済みである。
「辞めるって事前に言ってなかったから怒ってんの?」
千歳は優志の方は見ないで答えた。
「それもあるが、部活を辞める理由が思い当たらない」
なんで辞めるんだ、と呟く優志の言葉は、辞めるなんてありえないだろと主張している。
千歳は優志の方を見て、肩をすくめて答えた。
「もう無理だと思ったから。俺がこのまま、野球をやり続けられるほどの気持ちがなくなったの」
「はあ?意味わかんねぇ。俺たちずっと、ずっと野球やってきただろう!」
千歳も優志も、スポ少から中学、高校と、野球をやり続けてきた。野球をするのは楽しかったし、優志たちと過ごす時間を千歳は気に入っていた。
しかし、それも今日を持って終わりだ。自分で終わらせた。
「別に、長くやってようが関係ねえよ。俺にとって今が辞めどきだったの。それだけ」
2人はお互い睨み合って、しばらく沈黙が続いた。
優志とは幼稚園の時から一緒にいるが、怒っている顔を見たのは片手で数えられるほどしかない。
彫りが深く整った顔をしている優志の、滅多に見ない般若は、正直怖い。千歳は座っていて、優志は仁王立ちで立っているから、見下ろされていてもっと怖い。目を逸らしたくなるが、同じように睨み返して耐えた。
「…もしかして、菊池さんが原因か」
千歳を睨んだまま、優志は呟いた。
菊池とは、千歳たちの一つ上の先輩部員である。
運動神経も頭も良く、プレイヤーとしても周りから期待されている人物である。
そして、優志の言うとおり、千歳が部活を辞める理由の一つでもある。
「菊池さんに、何か言われたんか」
「いや、特に、何かされたって訳じゃない」
「じゃあ何だよ」
優志は理由を早く言えというように、千歳の言葉に被せてくる。
理由を言って、納得してくれる気はしないのだが、言わなければこのやりとりは終わらなそうだ。
それに、2人は長年の付き合いだから、千歳の誤魔化しにも、優志はちゃんと気づく。適当なことを言ったら、優志の般若はより悪化しそうだ。
「あの人、菊池さん、野球うまいだろ。選手として、チームの要だし、あの人がいるから、全国も狙えそうじゃんか」
「ああ、そうだな」
「みんなからも、慕われてる」
「ああ」
「だけど、菊池さん、佐々木のこといじめてるだろ。」
「…ああ」
千歳の言葉に、優志は目をスッと細めた。
同級生の佐々木は、普段の時も選手の時も、どちらかというと行動がトロい。そして究極に純粋で良いやつだ。
そんな佐々木を、先輩である菊池や、彼に引っ付いている他の先輩や同級生たちが、遊びの的にしている。
佐々木にわざと体や物をぶつけたり、本人が恥ずかしがるようなことを強要して菊池たちは笑っていた。いつもの、部活前後の部室の光景である。
そしていつも、佐々木は菊池たちに怒るわけでも、泣いたり大人へ相談することもなく、ただただヘラヘラ笑っていた。
「そんな菊池さんに、俺は冷めちゃったわけ」
「冷める?」
「そう。だから、辞めることにした」
「意味わからん」
優志の眉間の皺が深くなる。
「佐々木だけじゃなくて、チームメイトに対するあの人の態度が気に食わない」
だから辞める、と言うと、優志は、はあ、とため息をついた。
そして一歩前に出た優志は、千歳の胸ぐらを掴んだ。
「お前、馬鹿か!?」
鼻の先まで近づいた般若に、千歳は眉を顰めた。ギリギリと服を持ち上げられて苦しい。
「暴力はんたい」
「ふざけんなよ」
「ふざけてないし。ちゃんと考えた」
優志はもう一度、ふざけんなよと言った。
「あんなやつが原因で辞めるんか!?」
「あんなやつって、一応先輩だぞ」
場違いにもちょっと笑ってしまった。普段は礼儀正しい奴なのに。キレてもそこは変えるな。普段いい奴は、ちょっと悪い態度とっただけで好感度急降下なんだぞ。
「気をつけろよ」
「俺のことは今どうでもいいんだよ」
優志はギッと千歳を睨む。
「菊池さんは、確かに主力メンバーだけど、お前だって期待されてる選手じゃんか。それに、先輩たちは、来年の夏で部活辞めるんだぞ。俺たちはそれからあと一年あるじゃんか」
お前の実力で今辞めるなんて勿体なさすぎるだろ、と優志は言う。友人から褒められて、素直に嬉しい。
「わはは、直接褒められると照れる」
「ふざけんな。俺は本気で言ってるんだぞ」
「わかってるって。さんきゅ」
さっきまでの般若顔とは少し違う、真面目な表情の優志の言葉は、いつも千歳に自信を与えてくれる。
優志は、昔からずっと一緒に野球をやってきた奴だ。
あと2年、優志と野球をやれない寂しさみたいなものは確かにある。だけど。
「俺のレベルが高いとか低いとか、そうじゃなくて」
優志の腕を掴んで、身体を離す。
「俺みたいな奴が、チームにいちゃダメだと思って」
「は?」
優志は、ポカンと間抜けな顔をした。
「だから、いくら実力がある奴だろうが、期待されていようが、今のチームに、俺みたいな奴はいない方が良い」
今、菊池をはじめ、なかなかに有力な選手が集まっている。今年は叶わなかったが、来年は全国への切符も期待されているし、菊池をメインとして、側から見れば、チームは上手くまとまっているように見える。
だが、目標に向かって燃えているチームの中に、いつの間にか千歳は入ることができなくなっていた。
決定的だったのは、この夏、チームが3回戦で敗退した時だ。
菊池は、泣いていた。
勝ち気で負けず嫌い、だから努力も人一倍する菊池は、試合に負けて、人目も気にせず泣いていた。男泣きってやつだ。
泣いている菊池に、監督たちが菊池の肩に腕を回して慰めていた。
「悔しいな、頑張ったな。次だ。次は勝つぞ」と言って。
周りの先輩たちも同級生たちも、その光景を見て納得していた。
菊池は頑張った。
菊池はまだ2年だ。来年は勝てる。菊池がいるチームならやってくれる、と。
千歳はその光景を、なんだかテレビに映るドラマのような、遠い話のように見ていた。
佐々木のことなど、チームにとっては、とても些細なことなのだ。いつもの、どこにでもある、ワンコインで遊べるゲーセンみたいに、お手軽な遊びの一つなのだ。
千歳にとっても、それは毎日見る光景の一つでしかない。
佐々木と菊池たちを横目に、今日のメニューや、自分が修正したい動き、優志と新たにやりたい筋トレのことなどを、優志と話しながらロッカーの前で着替える。いつものことだ。
野球は好きだ。優志と一緒にプレイするのも好きだ。その延長で、優勝したいとか、全国へ行きたいとか、チームが盛り上がっている輪の中に千歳もいた。
でも、その中心部まで入り込むことはできなかった。
繰り返される、湿った匂いのする小さな部屋の中の日常に、千歳の気持ちは徐々に冷めていった。
「今のチームは、菊池さんがいるから、良いとこまで行けそうだろ。菊池さんは選手としてもうまいし、チームを引っ張ってく力がある。周りも期待してる。
だから、チームは、まとまりが大事じゃんか。
どんなに菊池さんが影で佐々木をいじめていようが、性格が捻じ曲がっていようが、選手として優秀なら、それでいい。」
「でも、俺は、冷めちゃったんだよ。」
平気なフリはできた。無感情にもなれた。隣にいる優志だって、他の奴らだってそうだ。
気にしなければいい。
でも、千歳は想像してしまったのだ。
「いつか、菊池さんをやっちゃうかもって」
「は?殺す?」
「ちっげぇよ。ただ、なんか、いつか俺が菊池さんを、ボコボコに?とか、恥かかせるとか、そういうことをしちゃいそうだなって思ったんだよ」
「何だよガキかよ」
「そーだよガキだ。でも、それを、試合中に思ったら、最悪だろ」
そんなこと思ってる奴のいるチームは、団結してるとはいえない。
そいつ1人のせいで、ミスが生まれるかもしれない。
勝てる試合も勝てなくなる。
考えすぎだ、と優志は言う。
「みんながみんな、綺麗な心な訳じゃないだろ。逆に気持ち悪ぃよ。千歳みたいな考えのやつだって、1人や2人や3人」
「そりゃ、いるだろうけどさ。少なくとも、上には、行けないだろ。そんなチーム」
「さあ、どうかな」
はぁー、と優志は息を吐いて天を仰いだ。
それからしばらく空を見つめていた優志は、ゆっくり千歳の方をみて、その額にデコピンをかました。
「痛ったっ! うわ、痛え! いきなりなにすんだよ!」
額を抑えて呻く千歳に、ふん、と息を吐いて優志は言った。
「一年、トレーニング怠けんなよ。」
「はあ?だから、もう辞めるんだって」
「部活を、だろ。野球を辞める訳じゃない。どうせお前のことだから、野球をそんな簡単に辞められる訳ない。俺が練習ない日はお前のとこ行くから、トレーニング付き合え。」
怠けてたらすぐわかるからな。
ビシッと人差し指を千歳の目の前に突き出し、眉間の皺を深くした顔で優志は言った。
「来年、絶対部活に戻らせるからな!」
「いや、無茶言うなって。そんなの、他の奴らが許さねえ」
「関係ない。葉山も松岡も鈴木も、お前の実力を認めてるんだ。誰も文句いわねぇ」
「どうだか」
妙に熱くなり出した優志は、何を言っても聞かないことを知っている。
「結局辞める理由も納得出来ねぇし。プレーは威勢いいくせに思考は相変わらずめんどくせえな」
「すみませんねぇ、めんどくさくて」
「本当にな。昔から変わんねえから諦めたわ」
「俺のことをよくご存知で」
「当たり前だろ。何年付き合ってると思ってんだ」
ふん、と息を吐いた優志は、帰るぞと言って背中を見せた。
「帰るって、今日も部活あるだろ」
「お前がふざけたことするから門倉に言って休みもらったわ」
「俺のせいかよ」
「そうだよ。お詫びに駅前のゲーセン付き合え」
金はお前持ちなーと言って、優志はスタスタ歩き始めてしまった。
「は?ふざけんなよこの前マック奢ったろ」
「記憶にございませーん」
いつものようにふざけた会話をしながら、2人は通学路へ向かった。
終
読んでいただきありがとうございました!
この記事が参加している募集
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
