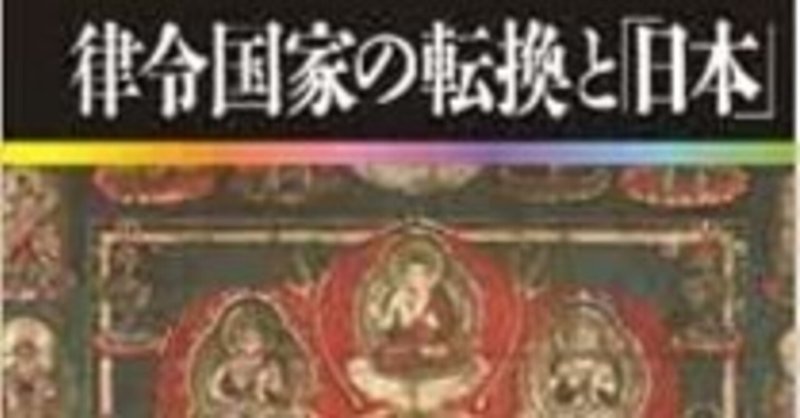
【書評】坂上康俊「日本の歴史05 律令国家の転換と『日本』」(講談社学術文庫)
本巻が対象にしているのは、八世紀の末から十世紀の初めまで、中心は九世紀、つまり初期平安時代である。この時期について、一般的にはどのようなイメージが抱かれているだろうか。あまり明確に像を結べない人が大半ではないかと思う。
本書は、筆者自身が「イメージが薄い」と述べる平安時代初期を対象としています。
桓武天皇、最澄と空海といった有名な人物もいますが、嵯峨天皇や仁明天皇、藤原冬嗣、藤原良房など、やや地味な登場人物が多いです。
とはいえ、「やや親しみが薄い」平安時代初期のトピックを過不足なく網羅した入門書の役割を果たしていると思います。印象に残るエピソードもいくつかあります。
「怨霊」の誕生
平安時代の初期、政争に巻き込まれて悲運の最期を遂げる皇族・貴族が相次ぎました。
桓武天皇の弟だった早良親王をはじめ、藤原吉子・伊予親王の母子、藤原仲成と薬子の兄弟、橘逸勢などです。
早良親王の事件の後に皇太子となった桓武天皇の息子(平城天皇)は、幼少から病弱でした。桓武は親王の祟りであると考え、その魂に謝罪し慰めようとしました。
不幸な最期を遂げた人々が、祟りをなす「怨霊」になるとして慰霊しようとする発想は、平安時代初期に登場したのです。
ある皇族の数奇な運命
810年、嵯峨天皇と平城上皇の間の権力闘争である薬子の変が起きました。平城上皇の息子で皇太子だった高岳(たかおか)親王は、平城側が敗れるとともに太子を廃立されます。
政治の表舞台を去った親王は、出家して真如と名乗り、仏に仕える道を選びます。
真如は、奈良の大仏が地震で損傷した際の復興を指導するなどの功績を残しました。さらに、彼は60歳を超えてから唐に渡って仏法を学ぶことを朝廷に願い出ました。
唐に渡った真如は、唐での学びに満足せず、天竺(インド)渡航を志願します。海路で天竺を目指した真如が帰還することはありませんでした。一説には、現在のシンガポールのあたりで亡くなったともいわれます。
皇族という生まれでありながら、遠い異国で亡くなったという人はあまり思いつきません(近代であれば、日清戦争中に台湾で戦病死した北白川宮能久親王や、フランスで事故死した北白川宮成久王がいます)。非常に特異な運命をたどった皇族といえます。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
