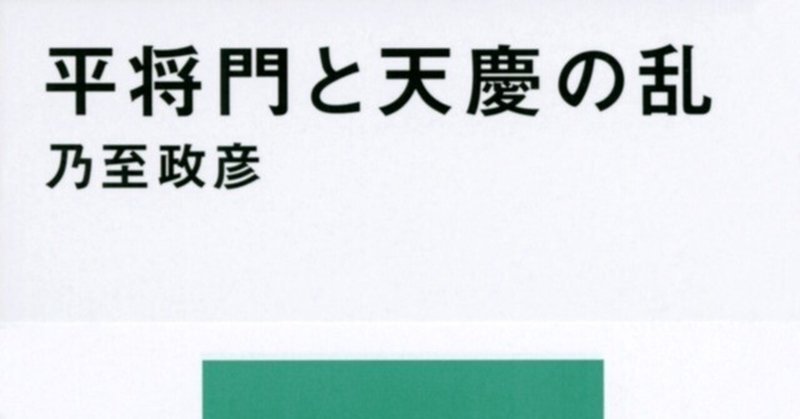
【書評】乃至政彦『平将門と天慶の乱』(講談社現代新書)
平安時代中期、関東地方で中央に反乱を起こした「逆賊」として知られる平将門。東京・大手町に残る首塚や怨霊伝説で有名です。
一方、彼の生涯や人物像について知っている人はあまり多くないと思います。本書では、良質史料である『将門記』を中心に、平将門の実像に迫っています。
造られた怨霊伝説
本書の序章は、著名な「将門の祟り」を検証しています。
戦後、GHQが首塚(将門塚)を壊して駐車場にしようとしたところ、事故が起きて死者が出た…といった伝説はよく知られています。
しかし、そうした怪異譚の出所を検証していくと興味深いことがわかります。本来、将門は神田明神の祭神として親しまれながらも、祟り神として畏怖される存在ではありませんでした。禍々しい「将門の祟り」の物語は、なんと昭和末期以降に流布したものだといいます。
将門はなぜ「逆賊」となったか
広辞苑で「平将門」の項目を引くと、反乱に至る過程はこう書かれています。
(前略)伯父国香を殺して近国を侵し、939年(天慶2年)居館を下総猿島に建て、文武百官を置き、自ら新皇と称し関東に威を振るったが、平貞盛・藤原秀郷に討たれた。
本書を読む前の私の認識もこんなものでした。すなわち、伯父との抗争が反乱の始まりであると認識していました。
しかし、実際の過程はそう単純ではありません。将門と伯父たちとの戦いが始まったのが935年ですが、937年時点では、「坂東で乱を起こしている者を将門に追捕させるように」という太政官符が諸国に発せられていました。
将門は若い頃京都で過ごし、朝廷の実力者藤原忠平ともパイプを持っていました。当初は将門が「官軍」で、反逆のつもりはなかったのです。
しかし将門は、関東各地の紛争に武力介入するうち、成り行きのように常陸国の国府を攻撃・制圧することになりました。将門自身も意図しないうちに後戻りできなくなり、下野・上野の国府も制圧に至ります。
反逆に至る過程は、まるでボタンの掛け違いのようです。個人的には、本書を読んでの最大の発見でした。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
