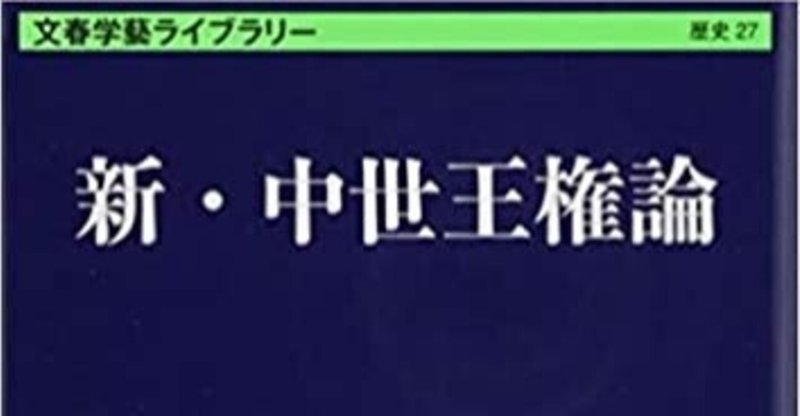
【書評】本郷和人「新・中世王権論」(文春学芸ライブラリー)
日本中世史を専門とする著者による、「鎌倉の王権」をテーマとした本である。書名は「中世」であるが、最後に後醍醐天皇が出てくるくらいで、鎌倉時代の議論がメインである。
鎌倉時代の日本の支配体制は、どのように理解すればいいのか。幕府と朝廷の関係については、研究者の間でも見解が分かれている。
1.権門体制論
天皇(朝廷)が中心となり、政治をつかさどる公家、軍事をつかさどる武家、宗教をつかさどる寺社が並び立つというとらえ方。公家・武家・寺社の「権門」は、それぞれを補完し合う。
2.東国国家論
京都にあって西国を所轄する朝廷と、鎌倉にあって東国を所轄する幕府の、二つの王権が並び立つというとらえ方。幕府は、朝廷から自立していたということになる。
筆者は後者の立場で、鋭い考察で東国国家論を深化させつつ、権門体制論への批判を展開する。
とりわけ、鎌倉幕府の内紛である霜月騒動への評価が面白い。日本史教科書などを見ると単なる内ゲバにしか見えない。しかし、霜月騒動の内実は、「御家人の既得権を守ろうとする平頼綱」vs「幕府を日本全体の統治者に脱皮させようとする安達泰盛」の対立であったという。後者は前者に敗れ、鎌倉幕府が「日本の統治者」に進化していくことはなかった。
中世史は複雑で敷居が高く感じるが、いろいろな掘り下げができる分野だと感じる。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
