
学年最下位から早稲田大学現役合格した歌手が実践した勉強法&仕事術②
超効果的な暗記術14選
今夜は勉強法&仕事術の後編をお届けします。すべて公開しますので、ぜひご活用くださいね!
そもそもぼくも受験生のとき、最初は勉強に行き詰まっていました。なんで入試などあるんだろうと思ったこともあります。行きたい学校に行かせてくれたらいいのに、とも思いました。しかし、入試に至るまでの受験勉強で人間として大きく成長でき、未来が開けました。頑張って掴み取った未来だからこそ、その先の日々もチャレンジして生きることができました。
ぜひ、受験を成長のチャンスにしてチャレンジし、そして夢を掴み取ってください。君の夢が叶うように、今日も努力が実る方法をお伝えします。
では、早速いってみましょう!

昔のように暗記力を問う試験は減る傾向にあるかもしれません。それでも、勉強には覚えることが付き物です。例えば語学でも、まずは単語を覚えた上で、その単語の組み合わせである熟語を覚えることができ、それらが土台となり長文読解やリスニングができるようになるんです。古文や漢文でも同じことですね。
ここで、受験勉強に役立ち、今でも活用している暗記術を書きます。
まずは、大前提として、
・意味、流れとともに覚える
ただ意味もなく暗記するのは面白くもなく興味も湧かず、覚えにくいです。なぜそうなのかの理由や、どのようにしてそうなったのかの歴史の流れなどを知って覚えると、覚えやすくなります。「〜だから〜なんだ」という自分なりでも良いので理由付けをすると思い出しやすいですよ。
興味のあるものは覚えやすいということを利用して、
・好きになってみる
もしかしたら苦手な科目かもしれません。好きとは言えないかもしれません。でもまずは好きだと思い込んでみる。何か楽しい部分、興味を持てる箇所を入口にして取り組んでみる。そのうちに少しずつその科目が楽しくなりますよ。単なる暗記対象に性格、人格を想定して興味を持つということもできます。
対象に愛を注げばその対象も自分の人生に愛を返してくれるのは法則のような気がします。壁を押したら壁から押し返されます。地面に立っているのは地面を押し、地面から押し返されているからです。嫌えば嫌われますし、好きになれば好かれます。人も物も勉強も同じくだと思います。好きな芸能人やスポーツ選手など、趣味ならすぐに覚えられると思います。それを置き換えてみる作戦です。
ちなみにぼくは、覚えにくい数字を、好きな野球選手の背番号やそのイメージに結び付けて覚えたりします。すると、単なる数字だったものがその選手の性格やプレイスタイルを理由付けとして、「〜だから〜なんだ」という記憶の復活に役立ちます。

また、覚えやすいタイミングとしては
・知りたい時、気になった時に調べる
自分が知りたくて調べたことならすぐ覚えられますし、なかなか忘れません。「今覚えたら一生忘れない!」という自発的に気になる瞬間を逃さず行動してください。
さて、覚え方の基本ですが、
・書く
・声に出す
・語呂合わせ
これは書く動作や、声にを出す、声を聴くといった、行動、視覚、聴覚などと結びついて記憶に定着しやすいと思われます。歌にしてしまっても良いかもしれません。
ちょうど覚えやすい語呂合わせがあればそれも良いと思います。数字や語学などに向いていますね。
合わせ技で、覚えたい箇所を喋って、それを録音して聴くというのも効果的です。声に出すためには頭の中で整理しますし、録音したらいつでも聴いてまた暗記できます。
歌のライブでも必ずライブレコーディングをして後から聴くことで発見があったり学びがあります。
そして、ここからは脳の機能を活かしたスペシャルな暗記術ですが、
・覚えるべき箇所を見ないで答えてみる
覚えるまでは見ないと答えられませんが、敢えて、早い段階で見ないで答えたり書いたり読んだりしてみる。
それによって、脳が「これは暗記しないといけない内容なんだ」と理解するそうで、その後にその箇所を脳が全力で暗記しようとするため暗記がはかどります。
時間帯も重要です。
・夜寝る前と朝起きた後に復習する
これは、眠っている間に脳が必要な記憶と不必要な記憶を整理して、記憶を定着させていることを利用した方法です。
寝る前に復習することで、これは必要な記憶だと脳に伝え、朝起きてから復習することでその記憶を絶対的なものにしていきます。
ちなみに、脳は眠っている間が一番活発だそうです。その次は無意識に掃除をしたりお風呂に入っているとき。
確かに、ぼくも眠っている時や掃除をしている時に歌が浮かぶことが多いです。
君の無意識の脳を信頼して、眠る前と起きた後に復習しましょう!
これを3日も繰り返せば、かなり記憶は定着します。

今でも沢山の歌やMCを覚えたり、ピアノを暗譜したり、時には英語やヴェトナム語、ドイツ語、中国語で歌ったりしますが、この方法で暗記しています。
脳の機能からも説明しましたが、単純な例え話として、一ヶ月に一回しか会わない人と、毎晩、毎朝通学などで会う人では、どちらの顔を覚えやすいですか?答えは明白ですね。覚えたい内容とも顔馴染みさんになりましょう!
このようにして、見なくても答えられるところまでいくと、大きなメリットがあります!それは、いつでもどこでも復習ができるようになっちゃうんです!
移動中やお風呂などでも復習できるため、かなり時間が有効活用できるようになります。隙間時間も活かせば時間が足りないことはありませんよ♪
そして、もう一つのスペシャルな暗記術があります。
・倍速で答えられることは確実に再現できる
つまり、暗記したことを早口で言ってみるのです。早口で答えられることは、ふつうのスピードではかなり余裕で記憶を再現して答えられます。
ぼくも歌を覚えたら一人リハーサルでは3倍速くらいで歌ったり喋ったりします。すると、本番の普通のスピードではかなり余裕で歌詞や話が出てきます。

ちなみに、これはかなり昔にタレントのタモリさんがテレビで紹介されていた暗記術だったと思いますが、瞬間記憶の裏技では
・自分の体のパーツに割り振って順番に覚える
というのがあります。瞬間的に覚えなきゃいけない物事や人の名前などを、自分の頭、おでこ、鼻、口、あご、などと順番に上から下に割り振って、その場所に紐付けて覚えるという方法です。これは長期的な受験勉強というより、初めてその場で会った人の名前などを複数人覚えるなど、短期的な暗記に向いているかもしれませんが、紹介しておきます。

以上のようにして、覚えたら、その記憶を更に強固なものにする方法があります。それは、
・覚えた内容を人に教えて頭の中を整理する
人に教えるためには、本当に理解している必要があります。自ずと頭の中が整理されて、記憶も更に定着します。その時、あやふやな箇所があれば復習したらいいだけですし、課題の再発見にもなります。人に教えられる時点で、その内容に関しては先生であり、プロレベルまで上がっています。もはや大得意な内容が増えましたね!
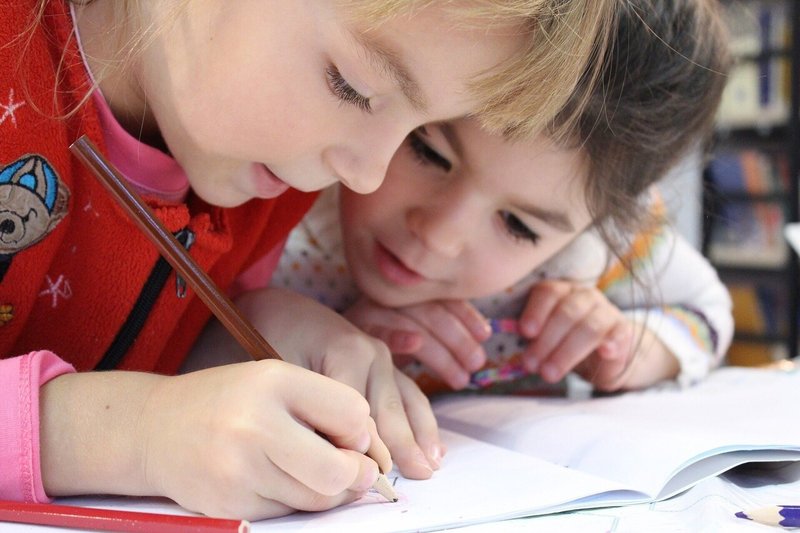
さて、どうしてもうまくいかないときは、
・行き詰まったら場所を変える、休む
景色が変わるとその景色の情報、音、匂いなどと記憶が結びつきやすく、脳への新しい刺激が記憶の効率を上げます。
また、移動自体も活用できます。
・歩いたり運動しながら暗記
これは、体を動かすことで血流が促進されて、当然ながら脳にも血液が行き酸素が運ばれますので、脳の機能が促進されて覚えやすくなります。最初に書いたように行動自体と記憶も結び付きやすいです。(危ないので歩いているときはスマホや教科書を見ないでね!)
旅行をしてリフレッシュできたりアイデアが浮かんだことはありませんか?ぼくも旅先で歌が生まれることは多いです。旅行をすると幸せホルモンであるセロトニンが分泌されて、ストレス源であるコルチゾールが減少してリラックスできるそうです。
スポーツ合宿や勉強合宿が短期間で効果が上がるのも納得ですね。
遠出ができなくても、勉強する場所を変えてみるプチ旅行学習をやってみませんか?

がんばってくれている脳に燃料となる栄養もあげましょうね!
・脳と心の栄養補給
糖分が足りないと脳が能力を発揮できませんので、栄養もしっかり摂りましょう。
また、心にも栄養を与えましょう!
ここまで頑張ったら自分にご褒美をあげる、という方法は有効です。そのワクワク感を持続しながら勉強にも良い影響が出ます。益々、勉強が楽しくなります。
改めてまとめます。
・意味、流れとともに覚える
・好きになってみる
・知りたい時、気になった時に調べる
・書く
・声に出す
・語呂合わせ
・覚えるべき箇所を見ないで答えてみる
・夜寝る前と朝起きた後に復習する
・倍速で答えられることは確実に再現できる
・自分の体のパーツに割り振って順番に覚える
・覚えた内容を人に教えて頭の中を整理する
・行き詰まったら場所を変える、休む
・歩いたり運動しながら暗記
・脳と心の栄養補給
以上、参考にしてみてくださいね!
一生役立つ要約力
それって、つまりこういうことですよね?
という要約力は、社会で仕事をするなかでもかなり重要なスキルになってきます。
相手が何を伝えたいかをまとめられる要約力は、相手が何を求めているかを悟る洞察力、直感力、共感力にも結び付きます。
なにかのプロということは、なにかの達人であり、その分野において、対価を払ってでも他者(社会)から頼り(必要)にされるということです。
それは、何を求められているかを理解し、最高の答えを提供できるということです。

また、逆にこちらが何かを相手に伝えたい時に、ダラダラと喋っていては何が言いたいかがうまく伝わりません。まずは自分が何を必要としているか、伝えたいことを要約して要点を伝えることで、円滑なコミュニケーションが成り立ちます。
このように、社会でも重要なスキルとなる要約力ですが、勉強においてもとても効果的な能力になります。
この問題の出題者は、つまりこういうことを問いたいんだな?という要約力、洞察力。これはすべての科目で役立ちます。
この要約力を養えるのは、まさに国語です。筆者の伝えたいことを要約せよ、と言った問題があると思いますが、まさにそれです。語学が変わっても英文などの長文読解にも役立ちます。
ぜひ、要点を理解する考え方を磨いてみてください。問題を出題しているのも人間ですから、要点に集中していけば、何を聞かれているかも見えてきて、自ずと答えも導かれてきます。
出題予想の仕方
出題する側も人間ですから、毎年やみくもに出題しているわけではないかもしれません。例えば、世界的なあの事件や戦いから何周年、という年は、もしかしたら、設問に出題されるかもしれません。あくまで予想になりますが、あれが出るかも?といった予想を持ちながら予習することは、試験に対しても積極的な姿勢になり、ただ受け身であるより、前向きな気持ちになれると思います。本番で役立つという意識を持つだけで俄然意欲が変わり、効果が上がります。
人生のどんな場面でも、受け身ではなくこちらに主導権がある前向きな姿勢を意識するだけで、アクティブになれます。自分の人生の主役は自分自身だという強い気持ちは勇気になります。ぼくも受験の時は出題が予想される箇所を改めて復習しておきました。

山勘の確率を上げる方法
それでも、どうしても解らない問題が出たとき、勘で答えるしかないかもしれません。
しかし、その勘の正解率を上げる方法もあります!
例えば、次の四つの中から正解を選べ、という設問の答えが解らないとき。その全てが正解に思えるのか?それとも、明らかに違うものが二つは明確なのか?
それなら、明らかに違うものを外した2つのどちらかを勘で選べば、正解率は4分の1ではなく、2分の1でかなり上昇します。
難関私大の受験問題などになると、明らかに習ったことがない難題もあります。しかし、イジワル問題だとびびることなくよくよく見てみると、選ぶ選択肢の中で明らかに違うものがあり、除外していくと答えが解るようにできていたりします。結局聞かれていることは、知っているべき内容が理解できているかどうかなのです。
自分も、難題で有名な早稲田大学の世界史の受験では、明らかに習ったことがない問題がありました。その設問の選択肢には、「歴史上の人物(この人は必ず教科書に出る)の親戚(ふぁっ!?)の実家は〜の農場を経営していた。」みたいな内容があり、そんな親戚の存在なんか絶対聞いたことありませんでした。他の受験生はここまでマニアックな内容を勉強してきたのか!?と一瞬焦りました。
ですが、選択肢を冷静に見ると、その親戚の叔父さん(?)のことは知らなくても、時代背景を理解していればそのタイミングでその内容の農場が経営されているのはおかしいと思い、これを除外し、最後は残された選択肢から勘で選びました。受験が終わり、早速キャンパスの外で大手予備校が配っていた模範解答を見たら、結果的にその設問は正解していました。その一点で合否が分かれるほどの人数が受験していましたので、冷静に対処できて助かりました。

最高のお守りは自分の足跡
最後に、試験会場で最高のお守りになってくれるものは、自分の努力の足跡が刻まれたノートやテキストです。
先に書いたように、どこが自力で解けて、どこは時間をかけて理解したと分かるようなしるしを見ながら、記憶を復習しつつ、安心感にも包まれます。
また、直前に見直した内容がそのまま出題された!なんていうラッキーも、頑張った人には得てして起きるものなんです。受験直前の最後の数分まで大切にしてくださいね。

これだけ頑張ってきたんだから絶対大丈夫だ!と思える時、試験会場はリラックスした君のホームグラウンドになります。試験開始直前の最後の見直しが終わったら、残りの時間は目を閉じて深呼吸をするなどリラックスして、自分のゾーンに入りましょう。すると集中力が高まります。深呼吸をすると体の隅々や脳に酸素が行き渡るため力が発揮できます。
両手の指を合わせてクルクル回す体操や、こめかみなど気持ちいいと感じるところを軽く押してマッサージするなども良いかもしれませんね。君がゾーンに入れる方法を、普段から試してみてください。それがいわゆる、君だけの“勝利のルーティン”になります。いつもと同じ行動に集中することで不安や緊張も消え、心地良い高揚感が残り、能力を発揮できます。
あとは自分を信じて、皆に感謝して、のびのびと努力の成果を答案用紙に書き込むだけです。
ちなみにぼくは、初めての東京だったため、試験日より前に会場までの電車の乗り継ぎなどを本番通りに試しました。あらゆるイレギュラーを想定して、余裕を持てたら安心です。当日の食事などの調達場所なども確認しておきました。手作りのおにぎり屋で数種類のおにぎりを買い、コンビニでホットのお茶とチョコ(糖分)を買いました。それを試験の合間に食べました。寒い時期ですし温かい飲み物は安心できます。これはあくまでぼくの例なので、君に合うプランを実践してみてください。朝ご飯はしっかり食べて行ってくださいね!

普段の勉強や練習では、逆に自分を疑って何度も確かめる。緊張したり体調や天候などが仮に万全じゃなくても解けるか、あらゆるケースを想定して模試や練習を繰り返してみる。練習こそ本番の緊張感と集中度で挑むからこそ、本番ではリラックスして力を発揮できます。それだけ頑張った自分を誰かに見てもらえる、力試しができる、それはとても幸せなことじゃないですか。喜びいっぱいで表現してください。
ちなみに、ぼくはこれだけ頑張ったんだから大丈夫だと思ってテキストやノートを全部北九州の自宅に置いてから東京に受験に行ってしまい、直前で恐ろしく不安になりました。
その時は姉のファインプレーで宿に郵送してもらえて本当に助かりました。絶対に置いていかないでください。
慣れ親しんだ書きやすいペンや使いやすい消しゴム、見やすい腕時計など、安心できるアイテムも会場に連れていってあげてくださいね。
100点を取る方法
それでは最後に、100点を取る方法をお教えします!
それは...
解答欄を全部埋めることです!
え?
当たり前?
そうなんです。
空欄があったら絶対に100点は取れません。
例え解らない問題があっても、全て埋めて提出しましょう!
そうすれば、1点でも2点でも加点できる可能性が出てきます。
空欄では1点も入りません。
それと、最後まで解答をどちらか迷った設問があった場合。
ぼくなら最初に書いた解答で出します。
最後にギリギリで書き直して、もし最初のままが正解だったら悔やまれますから。まあ、これはぼく個人の話なので柔軟に対応してください。
さて、勉強とは自分一人でやるべきものです。場面場面では友達と教え合うなども効果があるかもしれませんが、最初から最後まで戦い抜くのは君自身です。他者とペースを合わせることもなく、合わせてもらうこともありません。君の人生を歩めるのは君しかいません。君の代わりは世界中どこにもいません。君の本物は君だけです。
勉強は一人でやるものですが、決して孤独ではありません。君を応援してくれている人がいます。見守ってくれている人がいます。信じてくれている人がいます。そして、君の人生の未来で君との出会いを待っている人がいます。


共に夢に向かい進んでいきましょう!
最後はゆっくり寝て、良い状態でリラックスして本番へ臨んでください。君の目標が達成され、夢の花が開くことを心から応援しています!

質問や、こんな方法もおすすめだよということがあれば、コメントください。
ちなみに、自分が通っていた高校は、早稲田大学に合格する生徒は10年に一人いるかいないかと当時の先生に言われました。ですから、今の成績がどうかとか、環境がどうかよりも、やはり本人の意思とそれが実る正しい努力の方法が重要だし、それがあれば夢は実現できるということが伝えたくて長々と書かせていただきました。
そして、当時も後輩にその気持ちと勉強法を伝えたところ、なんと一つ下の学年からも一人、二年連続で早稲田大学に合格しました。
最後に、そのときにぼくが書いたちょうど20年前(!)の文章が残っていましたので、よかったら参考にしてみてくださいね♪






よろしければサポートをお願いします! コロナによりライブ中心の音楽活動は難しくなりました。 しかし変革のチャンスにして、レコーディング、撮影、配信機材を整えています。いただいたサポートを更なる向上と持続に活かし、ますます有意義であなたにお楽しみいただけるnote発信を続けます。
