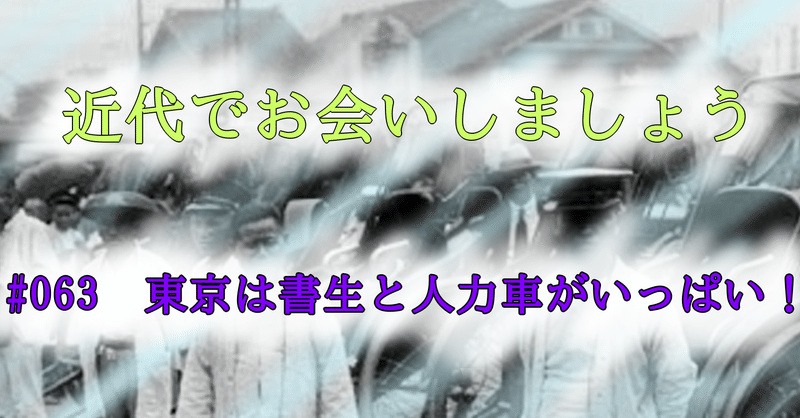
#063 東京は書生と人力車がいっぱい!
坪内逍遥の『当世書生気質』の第一回の続きを読んでいきたいと思います。
十人集[ヨ]れば十色[トイロ]なる、心づくしや陸奥人[ミチノクビト]も、慾あればこそ都路[ミヤコジ]へ、栄利もとめて集ひ来る、富も才智も輻湊[フクソウ]の、大都会とて四方より、入[イリ]こむ人もさまざまなる、中にも別[ワケ]て数多きは、人力車夫と学生なり。おのおのその数六万とは、七年[ナナトセ]以前の推測計算方[オシアテカンジョウ]。今はそれにも超えたるべし。到る処[トコロ]に車夫[クルマヤ]あり、赴く所に学生あり。彼処[カシコ]に下宿所[ドコ]の招牌[カンバン]あれば、此方[コナタ]に人力屋の行燈[アンドン]あり。横町[ヨコチョウ]に英学の私塾あれば、十字街[ヨツツジ]に客待[キャクマチ]の人車[ジンリキ]あり。失敬の挨拶は、ごっさいの掛声に和[カ]し、日和下駄の痕は、人車の轍[ワダチ]にまじはる。実[ゲ]にすさまじき書生の流行、またおそろしき車の繁昌。
なかなか前口上が終わりませんね!w
人力車は、記録上では、1870(明治4)年に、東京府が和泉要助、高山幸助、鈴木徳次郎の3名に発明者として製造と販売を許可したところから始まります。同じ年に人力車の運転免許証の発行が始まっています。
これによって、1872(明治6)年までに、東京市内に1万台あった駕籠は完全に姿を消し、人力車は日本の代表的な公共輸送機関になりました。
当時の東京府がまとめた統計によりますと、1876(明治10)年には東京府内で2万5038台あったと記録されています。明治20年代には、人力車夫は4万人近くいたといいます。事情は、現代のタクシーと変わらないようですね!w
ただ、当時の人力車は、木で作った車輪の外周に鉄板を巻いた鉄輪であったため、乗り心地は良くなかったでしょうね…。ゴム輪になったのは、1908(明治42)年頃からで、チューブ入りタイヤが普及し始めたのは、1911(明治45)年頃からだと言われています。
これしかしながら腕づくにて、金も名誉[ホマレ]も意の如くに得らるるからの奮発出精、まことに芽出たきことなれども、もしこの数万[スマン]の書生輩[ハイ]が、皆大学者となりたらむには、広くもあらぬ日本国[オオミクニ]は、学者で鼻をつくなるべく、また人力夫[ジンリキヤ]がどれもどれも、しこたま顧客[オキャク]を得たらむには、我緊要[ワガタイセツ]なる生産資本も、無為[ムダ]に半額[ナカバ]は費えつべし。されども乗る客尠[スクナ]くして、手を空[ムナシ]うする不得銭[アブレ]多く、また郷関[キョウカン]をたちでる折、学もし成らずば死すともなど、いうたその口で藤八五門[トウハチゴモン]、うつて変つた身持放埓[ミモチホウラツ]、卒業するもの稀なるから、この容体[ヨウダイ]にて続かむには、なほ百年や二百年は、途中で学者にあひたしこ、額合[ハチアワ]せする心配なく、先[マズ]安心とはいふものから、その当人の身に取[トリ]ては、遺憾千万残念至極、国家[ミクニ]のためにはあつたらしき、御損耗[ゴソンモウ]とぞ思はれける。
藤八五門とは、文化・文政(1804~1830)のころ、江戸で流行った行商の薬売りの事です。基本的に二人一組で歩き、一人が「藤八」と呼ぶと、もう一人が「五文」と応じて、ともに「奇妙」と合唱して、一粒5文の薬を売っていたそうです。
この時点で、まだ主人公すら登場してきませんね…w
というところで、また明日、近代でお会いしましょう!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
