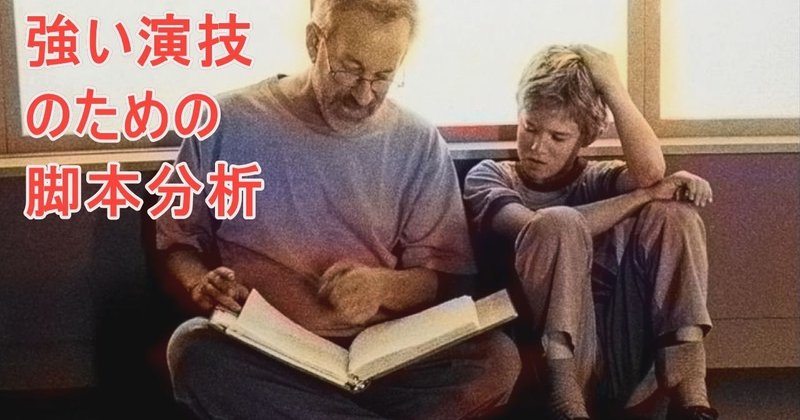
今こそ学んでほしい。アカデミー賞レベルの演技を可能にする【脚本の読み方】
【家にいながら自分のペースで疑似体験できる濃厚演技ワークショップを、期間限定で20,000円→8,980円。さらに動画3本+PDF2本の特典付き。全国の俳優はもちろん監督・脚本家にも!】
それにしても気が気でない日々が続きますね。
また以前のように安心して舞台に立ったり撮影したり、稽古やレッスンに足を運べる日はいつ戻ってくるのか……。
家で自主練習を試みようにも、住宅の事情で大きい声が出せなかったり動き回るスペースがなかったり。そもそも一人で演技の練習をするのに向いた題材・教材が出回っていなかったり。そんな問題に突き当たることも多いはず。
俳優としてこの時期やるべきこと・やっておけることはあるのだろうか?
この期間、この状況を、このまま本当に演劇文化、映像文化の危機にしてしまってはならない。そうした思いから様々な草の根活動も始まりつつあるなか、自分も出来ることがあるはずだと思って今回このノート公開に踏み切りました。
これから掲載するのは、演技ワークショップ「アクターズ・ジャーニー」のなかで提供してきた【脚本分析のやり方】についてまとめたものです。

突然ですが皆さんは「脚本分析」と聞くとどんな印象をお持ちでしょうか?
「堅苦しいイメージ」「理屈っぽくて小難しい」「分析という意味がよくわからない、普通に読むのと何が違うのか」「自由に、感性豊かに、伸び伸びやるのが演劇であるはずだ」
……そんな声が聞こえてくる気がします。
あるいはもう似たことを学ばれてきた方もけっこういるはず。すでに演技における脚本分析の重要性・必要性を理解し、自習・自力で分析に挑戦し続けてきたという方々。
そういう方々にまたお聞きしたいです。独力で満足・納得のいく分析結果をコンスタントに得られる状態になれているでしょうか?
脚本分析・台本分析、いわゆる俳優としてのホンの読み方には普通の読書とはまるきり違ったコツ・専門的なアプローチというものが必要です。
「セリフさえ頭に入れていけば、あとは監督や演出家の言う通り動いていればいい」……このような感覚が通用する現場がどれくらい残っているのかはわかりませんが、少なくとも「そういうレベルの俳優ではありたくない」という意欲をお持ちの方は、ぜひ続きを読み進めて頂きたいと思います。

「アクターズ・ジャーニー」ワークショップは、当初の発端が『イヴァナ・チャバックの演技術』(白水社)の自主練習会として2016年に始まったものでした。
現在世界でトップクラスの俳優たちが必ず学んでいる演技理論に、スタニスラフスキーの後期システムというものがあります。
上述の本もその方法に基づいたもので、これらの演技術では大前提として俳優自身が脚本を徹底的に読みこなし、演技のためにに必要な専門性の高い分析=ブレイクダウンを施すところまで自力でやっておく必要があります。
ところがワークショップを始めてほどなく浮き彫りになったのが、この「演技以前にホンを読むところで俳優たちがどれほど悪戦苦闘・孤軍奮闘しているか」ということでした。
それもそのはず、「脚本・台本の読み方」を専門的に学べる機会が日本の俳優にとって極めて少ない。しかもそれ以前に、かねてより問題視されている日本人の読解力の低さや「主体的に読む」とはどういう意味なのかの認識不足など、多くのハンデが「ホンと俳優」の間に横たわっているのです。
たとえば皆さんは、ご自身の「読解力」についてどのくらい自信があったりなかったりするでしょう。
それ以前に、そもそも「読解力」て何だ? とお思いになりませんか?
日本の教育者たちは日本人の読解力向上に対してほとんど「お手上げ」状態です。「読解力は教えられる性質のものではない」という結論にすら一部では至っているらしいのです。
しかしそんなことはありません。読解力を鍛え直すことは実はシンプルです。
アクターズ・ジャーニーではこうした「読むという行為の超基本・大前提」を見つめ直し、日本人のほとんどが自覚すらしてない「頭の混乱」をスッキリ整理させた段階からようやく脚本分析といったプロの読み方が可能になるのだということを示します。
「脚本分析という謳い文句のWSも他にありましたが、一つの脚本に関しての説明で終了したり「大量の脚本を読みなさい」と言われただけで他に指導もなく何も学べませんでした。そんな学べる場所も正しく教えてくれる人もなかった脚本分析を、このWSで始めて理論的に教わる事が出来、これまでにない成長を得られました」
「やはりここまで分析しなければキャラクターのことは分からないですし、参加するたびに奥深さを痛感します。とくに行動を起こす根本となる衝動を追求していくという考え方は新しくて、すごく納得できると感じました」
「脚本を渡された時、何からはじめれば良いか、どんな準備をするのか、分析のやり方と全体の流れが分かって慌てなくなった。読み合わせに行ったら演出の人とスムーズにキャラクターについて話すことができ、演技について提案もすることができた」

自分の演技を演出家や監督任せにしていてはとうてい飛び抜けることが出来ないのは日本も同じですが、その競争が何十倍も激しい海外では俳優自身が主体的・独創的に自分の演技を磨き上げていくために、脚本を読みこなすのは必須のこと。日本人よりはるかに多くの脚本を読み込み「演技のために何を脚本から見い出さなければならないか」を熟知しているのが、欧米の俳優たちです。
しかしそんな彼らですら実は「じゃあどんな読み方をすれば効果的にその答えを導きだせるのか」については各自の我流に依っており、苦労している場合がほとんどなのです。多くの演技指南では「あなたは俳優として脚本からこれこれを探し出さなければならない」で終わってしまっているのが実際のところだからです。

今回お届けする脚本分析術は、「そのためにどんな切り口で脚本を紐解いていけばいいのか」を他に類を見ないわかりやすさでつまびらかにしています。
この後に掲載する本編で、理論とケーススタディの二部構成にわたってこれ以上ないほど懇切丁寧にお伝えします。また第二部は実際の課題作に自分で取り組みながら対話形式で分析を進めていきますので、あたかもワークショップを疑似体験するつもりで臨んで頂けるようになっています。

というわけで前紹介が長引きましたが、いよいよ本題である脚本分析術の内容に入っていきたいと思います。
この後の目次以降の稿はこれまでワークショップ内でPDFとして配布していた文章を今回のnote向けに大幅に加筆修正したものです。以前「お試し版」を手に入れたことのある方にとっても頭から新しい内容として読めるはずです。
もともとは紙媒体で読んで貰うことを前提に書いてきたテキストであるため、分量からして一般的な書籍一冊相当となる長文です。そこで同一内容のPDFファイルを特典として用意しました。PCやスマホの画面で全文読むのは辛い、紙でじっくり読みたいといった方は目次から特典のPDF版に飛んで、ファイルを印刷したうえでご利用ください。
学習内容の性質上、一読して内容を把握したら終わり、というものではなく、課題作品を実際に自分で分析しながら読み進める形になります。本気で自分の力を鍛えるために取り組むなら、すべてを終えるのに少なくとも一ヶ月程度はかかるものと推定します。ぜひそのつもりで、ワークショップに疑似参加している感覚で高密度な技術習得を心がけて頂ければと思います。
今回さらに特典として3つの動画とPDFを用意しました。
本noteを購入し、SNSなどでご友人・俳優仲間などにこの記事をシェアして頂けた方に、特典として昨年行った「脚本分析講座2019」の内容の数々をプレゼントします。
まずは脚本家であれば知らない者はないジョゼフ・キャンベルの ”ヒーローズ・ジャーニー” を俳優向けにアレンジして講座内で解説した箇所をお届けします。人類が神話という形で残し伝えてきた壮大な「人生の秘密」。これを知っていれば分析作業がはかどることはもちろん、演技にも「神話レベルの魂」が宿ること間違いなし。脚本家や監督らとの会話も弾むかも?

またこの内容を図解し講座の際に配布した特製「英雄の旅マップ」もPDFにて添付します。ここでしか得られない、ググっても出てこない知見満載なので、ぜひ活用して頂ければと思います。
続いて2005年のリメイク版『キング・コング』(ピーター・ジャクソン監督版)を題材に、シンボル/象徴を通して物語を眺めるアプローチを紹介。この見方は難易度が高いものの、やはり俳優のみならずあらゆる表現者にとって非常に有益なメタファーが得られることを意図してお話します。

最後に言わずと知れた日本映画の金字塔、『七人の侍』から菊千代と勘兵衛のキャラクター分析を解説した動画。先の2本で解説したヒーローズ・ジャーニーのモデルやシンボリックな見方を当てはめることでようやく解きほぐせる人物像などについてじっくり取り上げます。

いずれも本編テキストの内容を学んで貰ったうえでさらに上乗せとなる情報が満載かつ多くの方に目から鱗の内容ばかり。テキストをやり終えた後からでもいいですし、あるいはちょっと先につまみ観してみるのでも構いません。もれなくこの特典を入手して頂ければと思います。
提供するすべてのコンテンツを読み観終えた後と前とでは、脚本はもちろんこれから仕事でも趣味でも出会うあらゆる作品に対する見方が天と地ほど違ってくるはずです。
自動車の運転免許証を獲得するまでには一定の期間と金額、教習訓練や試験勉強の負荷を伴います。しかしいざマイカーを手に入れ乗り始めた途端、どれほど世界が広がり、人生の自由度・可能性が高まるか。実際それを経験したことのある方ならご納得いただけるでしょう。
「プロとしての読み方の技術」を獲得するのもまさにそれと同じ、あるいはそれ以上の経験です。
その観点からも、また僕が過去に学んできた海外の教材やワークショップなどの料金相場から言っても、これまで行ってきた平均20,000円台での僕のクラスは本来妥当な金額より一桁安いと言って過言でありませんでしたが、今回はそこからさらにこの時世を鑑みての【期間限定割引き】となってます。
「今回みたく家から出られない状況にでもならなかったら、絶対こんな勉強しなかったはず……」
後に振り返ったとき、そう思ってもらえれば御の字です。
今まで通りの生活が続いていたなら気づくこともなかったであろう世界に気づいてはじめて、人は本当に成長できるのかもしれない。
この世界的な危機に周りと一緒に飲み込まれるか。逆にこれを飛躍の機会へと変えるか。その選択肢は決して誰からも失われていません。
ぜひあなたの「選択」で、この逆境をチャンスに変えて下さい。
それではお待たせしました。ここからいよいよ『強い演技のための脚本分析:最新note版』本編となります。
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
アクターズ・ジャーニー特別資料
“強い演技”のための脚本分析
これは演技ワークショップ「アクターズ・ジャーニー」のなかで提供されている脚本分析=スクリプト・ブレイクダウンの実践的・具体的な進め方をまとめたものです。俳優が自らの演技を強く魅力的なものにするために、脚本をどう読みこなしていけばいいのかについてまとめてあります。「強い」という形容詞は英語圏の演技コーチらが使う“Strong Choice”という言葉に倣っています。それは観る側にも演じる側にもチャレンジングでアピール力があり、ありきたりでない選択のことです。表現者である我々は、その創作過程の試行錯誤における選択において常に「強さ」というものを意識して、必ずより「強い」ものを選ぶようにしなさいという教えです。これに関しては以後に紹介していく具体的事例のなかでも感覚を掴んでいって頂ければと思います。
第一部:基盤となる考え
脚本分析の方法は多岐に渡り、作品によって毎回様々に異なる道のりを辿ることになります。「脚本」の分析とは言っても、その本質は描かれている人物の「人間性」に対してあたかも顕微鏡で見るかのように迫っていく行為であり、それはまるで探偵が犯人の人物像や動機に肉薄していくプロセスのようでもあります。たったひとつの手がかりの有無ですべてがひっくり返ります。脚本、ひいては「物語」という特別な構造を持った世界の中から特定のキャラクターに注目し、俳優がその人物に「成り代わる」ことが出来るまでに彼または彼女を知るにためは、どういった方法で取り組んでいけばいいのか。ここに強制されるべきルールはありませんが、暗い道のりを明るく照らしてくれるツール、様々な場面で確実に使え、時に必要不可欠でもある考え方は存在しています。それは数学で図形の問題を解く際に用いる「補助線」のようなものです。第一部ではこれらを順を追って紹介していきますが、まずは大前提としての演技理論:なぜ俳優がかくも自らの力で脚本を読み解かなければならないのか。それを行わないうちは演技をできる状態にすらなれないとはどういうことなのか、について説明します。
1:前提にある演技理論
・感情を「出そう」としてはいけない
俳優になりたての頃、演技を始めたばかりの頃を思い出して下さい。新しく手にした脚本・台本を一読したあと、いざ自分の役の演じ方を具体的にイメージし始める段階。そのときどんなことを考えていたでしょうか。何を頭のなかで問いかけていたでしょう。多くの場合、そこでなされてきたであろうものは「この台詞でこめるべき感情はなんだろう?」「このト書きはどういうニュアンスで演じるべきだろう?」といった類の自問自答だったのではないでしょうか。果たしてこれが演技を効果的にしていくために有効かどうか? というのが演劇史における積年の問題でした。その結論は今からおよそ1世紀近く前に出されています。その頃からすでに、目の肥えた観客に対して真実味や説得力のある「本物」の演技をしたいと望むならば、先にあげたような脚本への問いかけはやめなくてはならないというのが答えでした。現代の日本のテレビや映画・舞台等で見かける演技の大多数は、実はもう100年も遅れた水準なのだということになります。スタニスラフスキーの後期理論が日本語に訳されて伝わってきたのがごく最近のことなので、いまだ様々なスクールや劇団などの教習の場で教えられている内容にそうした以前の悪習が根強く残っている傾向があります。まずはその基本から説明します。
・バーバルとノンバーバル、随意と不随意
バーバルとは言語による、ノンバーバルとは言語によらない・非言語の、という意味です。脚本に書かれている台詞やト書き。これは文字通り言葉を使って書かれているのでバーバルです。いっぽう実際に演じるうえで求められる様々な感情の表出、声のトーンや表情、姿勢、動作のメリハリに至るまで、演技を真に演技たらしめる要素のほとんどはノンバーバルに属しています。日頃のコミュニケーションにおいて、情報の伝わっている比率はバーバルである言葉の内容が7%に対し、その他のあらゆるノンバーバル情報が93%と言われています。「愛してる」と誰かが言うとき、満面の笑みで高らかに謳い上げるか、打ちひしがれた無表情で押し殺した声を発するのかで、伝わる情報は全く違います。実際にはもっと精緻で微細なニュアンスの移り変わりを、我々は互いに読み取り伝え合っています。これは観客が画面越しに俳優を観るときにも例外ではありません。
そこで映画やドラマの撮影でも舞台の演出でも、俳優が指示される事柄の大部分はノンバーバルについてであるということになります。バーバルの領域においては台詞を書いてある通りに言えたかどうかくらいでしかないので、さして問題になりません。噛んだり間違えたりが多いときに「ちゃんと覚えろよ」と言われる程度のことです。本題は、台詞なら台詞を「どのように言う」のかであり、ト書きならその行為を「どのように行う」のかです。ここが俳優と監督・演出家の間においても、ときに俳優同士においても意思疎通の難しく、また面白いところでもあり、得てして演技の内容が評価されるにあたっての焦点となる部分です。
ここで問題になってくるのは、そのノンバーバルを意識的に模倣しようとすると「嘘」だとばれる、ということです。つまりト書きに「怒り狂って」「はにかんで」などと書かれているとき、あるいは「その台詞はもっと感謝の思いをこめて」などと指示されたとき、うっかりそうしたニュアンスをそのまま「出そう」「見せよう」とすると、その作為性・わざとらしさが必ず見破られるということなのです。どんなに器用にそれをこなしても、その器用さが評価されることこそあれど、観客の心を真に打つまでには至りません。
あなたは器用な俳優として評価されたいですか? それとも純粋に観客の心を打ち抜きたいですか?
これが新しい演技システムを学ぶにあたってのひとつの区分けとなります。実際には、どちらも必要なことです。現場でこれらの両方ともが必要になります。しかし偉大な俳優であるためには、確実に選択肢として後者が出来る状態を目指し達成しておいて頂きたいですし、多くの監督・演出家が、後者を可能としている人達とこそ共に創作を行いたいと願っています。ではノンバーバルの表情やトーン、ニュアンスを「器用に模倣」するの「ではない」、よりリアルで真に迫った演技とはどういうものなのか。
もともとノンバーバル領域における声や表情といった身体の運動・その表出は、日常においてほぼすべてが不随意に起こっています。ここで随意と不随意の違いを覚えておいて下さい。随意とは我々が意識的にコントロールできることを指し、不随意はそれができないことを意味します。
とても恥ずかしい思いをして顔が真っ赤になる。これは意図して制御できずに起こります。これが不随意です。思い出せるくらい近い過去に日常で本当に泣いた経験のある方は、そのとき自分の顔の歪みや呼吸の律動(横隔膜の動き)、そのほか全身の生体反応、溢れ出てくる涙や鼻水などが、いかにコントロール不能なところから生じてきたかを観察的に思い出してみて下さい。あるいは緊張した状態で何かを話さなくてはならないときに下唇が小さく震えたりしたことはないでしょうか。その震えを意識的に再現できるかどうかやってみて下さい。単純に「笑う」という行為ひとつ取っても、本当におかしくて笑いだしてしまう時に生じている無数の身体反射を、演技で意図して、随意で再現することはほぼ不可能です。
先に説明したノンバーバル領域93%の情報の中で、観客は俳優の身体表出が随意によって意図して作られているものなのか、不随意に、俳優自身にとってもコントロールの手放された状況で生じているものなのかを、的確に見抜きます。
そこで演劇においては長らく続いていた「模倣」に近いアプローチから離れ、どうにかして不随意の身体反応を引き出すべくイメージや記憶を喚起するといったテクニックが使われ始めました。いわゆる「メソード」と日本で呼ばれることの多いアプローチであり、これはスタニスラフスキーの初期の理論がアメリカで独自に発展したものでした。現実にこれが役立つ局面はいまも少なくはありません。しかしこれ「しか」知らずに満足していると、早晩限界を迎えることになります。なぜならその不随意のノンバーバル表出を「再現しようと意図している」とき、それゆえに演技者の内的状態が、キャラクターが実際そこで経験しているはずの内的状態と異なっていれば、観客はそのことにも気づくからです。
・キャラクターの内面をどこまで再現するか
例えば「試合に負けて悔し涙を流すシーン」を演じることになったとします。ここで最悪なのは、とにかく随意的に自分の意志で顔をしわくちゃに歪ませ、意識して呼吸を乱し声を引きつらせ、涙が出なければ目薬でも何でも使って泣いているように見せる、というものです。これが模倣・模写の演技であり、基本100%観客から見抜かれます。そこで多くの俳優は、自分の過去の経験や想像力を使って、このときのキャラクターの心情に近い内的状態を自分の中に生み出そうとします。じゅうぶん強い感情が記憶などから呼び起こされれば、不随意運動を伴った「リアルに見える」泣きの演技が可能になります。実際の現場などでも多くのケースで取られているアプローチがこれと似たようなものになるでしょう。
ところがこの方法にも限界がありました。たとえば一度泣いてしまうとスッキリしてしまってテイク2、テイク3と重ねていくことができなかったり、そもそもそこまで想像力だけで強く感情を喚起するのが難しいという人も少なくありません。しかし一番の問題は、先に言及したように、このとき俳優の内面と、キャラクターの内面とが、じゅうぶんには一致していないということなのです。
つまり「試合に負けて悔しいから泣いている」人は、その時何を思い考えているのでしょう。現実の生きた人間が、リアルにそのような状況にあるとき、「さあ過去に泣いた思い出を蘇らせてうまいこと泣いてやろう」と考えているでしょうか? そんなはずはありません。当人はそもそも出来ることなら泣きたくないとすら思っている場合も多いはずです。
もちろん俳優として演技をしている前提上、完全に想像上の人物と内面が一致してしまえばそれは妄想の世界に行ってしまったことになり別の問題が生じます。俳優は俳優としての自意識を残したうえで、どう自らの演技を見せるのかを常に念頭に置き続けなければなりません。一方でその手の自意識が強すぎると、観客からは「悔しくて泣いている人物」ではなく、「泣き顔をなんとか見せようと一生懸命なにかを思い出している人物」というふうに見えてしまうわけです。これは泣いたり怒ったりという強い感情を伴うシーンに限ったことでなく、フラットで何気ない会話のようなシーンであろうとどんな場面であっても当てはまります。伝わる情報はノンバーバルが93%と書きましたが、この93%に含まれているものは、要するにその時の伝え手の内面にあるあらゆる情景の総体であり、それがどう表立って現れてくるかを、意識ではとうていコントロールしきれないということなのです。
まぶたの1ミリにも満たない動きといった微表情や瞳孔の収縮、声のコンマ何秒の上ずり、肌の上気に伴う毛穴の開き……そうしたすべてが内面の状況に反応して不随意に生じてくるものであり、自分では制御できません。観客はそれらを無意識に、しかし確実に感じ取ることで、その人物の内面を読み取っています。観客に対しては、それほどまでに俳優の内面が筒抜けだということです。
だんだん恐ろしく感じられてきた人もいるかもしれませんが、そこまで悲観しなくても大丈夫です。先にも述べたように、内面すべてを完全にキャラクターと同一に持っていく必要はないのです。実際そのようなことは不可能ですし、出来てしまったら撮影や公演どころではくなってしまいます。大事なのは、必要な分量だけそれを行えればいい、ということです。俳優自らが演技時にコントロールできない無意識の不随意表出こそが、観客に伝わってしまう本当の情報であることは先だって説明した通りです。であるならば、観客に対してそのキャラクターの内面が伝わるに必要十分なだけの「キャラクターの内的情景」を、あらかじめ自分の無意識内に準備しておくこと。それこそが演技に先だって必要な準備になってくるというわけです。
目に見えるもの、コントロールできるものを書かれた通りの演技として行う前に、その人物のそのときその状況における内面の物語を再現することこそが本当は求められているのです。そのキャラクターがその瞬間、その局面において、どのような彼/彼女の人生のストーリーを生きているのか、その状態・状況を知り尽くしたうえで、そこに流れている物語を演技者が自らの内側に的確に再現することなのです。それが出来たとき、観客はスクリーンや舞台上に、俳優ではなくキャラクターを見ることになります。そしてその人に釘付けになります。
しかし、そんなことで果たして本当に見た目の上でも的確な感情やニュアンスが出せるのだろうか? 実際には多くの細かい指示もあるし、どうすればいいのか? そもそも「内面にキャラクターの物語を再現する」とは、普通に「その人物の気持ちになる」っていうのと何が違うのか? 様々な疑問が浮かんでいる方も多いかと思います。ここでスタニスラフスキーの後期システムから端を発する現代演技理論の話に進みたいと思います。
・感情や身体は「目的」に追従する
ここから先は
¥ 8,980
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
