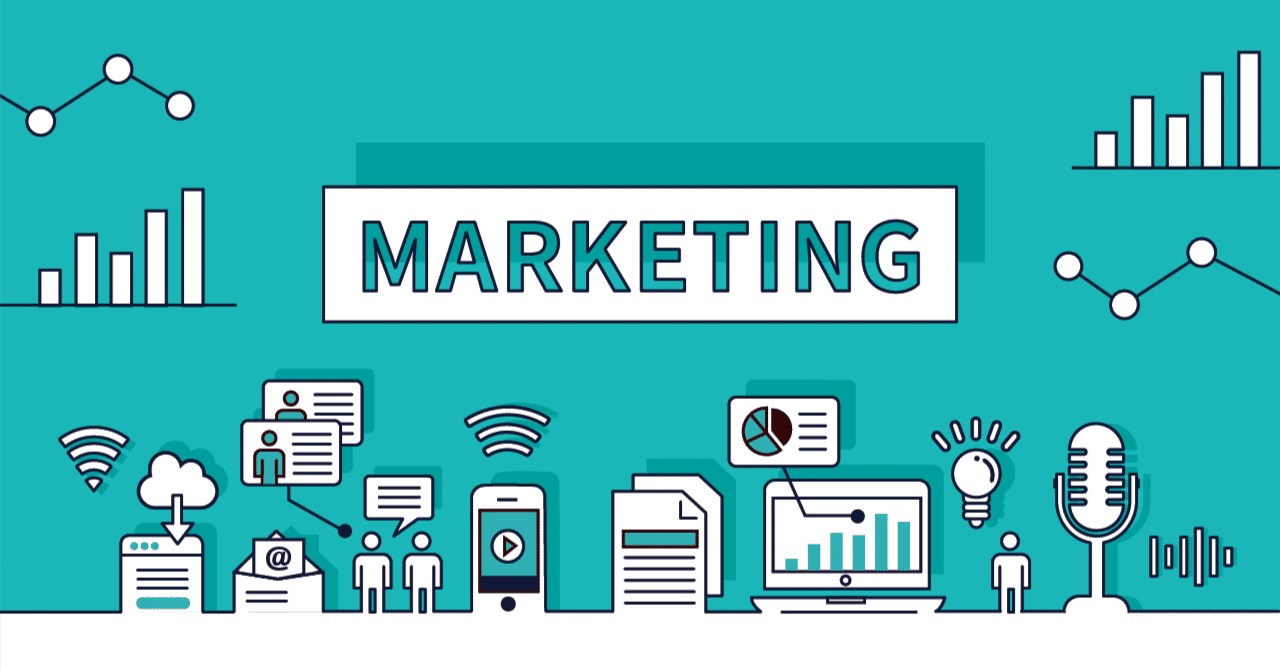最近の記事
- 固定された記事

そう、人生があるんだ。私たちには。『ドキュメント がん治療選択~崖っぷちから自分に合う医療を探し当てたジャーナリストの闘病記』(金田信一郎著,ダイヤモンド社,2021)を読んで
結構読んでいて辛いところもあり、飛ばし飛ばし読ませていただいた。 それでも刺さったのは、この一文。 そう、人生があるんだわたしたちには。 これは、私の人生なんだ。 「標準治療」とか、「〇〇科」というまな板の上の何か、なんかじゃない。 切った後には、そこから回復していく生活がある。 私たちは治療後の生活を生きようとする。 願わくば寛解して二度と再発しない人生を。 その人生の主人は、私たち自身だ。それを認めてくれて、寄り添ってほしい、力を貸してほしい。たぶんそれだけ。

『がんが自然に治る10の習慣』ケリー・A・ターナー、トレイシー・ホワイト著を読んで、自分が変えるべきは何だろうかと考えさせられる。
Radical Remission(邦訳『がんが自然に治る生き方』)の、いわば続編。前著では、自然寛解を経験した人たちにインタビューをし、共通する9つの治癒要因を紹介していた。今回は新たに10番目の治癒要因、運動を付け加え、それぞれに章をあてて個人の事例とともに紹介している。この大勢の個人の寛解の実例からは、奇跡のような驚きと、多くの気づきが与えられる。以下、メモ。各章に実践のステップが載っているので、気になった方は本書をお読みいただきたいと思います。 第1章 運動を生涯の