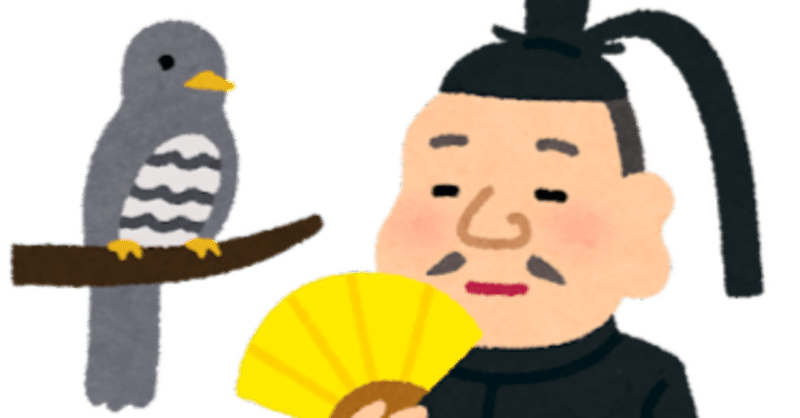
「どうする家康」第22回「設楽原の戦い」 天下人、信長の築く過酷な世界の真実とは?
はじめに
第22回は有名な設楽原の戦いです。一般には長篠の戦いとイコールで結ばれるほど知られるのは、鉄砲を組織的に使うことで戦国最強を謳われた武田を打ち破ったから。信長の先見性が戦を変えたような逸話にすり替えられ、信長伝説の一端を担っています。
本作でも彼だけが「武田を滅ぼす」と明言し、他の誰もが呆気に取られる軍略として描かれました。謂わば、信長こそが今回の話の中心にいます。「どうする家康」…と聞くまでもなく屈服以外の選択肢のない家康は、前回以上に見せ場がありません。
それでは、第22回は信長を中心に据えて何を描こうとしたのでしょうか?本作での、設楽原の戦いの流れと描かれ方からは、時代の転回点というよりも、その戦を支配した天下人、信長の覇道、その先が目指す世界を見せようとしているように思われます。
そこで今回は、本作での設楽原の戦いが象徴したもの、そしてそれがキャラクターたちにどう影響していったのか、ということを考えてみましょう。悲劇の歯車が高速回転し始めます。
1.信康を見る周りの目
冒頭、竹千代(信康)と亀姫の幼少期の回想シーンが入ります。ここでテントウムシに対して「虫も一つの命」と語る竹千代は「そうですよね、母上」と瀬名に念押しします。いかに竹千代がお母さん子であったかが分かる一幕ですが、思い返せば第1話の赤ちゃんの頃からいじる家康に対し、母にしがみついて離れない子だったのですよね。亀姫が言う「虫も殺せぬ兄上」とは、生来の優しさが瀬名と過ごすことで真っ直ぐ育ったのでしょう。
ここで場面が瀬名のバストショットへと切り替わります。この回想は、出陣前の信康を見る瀬名のものでした。ここで注目したいのは、出陣前のバタバタとした様子の中で信康を巡る家族の眼差しです。
武田を蹴散らしてみせようと意気込む信康の身繕いを手伝う妻、五徳は「頼もしいこと」と励まします。準備が整った信康を背中から眺める五徳の満足そうに眩しそうな惚れ惚れとした笑顔に、彼女の実は「信康が大好き」という本音が駄々洩れになっていますね(久保史緒里さんの表情が打って変わって爽やか)。
前回、離縁させられそうになった際に信康と目を交わすシーンを見ても五徳は、高すぎるプライド、振り幅が大きすぎる感情的な性格ゆえに信康と喧嘩も絶えず、家中でも腫物扱いですが、その心底は信康を心から慕っています。そして、その信康が、自身が理想とする立派な武将への道を進まんとしている、そのことを誇らしく思う妻の眼差しは純粋なものでしょう。
そんな血気に逸る信康を、戦うばかりが将ではないと窘めるのは家康です。彼は戦場をあまり知らない、未熟な信康を危険な死地に立たせることは避けようとします。それは、単に愛息を慮る個人的感情だけではなく、一国一城の主の心得を彼に説くためです。だからこそ「信長がいかにして戦うのかよーく見ておくのじゃ」と見聞を第一にするよう発言しています。
かつては若すぎるという理由から信康を岡崎城城主にするのもためらったことがある家康ですが、ここではもう信康を後継者、嫡男として戦場で鍛えようとしているのです。そして、三方ヶ原合戦にて一国の主は必ず生き延びなければならないことが身に染みている家康は、信康を必ず帰還させようと決心していることも窺えます。
それにしても、あの弱虫泣き虫洟垂れ(瀬名)だった家康が、人の親としてようも育ったものと妙な感心もしてしまいますね(笑)
父の換言に耳を傾けつつも信康はいざとなれば戦うと気負っています。そんな彼にけしかける発言をしてしまうのが家康の小姓、万千代です。初陣に対する自身の決意表明ですが、流石にこれは家康にも信康にも窘められます。しかし、この万千代の発言は将兵たちの意気込みそのものであり、それは信康に対する期待として伝染しているとは言えるでしょう。
こうした戦の機運が最高潮に高まる中、男たちは出陣しますが、五徳の「ご武運を」という送り出しの定番に対して、亀姫は「気をつけて」…そして瀬名は「無事のお帰りを」と伝えます。
この「無事のお帰りを」は示唆的です。冒頭の回想を見ても瀬名は、信康の優しさを大切に思い、それゆえに案じています。だから心優しい信康が武功を立てることよりも、無事に帰ることを願っています。
この想いは家康に対しても同じです。彼女は家康初陣の際も、役目が兵糧の輸送だけと聞き安堵しています。そして、このときも「ご武運を」とは言わず「上手に出来ますように」と願掛けだけをしています。彼が生き延びる、そのことだけを念じてきた瀬名の想いは今も変わらずであり、それは根が余りにも優しき息子ならば尚更なのです。
こうして見てみると、五徳は信康に理想の夫、武将を見ており、また家康や家臣たちは徳川家嫡男という期待を込めて彼を見ています。勿論、彼らの想いは真っ当なものです。しかし、心優しい信康という彼の本来の気質、つまり彼そのものを見ているわけではなく、自身の願いを託して見てしまっています。それは、信康が自覚しているかどうかはともかく、自然と大きなプレッシャーとなっているでしょう。
そんな中、瀬名だけが本来の信康の気質、性格、つまり信康そのものを見て案じているのは、後半の展開につながってきます。その点でも、そして瀬名自身の「もっと大きな夢」という点においても、この場面は重要です。
2.全ては信長と秀吉の掌の上
(1)秀吉が坂井忠次に言わせた鳶ヶ巣山砦への奇襲
織田・徳川連合軍の到着は長篠城の奥平たちを喜ばせるものの、一向に戦は始まりません。織田勢は、雨の中、粛々と馬防柵を拵えるばかり。信長は物見遊山のごとく、葡萄酒をグラスで飲み干しています。
そう言えば、ルイス・フロイスによれば、信長は下戸の甘党。だから金平糖を喜んだという話があります…となると前々回からちょくちょく葡萄酒を飲む場面が挿入されるのは何なのでしょうか。更に第20回では、下戸で知られる光秀とそれを酌み交わしていましたね…ということは、あれ、葡萄酒ではなく、ぶどうジュースでしょうか(笑)
となると、いち早く髪型を月代にした件も含めて、西洋文化に親しみ、流行にも敏いという先見性を天下人らしさの一つとして身にまとう演出をしているのが、今の信長という可能性がありますね。
一種の見栄っ張りですが、一方でそういう演出をしなければならない立場と心理状態が、権力を握った天下人なのかもしれません。穿ち過ぎかもとは思いますが、信長の人物描写に新たな要素が加わっている可能性は否定できません。
まあ、撮影現場で岡田准一くんが飲んだのはジュースでしょうね。100%濃縮果汁かウェルチかは分かりませんが(笑)
因みに馬防柵を作ることについては、『信長公記』によれば、設楽原は丘陵地が多く、見通しが悪いため、信長はそれを利用して軍勢を敵から見えないように布陣、連吾川を堀に見立て、鉄砲使用を前提とした馬防柵と土塁を築いていたとされています。こうした野戦築城は当時では珍しく、劇中で家康たちが意図を計りかね、武田軍が訝しんだのは当然だったりします。山県が信長たちのことを「よほど我らが怖いのか…?」と言っていますが、全くその通り。だからこそ、数千丁の鉄砲を用意し、絶対勝てる準備を整えて、戦に臨んだのですね。
とはいえ、同盟者にすらその策の全貌を知らせぬその対応は、長篠城を救う目的がある家康たちとしてはイラつかせるばかり。若い信康が信長への詰問を持ちかけ、父、家康が応じ、二人だとまた喧嘩になると忠次が付いていく…という阿吽の呼吸が良いですね。
信長の陣では、信長と秀吉が碁を打っています。秀吉は、打つ手がなく参陣した家康をと碁を打つ自分の状況と重ねて「どうしやーす」(どうする)と挑発します。前回の信長に引き続き、今度は秀吉にまでタイトル回収され、これにより何気に三英傑のヒエラルキーが見えますが、家康にとっては侮辱でしかありません。激昂する家康に自分が長篠に来たのは「長篠を救うため」でも「武田を撤退させるため」でもない…と冷徹な返事を返します。
前回の記事でも触れましたが、当時の信長は多くの敵を排除し、右大将に任じられたことで実質的に天下人となり、畿内の中央政治で安定した立場を手に入れていました。その上、鉄砲を揃えたこともみても分かるように、交易による経済的な利益も得ていました。逆に武田氏は、甲斐の死活問題ゆえに信玄が西上作戦を決行したようにジリ貧です。それは勝頼の現状では更に増していたはず。
つまり、実は、信長にすれば、放っておいても国力の差は日に日に歴然となる武田氏を可及的速やかに滅ぼす必要性は現時点ではないのです。ですから、本作では「武田を滅ぼすため」に来たことが後に明かされるもののこの場面では目的を伏せ、あくまで同盟者への義理で来たという体で振る舞えます。
一方で家康にしてみれば、信長がいるときに武田を叩いておかなければ、三河・遠江の安定は図れません。彼のほうは死活問題なのです。となると、信長のこの冷徹な言葉、家康には「この戦はお前の事情でしていることで俺には関係ない」という意味にしか取れないわけです。更には「お前に協力することで同盟者である俺にどんな利益があるのか」とも問われているようにも見えたことでしょう。
前回、他の手札もないのに信長を脅してここに引きずり出した家康の策がいかに悪手であったかが、ここでも証明されています。利益が共有されてこそ、同盟は対等関係で結ばれます。それを失った今、二人の関係は家康がへりくだるしかない。家康は立場上、秀吉を一喝していますが、現実には信長の家臣にすら頭を下げねばならないことを秀吉の挑発は突き付けています。
さて、困り果てた家康たちの前で秀吉がわざと地図のある地点に落とします。これにより、坂井忠次が長篠城の背後から城を攻めている鳶ヶ巣山砦を奇襲、結果的に武田の後背を突き、退路を断ち設楽原におびき出すという策を献じます。秀吉は、忠次のこの策に「啄木鳥の策」(昔、第四次川中島合戦で山本勘助が献じた策ですね)と誉めそやしますが、忠次が策を思いついたときの秀吉と信長の表情から、この策を家康側に言わせること自体を示し合わせていたことは丸わかりです。彼らは家康や家臣の能力自体をそれなりに買っています。その能力と追い詰められた状況ゆえに補助線さえ引いてやれば、逆にこちらの都合通り動くとタカを括られているのですね。
信長が、家康側にそれを言わせたのは、織田勢に都合のいい状況(武田軍が進撃してくること)を作るために自軍の戦力を極力使わないためです。だから「家臣に危ないことはさせられない、だが家臣でない家康がやるのはやぶさかではない」とせせら笑います。
この際、信長の家臣たちが家康に見せつけるため、わざと次々「自分が、自分が」と申し出ていますが、これこそが信長の軍門に降った後の家康たちに待っている自分たちの姿です。常に信長のために自ら手柄を立て続けねばならない、終わりのない過酷な要求に答え続けなければならない…これが信長の覇道の一端が垣間見えますね。しかし、追い詰められたとき、信長の家臣であれば、守ってはもらえます。
信長は、改めて厳しい二者択一を迫っているのです。ダチョウ俱楽部ネタを使っていますが、その裏にあることを見ると全く笑えないシーンになっているのがなんとも言えませんね。まあ、一々、遠回しに家康に説明してやるところは、信長には姉川のときと同じ親切心があるのかもしれませんが。
ともあれ、現状では家康は、鳶ヶ巣山砦攻略を自軍で引き受ける以外なくなりました。自陣に引き上げた家康の家臣団が、信長の家臣たちのように芝居がかるでもなく「我が我が」と申し出る中、土地に詳しいという理由で忠次に決まります(彼は東三河の旗頭です)。彼を景気よく送り出すために数正の音頭で海老すくいが始まる辺りは彼らの結束力ですが、それを交われないけど放置する家康、「何なんだ?!」と戸惑い馴染めない万千代が笑えます。
ところで鳶ヶ巣山砦攻略は『信長公記』『常山紀談』などで坂井忠次の発案であったとされています。最初、一笑して却下した信長が後で忠次を呼び寄せ、機密漏洩を恐れてあの場では却下したが秘密裡に決行するよう任せて成功、信長が激賞したと言われています。つまり、忠次の英雄譚として知られた逸話でした。しかし、本作では信長と示し合わせた秀吉がわざとらしく彼らから言わせるよう仕向けた形にしたことになりました。
このことは、設楽原の戦いが、最初から…もしかすると家康との一触即発も含めて、全ては信長の掌中で転がされただけであることを意味しています。つまり、信長の深謀遠慮のレベルが以前のそれよりも進化していること、そして、それによる数々の軍略を実行できるだけの圧倒的な軍事力も備えていることが明確になったと言えます。家康には、最初から信長の軍門に降る以外の選択肢は無かったというわけです。
そして信長が、家康に改めて自分の軍門に降るように示す総仕上げが、この後に繰り広げられる鉄砲隊による武田軍壊滅です。
(2)信玄の呪縛から逃れられない勝頼
さて、忠次の鳶ヶ巣山砦攻略は勝頼に気づかれましたが、当然、その成功が意味することも信玄並の軍略家である勝頼も、そして山県、穴山といった信玄以来の譜代の家臣たちも予測がついています。結局、忠次らの奮戦は功を奏し、長篠城を救い出し、武田の退路を断ち切りましたが、それでも勝頼は撤退を選択しませんでした。
『甲陽軍鑑』にあるとおり、譜代の宿将たちは撤退を進言します。それに際に「父上ならばどうしたか」と勝頼は問います。穴山は迷わず「信玄公ならば撤退する」と答えます。用意周到、必勝でなければ戦わない信玄ならば当然です。勝頼もまた、信玄のその判断の確かさを認めています。が、その上で「だから天下を取れなかった」と断じます。第16回の記事でも触れましたが、信玄は地の利と時の運がなかったために道半ばで逝きました、そのことは彼自身も理解しており、勝頼にだけはその嘆きを話していました。その会話、勝頼は深く深く考えていたのですね。
そして、彼は今こそ父を超える時と進軍を決意してしまいます。山県はその心意気を汲み、先陣を買って出ますが、知将穴山は呆然自失です。全軍が壊滅するかもしれない一か八かの勝負をする勝頼を見限る決定打かもしれませんね。
進軍を決行する前に「信長と家康の首が目の前にあること」「このような機会は今後、訪れない」と千載一遇を強調して兵らを鼓舞します。この際、彼の脳裏には信玄が浮かびます、そして信玄の言葉を準えながら語ります。まさに信玄自身を自分に憑依させて語ります。そして「我が父が申しおる。武田信玄を超えて見せよと!」と自身の本音を語ります。ここに勝頼の弱点が見えますね。末期の信玄が、期待と心配の双方から勝頼にかけた「わしを超える逸材」という言葉が、結局、信玄を超えなければならない呪縛となったということです。
結果、「わしの真似をするな」と言われ、自分自身の軍略でここまで切り拓いたにもかかわらず、肝心のところで信玄を自らに憑依させ、信玄の「真似」をして兵を鼓舞、信玄が西上作戦でなすべきだった信長殲滅を実現させようと動いてしまいました。それが出来てこそ、信玄を超えることだと思い込んでしまったのかもしれません。磨き上げられた能力の高さが自負となり、仇をなしたという点では氏真のそれとは正反対ですが、父の呪縛から逃れられないという点では同じになってしまいました。
因みに彼は兵を鼓舞する際、虹を指して「吉兆である」と止めを刺すように言っていましたが、何のことはない、晴れたということは火縄銃が使えるということです。つまり、虹の吉兆は信長の側のことであるというのが皮肉ですね。雨男で知られる信長が珍しく晴れた戦が設楽原の戦いです。時の運を引き寄せたのは、またも信長でした。信玄の「真似」をした時点で、時の運(この場合は撤退の機運か)を失ったのかもしれません。
ただ、勝頼の名誉のために言っておくと、馬防柵で待ち構える鉄砲隊に騎馬軍団を突撃させたことは当時では常識的な戦法(信長もこの戦法で危機を脱したことがあります)ですから、勝頼なりに勝算があってのことで愚策だったわけでありません。自らの軍団に対する自負があればこその最善の策だったのですね。ただ、勝頼が知り得ない鉄砲を組織的に使う戦法に破れたのです。甲斐では鉄砲を数千丁も運用することは出来ませんし(玉が足りません)、偵察、情報収集の失敗の可能性はあるものの仕方がないとことです。
だからこそ、信長は、一般的な撤退を選ばず、あくまで勝利を狙い、自分が取れる最善の策で攻めてきた勝頼を「武田勝頼見事なり」と誉め、合戦後、家康に対しても「武田勝頼、決して侮るな」と釘を刺しているのです。
実際、信長が勝頼を将の器として認めているのは正しく、勝頼はこの設楽原の戦い後、上杉や北条との外交政策も駆使して状況を立て直し、領土も一時的に信玄期以上にして家康を苦しめます。決して愚将・凡将ではないのです。
しかし、この戦で多くの人材を失ったこと、国衆らを動揺させ信頼を失ったことは取り返しのつかない問題として、武田家を徐々に崩壊に導いていくこととなります。
(3)信長の覇道の行末にあるもの
いよいよ、武田軍が襲い掛かろうというそのとき、家康の陣へ「邪魔するぞ」と信長が参陣します。最も見やすい場所へ来たとは秀吉の弁ですが、かつての弟分に今の自分の力を改めて見せつけるために来たことも疑いようがないでしょう。前回触れたとおり、ホモソーシャルな男性社会では自尊心とそれを守るための徹底的な上下関係を築くことが必須だからです。勿論、家康にだけ見せる信長自身の子どもじみた見栄っ張りとマウンティングもあるでしょう。
そして、いよいよ織田軍の誇る鉄砲隊の組織だった、機械的で断続的な射撃が始まります。雄たけびを上げ、突き進む山県たち、初撃こそ耐え抜きますが、2、3…と連発される中で次々と討ち果てていきます。駿河をあっという間に陥落させ、三方ヶ原合戦であれほど家康たちを窮地に追いやり震撼寒からしめた武田軍団が、見るも無残に散っていく姿に家康たちは呆然とします。
目の前の惨劇に鉄砲の数を問う家康に膨大なその数を答えた秀吉は、歓喜の嬌声をあげながら「もはや、兵が強いでだけでは戦にゃあ勝てん!」「銭持っとるもんが勝つんだわ」と続けます。つまり、この勝利はまず鉄砲とそれを扱う足軽を揃えられた経済力の賜物であると言うのです。国力とは経済力であることを、信長と秀吉は家康に見せつけながら教えるのです。やっぱり親切すぎますね…
後年、秀吉は太閤検地、度量衡の統一、各地の蔵入地を使用した国内貿易(相場で儲ける)、許可制の海外貿易、公共事業など優れた経済政策で富をもたらしており、これが彼の天下を支えています。その片鱗が、こうした発言にも表れていると言ってよいですし、家康の足りない部分と言ってよいでしょう。
さて、秀吉は次々死んでいく武田軍に対して「最強たる武田兵も、虫けらのごとくだわ!」「ああ、面白えように死んでくわ~、実に愉快でごぜ~ますなあ!」とサイコパスめいた発言で高笑いをします。流石に武人の心を重んじるところのある信長は「やめよ」と窘めますが、百姓上がりの秀吉にこの台詞を言わせたのが、この脚本の妙ですね。
一見、サイコパスにも見えますが、この台詞は彼が普段抱えている名家や生まれつきの武士、マッチョイムズ全開の武将に対する秀吉の強烈なコンプレックスの裏返しでもあるんですね。秀吉は百姓出身であり、特別、武芸に長けた人ではありません。武を重んずる傾向が強い本作の織田家において、彼が受けていた扱いは初登場時に勝家に蹴とばされていたとおりであり、実際は腸の煮えくり返る思いがあったことは想像に難くありません。
思えば、初登場時からムロ秀吉は満面の笑みでありながら、目が全く笑っていないという人物でしたから。家康に対する、小馬鹿にしつつも時折見せる嫉妬とも憧れとも思える二面性のある言動にも、彼の抱くコンプレックスが節々に表れています。
本作では、女性や領民など弱者への眼差しが描かれますが、彼らの目線の反転した負の感情が秀吉という人物を支えているのかもしれません。後年、そのコンプレックスが、出身の捏造、自身の貧しい親族への残酷な仕打ちなど様々な形で表れますが、そこまで描かれるかわかりません。
そして、完全に見せつけた上で秀吉は「本当に家臣にならんでよいので?」と囁きます。やり方に家康の気持ちを弄びたい気持ちも感じますが、前回の「気ぃつけなーせ。お怒りでごぜーますよ」といい結果的に家康には的確な助言にもなっているのも事実。勿論、家康を味方にしたい信長の意向を汲んでいるからこその言動でもあるでしょう。
しかし、一方で秀吉の心情にも、羨望と嫉妬、とことん利用してやろうという悪意など複雑なものがあるのではないかと察せられます。妹を家康に嫁がせる至るエピソードにも何かありそうです。
さて、この戦を呆然と見るのは家康だけではありません。まずは信康です。彼は初陣でこそありませんが経験浅く、戦の現実を知りません。恐らく彼が知る戦は、武士同士が魂をかけて戦うという認識だったのだろうと思われます。しかし、目の前で繰り広げられたのは武士の魂も人の尊厳もなく、ただただ効率よく機械的に人が虐殺されていく様です。
設楽原の戦いは、ある意味、戦の在り様を変えたのかもしれませんが、それを戦争の本質がより際立つ効率よく人を殺す形への変化であるとしたのが「どうする家康」流の解釈なのですね。兵器の進歩にそういう面があることは否めません。いかに味方に被害を出さずに敵を殲滅するかにあるからです。その現実を見せつけられた信康は、戦そのものに恐怖し、その恐怖に囚われ、呑み込まれてしまうことになります。
そしてもう一人、設楽原の嬲り殺しを、不快さを隠そうともせずに眺めていたのが井伊万千代です。彼は三方ヶ原合戦にて武田軍による家康方の虐殺を観てしまい、武田軍のあり方、弱肉強食の論理に疑問を抱き、それとは違う、民を笑顔にしそうな家康に仕えることにしたキャラクターです。
その彼が、この虐殺を見るという構成が巧いですね。これによって、彼だけが信長の覇道も信玄の軍略も同質の弱肉強食の論理でしかないと見抜いている。信長につくことは、結局、領民が幸せにならない、その行きつく先を彼だけが気づけるのです。
だから、この後、家康が信長の家臣になる決断をした際、家臣団の誰もが現実的に止む無しとする中、ただ一人、憤懣やるかたない顔をし納得していないんですよね。先の家臣団の海老すくいでの戸惑いといい、万千代が家臣団に染まり切っていない点は重要かもしれません。
彼は家中にいながら、別の視点を持ち、徳川家をも客観的に見られる立場にいます。家康の判断が致し方ないものであっても、その問題点を指摘できる万千代がいることが、どう活きてくるのか、今後に期待したいとところですね。
ともあれ、徳川方の手柄であったはずの鳶ヶ巣山砦攻略を含めて、全てが信長の掌中にあったとしたことで、設楽原の戦いは、信長の覇道の過酷さを端的に表現するものとなりました。そして、家康が、信長を脅したそのときから軍門に降るしかなかったことも、家康も家臣団も瀬名も視聴者も納得するより他ありません。
3.信長に従属したことによるそれぞれの過酷さの始まり
(1)より孤独にならざるを得ない五徳
こうなっては、家康は信長に従属するしかありません。それでも今川家の娘である瀬名を気遣うあたりは、家康なりの優しさがありますね。「お家がまず大事」という瀬名の返答も、彼女が内心抱く夢とも別に齟齬するものではありません。気がかりは心ここにあらずの信康です。
臣下の礼を取った家康は、秀吉から武田、北条、伊達など多くの敵と戦わざるを得ないノルマを課されました。ブラック大企業とも言うべき、織田家では結果だけが求められます。家臣としての安心と引き換えに、信長からの過酷な要求に答え続ける毎日が始まります。
それは、かつての弟分であっても例外ではありません。寧ろ、外様の家臣に過ぎない家康と信長の距離は大きく開いたと言えるでしょう。尊大な信長の振る舞いは、かつての彼らの兄弟のような関係の終わりを告げています。信長の家康への想いは残っているかもしれませんが、天下人らしく振る舞うこと、そして天下一統の実現が今の彼には何よりも大切です。
一部の視聴者には痴話喧嘩とまで言われた、金ヶ崎や長篠前夜のようなマウント争いや兄弟喧嘩はもう見られないでしょうね。
さて、この前後、大勝した信長は佐久間信盛の誉めそやしを受けながら、五徳を横に秀吉と碁を指しています。五徳は織田に属することが明らかにされていますね。また設楽原の陣からしても信長の秀吉の寵愛ぶりが窺えますね。信長は信盛に「我らの最大の敵は誰か」と問います。信盛が「相模の北条、越後の上杉……」と強力な外敵を上げますが、完全に的外れ…「ついてこられないものは置いていくぞ」と軽く叱責し、今度は秀吉に「お主は分かっておろう?」と問います。
このとき、秀吉はまず答える代わりに天元に石を打ちます。初手ではないので太閤碁ということでもないでしょうから、単に「ここ(岡崎城)にいる」と示したのかもしれませんね。
しかし、口では「猿の脳みそでは到底分からんことで」と謙遜めいたことを言いますが、この際の笑顔の底意地の悪さが最高に巧いですね。つまり、秀吉は、佐久間信盛こそが猿以下の脳みそだと言っているんですね。脳名がの意を汲み、謙遜のフリをして信盛を罵倒する機転に信長は爆笑しています。上司の意を汲み、かといって才気走らせることはなく、懐に入る悪魔的センスが秀吉の恐るべきところです。
信長のような自尊心が強く、それでいて優秀な者しか認めない人間は、自分より優れた者を嫌います。だから、彼は巧妙にバカも演じ、能ある鷹は爪を隠す、をほどほどにやっていますね。
逆に何も気づけず目を白黒させる信盛には追放フラグが立ちました。そして、これもまた信長の覇道を端的に示しています。主君に気に入られ、役に立ち続ける者以外は切り捨てられるのです。それが筆頭家老であろうとも安泰ではない。安息は存在しないのです。
さて、ここで、信長は五徳に同じこと問います。ただ飾りのようにそこにいた五徳は怪訝な顔をします(織田家ではいつも添え物の軽い扱いなのでしょうね)。そして、「最も恐るべき相手は徳川」と娘に釘を刺し、監視を怠らないように密命を下します。驚愕と怯えと拒否感の入り混じった五徳の表情が、顔をつかむ信長の手の甲越しにもよく伝わりますね。
このシーンは色々と示唆的です。まず、信長の意図です。一心同体とまで言った家康に対して、これはないだろうと驚いた視聴者もいたことでしょう。しかし、信長は「家康」と言わず「徳川」と徳川家と述べ、監視の対象も「この家を隅々まで」と言っています。つまり、家康個人よりも、徳川家家中を警戒しているのではないでしょうか。
信長は先の家康との一触即発で徳川家の家族、家臣が自分をどう見ているかを図ることが出来たはずです。皆、家康の忠臣ですが、それだけに信長に対して反感を抱いていることはありありと伝わったはず。挑発したのは彼とはいえ、誰ひとり臆することはなかった。そして、「信長への服従は家臣と相談した上で」と瀬名が述べています。つまり、徳川家は家康のトップダウンではなく、家臣との合議、家臣の意見に大きく左右される家中であることも改めて認識できたはずです。
そして、その家臣たちが優秀であることもこれまで見てきているはずです。何せ京都で元忠や親吉の二人が家康の家臣であることを覚えていた信長ですから、情報はつつがなく伝わっているでしょう。そんな家臣らが家康を唆せば、いつでも裏切ることになる…それを警戒している可能性が考えられます。更に岡崎は武田の調略が原因とはいえ、クーデター未遂があったばかりですから尚更です。
また信長の家康への個人的な思い入れも大きく作用しているかもしれません。信長は金ヶ崎での家康の反抗に涙目になるほどショックを受けました。姉川でパワハラをし、三方ヶ原合戦前夜の一心同体発言によって一旦は収まりましたが、今回、家康が脅しをかけてきたことで、そのトラウマが蒸し返された可能性は否定できません(つくづく家康は余計なことをしていますね)。
金ヶ崎や姉川での記事でも述べましたが、彼は、自分への自負、自信過剰から、裏切りに対する耐性が低く、何よりも自分のプライドが傷つけられます。こういう人が相手への信頼を取り戻すのは厄介で、とことん相手を試します。臣下になった家康が過酷なノルマを課せられているのも現実問題だけではなく、信頼回復の一貫もあるでしょう(苦笑)
そして、今度こそ徹底的に家康が自分を裏切らない、裏切れないよう環境を整えておくつもりというのも、これまでの対応からは考えられます。
反面、もう一つ考えられるのは、覇道を行く信長がもっと先を見ている可能性です。天下人が最も恐れるのはナンバー2です。本人にその気がなくても立場上、その人は彼を脅かします。そして三河遠江と地の利があり、尾張に隣接している譜代の家臣ではない弟分。つまりナンバー2になりかねない徳川を危険視する信長の判断は戦略上、正しいとも言えます。
信長の本心がどこにあるのかは現時点では見えませんから、とりあえずの可能性だけを並べてみましたが、どれをとっても家康や徳川家にとって良いことが無さげなのは明白ですね。五徳が嫌がるのも無理なからぬところです。
ところで五徳についても、気になる点はあります。覚えているでしょうか、五徳は岡崎クーデターについて全て父に伝えると家臣団に前で公言していましたね。あれは実行されたのでしょうか?こちらも二つの可能性がありますね。
一つは信長に報告済みという場合。この場合は、五徳のプライドから来る浅はかな報告によって徳川には反・織田家がいる危険な家中であるということを信長が認識していることになりますから、更に監視するよう信長が五徳に命じるのは、哀しいかな、自業自得ということになりますね。
そして、信長はクーデターの顛末を知ってわざわざ岡崎に救援に来たのだとすれば、家康を挑発したことも含めて徳川家の家中を疑ってその目で確認しにきたことになります。最初から武田家だけでなく、徳川家を標的に入れていることになります。
もう一つは、子どもの癇癪の常套句としての「親にいいつけてやる」に過ぎず、報告していない可能性です。この場合は、信長はクーデターについても間者あたりから通り一辺倒にしか聞いていなことになりますが、実はこちらのほうがたぶんにあり得ますね。
信長に密命を命じられた際の心底嫌そうな顔には、信長への恐怖心と岡崎への愛着もありそうだからです。まして、信康のことは大好きですから、彼が窮地に立つようなことはしたくないはずです。
寧ろ、クーデターについては肝心なことを報告していないことを折檻されている可能性すらあります(おそらく患者からあらましは聞いているでしょうから)。そうなると、前回、五徳が信長から目を反らしたことには実家への後ろめたさも加わりますね。
この場合、五徳はかなり可哀想ですね。信康のことが好きという気持ちが節々に出てしまうにも関わらず、周りにはそれが理解されないばかりか、腫れ物扱いで敬遠されているからです。それは、信長に従属したらますます五徳のワガママに困らされるとマゾっ気があるらしい親吉を除いた家臣団が揃って渋い顔をしているところにもよく表れていますね。
どこまでも徳川家の嫁になれず、織田の娘とされる五徳、実は瀬名を追い出そうとした彼女こそ居場所がないんですよね。そうした孤独感と父への恐怖感の中、彼女がどういう行動を選ぶのかが、すぐ先の悲劇のあり方を決定づけるでしょう。
(2)恐怖に呑まれた心優しき信康の顛末
さて、設楽原の戦いが信康の心に遺した傷は想像以上に深いものになりました。設楽原の戦い以降、信康は二俣城攻略などで果敢に陣頭に立って戦います。この活躍は、高天神城への締め付けにもなるもので、それを得意げに信康が語り、「わし以上だ」と家康が誉めるのも当然と言えます。あまりに得意げなため、五徳は「またそんなことを」を窘めたふうな口を利きますが、これもいつもの会話であり、信長からの密命がある五徳からしてみれば信康の活躍は安心材料です。
ただ、そんな信康から異変を感じ取るのが瀬名です。急激な変化に戸惑います。五徳にしても、家康にしても、信康の勇猛果敢な姿は自分たちの望む姿であり、その変化も成長以上には取りません。人は見たいものしか見ないものです。しかし、信康の元来の心根を知り、それゆえに案じていた瀬名だけは、本来の丸ごとの信康を見て、違和感を覚えるのです。そして、その瀬名の直感は、正鵠を射ていました。
信康は、あの虐殺で抱いた恐ろしい思いから逃げ出す、あるいはそれを押し隠すために勇猛果敢に振る舞おうとしているに過ぎなかったのです。そして、そこに従属した結果、信長から課せられた過酷なノルマが加わり、より彼を更に蝕んでいっているのでしょう。
ここで思い出されるのが、岡崎クーデターです。大岡弥四郎は、信康に「ずっと戦をしておる。ずっとじゃ。織田信長にしっぽを振って我らに戦って死んでこいとずっと言い続けておる」と訴えました。おそらく、その言葉どおりに戦い続けている今の信康には、彼の「信長にくっついている」限り「無間地獄」だという台詞が身に染みているはずです。彼自身の中で、信長への反発心、ひいては信長に従属することを選んだ家康への失望が渦巻いていることでしょう。
そして何よりもそれに苦しめられる自分の弱い心が許せない、だからこそ彼は突撃し続けます。しかし、夢では殺した敵、死なせた味方の兵たちが蘇り、彼を苛むという悪循環が生まれるばかりです。自分に期待する多くの者たちに打ち明けることもできず、人知れず悩む彼の心は限界を迎えます。
そこが彼の哀しいところです。有能ゆえに期待され、それに応えてしまえるために誉めそやされるばかりで、自分の悩みには気づいてもらえず、真面目で優しいだけに心配をかけないよう誰にも打ち明けることもできない。全てが重なり不幸になってしまう。
因みに信康が戦の自慢話をやたらとするのは、『三河物語』での戦の話ばかりしているという記述によるもので、これは信康の粗野な性格と乱行に結び付けられるのですが、本作ではPTSDによる変化ということになりました。家康譲りの優しさ、瀬名譲りの賢さと良いとこ取りの結果とすれば悲しいことですね。平時であれば名君となったはずですから。
結局、彼の行く先は、優しき母、瀬名のいる築山しかありません。冒頭のお母さん子だったかつての竹千代の姿が重なる瞬間です。ムカデ(武田の象徴)にアリ(織田の足軽、雑兵)が群がる姿を見つめ、設楽原の戦を思い返す信康…そして、信長の家臣になった今の自分もこの黒い蟻でしかありません。信長のため、粛々と人殺しをする毎日。子どものごとく涙を流すその姿に予想以上の心の傷を見て取り驚く瀬名…「家を守りたい」瀬名の想いが風雲急を告げないわけがありませんね。
おわりに
設楽原の戦い、それは実質的な天下人となった信長の覇道のあり方を象徴するものとして描かれました。そして、それに影響され、多くの人が悲劇に向かって、進み始めていく、それが22回でした。
信長の天下一統は独善そのものです。自分に逆らうものを経済力と圧倒的な軍事力で睥睨し、従順に従属する者だけを残し、後は滅ぼす。しかし、従う者にも、信長のために永続的に効率よく成果を出し続けてもらい、ついてこられない者は切り捨てるという過酷な弱肉強食の論理だけが待っている。安息はどこにもなく、希望がありません。
ある意味においては、現代社会を投影した世界が、信長の目指す世界です。信長がその大局的な視野で何を見ているのか、恐らく海外を含めた世界であろうことは第13回で示されています。しかし、人々が苦しむばかりの天下では灯台下暗しでしょう。彼は遠くばかり追いかけ、家臣すら見えていないかもしれませんね。信盛も、光秀も、そして重用する秀吉すらも。
夢ばかりで人を見ないからこそ、五徳は嫌がり、信康は心を病み、信長の在り様に未来を感じない瀬名が独断専行を始めていくことになります。信長のやり方は、敵を作るばかりですね。
それでは、その大局に位置することになる瀬名は、どういう未来を見据えているのでしょうか。ここで、家康の初陣前に瀬名が家康に語った台詞を思い出してみましょう。
瀬名は殿を戦に行かせず、共に隠れてしまおうかなどと
思ったくらいに ございます。
どこかにこっそり落ち延びようかと。
誰も知らない土地で小さな畑をこさえて世の騒がしさにも我関せず。
ただ私たちと竹千代とこの子だけで静かにひっそりと。
若い頃の浅はかな夢と言える部分もありますが、瀬名の思うところは、人々が安寧に暮らせるという非常にシンプルなものです。そして、誰もが願うことです。
瀬名はたくさんの悲劇を体験する中で、それが何なのか。実現するためにはどうすべきか、どうあるべきか。そうしたことをずっと長い間をかけて考え、知識などを蓄え、幸せの答えを探してきました。本来はもっと時間をかけるつもりだったでしょうが、家康が信長に従属したことで過酷なノルマを課され、信康は壊れかけています。手を携えるべき相手も滅びゆこうとしています。彼女にももう時は残されていないのですね。
信長と瀬名、両者が目指すものの違いを明確にし、そして両者が結果的に対決していくための状況づくりを整える。設楽原の戦いは、その起爆剤のような役割だったと言えるでしょう。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
