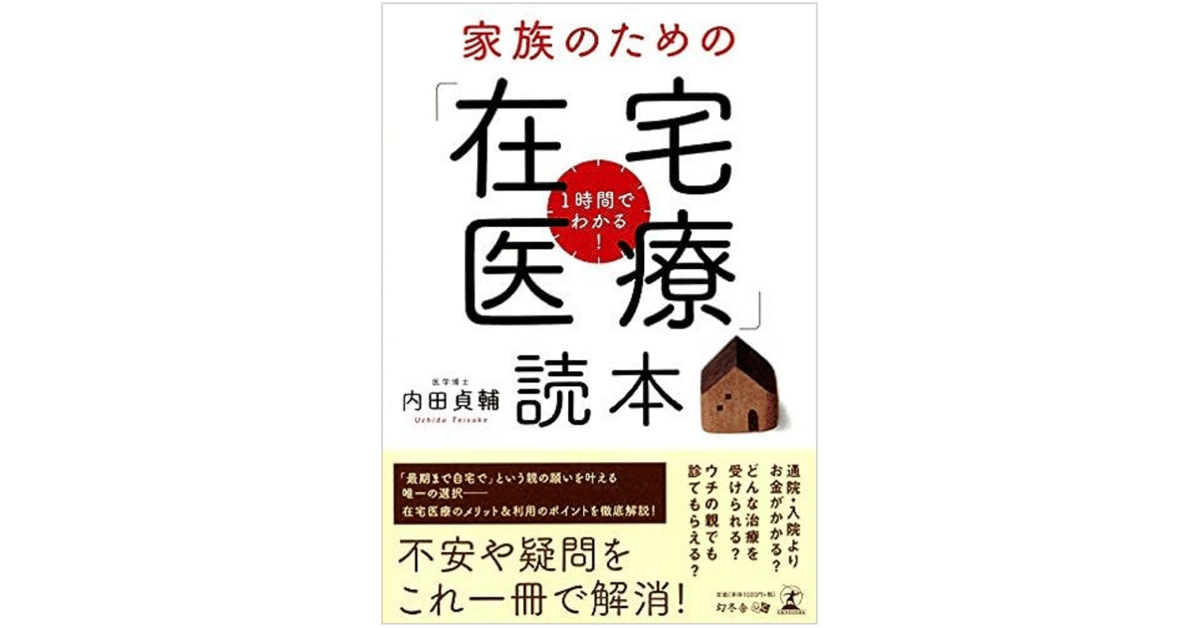
自宅で看取りをすると決めたときは
実際に看取り場所を検討するタイミングというのは、いわゆる「終末期」が近づいてきたころが多いと思われます。
終末期というのをあらためて定義すると、次のようになります。
「医師の診断に基づいて、心身機能の衰弱が著明で明らかに回復不能な状態であり、かつ近い将来確実に死に至ることが差し迫っている状態」
この終末期に至る経過というのは、病気の種類によっても、ずいぶん様子が異なります。
病気の種類により「最期までの経過」は異なる
日本人の死因の第1位を占めるがんの場合、いわゆる終末期は短い傾向があります。治療・療養を続けている間は心身の機能は比較的よく保たれていますが、最期の2カ月ぐらいで急速に全身の機能が悪化し、最期に至るケースが多くなっています。

そのため、病院での治療を終えて在宅医療に移行するときに、最初から「自宅で看取りまで」という希望を持って、在宅医療を始める人も少なくありません。
一方、心疾患や脳卒中、慢性呼吸器不全といった臓器の疾患の人の場合は、数年単位で徐々に終末期に至るという例が多くなります。
最初に発作が起きて倒れたときは、家族も慌ててしまいますが、治療やリハビリが奏功すれば、状態はある程度まで回復します。しかし、何度か発作を繰り返すうちに、全体として徐々に心身の機能が低下していき、2~5年程の間に多くの人が最期を迎えます。
こうした疾患の場合は、どこから終末期かという目安ががんほど明確でないため、家族も治療を続けるのか、看取りを進めるのか、迷いが生じやすいともいえます。
認知症や老衰の場合、さらに長い経過になることもあります。年々ゆっくりとしたペースで心身の機能低下が続き、数年から場合によっては10年近くの療養を経て、最期に至る例も多くあります。
この場合は家族の介護負担は長くなりますが、その分、看取りについてもじっくり考える時間があるともいえます。
いずれにしても、在宅療養をしている高齢者に「最期まで自宅で過ごしたい」という意思があり、家族もそれをかなえようということで気持ちが固まったときには、在宅医にその意思を伝えてください。意思を中心に、在宅看取りの準備を進めていきます。
また、いったん在宅看取りの方針を決めても、それを変えることはいつでも可能です。ご家族が不安や迷いを感じたときは、いつでも在宅医に相談してください。
何度も話し合いを重ね、ご本人にとっても家族にとっても「納得のできる最期」「満足できる看取り」を考えていくことが大切です。
終末期は、余計な治療をやめて穏やかに過ごす
終末期になって看取りのときが近づいてくると、高齢者の心身にはさまざまな変化が表れます。
まず水分や食べ物を欲しがらなくなり、食べることへの興味が薄れます。身体が食べ物を受け付けなくなっている状態です。
また呼びかけても反応が少なくなり、うとうとした状態が多くなります。時間や場所がわからなくなったり、亡くなった人がそばにいるといった幻覚のような話をしたいします。ほかにも、むくみや皮膚の乾燥が進む、呼吸が不規則になる、喉がゴロゴロいう、手足が冷たくなる、尿量が少なくなる、といった変化も表れます。
こうしたサインが表れてきたときには、余分な薬や治療をやめて、穏やかに過ごすことを第一に考えます。
療養中には、血圧や心不全などの薬を飲んでいる人も多くいますが、この段階になったら、飲み薬は原則ゼロにします。必要なときは貼り薬や点滴を使うなどして、薬の投与は必要最低限にします。
さらに、訪問診療や訪問看護の回数を増やし、本人とご家族の看守りを手厚くしていきます。
痛み止め、緩和の薬は最期まで必要
がんの終末期の場合は、痛みのケアが重要になります。
がんが進行したときに、がん細胞が浸潤することにより、組織が傷つくなどして起こる苦痛全般を、がん性疼痛といいます。痛みや苦痛は終末期の患者さんのQOLを大きく損ねるため、鎮痛薬などを使って緩和していくことが重要です。
身体的な痛みについては、痛みの程度に合わせて段階的に鎮痛薬を変えながら使います。痛みが軽いうちはアルピリンやアセトアミノフェンといった鎮痛薬を用い、中等度以上になってきたときにはオピオイド(麻薬)系のモルヒネやフェンタニルといった薬剤も用います。
鎮痛薬の剤形も当初は内服薬ですが、状態に合わせて貼り薬、座薬、皮下注射と切り替えていきます。
また神経性の痛みや心理的な苦痛が強いときには、そうした症状を緩和する薬剤を用いることもあります。状態に応じて適切な薬剤を使用すれば、がん性疼痛の80%はコントローンが可能になっています。
人工栄養や点滴をどうするか、一つずつ相談して進める
終末期に口から物を食べられなくなったときにどうするか、というのも難しい問題です。
人工的に栄養を補う方法には胃ろう、腸ろう、経鼻経管栄養といった経管栄養のほか、中間静脈栄養、末梢点滴などがあります。
かつて病院で行われる医療では、終末期の高齢者にもこうした方法を勧めることが少なくありませんでしたが、最近の緩和医療の世界では、こうした人工栄養や輸液は終末期の高齢者にとって、むしろ有害という認識が広まりつつあります。
欧米やオーストラリアなどでは、「死が迫った高齢者に胃ろうを造設するのは虐待」だと考えられています。消化吸収機能も落ちている高齢者に過剰な栄養や水分を与えれば、むくみや痰の増加による気道閉塞などを招き、かえって苦痛が増すからです。
また、食事や水分を取らずにいると脱水傾向になりますが、このとき脳内麻薬(βエンドルフィン)が増加して鎮痛鎮静作用が働き、本人は苦痛を感じない状態になるといわれます。
本人が「胃ろうなどは希望しない」という意思表示をしているときはそのように対応します。家族が判断しなければならないときは、医師とよく相談しながら、本人にとってより苦痛の少ない方法を検討しましょう。
食事も取れなくなって寝たきりでいる高齢者に対し「何もしないで見ているのもつらい」というご家族には、私は点滴を1日500ml程度入れるのは悪くないと思っています。
そのくらいの量であれば、むくみなどの心配もなく、点滴が施されている療養風景が、見守る家族の心を癒すのであれば、それはそれで意味があるのです。
いよいよ旅立ちというときのサイン
在宅看取りをするときには、患者さんに起こる心身の変化や、最期に向けてどのように進んでいくかという流れを、医師からご家族に説明します。また訪問回数を増やし、ご家族の不安にも寄り添います。
最期まであと数日という頃になってくると、患者さんはほぼ終日眠っている状態になり、呼びかけにもほとんど反応しなくなります。尿が出なくなく、血圧が下がる、指先などにチアノーゼ(紫色に変色)が出るといった変化も見れれ増す。臨終が近づくと、顎を上下させて大きく息をする独特の呼吸(下顎呼吸)が現れます。これは見ている人からするととても苦しそうに感じられますが、この段階では本人はもう苦痛を感じていません。自然な最期は、穏やかなものです。
看守るご家族にとってはつらいことですが、できるだけそばにいて付き添ってあげてください。そして別れの言葉やこれまでの感謝を伝えましょう。実は、どれほど意識が薄れても、聴覚や触覚は最後まで保たれています。ご家族の感謝の言葉はしっかりとご本人に伝わるはずです。
このように住み慣れた自宅で、家族や親しい人たちが心を込めて見送る時間を存分ン位持てるのは、在宅看取りならではです。
引用:
『1時間でわかる! 家族のための「在宅医療」読本』
著者:内田貞輔(医療法人社団貞栄会 理事長)
発売日:2017年11月2日
出版社:幻冬舎
