
【小説】お信(第一部)
『お信』
第一部
「モイスチャーってなあに?」
長い人生、このような質問を受ける可能性は誰にだってある。
お信はモイスチャーの意味をまったく知らなかったから、もしこの先「ねえねえ、お信ちゃん。モイスチャーってなあに?」と友達に尋ねられた場合、返す言葉を持ち合わせていなかった。
昭和六十二年。残暑も風が通り抜ければ多少は涼しい。お信は先程からここに腰を掛けて軒に吊った風鈴を眺めていた。しかしどこか落ち着かない。
「モイスチャー、調べてみようかな。」
お信の足は本棚へと向かったがそこに百科事典は無かった。そうなってはいよいよモイスチャーが気になって仕方がないので、まずは百科事典を購入しようと、お信は本屋を目指して家を出た。本屋はここから数分である。
店内は冷房が利いてひんやりと冷たく、あたりを見回すと様々な書物がお信の目に飛び込んできた──平積みにされた小説、週刊誌、漫画本、昆虫図鑑、そして百科辞典といった本がところ狭しとひしめき合っている。その時、お信は思いがけず「あッ。」と小さく声を上げると、店内に客が自分以外誰もいないことを確認してから目当ての書物を手に取ると、すぐさまレジへ向かった──お信が手にしていたのは百科事典ではなく『パイドロス』と題された本であった。
パイドロスを受け取った店員はお信を見て、
「おじょうちゃん……熱心だね。」
お信の顔は耳まで真っ赤になった。
「いいから早く会計してください。」
釣銭を受け取るとお信はパイドロスを奪い取ってそそくさと店を後にした。
紅潮した顔はそのままにお信は縁側に腰を下ろし、いざパイドロスを読もうとすると小猫がお信の膝に乗ってきた。仕方ないなあと猫をつまんで傍らにいる親猫の元に戻してやってから、ようやく読書に取り掛かろうとしたがパイドロスを前にして緊張のせいか、あるいは何かしら背徳感を覚えたせいか、お信は履いていた下駄の鼻緒を見つめてはため息をついた。お信の鼓動はいよいよ激しい。
「おとうちゃん、ごめんよ。」
お信は興奮に震える手でパイドロスの表紙をめくった。それから二ページ、三ページ、四ページと順に読み進めていった。小猫が再びお信の膝に乗ってきたが、今度はそれすらも気付かないまま夢中で読み進めていたところ、お信はある異変に気付いた。
「パイドロスは官能小説……だと思っていたあたしはバカだった。」
お信は何をどう勘違いしていたのか、パイドロスという字面と語感から何を想像したのか、高まりつつあった興奮は一時に冷め切った──恋だの神だの魂だのといったおよそ不可視的な事柄をパイドロスとソクラテスという古代人が延々と話し込んでいるだけで、たまに挿入される「エロース」といった単語には多少の胸騒ぎを覚えるものの、お信にとって『パイドロス』は要領を得ない退屈な書物であった。がっかりしたお信が本を放るとそれに驚いた猫は庭の奥へと散って行った。と同時に暮れ六つを告げる鐘が鳴った。
*
「あ、こんなことしてる場合じゃない!」
慌てて立ち上がったお信は庭に下りてそこから玄関に回り、軒下に長のれんを掛けた。
「ふう。これでよし、と。」
のれんには「ラーメンお信」と掲げられていた。続いて、脇からのぼり旗を持ってきてそれを軒先に立てた。晩夏の風を受けてはためくのぼりには「本日特売日」とだけ書かれてあるが、これといってラーメンの価格が普段より安いというわけではない。至って通常の価格である。ではどうしてお信は「本日特売日」だと言い張るのか。
「だって、あたしの作るラーメンは千円の価値があるのに、実際はそれを下回る三百円で販売しているんだよ。ってことは今日も明日も明後日も毎日が特売日になるでしょう?」
以前、お信からこういった説明を聞かされた常連客は、このお信独自の価格競争論に困惑するしかなかった。これはお信の「我」ともいえる。
「ラーメンお信」が開店して半時あまりが経った頃、一人の男がのれんをくぐった。
「いらっしゃいませ。なにしましょう?」
男はカウンターに腰かけながら、
「カレー。あとビールもください。」
と言ってスポーツ新聞を読み始めた。ラーメン屋でカレーを注文する行為は、果たしてラーメン屋に対する侮辱と捉えるべきか。挑戦と捉えるべきか、はたまた暴挙であろうか。
「はあい、カレーとビールですね。」
と言うとお信はすかさずビール瓶の栓を抜いてグラスと共に「まずはビールね。」とカウンター越しに男へ差し出すと、続いて炊飯器からご飯をよそって鍋のカレーを温め始めた。お信は鼻歌交じりであった。
カレーは侮辱、挑戦、暴挙になりえない。
いつもラーメンばかり食べているとたまには別のものを欲する客もいるであろう、そう予期したお信はラーメン以外の品もメニューに組み入れた。カレーはその所産であり、これはお信の心づかいでもある。ただ一方で「しめしめ。」と思う理由は自らで描いた筋書き通りに事が運んだからである。
*
「あ、煮えたぎる寸胴鍋に猫をぶちこもう。」
そんな残酷な事をしようとした酔っ払い客をこのあたしが取り押さえて警察に突き出したのはいつのことだったろう……
ふとそんな昔のことをお信が思い返している内に、鍋の中のカレーはすっかり煮えていた。
「カレーライス、できましたよ。」
注文した男はカレーでビールを飲み始めた。カレーをひとくち食べてはビールを飲み、またカレーを口にしてビール、そしてまたカレーをひとくち……といった所作を繰り返している。
人は普段が肝心という。
人のねうちは日頃の行いに因果が含まれており、いざというときに何もできないのは普段を怠るからだ。そう心得ているお信は、カレーでビールを飲むという風変わりな趣味の男に因果の妙を見た気がした。
それからしばらくが経ち、お信が皿を洗っているところへ店の戸が開くと、
「お信ちゃん、ただいま。」
「あら、おかあさま。」
母は店内に入るとカレーの男をよそに冷蔵庫から瓶ビールを取り出し、カウンターの奥へと座った。
「今、ちょっと忙しいから。」
とお信が栓抜きとグラスを母に渡すと「ありがとう。」とそれを受け取った。
*
お信は「産みの母」と「育ての母」という二人の母親を持つ。
産みの母はお信が三歳の頃に病で倒れたため、お信の中にこの母との思い出はほとんど残っておらず、血のつながりという「情」だけがただ残っているだけであった。一方、今お信の目の前にいる育ての母、つまり継母はお信が四歳の頃、父が再婚したことでこの家に迎えられ、そこから十八歳の今日に至るまで過ごしてきた「仲」である。たしかに血のつながりこそないが、お信にとって継母は長年に渡って苦楽を共にした存在であったから、親子でありながら気心の通じた友の様な感覚を抱いていた。継母は理智に富み、お信にとっての教育者でもあったがその半面、どこか奔放な性質も合わせ持っているため、お信と衝突することも度々であったが、お信はこうした継母との関係に現実や社会だけでなく、その処世をも垣間見たのであった。産みの母との「情」と育ての母との「仲」は絆としてお信の心に結ばれている。
しばらくして、ようやくお信が客を捌き終えると店内にはカレーの男、そして継母の二人が残った。継母は冷蔵庫から追加のビールを取るとカウンターから身を乗り出し、
「お信ちゃん、これいただいちゃうね。」
とメンマとゆで卵を自分の皿に移した。
「ラーメン、つくろうか?」
「いらない。」
とだけ言って継母はまた飲み始めた。
「あ、そうそう。芝エビ。」
と継母は芝エビの入った袋を差し出した。
「あらこんなにたくさん。おかあさまったら芝エビなんてどこで手に入れたの?」
「ここに来る途中、そこの魚屋さんからおすそ分けをいただいたの。お信ちゃん、悪いけどこのエビでなにか作ってくれない?」
お信は袋の中の芝エビを二本ばかりつまんで、勝手口の方へまわり、そこで寝ていた猫の鼻先に芝エビを近づけると、匂いで目覚めた親猫と小猫はわッと口を開けて芝エビにかぶりついた。おかわりをねだる小猫を差し置いて、お信は再び店内に戻り、
「この芝エビ、あの食通ネコが迷わず食べるぐらいだから、いきはよさそうね。」
「でしょう?だからお信ちゃん、これでなにか一品こしらえて。」
ではエビラーメンを作ってあげよう……とお信が言いかけた矢先、
「エビラーメンはやめてね。」
*
継母は、お信の安直な発想からなる「エビラーメン」という提案を既に見抜いていた。
「でもおかあさま。せっかくこんなにたくさんの芝エビがあるんですからこれでダシを取ればとっても美味しいラーメンスープができるわ……本当よ。ラーメンのことならあたしにまかせてくれなきゃ。だって、この店は『ラーメンお信』っていうぐらいだからさ、ここはひとつエビラーメンにしなよ。」
お信はエビラーメンを是非、とのことだが継母は不承知の様子で、
「お信ちゃんはつまり、ラーメン屋の自負だったり、ラーメンに対する情熱があるから執拗にエビラーメンを勧めるのよね?」
「もちろんよ。ラーメンお信だもん。」
お信は大人びているだけで幼さが混じっている。継母は内心で笑いつつ、
「ならお信に聞くわ。『ラーメンお信』と謳っておきながらなぜカレーがメニューにあるの?なぜラーメン一本で勝負しないの?」
継母の問いかけにお信は顔をしかめた。
カウンターの反対側ではカレーの男が相変わらずカレーを黙々と食べている。
「おかあさま、それにはれっきとした理由があるの。メニューがラーメンだけだとご常連が飽きると思ったからよ。手前みそかもしれないけどあたしの作るラーメンははっきりいっておいしい。でも毎回同じものを食べさせられるご常連の身にもなってちょうだい。たまには別のもの、つまりカレーなんかもつまみたくなるのが人情ってやつだわ。あの男性にしたってそう。他のお客もそう。一昨日はカレー、昨日はラーメン、今日はカレー。カレーとラーメンを代わりばんこで注文してるのよ。この『飽きさせない』という工夫こそラーメンお信の情熱といってもいいわ。そう、情熱なの。こうした心づもりがおかあさまに分かって?」
「いいえちっとも。」と言って継母は笑った。
「だって、お信ちゃんの言ってることは、ラーメンに懸ける情熱ではなくて、ラーメン屋の『経営』に懸ける情熱なんですもの。もしラーメンへの情熱があるんならまずメニューにカレーなんて入れないでしょう?まあラーメンとカレー、どちらに対しても同じ程度の情熱があるのかもしれないけど、少なくともラーメンお信を掲げるなら、最高のラーメンだけをお客様に提供するべきだわ。もしそのラーメンが美味しいのなら毎日でも食べたいと思うのがラーメンっ食いの性なんだから。この場合、カレーはむしろ邪魔者扱いされるでしょうね。あと、お信ちゃんは心づもりだとかなんとか言ってたけど、私にはラーメン自体に気後れしているようにしか見えないわ。ラーメンお信としての自負があるんなら、経営維持のためにカレーを手段として用いるのではなくて、採算を度外視してでもラーメンのためだけに情熱を捧げるべきだし、それこそがラーメンお信として至極当然の姿勢だと思うけど?」
継母の意見にお信は黙るしかなかった。
*
「そうだ、煮えたぎる寸胴鍋におかあさまをぶちこもう。」
荒々しい考えがお信の脳裡をよぎったが、それはお信の理性が瀬戸際で抑え込んだ──悔しいけどおかあさまの言い分は正しい。あたしは「ラーメンお信」ではなく「ラーメン経営お信」でしかなかった。これは認める。じゃあそのうえで経営お信を辞めて「ラーメンお信」として再出発するかといえばそれはできない。だって、カレーを廃止してラーメン一本となると、ラーメンとカレーを交互に食べ続けてきたこれまでのご常連が離れていくのは目に見えて明らかだし、これでは銭を稼ぐ算段がつかないから。ご常連の「ごちそうさま」「カレーもおいしかったよ」という声を聞いてあたしはたしかに嬉しかった。これは紛れもない事実だ。なら、これからも「ラーメン経営お信」として変わることなく商売をするのがお客だけでなく自分にとって一番の幸せだろう。それをおかあさまは気付かせてくれたのかもしれない。
お信はようやく落ち着きを取り戻した。
「おかあさまのおかげでやっと気付いたわ。あたし、なんだか勘違いしてたみたい。これじゃあラーメンお信じゃなくてラーメン経営お信だもの。だけどそれでいい。経営お信こそ一番の幸せなんですから。」
「お信ちゃんが幸せならそれでいいのよ。こちらこそさっきは口酸っぱいこと言ってごめんね。悪気はないから。」
「うん大丈夫。じゃあこの芝エビでエビラーメンを作るのはやめにして他の物をこしらえましょう。おかあさま、何が食べたい?」
「ガーリックシュリンプが食べたい。」
ガーリックシュリンプって一体……あろうことかお信はガーリックシュリンプを知らなかった。
「それぐらい作れるわよね?」
*
ガーリックのシュリンプとは何だろう。何をどうすればそんなものができるのか。ガーリックとはなんだ?シュリンプって?
不思議とお信の脳内には「モイスチャー」という文字列が渦巻いていた──厨房には煮えたぎる寸胴鍋がある。この中に芝エビをぶちこめばおかあさまの言う「ガーリックシュリンプ」が完成するのだろうか。いやいやそれではただのエビラーメンのスープではないか。では一体どうすれば……
「どうしたのお信ちゃん?ガーリックシュリンプよ。作れるの?」
お信はラーメン店経営者である以前に料理人である。知らないから作れません、では料理人・お信の名折れであると共にまたしても継母に小言を言われるという失態を演じてしまうことになる。つまり、ガーリックシュリンプには料理人としての面子が懸かっている。
「大丈夫?ガーリックシュリンプよ。簡単でしょ。作れるわよね?」
継母の含み笑いにお信は若干の苛立ちを覚えた。
その黒い瞳に芝エビの黒が重なったまま立ち尽くすお信、その後ろであの煮えたぎる寸胴鍋がめらめらと火勢を上げていた。
「作れるの?作れないの?どっちなの?」
「作れるわ。」
「なら作ってよ。」
「作れるわ、おかあさま。たしかに作れるけど……作るにしても今日は日和が悪すぎるの。だって考えてもみて。仏滅の日に祝言を挙げる夫婦もいなければ、大嵐の日にわざわざ船を出す漁師もいないじゃない?花嫁は決まって大安吉日に式を挙げるものだし、漁師は凪を選んで網を打つものよ。これはなんだってそう、ガーリックシュリンプにしてもそう。料理人お信に言わせれば今日の天気、気温、湿度、客入り、腹具合、虫のいどころ、食材の鮮度、芝エビとのフィーリング、包丁の切れ味、フライパンの重み、菜箸のグリップ感、ガスの火加減、鍋の迫力、町内の治安……これらすべてが本日今現在この時点で、ガーリックシュリンプの日和に適していない。作ってはいけない。必ず失敗する。それは日和が悪いから。『待てば海路の日和あり』とはよく言ったものね。だからおかあさま、今日はあきらめて。」
継母は「仕方ないわね。」と席を立ち、お信のいる厨房に入ると、
「ホラ、お信ちゃんはいいから下がって。ガーリックシュリンプは私が作るからあなたはそこで待ってなさい。」
とお信をカウンターに座らせた。継母は厨房、お信はカウンター、二人はあべこべになった。お信は内心、「嘘がバレなくてよかったよかった。」とほッとしていた。継母は首にかけていた手ぬぐいを姉さんかぶりにして頭へ結び、腰紐を取ると着物の袖下から回してたすき掛けにした。粋筋な格子縞の単衣で厨房に立つ継母の姿を見てお信は、
「あたしよりおかあさまの方がずっと料理人っぽい……」
と思わず声を漏らしたが継母は聞こえないフリをしていた。
まな板の上の芝エビをつけ狙う小猫をそっと追い払うと、継母はエビの背に楊枝を刺してワタを取り、髭と尾に付いている棘をちぎってボウルに入れた。これを繰り返すうちにボウルは芝エビでいっぱいになったので、今度はおろしニンニクとオリーブオイルを投入、塩コショウをして炒めはじめた。
「へえ、ガーリックシュリンプってそうやって作るんだあ……」
またしても本音が出たお信は「しまった!」と慌てて両手で口を押さえたが、継母は知らんぷりのままフライパンの中のバターが溶けるのを今かと待っている。カレーの男がようやくカレーを食べ終えた頃であった。継母は炒まったエビを大皿に移すと、
「ちょっとお信ちゃん。オレガノってどこにあるの?」
*
え、オレガノって何……お信は動揺した。オレガノというものをまるで知らなかった。ガーリックシュリンプに加えてオレガノを知らないとなると料理人お信としての面目はいよいよ丸つぶれである。
「オレガノがあるんなら持ってきてほしいんだけど。」
ここでもし、お信が「オレガノはこの店に無い」と言ってしまうと、継母は「料理店を営んでおきながらオレガノひとつ置いてないなんてお信……あなた本当に料理人なの?消費者のニーズとトレンドを日頃からキャッチアップしておくのがプロの料理人でしょ?」とたちまちお信に詰め寄るであろう。それは避けたい。ならば、オレガノはこの店にあるという「体」で継母に何らかの回答をしなくてはなるまい。そうお信は考えた。
「オレガノはあるの?ないの?どっちなの?」
「あるよ。」
「あるんなら持ってきてよ。」
「あるよ、たしかにあるけどおかあさま。今日はオレガノの日和が……」
「オレガノと『日和』に一体何の関係があるの?さっき、お信ちゃんは『ガーリックシュリンプを作るには日和が悪い』と言ってたけど、ほらご覧、ガーリックシュリンプはこの通りよ。日和の良し悪しに関わらず完成したわ。あとはこれにオレガノを振りかけて食べるだけという段になって、またしても日和のせいでオレガノをあきらめる私だと思った?日和を潔癖に信じるなんて馬鹿げてるわ。そんならお信が思う『絶好のオレガノ日和』とはいつなの?明日の日和は?明後日は?それが成立するための前提条件を提示してごらん、そんなものが本当にあるというのならさあほら早く。」
言い終えた継母の眼光は鋭く、その後ろであの煮えたぎる寸胴鍋が赤銅色に輝いており、その眩い光に思いがけず目が霞んだお信は継母から視線をそらして固まってしまった。
「お信、あなたひょっとしてオレガノを知らないだけなんじゃないの?」
「……ごめん、じつは知らないの。だから店にも無いの。」
お信は堪忍した。
「大方そんなことだろうと思ってた。日和なんて言い出すもんだから……お信ちゃん、大丈夫よ。ラーメン屋にオレガノなんて普通は置いてないから。」
「すでにお見通しだったのね。おかあさまったら……」
「もういいから食べましょう。あッ、そこのおにいさん。これおすそ分け。お代はもちろん頂かないからよろしければどうぞ。」
と継母がカレーの男にガーリックシュリンプを勧めると男は「ありがとうございます。」と言ってそれを快く受け取り、お信と継母もカウンターに揃って食べ始めた。
*
我先にと真っ赤な芝エビを口に運んだお信は──これがあのガーリックのシュリンプ。いわゆるガーリックシュリンプ。下味がしっかり付いていて、それに負けじと旨味も感じる。そこにバターとニンニクの風味がばっちり絡まって食べても食べても食べ過ぎたという気にならない。ぜんぜん飽きない。はっきりいって美味い。うますぎる。すげえうめえよ、おかあちゃん!
「おかあさま。これ、とってもおいしいわ。」
「そうでしょう。今日はガーリックシュリンプ日和だからおいしいのよ。」
お信が夢中になって食べ続けていると、
「さ、あんたはそろそろ仕事に戻りなさい。」
と継母が言うのでお信はしぶしぶ厨房へと戻った。しかし、ガーリックシュリンプの感動は未だ継続中であり、その最中にふと妙案が浮かんだ──このガーリックシュリンプを店の新メニューとして採用してはどうだろう?芝エビの原価なんてたかが知れている。ニンニクとバターはラーメン用のやつを兼用すればいい。とすれば五百八十円が妥当といったところか。おかあさまの調理工程を見る限り、その難易度は低く提供時間も短い。そしておかあさまだけでなく、カレーの男もビールのおかわりを注文していることからして、おつまみにもぴったり。そしてこのガーリックシュリンプはほぼ同じ材料でエビラーメンにもシーフードカレーにも化ける。この二つは裏メニューにしよう。よし。いけるじゃん、ガーリックシュリンプ。
そう考えたお信は早速、
「おかあさま。ガーリックシュリンプをこの店のレギュラーメニューにしてみようと思うんだけどどう?」
と提案したところ、
「そうね。そうするといいわ。この店のメニューは他と比べて品数が少なすぎるからそろそろ増やしてみるのもいいかもね。」
継母に異論は無かった。事実、この「ラーメンお信」にはメニューが少なく、どれも似たような品目で構成されていた。ここで、「ラーメンお信」の全メニューを挙げてみると、
・ラーメン ── 三百円
・お信ラーメン ── 四百円
・カレー ── 三百円
・お信カレー ── 四百円
・おしんこ ── 五十円
以上の五品である。たしかにこれは継母の言った通り品数が少ない。そして似通った料理も多く、その違いも一見して分かりづらい。
例えば、「ラーメン」と「お信ラーメン」の違いとは何なのか……と初めて来店した客は大いに戸惑ってしまい、注文の際に「あのー、このラーメンとお信ラーメンはどう違うんですか?」と店主であるお信に質問することも度々であったがその際、決まってお信は得意げな表情を浮かべながら、
「『ラーメン』は鶏ガラベースの醤油ラーメンで、トッピングにメンマ、なると、ゆで卵、ハムが乗っているんですよ。で、『ラーメン』を無化調・無添加で作ったのが『お信ラーメン』です。」
つまり、「ラーメン」と「お信ラーメン」の違いは「化学調味料と添加物の有無」である。
では、もうひとつの看板メニューである「カレー」と「お信カレー」の違いはというと、まず、「カレー」は何の変哲もない昔ながらの食堂のカレーライスであり、トッピングもこれといって際立った食材も使っておらず、豚肉、玉葱、人参、じゃがいもが放り込まれているだけである。一方で「お信カレー」とは、前述のカレーを無化調・無添加で作ったのではなく、いわゆる「キーマカレー」のことをお信カレーと称している。そのため、常連客からは、
「お信ちゃん。これってただのキーマカレーだよね?なら最初っから『キーマカレー』ってメニューに書いておいた方が分かりやすいと思うよ。」
といった指摘を受けたこともあったが、当のお信にしてみればキーマカレーを作った覚えは一切なく、お信は「お信カレーを作ったのだ」と言い張り、常連客の言い分に聞く耳を持たなかった。それもそのはずで、お信はそもそもキーマカレーの存在を知らなかったからである。
その昔、お信が寝る間を惜しみつつ新メニュー開発に取り組み、様々なアレンジの末に完成したカレーは不運にも「キーマカレー」であった。しかし、この偶然の産物を独自に編み出したと勘違いしたお信はこのカレーを「お信カレー」と名付けて販売することに決めた。こうした経緯もあってか、苦心の末にメニュー入りを果たしたお信カレーへの思い入れは非常に強く、そのため常連客が、
「いつものキーマカレーちょうだい。」
と言って注文しても、
「キーマカレーはこの店に無い。お信カレーなら、ある。」
とお信は一歩も譲らなかった。もしこの先、お信がインドカレー屋を訪れて「本当のキーマカレー」を食べたなら、「これってあたしが考案したお信カレーじゃん。ひどい、なんてことするの……」と、メニューを盗作されたと勘違いして悲しむであろう。このように、お信カレーはお信の主義が体現された成果であり、独善を象徴した一品といってよい。
五品目は「おしんこ」であり、これはいわゆる「ぬか漬け」である。
お信の祖母は嫁入り道具としてぬか床を持ってきた。祖母が亡くなると、ぬか床は「生みの母」へと受け継がれ、まもなく母が亡くなり父へと受け継がれ、そして父からお信へとぬか床が託された。お信には祖母との記憶も、生みの母との記憶もほとんど残っていないが、このぬか床からぬか漬けを取り出すにつけ、この世に居ないはずのふたりがぬかを通じてお信に優しく語りかけてくる様な心持がしていた。だがそれにも関わらず、お信はぬか床を触りたくなかった。
たしかにお信がぬか床に血縁めいたものを感じたのは事実であったが、それ以上にお信はぬか床に手を突っ込んでぬか漬けを取り出したくなかった。なぜなら、手がぬかみそ臭くなるからである。これは一見して幼稚な理由であるかのように思われるが、ぬかみその臭いというのは、いつの世もどこかで誰かを苦しめるものであり、そうしたぬかの因果は巡り巡って不幸にもお信へと降りかかってきたのである。とはいえ、父から託されたこのぬか床をないがしろにすることは断じてできない、いやしかし──ぬか床の奥底で眠っている古漬け。これを取り出すのはいつも決まって継母の役目であった。継母にとって「ぬか」はぬかでしかない。
「ちょっとお信ちゃん。あなた客商売してるんでしょう?ぬかみそ掻きまわして古漬けを取り出すぐらい自分でやんなさいよ。」
こればかりはお信も「ごめんなさい。」と言うほかはなかった。お信にとってぬか床は、血縁の親近感を感じさせながらも「触れたくない」という矛盾を孕んでいる。
以上に挙げたラーメン、お信ラーメン、カレー、お信カレー、おしんこ、これらの五品に加えてガーリックシュリンプが「ラーメンお信」のメニューへと新たに組み込まれようとしていた。
大皿に乗っていたガーリックシュリンプは残り少なになっており、おすそ分けを頂いたカレーの男もこれをすっかり平らげて満足気である。お信は「どうやら試食は成功したみたいだわ。」とこちらも満足して、引き続き新メニューの販売計画を練っていたところへ、
「お信!寸胴の火を止めなさい!」
「あッ、忘れてた!」
*
お信は、五徳の上で今まさに火を吹かんとばかりに煮えたぎる寸胴鍋のガス火を止めた。空焚き寸前の鍋肌は焦げ付き異臭を放っており、鍋の中の鳥ガラはもはや鳥ガラの原形をとどめておらず、湯に溶け込んで白濁化していた。
火を止めて一安心したお信が鍋の中を覗いてみると──
「これはもしや鶏白湯スープなのでは……?!」
「馬鹿を言わないでちょうだい。」
後ろに居た継母はそう言うと、続けて、
「鶏白湯スープがどうこう言う前にお信、あなたこの鍋どうするの。すっかり焦げてるじゃないの。もし私がアンタに火を消すように言わなかったとしたら、鍋の空焚きでこの店が火事になってかもしれないのよ?お客さんもまだ店にいるのよ?状況を見てものを言いなさい。あと、こんなの鶏白湯スープじゃないわ。鳥ガラを空焚き寸前まで煮込んで焦げ付かせるなんて工程はどこにもないし、料理にとって焦げの臭いは大敵よ、ありえない。どうせまたいつもの脊椎反射で鶏白湯ラーメンとかいう新メニューを思いついたんだろうけどお信には百年早い、あきらめなさい。そんなことよりもアンタにはまずやることがあるでしょう?鍋の洗浄よ。この鍋にこびりついた焦げを今日中に落としておかないと明日のスープの仕込みに間に合わないわ。開店できないってこと。鳥ガラスープをベースにしてラーメンとカレーを作ることぐらいお信にも分かり過ぎるほど分かってることでしょう?なのに、ラーメンもカレーも無いんなら残るは『おしんこ』しかないじゃない。じゃあ何?明日のラーメンお信のメニューはおしんこだけで勝負するとでもいうの?いつからこの店はおしんこ専門店になったの?この店の屋号をラーメンお信ではなく『おしんこお信』に改名するつもり?それは無駄なことだわ。なぜなら、世の中にはすでに漬物屋が存在するから。おしんこ専門店と漬物屋ではまるで勝負にならないわね。もしこの先、お信がラーメン屋を辞めて漬物屋に転身するというのならまだ望みはあるかもしれないけど……まあどうでもいいわそんな話。とりあえずまずはこの鍋に付いた焦げを落としなさい。それが終わったら反省しなさい。再発防止策は当事者のお信、あなたが考えなさい。もっと周りをよく見なさい。気を遣えと言ってるの。いいこと?」
お信は目が回っていた。継母に圧倒されてしまったからである。
今、お信の頭の中には継母のあらゆる発言が綯い交ぜになって渦巻いており──空焚き、白湯、火事、焦げ洗浄、仕込み、廃業、おしんこお信、漬物屋、気づかい、といった言葉を交えて繰り言が続けられている。
このように、お信は錯乱状態に陥ると目をぐるぐる回して放心してしまう事がよくあり、例えば店のピーク時、お信が多くの客の注文を聞いてそれを順に提供しなくてはならない場合にこの症状は顕著にみられる。これは「ラーメンお信」のメニュー名が見分けにくいことも原因の一端であり、ピーク時の伝票の一例を挙げると「ラーメン、お信ラーメン、ラーメン、お信カレー、おしんこ、ラーメン、お信カレー、カレー、お信ラーメン、おしんこ、カレー、お信カレー、おしんこ、お信カレー、おしんこ、おしんこ、お信ラーメン、ラーメン、ラーメン、ラーメン、お信ラーメン、おしんこ……」といった具合で非常にややこしく、これを目の当たりにしたお信は大混乱を起こしてしまい、客の「お信カレーちょうだい。」という注文にも関わらず「はあい。おしんことカレーですね。」といった間違いを連発し、その結果、お信は目をぐるぐる回して作業を中断してしまうのである。ここでもし、店あるいは家に継母が居る場合、ぐるぐるのお信に代わって厨房に立ち、停滞していたオーダーを次から次へと捌いてお信の窮地を救ってやり、そうしているうちにお信が「ハッ、ここはどこ?」とようやく意識を回復したところで、継母は二階の自室にさっさと戻るのが常である。
──そして今、寸胴鍋を焦がしたことで継母にこっぴどく叱られたお信は、依然として目を回して心ここにあらずであった。
「ちょっとお信!聞いてるの?」
「…………」
継母の声はお信に届いていない。
「お信!お信ってば!」
「…………」
あらら、またこれだよ……と状況を察した継母が仕方なく寸胴鍋に水を張っていると、
「ハッ、ここはどこ?」
お信はようやく意識を取り戻した。
*
「お信、ここは店の厨房よ。」
「あッ、寸胴鍋が焦げてる!くそう、いったい誰がこんなイタズラを……」
と、記憶が甦ったお信はとりあえずしらばっくれた。
「鍋を焦がしたのはお信、アンタよ。」
「そんなまさか。このあたしが商売道具を焦がすなんてありえないわ。」
「それが今回はありえたのよ。お信の不注意の末に鍋は焦げたの。思い出した?」
「いいえ、それがまったく思い出せないの。」
嗚呼……煩わしい。この子は鍋を洗うのがイヤなだけではないのか。口にこそ出さないが継母は、シラを切り続けるお信に嫌気がさしてきた。
「いやあ、ぜんぜん思い出せないや。」
「お信。残念だけど証拠ならあるわよ。」
「何ッ。」
驚くお信をよそに継母が指を差したその向こうには、カレーの男が居た。
「あのおにいさんに聞けば、誰が鍋を焦がしたかなんてすぐに分かることだわ。あの方に客観的な証言をさせてみましょう。」
「え、それはちょっと待って……」
とお信が言うが早いか、継母は、
「おにいさん。ごめんなさいね、少しお伺いしたいことがあるんだけど。」
「何でしょうか。」
「あそこに焦げた鍋があるでしょう?」
「ええ、ありますね。」
「私と娘のみっともない親子ゲンカ、きっとおにいさんの耳にも入って来たわよね。」
「はい。」
「そこでお聞きしたいんだけど、あの鍋を焦がしたのは誰ですか?私?それとも娘?」
「完全に娘さんの不注意で焦げました。」
お信はがっくりとうなだれた。
「ありがとう。それだけ聞ければ十分だわ。変なこと聞いてごめんなさいね。娘にもよおく言い聞かせておくから。あ、焦げについては店の評判に関わるから他言しないでね。」
「はい。」
継母はお信に向き直ると、
「ね、お信ちゃん。鍋を焦がしたのはやはりあなただったでしょう。ただ、今日はもうこれ以上、失敗を責めたりしないから安心なさい。私からお信ちゃんへのお願いはひとつだけ。あの焦げた鍋を綺麗にしなさい。それさえしてくれればいいから。」
「いえ、おかあさま。ちょっと待って!」
──この期に及んでまだガタガタ吐かしてくるとは。ということはこの不毛極まる議論がまだ続くのか。「我」も張り通せば不屈の精神に見えなくもない。こんな事なら焦げた鍋は打ち捨てて、新しい鍋を一緒に買いに行った方が手っ取り早いかもしれない。いや、鍋を買おうが買わまいがどちらにしても面倒なことに変わりはない。そう、面倒なだけだ。そうした継母の内に ″In sooth I know not why I am so sad.″という『ヴェニスの商人』の台詞が浮かんで来たが、自身の料簡があらぬ方へと発展しそうになったため、それはすぐに打ち消した。
*
「お信。いい加減くどいわよ。証拠まであるのに『ちょっと待って』とはなんなの?そんなら私は何を待てばいいのよ?」
「鍋を焦がしたのはあたしじゃない、という可能性を信じて待っててほしいの。希望を捨てないでほしいの。」
「とうに捨ててるわよ。そもそもお信の無実なんて望んでやしないわ。アンタは鍋に付いた焦げを落とすのが面倒でイヤなだけでしょ。なら最初からそう言えばいい。」
と言い捨てて、継母は自らで鍋を洗おうとしたところ、
「おかあさまが鍋を洗う必要なんてないわ!鍋を焦がした人が洗うべきよ!」
お信は鍋を焦がした自覚がありながらも、ここはあえて「鍋を焦がした人」と表現して継母を気遣った。こうすることにより、まず「鍋を焦がした第三者の存在」をほのめかして継母を撹乱させておき、その上で「おかあさまが鍋を洗う必要なんてない」と、慈愛あふれる言葉を継母に掛けてやることで、それらを真に受けた継母が「こんなにも慈愛に満ちた誠実なお信ちゃんが鍋を焦がすわけがない……うちの娘は無実よ!」といったお信びいきの流れに仕向けようと企んだのである。
多少のリスクはあったけど我ながら名演技だったなあ、と得意になったお信は再び、
「だからおかあさま!鍋を洗わないで!洗っちゃダメ!」
「その猿芝居をいつまで続けるの?」
継母はお信の目論見を見抜いていた。
「もしやあなた、猿なの?」
「猿じゃないわ。」
「じゃあ何なの?」
「慈愛に満ちた誠実な人間よ。」
「ウソばっかり。アンタは慈愛に満ちた誠実な猿よ。もういい。猿に用はない。」
継母は金ダワシを使って鍋の焦げを落とし始めた。──お信の目論見の半分は成功したが、もう半分は失敗に終わった。つまり、当初の目的である「鍋の洗浄はやらない」はとりあえず維持できたものの、そのせいでお信は継母からの信頼を失い、さらに「慈愛に満ちた誠実な猿」という烙印まで押されたのである。
お信は屈辱を覚えた。慈愛に満ちた誠実な猿とは要するに「性格の良い猿」だからだ。猿は猿でしかない。こうした点にお信の自負心は大いに傷つけられたのである。
*
継母は依然変わらず無心で鍋の焦げを落としている。
「ちょっとだけ手伝ってあげようかな……」
お信はふとそう思った。焦げた鍋の洗浄を手伝うことで、一度失った継母からの信頼を再び取り戻すことができると考えたのである。いやそれだけではない、とお信は思った──おかあさまの信頼回復とは即ち、猿から人間への復帰であり、かつて受けた屈辱からも立ち直ることができるではないか。よし、おかあさまをほんのちょっとだけ手伝ってあげよう、そうしよう。
「おかあさま。あたしも少し手伝うわ。」
「いいえ。猿ができる作業はないの。」
ウキキー。またしてもお信は屈辱を受けた。
「そんなこと言わずに。ね、おかあさま。なにか手伝えることってないかしら?」
「ない。」そう言って継母は立ち上がると、
「お信。その『手伝う』という表現を改めなさい。これは本来なら鍋を焦がした張本人のあなたが担当する作業です。この場合、『手伝う』はまったく不適切だわ。」
「ちょっと待って!鍋を焦がしたのはあたしじゃない!」
「そう。また猿芝居の幕開けってわけね。やっぱりあなた、猿なの?」
「猿じゃないわ!」
「じゃあ何なの?」
継母から再び迫られたお信は「なぜあたしは鍋を焦がしたことを頑なに認めないのだろう?」と自分の胸に問いかけた。鍋を焦がしたのはお信。それはお信ですら分かっている。ではこれが一体何を意味するのか──鍋を焦がした失敗、猿と呼ばれた屈辱、認めたくない事実、ラーメン屋としての恥、いや意地、ではなく誇り、誇り……お信は気づいた。
「猿じゃないならあなたは何なの?」
「……あたしは料理人、お信よ!」
お信は継母の目を見てしっかり答えたが、
「で、どのへんが料理人なの?」
「どのへんって言われても……」
「答えられないのね。ならお信、やはりあなたは猿よ。猿は猿らしく山でアケビでもかじってなさい、今が旬だから。」
継母の嫌味にお信は苛立った。
「ちがう!あたしは猿じゃなくて料理人よ。」
「料理人ならアケビぐらい当然知ってるわよね?」
「今が旬の食材だわ。」
「それはさっき私がお信に言ったことじゃないの。そんならプロシュートって何か答えてごらん?」
「サッカー選手のことね。」
「ちがうわ生ハムよ。」
そう言うと継母は再びお信に背を向けて鍋を洗い始めた。
*
──無知の知。知識を誇示する者はやがてその知識に縛られる。知識の果ては無い、この前提が無い者は「上」が存在することを知らない、もし仮に知っていたとしても認めないだろう。だから驕慢が生じる。だから縛られる。だから発展が無い。己の無知への依拠、知らないことを知っていると断定する態度、例えば、お信は「プロシュートはサッカー選手」だという事を知っている。そう、なぜか「知っている」ものとして完結しており、これでは思考の停止だろう。ならば、可能な限り思い込みを排除して意欲的に知ろうとするべきではないのか。つまり謙虚さを自覚の上で探究をするのが無知たる者として当然の態度ではないだろうか。それはこの私も含めてだ……
そう考えた継母は再びお信の方へ向き直ると腕を組み、そして目を閉じたまま「お信、よく聞きなさい。」と次の様に語り始めた。
「お信、よく聞きなさい。あなたは料理人だと言い張っておきながらアケビ、プロシュート、ガーリックシュリンプ、オレガノがどういったものかまったく知らなかったでしょう。でもそれはどうだっていい、何も問題は無い。なぜなら、さっきお信は私がガーリックシュリンプを調理する工程を見て、出来上がったそれを食べて、そして『とても美味しい』と言ったから。料理人としてガーリックシュリンプを学ぶことができたから。いや、それだけじゃない。お信はこのガーリックシュリンプを新メニューにしようと私に提案したわよね?そして私はこの提案に賛成したでしょう?それはお信の成長を見込んでの賛成なの。ガーリックシュリンプを知らなければここまでの発展はなかったはず。……はい、ではこれを踏まえて本題に入ります。つまり、お信が不注意で鍋を焦がした件についてです。まず、お信には『鍋を焦がすのはプロの料理人として失格だ』という思い込みがある。それはお信の傲慢な精神がそうさせている。自分自身に忠実なのは良いことなのかもしれない、でもそれがあまりに過ぎれば傲慢でしかない。だからお信は鍋を焦がしたことを認めようとしない。思いあがりともいえるわね。で、あなたは料理人として大成したければこの思いあがりを捨てなさい。人間である以上、プロでも鍋は焦がす。人間に絶対は無いから安心しなさい。失敗を認めて学びを得る。そうしてお信は成長する。その基礎となる謙虚な姿勢を忘れず日々精進しなさい。私からは以上。……もし、お信が私の考えに納得できたのなら、これから私に代わってあなたがこの焦げた鍋を綺麗にしなさい。何の苦も無く作業に取り組めるはず。そのうえで私はあなたのことを料理人だと改めて認めることにする。さあお信、納得したの?どうなの?」
*
すでにお信は目をぐるぐる回していた。
お信目がけて飛び込んでくる大量の言葉によって再び頭が大混乱を起こし、その結果、お信は継母が話した内容のほぼ全てを聞き逃していた。
継母は激しい憤りに震えた。しかし理性がそれをかろうじて抑えつけた。
「ハッ、ここはどこ?」
お信は我に返ると、
「そうだ……思い出した!おかあさま!プロシュートは生ハムじゃなくてサッカー選手のことよ!サッカー選手に決まってるわ!」
「お信がそう思うならもうそれでいい。プロシュートはサッカー選手のことかもしれないわね。なら、そうなるように、サッカー選手がプロシュートに限りなく近づけるように、あなたはあなたの探求を続けなさい。」
継母はため息交じりにそう言った。そして再び「はぁ……」と今度は深いため息が出た。その態度にお信は思わず、
「馬鹿にしないで!かしこぶらないでよ!あたしだって何でも知ってるもの!プロシュートだってガーリックシュリンプだって前から知ってたわ!おかあさまの方こそなにも分かっちゃいないくせに!」
「ええそうよ。私は無知な存在だと自分で認めてるわよ。ま、少なくともお信の知識量より私の方が圧倒的に上だけどね。」
皮肉が継母の口をついて出てきた。
「そんなわけないわ!なにも知らないはずよ!」
「少なくともお信よりは知ってるわ。お信よりはね。ためしに何か質問してごらん?」
最早どうでもよくなりつつある継母は無意識にお信を弄びはじめた。
「ええと、じゃあさっそく聞くけど……」
とは言ったもののお信は「ええと、じゃあ」を繰り返している。さらに数分が経った。
「ああもうホントじれったい子ね。質問すら思いつかないの?答えてあげるってんだからさっさと質問してみなさいよ。」
「…………あッ!」お信は閃いた。
「ではおかあさまに質問します。」
と言ってお信は一呼吸置くと、
「モイスチャーってなあに?」
*
「え……?」
「モイスチャーが何なのか、おかあさまなら分かるはずよね?」
継母は己を恥じた。継母はモイスチャーなるものを知らなかった。が、かといって、継母は知らないことに恥じたのではない。先程お信に対して、謙虚な姿勢で知ろうとすべきだとあれほどまでに訴えたにも関わらず、お信が話を聞いていなかったことに腹を立て「お信の知識量より私の方が圧倒的に上だ」と傲慢な態度を取ったこと、この己の未熟さに今さら気付いて恥じたのである。
「物知りのおかあさま、早く答えて?」
「私の能力ではモイスチャーの説明はできない。自分で調べなさい。」
この言葉を聞いてお信は勝ち誇った。
「……ってことはおかあさまはモイスチャーを知らないのね、あはは。あのおかあさまがモイスチャーすら知らないなんてねえ。こんなの一般常識よ、常識。知ってて当然よ、当然。」
「常識?当然?そんならお信、アンタは答えを知っているとでもいうの?さっきから知ってる風で私の事を小馬鹿にしてるけど当然知ってるのよね?」
「いや全然知らな……」
と言いかけてお信は口ごもった。
当然お信も継母と同様、モイスチャーを知らなかった。
しかし、ここはあえて「知ってる」と答えるのが最適だと判断した。そうすることで「モイスチャーを知らない継母」に対し「モイスチャーを知っているお信」という関係が生じ、その結果、継母よりもお信が知識の面で優位な立場となり、つまり、ガーリックシュリンプやプロシュート等々を知っている継母への復讐が成立するのである。
──でも、それにしてもモイスチャーって何だろう?ここでもし、あたしが「知ってる」とおかあさまに言えば「じゃあ教えて」と言い返してくるに違いない。それをどうやって乗り切るか……と、お信は一瞬悩んだがふと、「あッ!」とある事を思いついた。
*
店内のカウンターには依然としてカレーの男が座っておりその目線の先には、焦げた寸胴鍋の前で対峙した娘と母親の姿があった。
「モイスチャーを知ってるの?知らないの?どっちなの?」
「知ってるよ。」
「そんならモイスチャーとは何か説明してみなさいよ。」
「では、無知なおかあさまのためにこのあたし、お信が説明してあげます。モイスチャーとは……あ!でも待って!もうすぐ店の閉店時間だ!のれんを外さなきゃ!のぼりもしまわなくっちゃ!おかあさま、ちょっと待ってて!」
と慌てたフリをして厨房からカウンターに回るとカレーの男に、
「お客さん、ラストオーダーですけど注文どうします?」
と声を掛け「いえ、もうけっこう。」と男からの返事を聞くと、お信はそのまま店の外に出て戸を閉め、のれんものぼりも片付けることなく、着物の裾をからげて一目散にどこかへ駆けていった。
そうして店には継母とカレーの男が残った。
継母は、お信が表の片付けを終えたらすぐに戻ってくるものと思っていたが一向に戻らないので、焦げた寸胴鍋を仕方なく洗い始めた。
一方その頃、お信はというと──ある場所を目指して走っていた。
「この企みがおかあさまにバレてはまずい、すぐに戻らなくては……」
とお信は履いていた下駄を脱ぐとそれを掴んで裸足になって先を急いだ。お信の不審な行動に気付いていない継母は相変わらず鍋を洗っている。
「ふう、やっと着いた。」
と肩で息をしているお信の目の前には、お信が昼間に訪れて『パイドロス』を購入したあの本屋があった。お信はあらためて下駄を履き、呼吸を整えてから店に入ると百科事典のある棚へ一直線に向かった。
つまり、お信は「モイスチャー」の意味を百科事典で調べようとしたのである。
*
しかし、昼間に訪れた時はたしかにあったはずの百科事典はそこには無かった。
おかしい!絶対この棚にあったのに!まさか売り切れ?百科事典を買う人がいるなんてまさかそんなことって……
「ちょっとおじさん。」
とお信が店員に声を掛けると、
「ああ、たしか昼間にパイドロスを買ったおじょうちゃんか。どうしたんだい?」
「百科事典はどこ?買うから早く出してちょうだい。」
「さっき売れたからもう無いよ。」
一瞬、お信は呆然となったが、
「在庫も、無いの?」
「無いよ。あの棚にあったのが最後の一冊だったんだ。残念だね、またおいで。」
これを聞いたお信の呆然はみるみるうちに怒りへと変わった。
「おい本屋のおやじ!残念だねじゃないわよ!残念なのはアンタのその能天気な仕事っぷりよ!百科事典は売れるに決まってるんだから在庫管理ぐらいちゃんとやっとけってのよ!それがなんだ、売り切れだあ?なに勝手に売り切れてんのよ?!百科事典ぐらい常に仕入れときなさいよ!一生涯に渡って仕入れ続けなさいって言ってんの!どうせ売れるんだから!どうしても仕入れたくないってんならこのアタシのためにキープしておくぐらいの気を利かせろってのよ!ねえアンタそれでも商売人なの?!客商売やってんならもっとアタシのことを見据えた商売しろってのよ!アタシ中心にこの本屋を回せって言ってんの!わかる?なにボーっと突っ立ってんのよ?そんなヒマがあったらアタシのためにさっさと仕入れに行って来なさいってのよ!ああもうすべての歯車が狂った!どうしてくれるの?!パイドロスとかいう珍妙な本は置いてあるくせに売れ筋メガヒット商品の百科事典が店に一冊しか置いてないってのはアンタさあ……客をバカにしてるのと同じよ!おととい来やがれ!二度と来るか!このケチ!」
興奮のままに言い終えるとお信は店を飛び出した。
本屋のおやじは自分がどういう理由で怒られているのかよく分からないまま、下駄を脱いで裸足で駆けていくお信の後姿を不思議そうに見ていた。
この間、店にいた継母はお信が表で片づけをしているものと思い込んでいたが、十数分経っても戻らないことを不審に思った。
百科事典を求めて次なる本屋へと急ぐお信の頭の中には「お信めがけて容赦なくモイスチャーを投げつけてくるおかあさまの図」なるものを無意識に思い描いていた。ここでいうモイスチャーとは、モイスチャーの実体ではなく、単純に「モ」「イ」「ス」「チ」「ャ」「ー」という文字列がお信に襲い掛かってくるだけであったものの、これに恐怖と焦りを覚えたお信は一層せかせかと走り続け、町内にあるもう一軒の本屋「民々書房」という古書店にようやくたどり着いた。
「民々書房って汚いからあんまり入りたくないんだよなあ。」
と店に入るのが一瞬ためらわれたが、そうも言ってられないので、立て付けの悪い引き戸をガタガタと開けてお信は中に入った。予想通り、店内は古書から発散された独特の匂いが充満しており、大量の古書で埋め尽くされた茶色い汚らしい空間を恐る恐る進むと、その奥で店主と思しき老人がお信の目に留まった。
老人は干柿をかじっていた。
「すみません。百科事典ありますか?」
「ああ。ちょっと待ってな。」
と言って老人は立ち上がると、うず高く積み上げられている本と本の間に挟まれていた百科事典を造作も無く引き抜いてお信に手渡した。古書というだけあって装丁はボロボロであった。
「ちょっと古いけどこれでいいかい?」
「……ええまあ、はい。じゃあこれをください。いくらですか?」
「五千円。」
高過ぎやしないか。とお信は怪しんだがやむを得ず購入して民々書房を後にした。ボロボロの百科事典は懐に上手く隠してある。
*
「お信の様子が明らかにおかしい。」
そう確信した継母は、店の表で片づけをしているであろうお信の様子を確かめるべく、自分も店の表に出ようと戸に手を掛けようとしたところ、戸は向こうからガラッと開き、
「おかあさまおまたせ!」
と汗だく姿のお信が戻ってきた。その両脇には店ののれんとのぼりを抱えている。
「お信。アンタやけに遅かったわね。どうしてそんな汗まみれなの?」
「一生懸命になって表を片付けてたからよ。」
「片付けるのはのれんとのぼりだけなのにどうしてこんなに遅くなるの?」
と言って継母は壁の時計を指差すと、既に二十二時を回っていた。これはお信が本屋に行って帰って来るまでに三十分が経過していたことになる。
「いえ、おかあさま。それにも理由があって……」
とお信はなおも食い下がり、
「あたしが一生懸命に表を片付けてたら、偶然そこを通りかかった昔の親友とバッタリ会って、で、久々の再会に嬉しくなって、ええと、その友だちとさっきまでずっと表で話し込んでたの。だから遅くなったってわけ。」
「久々の再会?誰と再会したの?」
「パ、パイドロ……パイド郎くんよ!」
「ぱいどろう?変な名前ね。外国人かしら。」
「そうなの。パイド郎くんは留学生なの。」
「ふうん。どこの国の人なの?」
「古代ギリシャ。」
これを聞いて呆れた継母は自室に戻ろうと思い、何も言わず踵を返そうとしたが、
「おかあさまちょっと待って!そんな話はどうでもいいの。本題はモイスチャーでしょう?モイスチャーを知りたいんじゃなくて?」
そういえばそうだったな、と継母はモイスチャーの件を忘れていた事に気付いた。
「そうね。ならモイスチャーって何なの。」
「では説明します。でもその前に……」
とお信は継母にサッと背を向けて、懐からボロボロの百科事典をこっそり取り出すと、気づかれないよう慎重に百科事典のページをめくり始めた。お信はモイスチャーの意味が書いてある「も」の索引が近づくにつれて心の中で高笑いしていた──モイスチャーを知らない馬鹿なおかあさま。もうじきすべてが明らかになるわ。あたしがこれまでに受けた屈辱、今度はおかあさまが味わうがいい……
と百科事典のページを順調にめくっていたが瞬間、お信の手がぴたりと止まった。そして震え始めた。震えたのは手だけにとどまらず、全身までもがぶるぶると震え始めた。
なぜなら、この百科事典は「も」のページがごっそり抜け落ちていたからである。
「ちょっとお信。どうしたの?さっさとモイスチャーを説明しなさいよ。」
「…………」
「お信、こっちを向きなさい。お信ってば。」
「…………」
またお信の様子がおかしい、そう思った継母は背後からお信を覗き込むと──
「も」が欠落した百科事典を両手に握りしめたまま、ぽろぽろと涙を流して震えているお信の姿があった。
*
「なるほどな。」
お信の目論見を察した継母は、背後から正面に回り込むと、
「お信ちゃん、そんなことぐらいでなにも泣くことないでしょう。」
「だって、だって……」と言ってお信は泣き止もうとしない。
「大丈夫、気にすることなんてないわ。わざわざ百科事典まで買ってモイスチャーを調べようとしてくれたのね。」
と言って継母はお信から百科事典を取り上げてページをめくりながら、
「まあひどい。こんな状態ならページが抜け落ちててもおかしくないわ。ねえお信ちゃん、この百科事典は一体どこで買ったの?」
「民々書房……」
え、よりによってあの悪評高い民々書房で買うなんて。継母は驚いた。
「で、いくらしたの?」
「五千円……」
──高過ぎる。ぼったくり価格ではないか。もしこんな紙屑同然の百科事典に五千円を払う者がいたとしたら、それは間違いなく馬鹿だ。紛れもない「愚」だ。正真正銘、疑う余地もない完全なる馬鹿野郎だ。そしてそれは我が娘、お信。今現在、この裁量は親である私に委ねられているが判断するまでもない、まさに烏滸の沙汰というやつだ……
継母は無性に苛立った。
「お信、アンタわざわざ百科事典なんて買ってまでモイスチャーを調べようだなんて馬鹿げてるわよ。第一、まだ営業時間中だというのに店をほったらかしにして本屋へ行くのも言語道断だわ。そんなのただの業務放棄でしょう。アンタ今年で何歳になったのよ?十八にもなって馬鹿な真似してんじゃないの。もっと仕事に責任感を持ちなさい。」
「だって、だって……」とお信が未だに目を腫らして泣いているのも気に食わないので、
「しつこいわね。だってがどうしたというの?何が『だって』なのよ?」
「だって……あと少しでおかあさまにトドメを刺せそうだったんだもの。」
この発言に再三の苛立ちを覚えた継母は、今一度の冷静と泰然を自身に促した──結果はどうあれ、お信もお信なりに必死になってモイスチャーを調べようとしたのは事実だ。とすれば、お信のそうした果敢な姿勢と行動力は評価してあげてもいいのではないか。若さに勢いは肝心だ。その「勢い」があらぬ方へ向かうことのないよう、軌道修正してやるのが私の役目だろう。我が娘、お信なら今回の失敗を糧にきっと成長してくれるはず。だからあの五千円はあの子が成長する上での代償、すなわち良い勉強代になったと考えれば安いものだ。
継母の怒りはほんの幾分かやわらいだ。
「お信、さあ涙を拭きなさい。今日はもう遅いからモイスチャーはまた明日以降に調べることにしましょう。大丈夫、私も一緒に手伝ってあげるから。ほら、もう閉店時間よ。店じまいしましょう。」
こう言うと継母はお信の背中をさすってやった。
「おかあさま、今日は変なことばっかり言ってごめんね。意地っぱりでごめんね。」
お信はようやく素直になった。
時刻はとうに二十二時半、『ラーメンお信』の閉店時刻である。それに合わせてカレーの男が帰り支度を始めようとすると、
「お客さん、すみませんが閉店なのでお会計お願いします。」
「はい。」
カレーの男はお信と共にレジへ進んだ。
「千八百円になります。」
男は財布から丁度の額を支払った。
「ありがとうございました。ではお気をつけて。」
とお信がカレーの男を送り出そうとすると、男は不意に、
「娘さん。僕は『モイスチャー』を知っていますよ。」
「え!ホントですか!」
驚くお信とは反対に「本当です。」とカレーの男は至って冷静である。継母は二人の様子に黙って聴き耳を立てている。
「モイスチャー、知りたいですか?」
「はい!ぜひ教えてください!」
「お教えしましょう。モイスチャーは……」
お信は息をのんで男の説明を待った。
「モイスチャーは……熱海にある。知りたければ熱海に行きなさい。」
*
「え、熱海?」
「そうです。熱海に行けば分かります。」
こうしたカレーの男からの回答を聞いて、またしてもお信は不服を覚えたため、
「おにいさん、それは回答として不十分だと思いますよ。だってそうじゃん、モイスチャーの性質なり特徴なりを具体的に説明してないんだもの。おかあさまと同じでおにいさんも不親切よ。」
と不満の声を上げたがそうしたお信をカレーの男は意に介さず、
「どこが不親切なものか。熱海にあると断言してあげたでしょう。言い換えれば、モイスチャーは熱海に行かないと分からないと言うこともできます。モイスチャーを言葉で説明してほしいですか?先に言っておきましょう、それは断じて不可能です。」
と言い切った男はお信と継母を交互に見ると、続けて、
「言葉で説明できないものは世の中に無数にあります。例えば、カレーを食べたことがない人に『カレー味』を伝えるのは不可能だと思いませんか?ターメリック、ガラムマサラ、クミン、コリアンダー、オールスパイス等々、数十種類のスパイスで味付けした料理がカレーです、と言われてあなたは味の想像がつきますか?納得できますか?到底承知できないでしょう。つまり、カレーを食べてみないことには『カレー味』は分かりません。モイスチャーもそれと全く同じ代物です。ではどうするか。百聞は一見に如かずといった故事もある様にモイスチャーを知りたければ熱海へ行きなさい。それがモイスチャーを知る唯一の手段なのですから。」
カレーの男が言い終えるとお信は、
「なるほど……」
とどうやら腑に落ちた様子であり、継母の方へ振り返ると、
「おかあさま、モイスチャーは熱海にあるんですって!行きましょうよ!」
「待ちなさい。熱海にある、と漠然と言われても熱海のどこにあるか分からないわよ。第一、モイスチャーが物質なのか事象なのかといったように概括をはっきりさせた上で地図でも書いてもらわない限り、熱海に行ったところで路頭に迷うのは目に見えて明らかだわ。」
このように継母は半信半疑だったが、そこにカレーの男が割って入り、
「心配ありません、熱海に行けば否が応でも分かりますから。モイスチャーとは元来そういうものです。繰り返しになりますが、理論と伝聞を把握する前にまずは体験という証拠から理解に臨んでみてはどうですか?『ガーリックシュリンプ』という字面から完成形を想像するのはいともたやすいことですが、それだけで価値判断をくだすのは真実を捕らえたのではなく、想像をたくましくしただけですからね。」
「……そうね。」
継母は再びお信へ顔を向けると、
「せっかくこのお兄さんが情報提供してくださったんだし、物事を知るには実地にて確かめるべきという考え方に関しては私も賛成だわ。お信、熱海に行ってみましょう。」
「やった!熱海旅行だ!」
お信が喜んでいる傍らでカレーの男は薄ら笑いを浮かべていた。
*
「じゃああたしたちはモイスチャーを探しに熱海へ行ってみようと思います。おにいさん、今日は色々と教えてくださってどうもありがとうございました。」
お信が礼を述べると、
「こちらこそごちそうさま。」
と簡単に済ませて男は店を後にした。
男を見送るとお信は嬉しそうに店内の後片付けを始めた。
「お信ちゃん、じゃあそろそろ私は部屋に戻るから。あとは頼んだわよ。」
と言うと、継母は厨房奥に続く土間を上がり居間を抜けて二階の自室へ戻っていった。
「はあい。」とお信は返事をしたものの、頭の中は熱海旅行で一杯である。
カウンター席の掃除を終えたお信は続いて厨房へ入ると「あッ。」と声をあげた。そこにはお信が焦がした寸胴鍋がすっかり綺麗な状態で置いてあったからである。
自室に戻った継母は椅子に腰かけると机に片肘を付き、何を考えるでもなくある一点を見つめていた。階下からはお信が店内を掃除する音が聞こえてくる──フライパンやバットといった調理器具をごしごし洗い、デッキブラシで床をしゃかしゃか擦っては、バケツから床めがけて勢いよくザーッと飛び出す水、それらの音はいつもより小気味良く、それはそのままお信のすうっとした気持ちの現れでもあり、そこに鼻歌も重なってやはり上機嫌のお信であった。
継母はおもむろに椅子を離れると、傍らの本棚からオックスフォード英語辞典を取り出して「moisture」の見出しに目をやった。そしてmoistureの語意だけでなく語源・用法にまで目を通して理解し終えると、およそ安堵とも落胆とも似つかない深い溜息が漏れた。
【第二部へつづく】
付録その①「お信 絵かきうた」
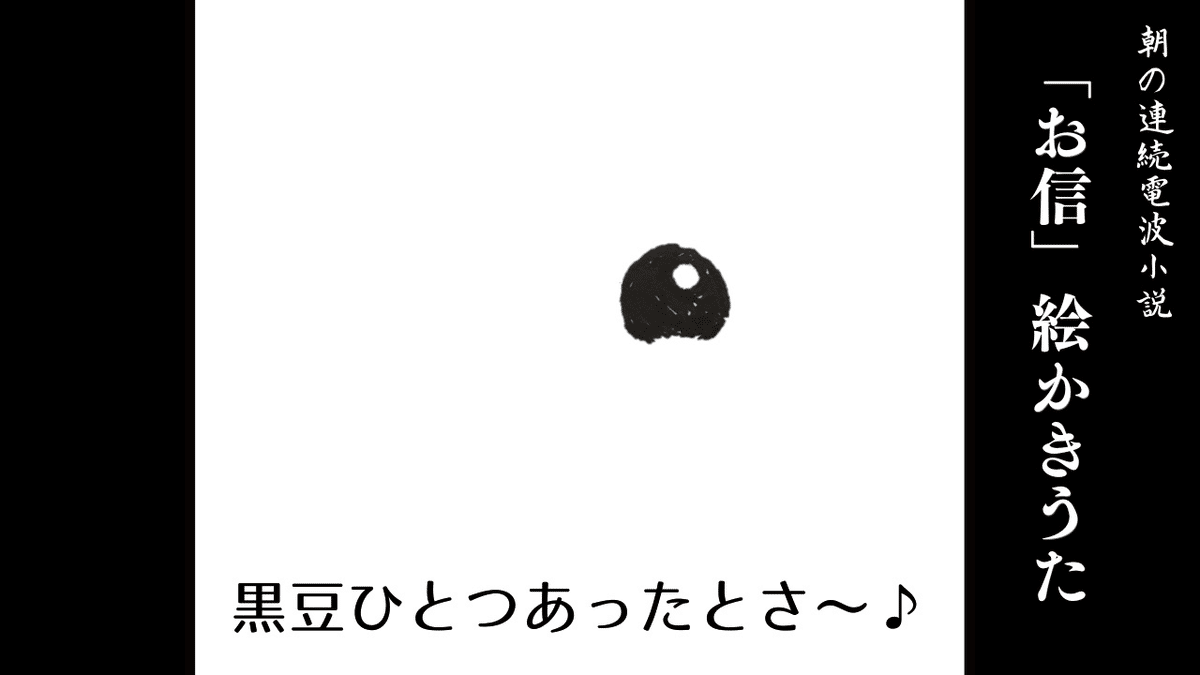










付録その②「お信百景」


母は店内に入るとカレーの男をよそに冷蔵庫から瓶ビールを取り出し、カウンターの奥へと座った。



「ぱいどろう?変な名前ね。外国人かしら。」
「そうなの。パイド郎くんは留学生なの。」
「ふうん。どこの国の人なの?」
「古代ギリシャ。」





以上
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
