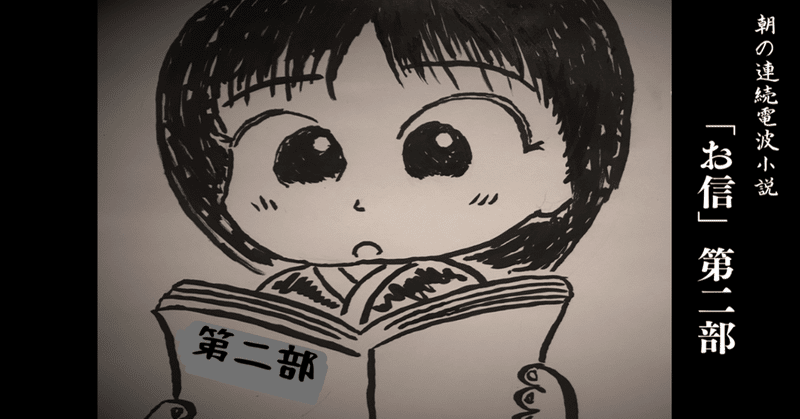
【小説】お信(第二部)
『お信』
第二部
翌朝。お信が目を覚ますと六時であった。
お信の普段が今日も始まる。
お信は布団からのそのそと這い出て眠い目を擦りつつ雨戸を開けると、部屋中に朝日が差し込んだ。それに気づいた小猫も起き上がり庭へ駆けて行けば、その後ろを親猫もそろそろと追いかけていく。
簡単に顔を洗い終えたお信は庭から表玄関へまわって、格子戸に挟まれていた朝刊を抜き取り、そこで大きな伸びをした。
玄関の軒に掛けた簾にはつるが絡み、そこから朝顔が花を咲かせている。その見事な大輪に思わずお信は、
「手塩にかけて育てたかいがあったわ。」
と感慨深げにつぶやいたが、この朝顔を手塩にかけて育てたのは継母である。
お信は玄関から庭へ回り、縁側に腰を下ろすと朝刊に目を通した──まずは一面に掲載されている今日の天気、気温、湿度を確認した。
「天気はくもり、気温は二十四度、湿度は五十二パーセント……ってことは、今日はおしんこの注文が殺到しそうだわ。たくさん仕込んでおかなきゃ。」
このようにお信は天気予報から今日の客入りであったり、よく出る品を直感で予想するのが日課である。続いて、お信は新聞を裏返してテレビ欄を熟読した。が、これといっておもしろそうな番組が無いのを残念がった。そして最後に社会欄を開き、その左端に掲載されていた四コマ漫画を読んでお信はゲラゲラと声を上げて笑った。新聞の四コマ漫画でゲラゲラ笑うのはこの町内でもお信だけである。
朝刊を読み終えると、お信は居間を通じて「ラーメンお信」の厨房へと入り、土鍋で米を炊き始め、並行してどくだみの葉をヤカンに入れ、火をかけて茶を沸かし始めた。お信にとって茶といえば、それは「どくだみ茶」のことを指している。ここで冷蔵庫から昨日の売れ残りの食材を取り出し、それを猫に与えてしばらくぼんやりしていると土鍋の中の米がようやく炊き上がった。
お信は父の霊前に一膳飯とどくだみ茶を供えた。椀はいずれも父が生前に愛用していたものである。
「おとうちゃん、おはよう。今度あたしは熱海に行くことになったんだよ。いいでしょう?なんだかよくわかんないけどさ、熱海にはモイスチャーがあるみたい。なに心配いらないわ、おかあさまも一緒だから。熱海から帰ってきたらおとうちゃんにもモイスチャーがどういうものなのか教えてあげるね。」
言い終えたお信は位牌に向かって手を合わせると、つい先ほど供えた一膳飯とどくだみ茶を父から取り上げてちゃぶ台に移し、そして椀の飯を食べ始めた──美味い。飯は土鍋で炊くに限る。あっという間に食べ終えたがしかしまだ食べ足りない。お信がおかわりに立ち上がろうとすると、
「またいつもの柔ご飯か。あんたも飽きないわね。」
一部始終を後ろで見ていた継母がお信に声を掛けた。
「あ、おかあさま。おはよう。」
とお信は言ったが、継母は特に返事もなくそのまま表に出た。
それから少し経って自販機から缶コーヒーを買った継母が戻って来ると、お信はご飯のおかわりを食べていた。継母はちゃぶ台の上にボロボロの百科事典と『パイドロス』が置いてあるのに気付いた。
「お信はパイドロスなんて読むのね。」
「ちょっと読んでやめたの。難しくてよく分からないんだもの。」
「単なる会話劇だと思えば読みやすいわよ。ま、お信にはまだ早いかもね。」
そう言って継母はパイドロスを取ると、
「ちょっと借りてくわよ。」と言ってから、
「あと、これも。」
とボロボロの百科事典も借りて自室に戻ろうとしたが、
「おかあさま、ちょっと待って!昨日のこと忘れてないわよね?」
「忘れたわ。」と継母はシラを切ったが、
「熱海に行くって約束したじゃん!モイスチャーを探しに行くって昨日決めたじゃん!忘れたなんていじわるよ!」
その声だけでなくお信の大きな目もほとばしる熱意となって継母に訴えかけてきた。こうなっては朝から鬱陶しくて仕方ないので、
「ああ、旅行の約束ね。行きましょう。」
とだけ済ませて継母は自室に戻ろうとしたが、お信がまだ離そうとしない。
「いやちょっと待ってってば!おかあさま、熱海旅行はいつにするの?明日はどう?あたしはいつでもいいよ。ねえどうする?」
「まあ少しは落ち着きなさい。明日すぐに熱海だなんてそんな急には無理よ。」
「じゃあ、おかあさまはいつがいいの?」
とお信に尋ねられた継母は「そうね……」と居間の隅にある仏壇を見た。お信が立てた線香の煙がうっすらと漂っている。
「今度のお彼岸に行きましょう。」
こう言うと継母は二階の自室へさっさと戻っていった。
継母は死者への儀礼、その形式に甚だ無関心である。たしかに「死」という客観的事実は誰の目にも共通しているが反面、残された者にとって死から受ける感情は各人に相違あって然りと考えた継母は、その態度として供え膳といった一般的な供養に己の感情を象徴させたくないのである。かといって、継母は今朝お信が行った父に対する一膳飯、焼香、合掌といった一連の行為を決して厭わしいものだとは考えておらず、それがお信から亡き父に対する奉仕の形として「善い」と本人が判断したのなら異論は特に無い。そして共感も無い。ただ継母はそうした形式に従わないだけである。
──おそらくはあの子が興味本位で買ったであろうパイドロス。そしてモイスチャーのために止むを得ず買った百科事典は「も」の索引が抜けているという始末。
この二冊を机に並べて継母は昨日の事をうっすらと振り返っていた。百科事典を手にすると「も」が欠落したページには当然大きな隙間ができている。継母はそこにパイドロスをなんとなく挟んでみた。パイドロスは隙間にぴったりとはまった。
「そういえばお信と遠出したことは今まで一度も無かったな。」
継母は缶コーヒーを一口飲んでから手元の本を机の隅に押しやるとそのまま書き物の仕事を始めた。
*
お信は壁に掛けてあるカレンダーの九月二十三日の箇所にマジックペンで大きく目印を付けて、そこに「熱海モイスチャー」と書き込んだ。まだ二週間先である。にも関わらず、お信はすでに旅気分でそわそわして気が気でない。気が付けば土鍋の飯はとうに平らげており、どくだみ茶はすっかり冷めきっていた。
お信は少し横になった──これがあの旅枕というやつか。当日は果たして眠れるだろうか。いや前日こそ一睡もできない気がする。ああ、だめだ。どうしても落ち着かない。
「ちょっと気分転換でもしようかな。」
お信は庭に出て納屋から竹馬を取り出し、そして「そりゃッ!」という掛け声と共に竹馬に飛び乗ると庭をぐるぐると歩き始めた。
竹馬は、通常の歩行とは違って右手と右足、左手と左足を同時に動かして歩くのが特徴であり、これに違和感を覚えてしまうとたちまちバランスを崩してしまい、竹馬から落ちてしまう。そうならないよう、お信は自らの手足を竹馬に託すことで、つまり、竹馬との一体感を意識することで完全なる手足と竹の連動を実現、その結果、お信は自由自在な竹馬歩行をものにしたという。こうしたお信の普段の努力は「竹馬」という特技となって実を結んだのである。
竹馬に乗ったお信がずんずんと音を立てて庭を周回していると、その後ろから小猫がついて来た。
「ほらほらネコちゃん、ここまでおいで。」
小猫も負けじとみゃーみゃー鳴いてはお信を追いかける。
「そんな四足歩行のネコにあたしの竹馬歩行が負けるわけないわ!」
みゃーみゃー。
「のろまなプチネコちゃん!こっちよ!」
みゃーみゃー。
「あはは!ここまでおいで!」
みゃーみゃー。
「所詮ネコだわ!ほらほらこっちよ!」
と、突然二階の窓がガラッと開いて、
「お信、朝からうるさい。近所迷惑よ。くだらないことしてないでさっさと仕入れにでも行ってきなさい。」
と言って継母が勢いよく窓を閉めた途端、驚いてバランスを崩したお信は竹馬から転げ落ちた。小猫は塀をよじ登って「みゃあ」と鳴いてどこかへ去って行った。
お信と継母の二人は「ラーメンお信」の売り上げだけではとても生活していかれない。お信がラーメン屋を営む傍らで、継母は書き物の仕事で得た収入を当面の生活費に充てている。ただ、継母は年がら年中休まず仕事をしている訳ではなく、二人がむこう半年は暮らしていける程度の貯蓄が出来ると、仕事をすっぱりと止めてあとは気儘に過ごすのである。継母が「ラーメンお信」を手伝うことはほとんど無く、店の経営に影響を及ぼしそうな場合に限り事態収拾に努めることにしている。そもそも継母は仕事や家事労働といったものに興味が無く──たしかに才や腕はあるにせよ、そういった事は他人がやればいいとすら思っているが日々直面する衣食住という基礎を維持しなければならないため、継母も他人と同様に仕事せざるを得ないのが実際のところであった。継母にとって仕事とは時間の虚しい浪費でしかない。
「とりあえずお彼岸までにはある程度片付けておくか。」
そう言うと継母は今日の仕事に仕方なく取り掛かった。
お信は自分の上半身程もある大きな買い物カゴを提げて、今まさに勝手口から表に出ようするところであった──ああ、早く旅行に行きたい。恋しい、熱海が恋しい。モイスチャーも恋しい。愛しの、麗しのモイスチャー様。早く貴方に会いたい。すると感極まったお信は、
「これがきっと『エロース』なんだわ!」
と叫ぶとそのまま勝手口の扉をドタンと乱暴に閉めて仕入れに出掛けた。二階で仕事中の継母は「気でもふれたのかしら。」と言ってみたがお信に聞こえるはずもなかった。
*
夢見心地のお信が商店街へ向かって歩いていると、
「お信ちゃん!」
と後ろから声を掛ける者がいる。
「その声は……しーちゃん!ひさしぶりだね!」
「お久しぶり。お信ちゃんがあいかわらず元気そうでよかったわ。どう?お店は順調?」
「もちろん順調よ。しーちゃんに会うのは学校を卒業して以来かしら……」
しーちゃんはこの町内に住むお信の幼馴染だが、中学を卒業してからというもの二人はめっきり顔を合わせなくなっていた。卒業後、しーちゃんは高校へ進学、現在は都内にある大学へと通い、学業もそこそこにサークル活動やコンパにも積極的に参加したりと日々忙しく、いわゆるキャンパスライフを謳歌している。一方のお信は中学を卒業後、高校へは進学せずに父が営む「ラーメンお信」で働き始め、父亡き後も辞めることなく引き続き店を切り盛りして今に至っている。
そして今、お信はしーちゃんとの再会を喜んだが久々に見た彼女の風貌に驚いた。
「しーちゃんのお洋服、すんごいハイカラで素敵だね。」
しーちゃんは花柄のキャミソールワンピースに厚底のミュールサンダル、首にかけたシルバーネックレスにはプラチナペンダントが輝いており、そして肩から掛けてあるバッグにはおよそ学校の教科書は一冊も入らないであろう、彼女はまさに「今風」といった恰好をしていた。一方のお信は、木綿浴衣に駒下駄、肩からは巨大な買い物カゴがだらしなくぶらさがっていた。
「しーちゃんったら、しばらく見ないうちに大人びた恰好をするようになったのね。」
「いいでしょ。買ってもらったんだ。」
「へえ、そんな高価そうなもの、一体誰に買ってもらったの?お父さん?」
「彼氏よ。大学のサークルで知り合ったの。家がすっごくお金持ちだからなんでも買ってくれるんだよね。」
よし、ピカピカになった寸胴鍋にしーちゃんをぶちこもう。
とお信は思ったが、「へえ……」と生返事をするにとどめた。
よく見るとしーちゃんの指には指輪がはめてある──この指輪もその彼氏とやらに買ってもらったんだろうか。他人の金で買った指輪はさぞ、はめ心地が良いだろう。おねだりすれば何でも買ってくれる彼氏、断じて買ってくれないおかあさま。しーちゃんとはしばらく会ってなかったけど、なんか鼻につくオンナになったよなあ……
お信から羨望と嫉妬の入り混じったまなざしを受けたしーちゃんは少し得意気であった。
「お信ちゃんも金持ちの男を捕まえて彼に買ってもらえばいいだけの話よ。そういえばお信ちゃんってさ、まだ彼氏いないの?」
この「まだ」というしーちゃんの発言を受けて対抗意識を燃やしたお信は思わず、
「あたしだって彼氏ぐらいいるわ。」
と言ってしまった。
「お信ちゃんも彼氏できたんだあ。ねえねえ、お信ちゃんの彼ってどんな人なの?」
ええと……と言いながらお信はこの場を上手く乗り切る策を考えたが、とりあえず、
「あたしの彼氏はね、彫りが深くって、それで目もパッチリしてて、鼻も高くって、それはそれは良いオトコなの。本当よ。思わずひとめぼれしちゃったんだから……」
「へえ!お信ちゃんってばそんなカッコイイ人と付き合ってるのね!いいなあ!」
と羨ましがるしーちゃんを見てお信はとりあえず「まあね。」とだけ言ったが、お信の彼氏に興味津々となったしーちゃんは「彼氏のこと色々教えてよー。」と言って質問を重ねてきた。これにはお信も大いに辟易してしまったが、こうしたしーちゃんからの質問責めに対し、お信は噓に嘘を上塗りしつつ、巧みに回答していた。しかし、
「お信ちゃんの彼氏って何て名前なの?普段は彼を何て呼んでるの?」
この質問にお信の顔は引きつった。
交際経験の無いお信にとって、恋人を呼びかける際の適切かつ自然な呼称が思い浮かばなかったからである。
「ねえ、もったいぶらずに早く教えてよ。彼の名前は?二人は何て呼び合ってるの?」
──これ以上は回答に時間を掛けられない。しーちゃんに怪しまれる。ならば仕方あるまい。そう判断したお信は、
「彼の名前は……パイド郎くんよ!」
とまずはそう言い放ってあとはそのまま勢いに任せて、
「パイド郎くんよ!あたしは普段から『おーいパイド郎くーん』って感じで彼を呼んでるの!そしたらパイド郎くんは『なんだーい?お信ちゃーん』って聞き返すの!本当よ!」
「ぱいどろう?パイド・ロウっていう名前なの?え、もしかしてお信ちゃんの彼氏って外国人なの?」
「うん。パイド郎くんは外国人なの……」
「やっぱりそうだったのね!」
渾身の大嘘がバレずに済んでお信はホッとしたが、まだ完全には気が抜けない状況が続いていた。
「すごいね!だからパイド・ロウくんは彫りの深い顔立ちなのね。外国人の彼氏がいるなんてお信ちゃんも隅に置けないなあ。」
まあね……とお信は言ったものの、内心では、この話題が早々に終わってくれることを心の底から願っていた。
「ねえお信ちゃん!今度わたしの彼氏とパイド・ロウくんも連れてダブルデートしましょうよ!きっと楽しいわ!」
──ダブルデートは流石にマズい、あたしのウソがばれてしまう……お信は焦った。
「しーちゃん、ごめんね。ダブルデートは無理なの。」
「えーどうして?何で無理なの?」
お信は思案に思案を巡らせた。ダブルデートが不可能であるとした理由を早急に捏造する必要に迫られていた。
「無理よ。だってついこの間、あたしとパイド郎はお別れしたんだもの。」
「え……どうして別れちゃったの?」
取り急ぎお信は悲しそうな表情を作り、そして空を見上げると次の様に語り始めた。
「パイド郎とあたしは止むを得ず別れたの。あたしたちは遠距離恋愛だったからよ。そりゃあ付き合いたての頃は、パイド郎はあたしを想っていてくれたし、あたしもパイド郎のことを想っていた。でも、そんな二人の仲を裂いたのは物理的な距離だった。離ればなれで会えない苦しみだったの。空間の隔たりは恋路の障壁となって愛し合う二人を断絶したの。そう……愛という名の地平線はギロチンという名の国境によってぶった斬りにされてしまったのよ!ねえ、しーちゃん!あなたはギロチンによる切断の痛みを、遠距離の苦しみを味わったことがあって?遠距離恋愛の経験があって?ないでしょうね。いいえ、ないに越したことはないわ。なぜなら、苦しむのはあたしだけで十分だから……とまあ、そんなわけでダブルデートはできないの。ごめんね。傷心旅行ならいつでも誘ってね。」
これを聞いたしーちゃんはお信に少しだけ同情した。
「そっか……遠距離恋愛でお互いの心がすれ違ったのね。だからお別れしてしまったのね。なのにダブルデートしようだなんて軽はずみなことを聞いてごめんなさいね。ちなみに遠距離恋愛って言ってたけど、パイド・ロウくんはどこに住んでるの?」
「古代ギリシャ。」
──どうも話がうさんくさいな。
しーちゃんはそう思ったが口にこそ出さなかった。
「お信ちゃん。わたし一限目の授業が始まるからそろそろ行くね。」
しーちゃんは足早に立ち去ろうとしたが、
「あ、待って。」
と言って、お信はしーちゃんの後ろに回り、髪をじろじろ見ている。
「ん?この髪がどうかしたの?」
「ハイカラな髪型ね。お団子みたい。」
しーちゃんの耳から上の髪の毛は後頭部のすぐ下で束ねられており、それをゴムで球状に結びあげ、丸い形が崩れないようにピンで留められていた。緩く巻かれた髪は首元まで垂れ下がっている。
「丸い部分がなんだかお団子みたいで可愛いわ。ねえ、それは何ていう髪型なの?」
「ハーフアップのシニヨンよ。お信ちゃん、ホントにごめん!学校始まるからもう行かないと!じゃあまたね!」
そう言ってしーちゃんは駅の方へと駆けて行った。その後ろ姿を見送りつつ、
「ハーフアップのシニヨンかあ……」
とつぶやいてお信は自分の髪を撫でてみると、何の混じりも無い黒一色の髪の毛が鎖骨の下までだらしなく伸びていた。
*
そこから半時あまりが経ち、商店街で仕入れを終えたお信は、大量の食材が詰め込まれた買い物カゴを抱えて店へと戻った。
厨房に入るとまずは冷蔵庫を開け、カゴの中の食材を次から次へと押し込んだ。
「とりあえずこれでよし。」
そして勝手口の方へ回り、お信が仕入れに行っている間に卸業者が置いていった、本日分の鳥ガラを力いっぱい持ち上げて厨房へ戻ると、目の前の寸胴鍋めがけて全てぶちまけ、水を張って火をかけた。
「これはこれでよし。」
少し経つと寸胴鍋の水が徐々に沸騰してきた。お信は頃合いを見計らって、鳥ガラから出たアクをすくおうと寸胴鍋に近づいたところ、すぐ正面の壁に、
「鍋焦がすな!」
と大きく貼り紙がしてあり、焦がすな!の下には髑髏の絵が描かれていた。
「おかあさま、ごめんなさい。」
と昨晩の失敗を今になって反省したお信はアクをすくい始めた。
塩や胡椒といった卓上の調味料だけでなく、楊枝や割り箸、そして厨房で使うネギやニンニクといった薬味類の補充を終えたお信が時計を見ると午後三時であった。ラーメンお信が開店する六時まで、空き時間はおよそ三時間ということになる。
「退屈だな。さてどうしよう。」
お信は今朝のしーちゃんとの一部始終をぼんやりと思い返していた──しーちゃんはいいよなあ。あたしもあんな風になりたいなあ。小奇麗な洋服、宝石、彼氏、そしてあの素敵な髪型、たしか「ハーフアップのシニヨン」って言ってたっけ……
「よし、床屋に行こう!」
とお信は思い立った。しーちゃんの四大構成要素である洋服、宝石、恋人、髪型の内、「髪型」に限っては、比較的容易かつ手っ取り早く真似できると考えたからである。
*
二階の自室で継母が仕事をしていると勢いよく襖が開き、そして開口一番、
「おかあさま!金!」
と嬉しそうに言うお信を一瞥した継母は、
「まるで居直り強盗の言い草ね。お金が欲しいってことなの?」
「うん。お金ちょうだい。」
「用途は?何のためのお金なの?」
「しーちゃん敗北者救済のための臨時特別自立支援金。」
「だから、その支援金とやらを何に使うのかはっきり言いなさい。」
継母が鋭い視線を投げるとお信は自分の髪をつまんで毛先を指に絡ませながら、
「そろそろ髪も伸びてきたから床屋に行きたいなあと思って……」
「要するに散髪代が欲しいってことね?」
「そうなの。」
継母は改めてお信を見た。たしかに髪の毛が鎖骨や肩にまで掛かっている。継母は財布からお札を一枚だけ抜き取ると、
「ほら、これで行ってきなさい。」
「やった!ありがとう。じゃ、開店までには戻って来るから。」
と足早に部屋から出て行こうとするお信を呼び止めて、
「あとね、お信。人にお願いする場合はまず目的を先に言いなさい。」
「目的は金ってちゃんと言ったわ。」
「違う、目的は金じゃなくて散髪でしょう。」
「でもおかあさま、お金が欲しかったのは事実よ。」
「かといってお信、あんたはお金のためにお金が欲しいわけじゃないでしょう?散髪のためにお金を必要としたのよ。それを不躾にも『おかあさま、金!』とだけ言われても私は困惑する一方でしょう。相手の為にもう少し優しくなりなさいと言ってるの。まあそんなところね。あと、今日はまだ仕事が残ってるから邪魔しないで。さあ行った行った。」
「はあい。」
とだけ答えるとお信は継母から貰った千円札を握りしめて床屋へ向かった。
*
数分後、赤白青の縞模様が渦を巻くように回転している例の柱がお信の目についた。
「バーバー小鉄」とは、この町内の多くが通う床屋である。
お信も幼少期から現在に至るまでこの店へと通っており、すっかり慣れ親しんだ、いわゆる行きつけであった。
今、バーバー小鉄の店内には店主である小鉄と、さきほど散髪を終えたばかりのご隠居がおり、馴染みの二人は将棋のテレビ番組を見ながら他愛のない話に興じている最中であった。
そこへ扉が開き、カランコロンという鈴の音と共にお信が入って来た。
「小鉄おじさん、こんにちは!」
「おう、お信ちゃんじゃねえか。今なら待たずにすぐ刈れるからそこに座んなよ。」
小鉄は早速お信を椅子に座らせて、敷布をお信の首からマント状に掛けながら、
「で、お信ちゃん。今日はどうする?いつも通り、伸びた分を刈ればいいのか?」
「いいえ、ちがうわ。今日はまったく新しい髪型にチャレンジしようと思うの。」
「へえ、とうとうお信ちゃんも色気づいたってことか。で、どんな髪型にすりゃいいんだ?」
と小鉄に聞かれたお信は満を持して、
「ハーフアップのシニヨンでひとつ頼むわ。」
「ハーフパンツの死代?誰だい死代さんってのは?ソイツがパンツ一丁で近所をウロウロしてるのか?そんな変な通り名のヤツ、この町内にいたっけか。」
「いるわけないじゃん。」
「なるほど、とっくに死んじまっていないってわけか。まあ死代さんっていうぐらいだから名前負けはしてねえな。」
「いや、そういうことじゃなくて……」
お信は半ば呆れつつ鉛筆を借りると、傍らに置いてあったチラシの裏に「ハーフアップのシニヨン」と大きく書いて小鉄に手渡した。
「ほら見て。この髪型にしてほしいの。」
小鉄はますます顔をしかめてチラシに書かれた文字とお信の髪を交互に見た。
「ハーフアップのシニヨン?何だいそりゃ。そんな髪型聞いたこともねえんだが……なあ、ご隠居。あんた知ってるかい?」
「知らんな。」
「ほらな、やっぱり知らねえや。お信ちゃん、大の大人二人が知らねえってんだから、そんな髪型は存在しないんじゃねえのか?」
「いいえ、存在するの。なぜなら、ついさっき実際に見たんだもの。」
「実際に見たって言うけどよ、そんなややこしそうな髪型、一体誰がしてたんだ?」
「しーちゃんよ。」
「しーちゃんって……あのタバコ屋の娘のシヅちゃんのことかい?」
「うん。あの女がなんとハーフアップのシニヨンだったの。」
「へえ、そんな身近にシニヨンが居たなんて驚きだな。」
「だからさあ、おじさん。早い話があたしもあの女と同じ髪型にしてほしいってわけ。しーちゃんなら何遍もこの店に来たことがあるだろうし、おじさんもしーちゃんの髪型ぐらい覚えてるわよね?」
「いや忘れたよ。だってあの子はここ数年めっきり店に来ねえからな。」
と言うと小鉄は煙草を吸い始めた。
事実、しーちゃんが髪を切るのはバーバー小鉄ではなく、ここ数年は専ら銀座のヘアサロンであった。そもそもお信が熱望する「ハーフアップのシニヨン」という髪型は、ヘアサロンのアートディレクターによる最新美容技術を駆使して仕立て上げられた一品であり、そのため、横丁の床屋風情が見よう見まねでできる代物ではない。
*
「もう!じゃあどーすんのよ!」
とうとうしびれを切らしたお信から悪態が飛び出した。
「どうするもこうするもねえやな。そんな髪型知らねえんだから。」
「なんでそんなことも知らないのよ!プロならハーフアップのシニヨンぐらい知っときなさいよ!」
「もしそれがプロだってんならこの町内にある床屋はみんなド素人ってことになるぜ。」
「ええそうよ。でも素人なら素人なりに工夫してこの局面をなんとかしなさいよ!」
「なんとかしろったって……どうしてもお望みだってんならしーちゃんを引っ捕まえてこの店に連れてきな。あの子を手本にしてそっくりそのまま同じ髪型にしてやるから。」
「無理な話だわ!」
「どうして?」
「だってあの女はもう学校に行っちゃったんだもの!どうせ今頃は彼氏と乳繰り合ってる最中で当分帰ってこないに決まってるわ!捕まえたくても捕まえられないじゃないの!」
「そんならあきらめるしかねえな。」
「いやだ。絶対にあきらめない……」
お信と小鉄が正面の鏡越しにしばらく睨み合っていると、
「まあまあ。二人とも少しは落ち着きな。」
となだめるのは、お信と小鉄の言い争いを先程から聞いていたご隠居であった。
「でもよお、ご隠居。こりゃもうお手上げだぜ。」
「早まるな。落ち着けと言ってるだろう。こういった場合はな、まず状況を整理してから打開策を講ずればよい。おい、その鉛筆をこっちによこしな。」
と言うとご隠居はチラシの裏にさらさらと何か書き始めた。そして数分後、
「ほい、できた。二人ともこれを見てみな。」
お信と小鉄はご隠居から手渡された紙を覗き込んでみると、そこには、
「ハーフアップのシニヨンを巡る事実関係の整理」
という表題が掲げられており、それに続く内容は次の通りであった。
・しーちゃんはハーフアップのシニヨンそのものである。
・しーちゃんをハーフアップのシニヨンに仕立てた床屋が存在する。
・お信はしーちゃんを見て、その髪型に憧れている。
・小鉄はその髪型を知らない。
・私(ご隠居)もその髪型を知らない。
これを読み終えた小鉄は、
「なんだこれ。だからどうしろってんだ?」
と眉をひそめたが一方のお信は、
「なるほど……」
と何やら納得した様子で関心を示しており、それを見たご隠居は安堵の笑みを浮かべた。
「どうだい、お二人さん。これを見て気付いたことがあるだろう?ハーフアップのシニヨンに関する当事者連中が不在ならば頼るべきは小鉄でもなければワシでもない。しーちゃんを見た経験を持つお信、すべてはお前の『智』に懸かっている。」
「そうか!言われてみりゃあたしかにご隠居の言う通りだ。早い話、ハーフアップのシニヨンを見たことがあるお信ちゃんがその特徴を俺に伝えて、あとは言われた通りの髪型にすりゃあいいだけじゃねえか。」
「まさにそう。だからあとはお信次第だ。」
「じゃあ早速だけどお信ちゃん、髪型の特徴を言ってみなよ。」
小鉄から聞かれたお信は「そうさね……」と髪型の記憶を辿り始めたところ、すぐに頭の中は「団子」という文字で埋め尽くされた。
「おいお信ちゃん、何でもいいから早く言いなよ。お誂え向きにしてやるからよ。」
するとようやく頭の中で整理が着いたのか、
「……では髪型の特徴を説明します。」
と真剣な顔つきのお信が言うには──
「ハーフアップのシニヨンっていうのはね、まず全体の感じはお団子で、丸くって、いやお団子だから丸くて当然なんだけど、まずそれがあって、そこから毛がシュルシュルーって感じで流しソーメンみたいに流れてて、でもそのソーメンの麺は麺っていうよりも死にかけのドジョウみたいなちぢれ麺で、で、そのドジョウの流しソーメンが首元ぐらいまで少しかかってて、ただ基本は団子で、その周辺をフワっとさせたような団子っぽい感じの、そうね、もし例えるとするなら、団子みたいなヤツね。髪型の説明は以上。というわけで小鉄おじさん、あとは注文通りお願いね。」
「いやちょっと待ってくれよ。まったく想像がつかねえ。やれ団子がどうした、ソーメンがどうした、ドジョウが死にかかっただの、肝心の髪型の手掛かりがまるで伝わってこねえんだがな。」
「そう……じゃあさ、絵を描いて説明してみるってのはどう?」
「そいつは名案だ!是非そうしてくれ。」
お信はチラシの裏にハーフアップのシニヨンのイラストを精一杯描いた。
「完成したわ。さあおじさん、この絵の通りの髪型にしてちょうだい。」
と自信ありげなお信から手渡された紙を見て、小鉄は衝撃を受けた。そこには「大きな団子の周りでドジョウの親子が流しソーメンを仲良く食べている様子」が殴り書きにされていたからである。
小鉄の目には確かにそう映った。
「だめだ。さっぱりわけが分からねえ。」
「これだけ説明してあげたのにまだ分からないなんて……」
なかば失望気味のお信であったが、それを案じたご隠居が二人に割って入り、
「心配するなお信。たった二回の説明で他人を納得に導くのはむずかしいものだ。何度も何度もやりとりを重ねていく内に真実は必ずや見えてくる。おい小鉄、さっきのお信の説明の中で不明点があったんだろう?なら本人に質問してみな。」
小鉄は、あまりにも不明点が多過ぎて何から質問していいのか迷いに迷ったが、とりあえず基本的な点から尋ねることにした。
「じゃあ聞くけどよ……その団子ってのは、みたらしか?それともヨモギか?」
「あん団子よ。」
「団子の数はいくつだ?」
「ひとつよ。」
「ソーメンは何人前なんだ?」
「四人前よ。」
「ドジョウは最近いつ食べたんだ?」
「おとといの晩よ。」
「ソーメンはどれぐらいの長さなんだ?」
「首元までよ。最初に説明したじゃん!」
こうした二人の問答はおよそ三十分に渡って繰り広げられたのであり、そして小鉄はお信から得た回答を総合した結果、ハーフアップのシニヨンという髪型を、
「団子」
と結論づけたのであった。
*
「おじさん、どう?いけそう?」
「まかせときな。へへ、ようやく俺にも見えたぜ、ハーフアップのシニヨンってやつがな……」
自信に満ち溢れる小鉄が煙草を勢いよくもみ消すと、それを見たお信とご隠居は互いに顔を見合わせて深くうなずいた。
腕まくりをして櫛とハサミを手にした小鉄の目の前にはお信の頭が鎮座している。
小鉄は大きく深呼吸した。
「さて、お信ちゃん。今日は一体どんな髪型にしてほしいんだい?」
「そうさねえ……それじゃあ、ハーフアップのシニヨンにしていただこうかしら!」
「がってんだ!」
と言うが早いか、小鉄はお信の髪を切り始めた。そのハサミさばきは何ひとつとして迷いはなく、これは自信の裏付けでもあろうか、小鉄は一心不乱であった。
一方のお信はしかと目を見開いて、鏡に映る己の髪を見つめていた。しかし、すぐ目の前をはらはらと落ちていく髪の毛、その一本一本にしばしの別れを惜しみつつも耳を抜けて頭の中で鳴り響くのはチョキン、チョキンという小鉄の仕事、その軽快で歯切れの良いハサミの音に身を任せていると、ここに至るまでの紆余曲折が一段落したことを実感したせいか、お信の元に急激な眠気が訪れた。ふと脇に目をやるとご隠居は既に眠っており、それに引き込まれるかのようにお信もそのまま眠りへ落ちていった。
*
「おい、お信ちゃん!起きなよ!」
あ、すっかり寝てしまっていた……とお信が目覚めると、
「ほら、鏡をよおく見てみな。ご注文のハーフアップのシニヨンだぜ。」
お信は鏡を見た──肩まであった長い髪は襟足まで短く刈り上げられ、丸い顔の輪郭を沿うように毛髪で縁取られており、そのシルエットたるや紛れもない「団子」であった。
つまり、お信の髪型はハーフアップのシニヨンではなく「カリアゲのショートヘアー」だったのである。
お信の思惑は大きく外れた。
「どうだいお信ちゃん。初めてにしては上出来だと思わねえかい?」
「ま、ハーフアップのシニヨンってのは要するに団子みたいな髪型ってことだろ?」
「だったら最初っから団子刈りにしてくれって言えばいいじゃねえか。お信ちゃんも意地の悪いやつだなあ、へへへ。」
「団子っぽく見えるように襟足はカリアゲにしておいたぜ。安心しな。」
お信は小鉄の顔を直視できなかった。
勢い余って殺してしまうかもしれなかったからである。
お信は怒りを鎮めるために歯を食いしばり、深呼吸を繰り返した。しかし効果はまるで無かったため、とりあえず席を立ち、そして傍らで眠りこけていたご隠居にふらふら近づくと、
「ねえねえ、おじいちゃん。いつまで寝てるのかなあ?さっさと起きろ。このハゲ!」
と囁いてご隠居を起こした。
これは、小鉄一点に集中していた怒りの矛先をご隠居に向けることで怒りを分散させ、荒ぶる気持ちを落ち着かせるための措置である。
しかし、怒りは依然として鎮まらない。茫然とするご隠居を後にしてお信は無言のまま店のトイレへと向かった。
トイレの鏡を見ると髪はやはり短い。襟足のカリアゲに触れると「ジョリ」という音がした。不快な音であった。
顔面蒼白のお信がトイレから戻ると、その目に小鉄の姿が映った──誇らしげに煙草を吹かす小鉄の佇まいは、まさしく一仕事終えた「職人」の姿であった。しかしそれは、お信にとって怒りを駆り立てる挑発のポーズでしかなかった。
お信はゆっくりと小鉄に近づくと、まずは小鉄が口に咥えていた煙草を奪い取り、それを拳で握りつぶした。
「次はアンタがこうなる番よ……」
お信の指と指の間から煙が上がったが興奮状態のお信に痛みは無く、「えっ。」と驚く小鉄をよそに煙草を放り捨てるとすぐ脇に置いてあったバリカンを掴んで小鉄の顔面に叩き込もうとしたが、そのあまりの勢いに足を滑らせて転倒してしまったお信は床に顔面を強打、もう何もかもが嫌になりその場に倒れ伏したまま、おいおいと声を上げて泣き始めたのである。
十数分が経過した。お信はいっこうに泣き止む気配がない。
「お信ちゃん、俺が悪かった!お代はいらねえからゆるしてくれ!」
「お信、ワシからも謝るからどうかゆるしてやってくれ。」
小鉄とご隠居は何度も詫び続けたが、相変わらずお信は泣き崩れたままであった。
「だめだ、全く埒が明かねえ。なあご隠居、ここは詫びるよりも元気づけてやるほうが得策かもしれねえぜ。」
「確かに小鉄の言う通りだ。人間、前向きが肝心というからの……」
そう言うとご隠居は早速、お信を元気づけることにした。
「お信よ。なにも髪型ひとつでそこまで落ち込むことはない。なあに大丈夫さ、髪は伸びる。そしてまた元通りの髪型に戻る。だから毛が生え揃うまでの辛抱さな。」
「ハゲのご隠居にあたしの気持ちなんて分かりっこないわ。いい加減なこと言わないで……」
と言ってお信は再び泣き始めた。
「なるほど、ご隠居はハゲてるから髪に関する説得力に欠けるってわけか。一理あるかもしれねえ。こりゃあ傑作だぜ、あはは。」
「馬鹿野郎、笑ってる場合か。」
こうして行き詰まりの雰囲気を漂わせつつ、無為な時間だけが過ぎて行った。
*
一方その頃、仕事が一段落した継母もお信同様に散髪の最中であった。
継母は床屋へは行かない。髪結が自宅までわざわざ出向いて継母の髪を梳き払い、手入れするのである。
「然るべく整えてちょうだい。」
継母がそう言えば髪結はその通りに仕事をこなす。その間、両者はわだかまることもなく、事はすんなりと運び、そして今日もいつも通りにすべてを終えた。
継母の髪は日本髪に結われ、鬢は掻き上げてあり、白の混じりもなくまだなお黒い。しかしどこか痩せていた。
継母が髪結と床の間で世間話をしていると「お店のお邪魔になってもいけませんから私はこれで。」と暇乞いをするので、時計を見ると時刻はとうに五時半を過ぎていた──もうすぐ開店だというのにお信の帰りが遅い。たしか散髪に行ったんだっけ……そう思いつつ継母は髪結を見送った。
*
「ぜんぶアンタたちのせいよ!」
「だから俺もご隠居もさっきから謝ってんじゃねえか!いい加減しつこいってんだよ!」
泣き止んだお信は一転して今度は小鉄と言い争っており、あまりに口うるさく騒ぎ立てるお信に対し、小鉄だけでなくご隠居ですら既に嫌気が差していた。
「じゃあ謝らなくていいから失敗の責任を取りなさいよ!」
「責任なんざ知るか!とっとと帰れ!」
「ええもちろん帰るわ。もう二度と来てやらないんだから……その代わりアンタたちもあたしの店に二度と来ないでよね!出禁よ!」
「ラーメンお信」への出禁を言い渡された小鉄とご隠居はふたりして、
「え、出禁は勘弁してくれ……」
と心の中でそう思った──出禁にされてしまうとラーメン屋に時おり姿を見せるあの美しい母親に会えなくなるではないか!常連の我々にいつだって優しく語りかけ、我々がこぼす冗談や愚痴に嫌な顔ひとつ見せず耳を傾けてくれる度量の深さ、微笑みながらも憂いを帯びた表情、娘にだけ向けるキリッと引き締まったまなざし、そしてなんといっても、たまに披露してくれるあの手料理、その手捌きと味は華麗にして絶品。我々の癒し。明日への活力源。横丁の母。日本のおかあさま。あの母親にもう会えないなんて……
このように小鉄とご隠居は継母との接点が消滅してしまうのを非常に恐れた。この際、娘のお信のことはどうでもよかった。
そのため、この度のラーメンお信への出禁は何としてでも撤回させなくてはなるまい、と二人は同時にそう思い立つと、互いに顔を見合わせた。
「おいご隠居。こいつはえらいことになったぜ。このまま出禁にされた日にゃ、あのべっぴんの母親を拝めなくなっちまう。どうにかして出禁を取り下げる策はねえのか?」
「策は……ある。」
「おお、そいつはありがてえ。で、どうすりゃいいんだ?」
「責任の所在を明確にすることで、我々の出禁は回避できる。」
「責任の所在?」
「まあ見ておけ。」
とご隠居は腹を括ったのか、普段以上に落ち着き払っていた。
愛想を尽かしたお信が店を出ようと扉に手を掛けたところ、
「待てお信。」
「あ?隠居風情に、待てと言われて素直に待つほど単純なあたしじゃないってのよ。帰るわ。」
「いいから待て。黙ってワシの話を聞け。」
「何よ?文句でも言いたいわけ?」
「文句ではない。よく聞け……」
そう言うと、ご隠居はお信の前に立ちはだかった。小鉄は「頼んだぜご隠居。ここが正念場だ。」と心の中で激励した。
「お信よ。お前は重大な勘違いをしている。」
「はァ?勘違いですって?」
「そう。今回、お前はハーフアップのシニヨンを望んだが、結果的にカリアゲの団子みたいな髪型にされてしまい、失敗に終わった。ではお信に聞くが、失敗の原因はお前の頭をカリアゲ団子にした小鉄だと思うか?」
「そうよ。」
「では、お信に様々な助言をした結果、カリアゲ団子に導いたワシにも責任があるか?」
「あるわ。」
「ということは、失敗の原因は『小鉄の散髪』と『ワシの助言』の二点ということだな?」
「何を今さら。その通りよ。」
「やはりな。その考え方がてっぺんから誤りだ。さっきワシがお信に言った、重大な勘違いとはまさにこの点を指している。」
「全然納得いかない。原因はアンタたちに決まってるじゃないの!」
「ちがう。それは直接の原因に過ぎない。本件についてワシが分析したところ、どうやら『真の原因』が存在したのだ。」
「真の原因?なに言ってんだか。アンタたち二人のせいでしょ。ご隠居は耄碌してるだけなんじゃないの?」
「ガタガタぬかすな!真の原因を説明してやるってんだから黙って聞け、この小娘が!」
不意に凄まれてお信が一瞬怯んだため、ご隠居はここを逃すまいと次の様に説得を試みた。
「まずは、さっきワシが書いた『ハーフアップのシニヨンを巡る事実関係の整理』をもう一度よく見ろ。この中に『しーちゃんはハーフアップのシニヨンそのものである』と書かれており、これは我々三人の共通理解だった。が、どうやらこの理解は大間違いだったようだ。実は、しーちゃんはハーフアップのシニヨンではない。それはなぜか?まず、お信はしーちゃんを通じてハーフアップのシニヨンを知り、その情報を元にして小鉄は髪を切った。しかし、完成した髪型は無惨にもカリアゲ団子だった。これすなわち、お信がハーフアップのシニヨンを知らなかったことに起因している。なぜなら、もしお信がその髪型を確実に知っている場合、お信の知見に基づいて小鉄はハーフアップのシニヨンを完成させたからだ。」
「は?なにそれ。失敗はあたしのせいだとでも言いたいわけ?」
「いやお信に非は無い。前述の通りしーちゃんはハーフアップのシニヨンではないから。」
「でも、あたしはしーちゃんに会ってその髪型を実際に見たのよ?」
「お信には悪いが……お前はハーフアップのシニヨンを本当に見たのか?そこが非常に疑わしい。なぜなら、そもそもワシと小鉄は、お信がハーフアップのシニヨンを見たという客観的事実を知らないから。そしてお信はハーフアップのシニヨンを知らないのにどうして『見た』と断言できる?」
「だって、当事者のしーちゃんがあたしに『この髪型はハーフアップのシニヨンだよ』って教えてくれたんだもの。」
「馬鹿野郎!いい年して他人が言ったことを易々と鵜呑みにするな!まずは疑え!なぜだかわかるか?ここで今一度『ハーフアップのシニヨンを巡る事実関係の整理』をよくよく読んでみろ。『しーちゃんをハーフアップのシニヨンに仕立て上げた床屋が存在する』と書いてあるだろう?しかし、お信はその床屋を見たことがない。そればかりか、この床屋自体が、ハーフアップのシニヨンを知っているのかどうかも分からない。とすれば、あのしーちゃんですら髪型を正しく判別できていないかもしれない。ゆえに、しーちゃんはハーフアップのシニヨンではない可能性が濃厚である。と、このように全てが疑わしい状況を踏まえると、真偽不明の『ハーフアップのシニヨン』なるものはそもそもこの世に存在しないのではないか?誰も真実を知らない、存在すらしない、そんな髪型を無理矢理でっちあげようとした結果、お信の頭はカリアゲ団子になってしまった、と考えた方が自然だし合点もいくだろう?それぐらいお信にも分かるよな?分かるよな?」
ご隠居の語りには有無を言わせない語気があり、お信はここまでに聞いた主張を吟味する以前に頭が混乱していた。
──ああ、もう目が回りそう。なんだかハーフアップのシニヨンなんてはじめから無かったような気がしてきた。あたしの勘違いかもしれない。なのに、あたしも含めて知らない人同士が知ろうとしたところで無茶だよな。正解が無いんだから。ってことは、ご隠居の言うことは道理といえば道理なのかも……
お信は混乱の中で納得しつつあった。
「言いたいことはなんとなく分かるわ。」
「おお!分かってくれたか。ありがとうな。それにしても、嗚呼……なんてかわいそうなお信。お前の望むハーフアップのシニヨンはインチキだったのだから。お信、お前は決して悪くないぞ。いや、お信だけじゃなくここに居る我々三人は被害者だ。被害者同士、これからもみんなで仲良くしような。とまあ……そういうわけで、被害者であるワシと小鉄には失敗の瑕疵担保責任は発生しないってことになるから、お前がくだした『ラーメンお信への出禁』はまったく不当な裁決となり、これは今をもって無効とする。よって、ワシと小鉄は今後もラーメンお信へ出入り自由とさせていただく。では最後にこうした経緯も踏まえて、散髪失敗における『真の原因』とは何か?誰が失敗の責任を取るのか?そもそも誰が悪いのか?について説明する。なあに簡単な話だ。お信、よく思い出せ。ハーフアップのシニヨンじゃないくせにお信に対し『この髪型はハーフアップのシニヨンだよ』と嘘の情報を吹き込んだ者が一人いただろう?お信はそいつにまんまと騙されたのだ。つまり、諸悪の根源は……」
とご隠居が結論を言おうとすると、そこにお信と小鉄も加わり、三人は口を揃えて、
「諸悪の根源はしーちゃんである!」
と宣言したのであった。
*
そこからしばらくの間、三人は散髪失敗の労を互いにねぎらった。
「小鉄おじさん。それにご隠居のおじいちゃん。さっきは失礼なことばかり言っちゃって本当にごめんなさい。またいつでも店に来てちょうだいね。だって、あなたたち二人はなにひとつ悪くないんだから……悪いのはすべてあの女なんだから……」
「もう気にすんな。いいってことよ。」
「小鉄もワシも平気だから安心しな。」
小鉄とご隠居はそう言いつつも、しーちゃんひとりを悪者に仕立て上げたことに心を痛めた。だがそれはラーメンお信への出禁を回避するためにはやむを得ない決断であった。
小鉄はご隠居の方へ向くと耳元で、
「それにしてもよお、ご隠居。あんたすげえな。あんなにも上手く誤魔化せるなんて驚いたぜ。」
「ま、ざっとこんなもんさな。とはいえ、しーちゃんには申し訳が立たねえがな。」
「ああ、そうだな……」
とやはり意気消沈の二人であったが、それ以上に気を落としているのは、頭をカリアゲ団子にされてしまったお信であった。
「あーあ。こんな頭でウロウロしてたら町内の笑い者だわ。これからどうやって生きてゆけばいいんだろう。」
嘆くお信を見て、小鉄は「ちょっと待ってな。」と店の奥に引っ込むと、ガサゴソと音を立てて何か探し始め、そして「あったあった!」と言って再びこちらに戻って来た。
「ほらお信ちゃん。これをかぶりなよ。」
小鉄が差し出したのは、白い頭巾であった。
「なるほど。この頭巾で頭を隠せば笑い者にされずに済むってことね!」
「髪が伸びて元通りになるまでの辛抱だ。さあさあ、かぶってみな。」
早速、小鉄はお信の頭に白い頭巾をかぶせると、外れないようにヒモを顎下で結んだ。
「おお、よく似合ってるじゃねえか。」
「赤ずきんみたいで愛らしいのう。」
取り急ぎ小鉄もご隠居も頭巾姿のお信を褒めたところ、
「えへへ、そうかなあ。」
と当のお信も鏡に映った自身を見てまんざらでもない様子であった。
そうしてすっかり機嫌を取り戻したお信を中心に三人で談笑していると、
「そういえばお信ちゃん、そろそろラーメン屋に戻らなくてもいいのか?」
と小鉄が言うのでお信は時計を見たところ、時計の針は六時半を指しており、ラーメンお信の開店時刻から三十分が経過していた。
「まずい!早く戻らなきゃ!」
慌てたお信は二人に「じゃあまた!」とだけ告げて店を飛び出した。
「開店してないことがおかあさまにバレたら𠮟られる……」
と内心で焦りつつ先を急ぐお信、その頭巾姿を見た町内の子供たちはみんなして笑ったが、焦るお信の目には映らなかった。
*
お信が「ラーメンお信」の店の前まで戻ると既にのれんが掛かっており、店内の明かりが窓越しに地面を照らしていた。
「ってことは、おかあさまにバレている。」
絶望したお信はどういうわけか、バーバー小鉄へ引き返そうとしたところ、店の戸が勢いよく開き、
「遅い。」
継母はそう言うとピシャリと戸を閉めた。
「ごめんなさい……」
お信が謝りながら戸を開けて店内に入ると、幸いにも客はまだ誰もいなかった。
継母は、付けていた前掛けを外してお信に放るとカウンター席に座った。
「で、お信。開店時刻はとっくに過ぎてるわけだけど遅くなった理由は?」
「散髪してたから遅くなったの。」
お信は前掛けの帯を締めながらそう答えた。
「お信の散髪なんていつも三十分程度で終わるでしょう。なのにどうして今回は三時間もかかったの?」
「いやまあそれは……」
「ふうん。で、あんたはどうして頭巾なんてかぶってるの?」
「今、巷は空前の頭巾ブームなの。だからあたしも便乗したの。」
「嘘ばっかり。頭巾のまま働くつもり?みっともない。町内の笑い者よ。さっさと脱ぎなさい。」
「いやだ。絶対に脱がない。」
そう言って両手で頭巾をかばうお信の態度に継母は、お信が遅くなった理由の察しがついた。とはいえ「まあ一応聞いておくか。」と思ったので、
「あんたが頭巾を脱ぎたくないってんならそのままでもいい。ただし、どうして頭巾をかぶることになったのか。そのいきさつはちゃんと説明しなさい。」
と言って鋭い視線を投げると、
「ええとね、おかあさま、実はね……」
お信は頭巾をかぶることになった経緯を、つまり散髪失敗に至るまでの一部始終を継母に全て打ち明けた。
「……というわけで、あたしは頭巾をかぶるハメになったの。」
語り終えるとお信は深い溜息をついた。
継母は呆れた。
そして「はあ。」と継母からも溜息が出た。
「おかあさまもあたしに同情してくれたのね。ありがとう。」
「いいえ。同情なんて一切してない。呆れてるのよ、あまりの馬鹿々々しさに。」
そう言うと継母は冷蔵庫から瓶ビールを取り出して、再びカウンターに腰を下ろした。
「ちょっと待って。なんで馬鹿々々しいなんて言うの?あたしは切実なのよ。」
「どこが?」
「だからさっきも言ったけど、せっかくハーフアップのシニヨンにしようとしたのに、しーちゃんにダマされた挙句、あたしの頭はカリアゲ団子になってしまったの!あたしは被害者なの!」
「どこが?」
「だからご隠居も言ってたでしょ!『諸悪の根源はしーちゃんだ』って!」
これを聞いて継母は再び呆れかえった。そしてグラスに注いだビールを呷ると、
「ちがうわ。諸悪の根源はしーちゃんではない。しーちゃんなわけがない。」
驚いたお信は「じゃあ誰なの?」と恐る恐る尋ねたところ、
「散髪が失敗した諸悪の根源はお信、あんたよ。」
そう言うと継母は、持っていたグラスをドンッと荒々しくテーブルに置いた。
「でもおかあさま!ご隠居はしーちゃんが悪いって言ってたし、あたしもそう思うの!」
お信は継母の発言を信じようとしなかった。
「ということは、お信はご隠居の主張に納得しているのよね?」
「そうよ。」
「で、私の意見には到底承知できないと。」
「おかあさまには悪いけどその通りよ。」
「たしかご隠居の主張は──ハーフアップのシニヨン、それ自体の存在を裏付ける関係者の情報が曖昧ゆえ、そんな髪型はおそらく存在しない。この理解で合ってるかしら?」
「ええ、合ってるわ。」
「ふうん。で、そうした状況において『存在しない髪型が存在する』という嘘の情報をお信に提供したしーちゃん。お信を騙すという不正を行った彼女こそ、諸悪の根源である。これがご隠居による主張の全てなのよね?」
「ええ、そうよ。」
「ではお信。そうした全ての情報が曖昧であるにも関わらず、どうしてご隠居の主張だけ納得したの?ご隠居の発言だけ愚直に信じたの?それすら嘘かもしれないわよ。」
いやまあそれは……とお信が回答に窮していると、継母は続けて、
「もっと言うと、しーちゃんがお信を騙そうとした事をどうしてご隠居が知っているの?ご隠居は超能力者なの?」
「さあ。よく分からないわ。」
「お信は分からないのに納得したのね。私が言いたいのは、ご隠居のあらゆる言説が乱暴な憶測でしかないってこと。その一環でしーちゃんは利用されただけ。だからあの子に非はない。あんたはご隠居の口車にまんまと乗せられたのよ。」
これを聞いてお信は愕然とした。
「くそう、ご隠居め。あのハゲ……」
「口を慎みなさい。頭が禿げるのは老衰による当然の変化です。」
継母はご隠居をかばいつつも──ご隠居が言葉を弄して何かしら不徳なものに導こうとしたのは歴然。とすれば、お信が怒るのも無理はない。こんな私的で独善的な行動原理によって、真理への衝動をないがしろにする態度こそ教養の退廃、ご隠居はそのなれの果てといったところか。いやしかし、ご隠居の確信にすら迫らずに納得したお信。一体この子には吟味というものが欠けている。これは親である私にしても痛恨だがお信が「納得」した以上は仕方あるまい……
「とにかく、憶測まみれの詭弁に納得したお信が迂闊だわ。これは認めなさい。」
「……わかった。」
「認めたわね。ではこの件に関してこれ以上ご隠居を責めないであげてね。あの人にだって何かしらの事情があったのかもしれないから。」
「事情……あ、そういえばご隠居に店の出禁を伝えたとき悲しそうだったな。」
「ということは、ご隠居はあんたの作るラーメンのファンなのよ。だから出禁にされないよう、やむを得ずあんなデタラメを言ったのでしょうね。お信、よかったわね。あんたにはファンがいるのよ。」
「そっか!ならご隠居は良い人ね!」
すっかり嬉しくなったお信は「さあ仕事仕事!」と言って厨房へ向かおうとしたが、
「お信、待ちなさい。私の話はまだ終わってない。」
「え。まだ何かあるの?」
「ある。」
そう言うと継母はお信を隣に座らせた。
再び真剣な顔つきに戻った継母、その隣でお信は露骨に顔をしかめた。
*
「私がここまでお信に説明したのは、散髪が失敗した諸悪の根源はしーちゃんではない、ということ。ここからが本題の『諸悪の根源はお信』だということを説明してあげる。」
やはりそうきたか……とお信は思った。
「まずお信に聞きたい。どうしてあんたはご隠居のデタラメな説得を真に受けたの?そして納得してしまったの?」
「それっぽいなあ、って思ったからよ。」
「それっぽい?つまり、お信にとって都合がよかったということなの?」
「そうなの。好都合だったの。」
「ではどうして好都合なの?」
「あれ、どうしてだっけ。忘れちゃった。」
と咄嗟にお信は嘘をついたが、
「忘れたのなら仕方ないわね。そんなら私が思い出させてあげましょう。」
継母はお信の嘘を見抜きつつも意に介さず、
「で、お信はしーちゃんと会ってハーフアップのシニヨンを実際に見たのよね?」
「そうさね。」
「もし仮にその髪型がハーフアップのシニヨンじゃなかったとしても、お信が見たという事実は変わらない。」
「そうさね。」
「よって『ハーフアップのシニヨン』という名前が与えられていないだけであり、髪型自体は存在する。そうでしょう?」
「まあ、そうさね。」
「ということは、お信が見たままを小鉄さんに注文すればいいことになる。」
「そうさね。」
「だからお信はその通り髪型を注文した。それにも関わらず失敗に終わった。以上の経緯から導かれることは……」
お信は話の雲行きが怪しいと察したので、
「あ、いけない!ネコちゃんにエサをあげなきゃ!おかあさま、ごめん!ちょっと行ってくるから!」
「エサなら既に私があげた。安心しなさい。」
継母は、この場から逃れようとするお信を制すると次の様に語った。
「お信の髪型はハーフアップのシニヨンではなくカリアゲ団子になった──これが今回の事象です。ではなぜそんなことになったのかというと、小鉄さんが髪型をカリアゲ団子だと勘違いしたから。なぜ勘違いしたのかというと、お信によるハーフアップのシニヨンの説明はカリアゲ団子を連想させるから。なぜかというと、あんたの説明は『団子』『丸い』といった言葉を感情的に連呼しているだけで、髪型の特徴に関する情報が曖昧で、そのため、小鉄さんは想像に頼って散髪するしか術がなかったから。よって、散髪失敗における真の原因は、情報提供者であるお信の伝達能力不足、となる。要はあんたの口頭説明がヘタなだけってこと。ついでに絵もヘタとくればカリアゲにされても不思議じゃないわ。そしてタチの悪いことに、散髪が失敗したのは説明ベタなお信、という自覚がありながらそれを認めるわけにはいかず、ご隠居の滅茶苦茶な主張を全面的に支持し、その結果、しーちゃんに全責任を負わせた。だからあんたはさっき『好都合』と言ったのよ……思い出した?相変わらず傲慢な子ね。いずれにしても真の原因──つまり諸悪の根源はお信、あんたよ。」
「そうさね!」
とお信は同意したものの、そのそうさねには不満の念が込められていた。
「さっきも言った通り、髪型の特徴を小鉄さんにしっかり伝えられなかったお信が悪い。あんたは他人の事を超能力者とでも思ってるの?相手は単なる人間よ。人間ごときがあんたのことを全て理解できてるなんて思わない方がいい。」
「……そうさね。」
「あのね、お信。私の結論に関する妥当性は私が勝手に確信しているだけでそれが正しいかどうかは私ですら知らないわ。だからお信も勝手に判断すればいい。それにしても……昨日は鍋を焦がした。今日は散髪に失敗した。この二件、終わったことは気にしても仕方ないけど、私が言いたいのは、物事はよく吟味した上で納得しなさいってこと。その際、傲慢は吟味にとって邪魔な存在ってこと。わかった?」
「……そうさね。」
お信の頭の中には「モイスチャー」という文字がぼんやり浮かんでいた。
*
「ところでお信。ハーフアップのシニヨンって、わざわざ床屋になんて行かなくても自分でできるわよ。」
「え、ホントに?」
すると継母は折角結い上げた日本髪を解き、ゴムだけを用いて自分の髪をハーフアップのシニヨンにしてみせた。
「ほら。しーちゃんはこんな髪型だったでしょう?」
「まさにそれだわ!おかあさまってば、知ってるんなら先に教えてよ……」
「また人のせいにしようとする。それをやめなさいと言ってるの。」
「ごめん。」
「そもそもお信が私の部屋に散髪代をねだりに来たときに目的をはっきり言わないのが悪い。床屋に行きたいからお金をちょうだい、ではなくて『ハーフアップのシニヨンにするために床屋に行って散髪したいからお金をちょうだい』と言うべきだったわね。そうすれば私はお信が床屋に行かなくても自分で髪を整える方法を教えたわ。だから、真の目的を私に伝えなかったお信が悪い。というわけで、諸悪の根源はお信、やっぱりあんたよ。」
そう言うと継母は笑った。
「ええ、そんなあ……」
がっかりしたお信はそのまま厨房へ回ると、ようやく今日の仕事に取り掛かった。
*
そこから十数分あまりが経った頃、
「ダメだ!暑苦しくてやってらんない!」
「当然よ。頭巾なんてかぶって仕事してるんだから。そんなに暑いんならとっとと脱げばいいでしょ。」
「いやだ。髪が元に戻るまでこの頭巾はかぶり続ける。でないと生きてゆけない。」
「大げさね。ま、好きにすれば。」
と言うと継母は立ち上がってそのまま自室へと戻っていった。
そうして店内はお信ひとりだけとなった。客が来る気配はいっこうにない。
お信は頭巾を脱いだ。
思わず「涼しいなあ。」とひとりごとが出た。そして蒸し暑い厨房からカウンターへと回ったお信は、角に設置してある扇風機の前まで来ると、風量ボタンの「強」を押して頭全体に風を当てた。
「いよいよ涼しいなあ。」
と再びお信の口からひとりごとが出た。
「頭巾は脱がないんじゃなかったの?」
「おかあさま!いつの間に!」
驚くお信を差し置いて、継母はお信の頭を丹念に見ている──肩に掛かる程に長かった髪の毛は首回りまで短くなっており、すっきりとした印象を受けた。顔回りから耳にかけてはさほど短くもなく前髪が輪郭を沿うように垂れ下がっている。そして癖の無い髪質のおかげであろう、後ろから正面に目を移すと首、顔、頭のすわりも良く、何ら違和感は無い。お信は生まれつき綺麗な頭の形をしていたんだな、と継母はふと気づいた。
一方、散髪に失敗した頭を継母に見られて茫然自失となったお信は、その場からよろよろと後ずさりして店の戸に手を掛けると、
「もういい。ちょっと行ってくる……」
「お信、待ちなさい。どこに行くのよ?」
「バーバー小鉄。」
「行ってどうするつもり?」
「小鉄を殴る。」
「やめなさい。落ち着きなさい、ね。」
荒れるお信をなだめながら、継母は「素敵な髪型じゃないの。」とまずは率直な感想を述べた。
「あのね、お信。散髪は失敗ではなく大成功してると思うけど。」
「ウソに決まってる。おかあさまのおべんちゃらだわ。」
「いいえ。私は腹の底から『素敵な髪型』だと言った。」と続けて継母は先程見た、ありのままをお信に伝えた。そして最後に、
「そもそもしーちゃんとお信は顔の作りが違うんだからハーフアップのシニヨンなんてあんたには似合わない。お信は顔が丸いんだから輪郭が際立つ髪型がよく似合う。その髪型こそ、今回の短髪だったの。よかったわね、お信。小鉄さんに感謝しなさい。」
これを聞いてお信は耳を疑った。
「ほんとうに、この髪型はあたしに似合ってるの?」
「モダンガールに見えるわ。ま、今回の散髪はとどのつまりが怪我の功名、いわゆる結果オーライってことね。」
お信は「モダンガール」「とどのつまり」「怪我の功名」「結果オーライ」これら全ての言葉を知らなかったが、とにかく前向きな発言として捉えた。
「これはこれでよかったのかも。」
とつぶやくと、お信は厨房へ戻り再び仕事に取り掛かった。
継母はカウンターの隅に放置されている頭巾を手に取ると「これ、小鉄さんに返すのを忘れないでね。」「はあい。」と答えるお信の声を背中で聞きながらようやく二階の自室へ戻っていった。
*
一方その頃、店仕舞いを終えた小鉄はご隠居と連れ立って表に出た。ふたりは特に何を話すでもなかったが、どこか寄り道でもして帰ろうかという漠然とした心境で通りをぶらついていた。
往来はとうに日暮れ過ぎではあったが、そこに静けさや物寂しさは無く、道沿いの人家、飯屋、酒場からこぼれる朦朧とした光が行き交う人々を活気づけるかの様に通りを彩っていた。
そうした中を小鉄とご隠居が歩いていると、向こうから近づいてくる女性の姿が見えた。彼女はすれ違いざまに「こんばんは。」とだけ言ってそのまま行き過ぎようとしたが、
「お、誰かと思ったらしーちゃんか。しばらくだなあ。」
「お久しぶりです。」
「大学とやらは楽しいかい?」
「ええ、楽しくやってます。」
「そらあ何よりだ。」
「おじさまこそ元気そうで。」
そうしたしーちゃんと小鉄のやり取りを見ていたご隠居はふと、
「もしかして、その髪型は……ハーフアップのシニヨンか?」
としーちゃんに尋ねたところ、
「ええまあ、はい。そうです。ハーフアップのシニヨンを知ってるだなんて、おじいさんってばお詳しいですね……」
出し抜けの質問にしーちゃんは多少戸惑いを覚えたが、一方のご隠居は「やはりな。」と満足気であった。
「わたしそろそろ行きますね。」
「ああ。足止めしてすまなかったね。」
「いえこちらこそ。ではおやすみなさい。」
と言うとしーちゃんはその場から足早に去っていった。その後ろ姿を見ると、団子状にまとめられた髪の束が後頭部でゆらゆらと風に靡いていた。
「小鉄、どうやらあれが例のハーフアップのシニヨンだそうだ。」
「そうらしいな。」
とだけ答えると小鉄は続けて、
「なあんだ。あれなら俺にだってできるぜ。」
そう言うとふたりは笑った。そしてもう少しだけ歩き続けた末に「来たよ。」と言って「ラーメンお信」ののれんをくぐったのである。
*
継母は二階の自室に居た。
階下の店内に居るお信、小鉄、ご隠居の笑い声がここまで聞こえてくる。
「久々に『パイドロス』でも読んでみるか。」
継母は机に向かったがそこにパイドロスは無かった。
「本棚にしまったんだっけ。」とすぐ脇の本棚に目を移すと、ボロボロの百科事典の隣にパイドロスがあったので取ろうとしたところ、
『ゴルギアス』
という本が目にとまった。
継母はパイドロスではなく、ゴルギアスを手に取った。そしてページを次から次へとめくっては過去の記憶を辿るように再び読み始めた。
ゴルギアスを読み返して終盤に差し掛かった頃、継母の目に「鉄と鋼の論理」という文字が飛び込んできた。ここで継母はページをめくる手を止めた。
──鉄と鋼の論理。さっきの私は大人げなかっただろうか。お信には論理が無い。いや、あの子自身の中には理路整然とした理屈が組み立てられているのかもしれない。ただ、他者から「お信は論理的ですか?」と問われれば私はノーと答える。一体、あの子には鉄と鋼により構築された確信が無い。そこに至ろうともしないのはあの子の普段の賜物だろうか。その普段の中に私は確かに存在しており、私自身の経験から培った学びを教育という形に込めてお信に捧げてはいるものの、成果は全く見られない、昨日も今日もこれまでも。……マサヱさん。そしてあなた。お信は十八を迎えました。これでいいのでしょうか。
継母は、お信の亡き実母・マサヱ、死別した夫にそう語りかけた。
死別した夫、つまりお信の父は臨終の際、お信に向けて「善く生きろ。」と残してまもなく死の床に着いた。その死は継母にしてみてもここまで堪えてきた心痛の堰が一時に切れたかの如く涙が溢れたが、それを拭うことなく我が夫の死を真摯に受け止めた。一方で当時中学生のお信は父の死に対し、ただ泣きじゃくるしか術を持たず、これを目の当たりにした継母は幼くして実の両親を失ったお信が不憫でならなかった。
そして今、継母は夫の「善く生きろ。」という言葉について改めて考えていた。
──お信にとって善く生きるとは何だろうか。昨日、お信は「ラーメン屋の経営こそが自分にとって一番の幸せだ」と言っていたが、経営それ即ち、善いことに結び付くのだろうか。それはお信だけでなく他者に対しても善をもたらすのか。善の反対概念は悪。ラーメン屋経営自体は悪ではない。といってそれが完全無欠の善かと言われればそれも違う。ラーメン屋の経営、功利的手段に基づく幸福が善といえるのか。それも全く違う。夫にしてみても死に際に「善く経営しろ」だなんて馬鹿な事を考えるわけがない。お信という我が子の人生こそ善きものであれと望んだから夫は、善く生きろと言ったのだろう。考えが堂々巡りになってしまったが、継続してお信を助けてやらないといけないのは確かだ……いやしかし。どうしてこうも気だるいのか。
──ハーフアップのシニヨン、それを前にして理解できなかったお信。あの子は「モイスチャーは熱海にある」という大ウソを本当に信じているのか?そういえば今朝、仕入れに出かける際にお信は「エロース」と叫んでいたがあれはどういうことだろう。
継母はゴルギアスを閉じ、今度は『パイドロス』を手に取って読み始めた。
──お信がパイドロスに感化されたのだとすればモイスチャーへ向けたエロース、つまり愛智者たらんとするお信の意志を現わしたのだろうか。お信にとってモイスチャーは善い事なのだろうか。モイスチャーを知る真の目的はなんだろう。
最後に、継母はゴルギアスとパイドロスを机に並べて眺めてみた。
「何だかよく分からなくなってきた。」
*
階下のお信、小鉄、ご隠居の笑い声が先程よりも騒々しさを増して聴こえてくる。継母は、お信が散髪の件で小鉄とご隠居に迷惑をかけた事をふと思い出した。
「とりあえずお詫びしておくか。」
継母は階段を下り、そしてお信達が居る店内へ重い足取りで向かった。
【第三部へつづく】
付録「お信百景」























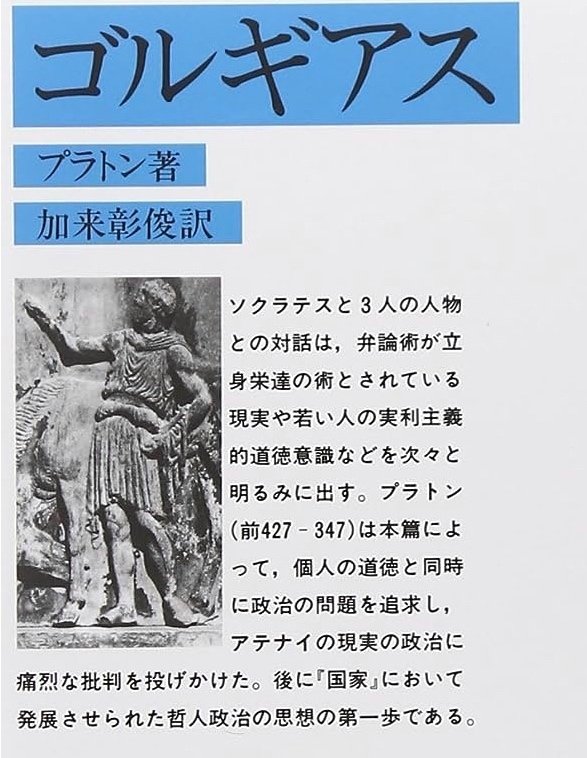
以上
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
