
【書評】 科学的な適職 鈴木祐 最高の職業の選び方
今回紹介する書籍はこちら!
Youtube大学でオリエンタルラジオのあっちゃんも紹介していた
科学的な適職!!
人材紹介の法人営業をやっている自分からすると、仕事にも活かせそうな非常に興味のあるテーマであった為、本書を手にとってみました!!
仕事選びを『科学的に』最適化する。という切り口が非常に面白く、納得感もある内容になっています。
これから就職活動をする方、転職活動中の方、近い将来転職を考えている方にとっては非常に参考になる内容になっているかと思います。
■著者 鈴木祐さんについて
1976年生まれ、慶応義塾大学SFC卒。16才のころから年に5,000本の科学論文を読み続けている、人呼んで「日本一の文献オタク」。大学卒業後、出版社勤務を経て独立。雑誌などに執筆するかたわら、海外の学者や専門医などを中心に約600人にインタビューを重ね、現在は月に1冊のペースでブックライティングを手がける。現在まで手がけた書籍は100冊超。科学論文で得た知識を仕事の効率アップに活かし、1日に2~4万文字の原稿を量産するいっぽうで、ライター界では珍しい「100%締め切りを守る男」としても知られる。近年では、自身のブログ「パレオな男」で健康、心理、科学に関する最新の知見を紹介し続け、現在は月間250万PV。近年は自著「最高の体調」(クロスメディアパブリッシング)や「パレオダイエットの教科書」(扶桑社)などを上梓し、ヘルスケア企業などを中心に、科学的なエビデンスの見分け方などを伝える講演なども行っている。
■本の構成と読みやすさ
■序章 最高の職業の選び方
■1 幻想から覚める―仕事選びにおける7つの大罪
■2 未来を広げる―仕事の幸福度を決める7つの徳目
■3 悪を取り除く―最悪の職場に共通する8つの悪
■4 歪みに気づく―バイアスを取り除くための4大技法
■5 やりがいを再構築する―仕事の満足度を高める7つの計画
前半部分は、仕事選びにおける『ポイント』を科学的な知見を基に、解説。後半部分では仕事選びの為の自己分析、企業分析の具体的な方法をワークシート等を用いて解説する内容となっています。
全体ボリュームは280ページ!!
比較的読みやすい内容となっており、1~2時間で読み終える事が出来るかと思います。
それでは、本書の内容をご紹介!!
■3年以内に3割が会社を辞める
仕事選びって結構難しいですよね。
僕自身、大学時代、就職活動中に約130社ほど会社訪問などをして就職先を銀行に決めましたが、1年5ヶ月で見事退職しました。笑
厚労省のデータを見ると、現在、入社から3年以内に離職する人の割合は30%を超えるとの結果が出ています。
前向きな転職ならいいのですが、離職理由の多くは「思っていた仕事と実際の内容が違った」というネガティブな項目が占めており、仕事選びの難しさを表しています。
また欧米やアジア圏の約2万件のデータによれば、ヘッドハンティングにより会社の管理職等に転職をした人のうち、約4割が何かしらの理由で退職をするか、ポストをおりるという選択をするという結果が出た事が分かっています。
人生の中での大きな決断である仕事選び。
私たちは、十分慎重に検討をしているはずなのに、なぜ間違えてしまうのでしょうか。
■なぜ私たちは仕事選びが下手なのか
就職と転職の失敗の7割が「視野狭窄」によって引き起こされる
「視野狭窄」とはものごとの一面にしか注目できず、その他の可能性を全く考えられない状態を意味します。
仕事選びの際には十分に選択肢を吟味し、慎重な判断をされる方が多いイメージがありますが、なぜそんな事が起きてしまうのでしょうか。
「視野狭窄」を引き起こす定番パターンは以下3つとのこと。
・お金に釣られる
給料UPに釣られて転職を決めて、それだけしか考えられなくなるケース
・逃げで転職を決める
現在の仕事に不満が募り、将来の為ではなく、逃避で職を転々とするケース
・自信がありすぎる、または無さすぎる
自己評価がやたらと高いせいで、「私はどんな会社でもやっていける」「今の会社には問題がありすぎる」などと断定してしまい。実は自分の方に問題がある可能性やありがたみに思いが行かないケース。
または自分に自信が無さすぎて「あんな会社は自分では到底無理だ」と思い込んでしまい選択肢を狭めてしまうケース
何だか、思い当たる節がありますね。。。
いずれのパターンにしろ、仕事探しの、一部のポイントにしか目が向かず、考えうる選択肢を自ら狭めてしまっていますね。
脳内が黒か白かの二択だけになり、もっと良い可能性を考えられない状態となっているのです。
「視野狭窄」によって選択を誤ってしまう現象は、あらゆるシチュエーションに存在し、どんなに頭の良い人でも避けられないと言います。
■人間の脳は職業選択に向いていない
なぜ、人間は職業選びという大事なシーンで「視野狭窄」に陥ってしまい、誤った選択をしてしまうのでしょうか。
その理由は以下の2つに集約するといいます。
・人間の脳には職業を選ぶ為の「プログラム」が備わっていない
・人間の脳には適職選びを間違った方向に導く「バグ」が存在している
人類史の大半において、人間は、職業選択の自由とは無縁の暮らしをしてきました。
原始時代に生まれれば狩りを行い、江戸時代に生まれれば士農工商の制度に従い、中世ヨーロッパに生まれれば農奴隷として働く。
使命としての職業が、生まれた時から決まっているのが常識だった為
職業選びの際に起こる「複数に分岐した未来の可能性をうまく処理する能力」が進化しなかったと言うのです。
だからこそ、職業選びという多くの選択肢を前にして、不安や混乱などの負の状態に陥ってしまう人が多く生まれてしまうそうです。
もう1つの原因が、脳に備わったバグの存在。
偏見、思い込み、思考の歪み、不合理性、、、
呼び方は様々ですが、いずれにおいても人間の脳には生得的なエラーが存在し、大事な場面でいつも同じような過ちをおかすように出来ているのだそうです。
職業選びのおけるバグの発生例は以下です。
【利用可能性ヒューリスティック】
1つの転職エージェントや友人の紹介だけで、転職先を決めたら、全く社風に馴染めない会社だった。
【現状維持バイアス】
就職した企業が自分に合っていないと分かっていながら、「転職しても改善するとは限らないし、、、」といつまでもだらだらと居座ってしまう。
【インパクトバイアス】
憧れの会社に入ったのは良かったが、時間が経つにつれて、「もっと良い会社があるのではないか」と思えてきた。**
実際に仕事をしてみないと分からない部分ももちろんありますが、事前の情報収集や分析方法に工夫を加えることで、誤った職業選びをしてしまう可能性を抑えられると筆者は言います。
一体、私たちはどのように職業選びをすれば幸せになれるのか。。。
大切なのは『仕事選びにおいて、多くの人がハマりがちな定番もミスを知っておくこと』だと筆者は言います。
■7つの大罪
仕事選びにおいてやりがちなミスとはどういったものがあるのでしょうか。
現時点で多くの研究が『人間の幸福とは関係のない要素』について信頼性の高い答えを示しています。
まとめると以下の7つに集約されるそうです。
・好きを仕事にする
・給料の多さで選ぶ
・業界や職種で選ぶ
・仕事の楽さで選ぶ
・性格テストで選ぶ
・直感で選ぶ
・適性に合った仕事を求める
いずれも良く見かけるアドバイスですよね!
しかし、この観点で仕事を選んでしまうと、短期的な喜びは生まれても、中長期的には仕事の満足感を下げ、最悪の場合は不幸な職業選択となってしまう可能性が高いと筆者は言います。
具体的に紐解いて行きたいと思います!
【大罪1】好きを仕事にする
『好きを仕事にしよう!!』良く聞く言葉ですよね!
多くの人が好きを仕事に出来たら幸福になれると感じているのではないでしょうか。
しかし、多くの職業研究によれば、自分の好きなことを仕事にしようがしまいが、最終的な幸福感は変わらないそうです。
2015年ミシガン大学が仕事の考え方が幸福度にどう影響するのか、という大規模調査を行いました。
被験者の仕事観を以下の2パターンに分け、分析を行ったのです。
適合派
好きを仕事にするのが幸せだ!!と考えるタイプ
給料が安くても満足感できる仕事をしたいと答える傾向がある。
成長派
仕事は続けるうちに好きになるものだ!!と考えるタイプ
そんなに仕事はしなくても良いけど給料は十分欲しいと答える傾向がある。
一見、適合派の方が仕事の満足感が高そうに見えますが、結果は意外なものでした。
適合派の幸福度が高いのは最初だけで、1〜5年程度の長いスパンで見た場合、両者の幸福度・年収・キャリアなどのレベルは成長派の方が高かったのです。
研究者は、「適合派は自分が情熱を持てる職を探すのがうまいが、実際にはどんな仕事も好きになれない一面がある」と言います。
好きな仕事を求める気持ちが強いと、その分現実の仕事に対するギャップを感じやすくなり、適合派の中には、「今の仕事を本当に好きなのだろうか」と疑念が生まれやすくなり、最終的に幸福度が下がるそうなのです。
【大罪2】給料の多さで選ぶ
どうせ働くなら給料が多い方が良いですよね!?笑
求人を選ぶ時も、給料の高いほうから探していくという人も多いかと思います。
しかし、給料が多いか少ないかは、私たちの幸福や仕事の満足度にほとんど関係ないと言うのです。
これもフロリダ大学の「お金と仕事の幸福」という研究により精度の高い答えであると結論付けられています。
お金で幸せが買えない理由は大きく以下の2つに集約されるそうです。
・お金を持つほど限界効用が下がる
・お金の幸福は相対的な価値で決まる
限界効用は経済学で使われる用語で、モノやサービスが増えるほど、そこから得られるメリットが下がってしまうという現象を表したものです。
つまり、私たちがお金持ちになり、いくら贅沢をしようが、いずれはそれに慣れてしまいメリットを感じなくなるのです。
また、年収に限って言えば、給料アップによる幸福度の上昇は平均して1年しか続かないと言います。
給料から得られる喜びは実に短命なのです。
そしてもうひとつ、お金から得られる幸福は相対的に決まる。という問題もあります。
年収アップの喜びは給与明細の絶対額ではなく、他人がもらっている給料との比較で決まるのだと筆者は言います。
もしあなたが百万長者であったとしても、周囲が億万長者ばかりであれば幸福度は上がりません。
【大罪3】業界や職種で選ぶ
業界や職種の将来性を測るのは、あまりにも難易度が高いため
おすすめをしないと筆者は言います。
理由は大きく以下の2つです。
・専門家だろうと将来有望な業界を予測できない
・人間は自分の個人的な興味の変化を予測できない
第一の問題に関して、専門家の業界予測は全くあてにならないと筆者はいいます。
業界の未来予測といった情報は一定の需要がありますよね!!
僕もこの市場がこうなるだろう、こうなったら面白いなと良く予想をしています。
ところがこういった専門家の予測は全く当たらない。
どんなに知名度のあるエキスパートであろうと、予想の精度はコイン投げと変わらないと言うのです。
業界の未来予測に関して、ペンシルベニア大学が研究を行ったものがあります。
1984年から2003年にかけて、有名な学者やジャーナリストなど248人の専門家を集め、3~5年後の経済や企業の状況、政治がどのようになっているか予想させたのです。
最終的に集まった2800超の予測データを全てまとめたところ、結果は
『専門家の予測は約50%の確率でしか当たらない』というものでした。
また私たちの興味や関心も、移ろいやすいという傾向があるというのも、問題のひとつです。
ハーバード大学での研究によると、若い頃から抱いていた夢を中長期的に抱き続ける人はごくわずかで、多くの人は時間をかけて興味や関心は変化していくと結論付けられています。
若いころにタトゥーを入れていた人が、大人になるとタトゥーを消したくなったり、恋い焦がれたパートナーと離婚をしてしまう人が後を絶たないように、私たちは、自分自身の変化さえ予測出来ないというのです。
未来の状況は分からないけれど、少なくとも『私たちが予想しているものとは大きく異なったものになる』ということを認識することが大切だと筆者は言います。
【大罪4】仕事の楽さで選ぶ
多くの人が、ハードは仕事は好まないでしょう!!
僕は嫌いではありませんが、、笑
できる限り負担の少ない仕事を選んでしまうのが、多くの人の人情かと思います。
しかし、そうした背景から楽な仕事を選ぼうとするのも、幸福度の低下に繋がる可能性があると言います。
ストレスが体に悪いのは確実なものの、その一方で『楽すぎる仕事』もまた、あなたの幸福度を大きく下げてしまいます。
イギリスの研究によれば、組織内で地位のランクがもっとも低い人は、ランクが高く、より重大な仕事を行う人と比較して、死亡率が2倍高かったとの結論が出ています。
これは人間以外の種族にもあてはまる現象のようで、アフリカのサバンナで暮らす『バブーン』を調べて研究でも、仕事の少ない個体の方がストレスホルモンが多く発生するという結果が出ています。
※バブーンとやらはこいつのことです。
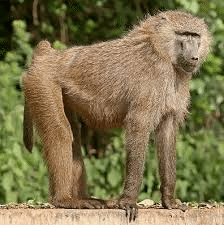
仕事の負荷が少なければ、必ずしも楽になれるわけではないと筆者は言います。
また適度なストレスは仕事の満足度を高めるということもわかっています。
適度なストレスがもたらすメリットは以下の3つがあると言われています。
・仕事への満足度を高める
・会社へのコミットメントを改善する
・離職率を改善する
ほどほどのストレスであれば、なんの問題もないどころか、幸福度を高めてくれる働きがあるのです。
体を鍛えるのに、ランニングや筋トレによって適度は負荷を与える必要があるように、私たちの幸福度も適度のストレスが無いと成長しないと言うのです。
【大罪5】性格テストで選ぶ
就職サイトや転職サイトにアクセスすると簡単に性格診断を受けられますよね!!
個人的にこういうの大好きで積極的に受けていました!
どうやら『エニアグラム』という理論をもとにしたテストなのだそうですが
残念ながら性格テストによって自分に合った仕事を見つけられる保証はどこにも無いと筆者は言います。
具体的に『エニアグラム』の考え方を見ていきましょう。
『エニアグラム』では、人間はそれぞれが特有の欲望と恐怖のパターンを持ち、その種類によってパーソナリティが決定していくと考えられています。
例えば『信頼を求める人』は、安全を求めて孤独を嫌い
『平和を求める人』は安定を求めて葛藤を嫌うと定義されています。
お気づきの方もいるかもしれませんが、『安全』と『安定』は非常に似通った概念であり、両者をはっきり区別することは出来ません。
不安症の人がそれぞれの概念を見たときに、どちらも「自分のことだ!!」と認識してしまうのは言うまでもないでしょう。
この認識は学問の世界でも広く認められており、『エニアグラム』の有用性を示したデータはこれまでにないと言うのです。
他にもMBTIやライゼックといった多くの性格検査が現在、職業選びに使われていますが、どれも信ぴょう性の高いデータは見つかっておらず、性格検査だけが、一人歩きしてしまっている状況が続いていると筆者は言います。
【大罪6】直感で選ぶ
『最後は自分の直感で決めるしか無い』
『直感で出した答えは意外と正しい』
これもまたキャリアアドバイスの世界で良く聞く言葉です。
スティーブジョブズもこう述べています。
『何より大事なのは、自分の心と直感に従う、勇気を持つことです』
確かに直近では一部のデータが直感の有用性を示しているといいます。
例えばプロのチェスプレイヤーを対象とした実験では、直感重視の「早指しチェス」をすることで優秀な成績を納めることが可能になるという結果が出ています。
しかし、直感が有効に働くには以下の条件があるそうです。
・ルールが厳格に決まっている
・何度も練習するチャンスがある
・フィードバックがすぐに得られる
チェスはこちらの条件に当てはりますね。
ルールが決まっていて、何回も練習が出来る。
試合が終わればすぐにフィードバックが得られます。
しかし、仕事選びは、この条件に全く当てはまりません。
仕事選びにルールは無く、選考は1発勝負。
良い会社かどうかだって、入社して数ヶ月しないと分からないでしょう。
このような悪条件のもとでは、私たちの直感力は正常に働かないと筆者は言います。
またアメリカの大学で行った研究では、論理的ではなく、直感で決めた選択は合理的でなく、盲目となり自己の正当化につながり、他者からの評価も悪くなるとの結論が出ています。
ほとんどの人生において、論理的に考える人の方が、人生の満足度が高く、日常のストレスも低いというのです。
【大罪7】適性で選ぶ
『適性』というフレーズも仕事選びにおいて良く登場するワードですよね。
新卒採用でも中途採用でも適性検査を重視する企業は増えています。
それでは、私たちは、適性検査によって、自分たちに合う仕事を事前に見抜くことが出来るのでしょうか。
この問題に関する研究の中で、最も精度が高いと言われているメタ分析という研究があります。
過去100年に渡る、職業選択のリサーチから
『仕事のパフォーマンスは事前に予測が出来るのか』
という問いに対する、結論を出したのです。
この研究では「事前面接」や「IQテスト」といった適性検査をピックアップし、それぞれの相関関係を求めました。
結論、多くの適性検査は、就職後のパフォーマンスを測るには、相関関係が低すぎて、役には立たないという見解となりました。
最も精度の高いテストですら、候補者の能力の29%しか説明が出来ないとうデータが証明されたのだそうです。
要因は、私たちのパフォーマンスを左右する変数が多すぎることにあると言います。
現実の世界では、仕事に必要な能力や適性は多岐に渡っており
その全てを網羅してテストを行うことは不可能に近いと言うのです。
【まとめ】
いかがでしたでしょうか。
今回は私たちの幸福度を高める為の仕事選びにおいて、可能な限り避けたい
『7つの大罪』に関してご紹介させて頂きました。
それではどういう項目を重視して仕事選びをすれば良いのか??
答えは本書の後半部分で語られています。
詳細を知りたいという方は、ぜひ一読頂ければと思います。
今の仕事が自分に合っているのかどうかを確かめる、モノサシとしても非常に参考になるかと思います。
本書の内容は、あくまでも『幸福度を高める』為の仕事選びの為に大切な指標を定義しています。
それぞれ、仕事に対する想いはいろいろあるかと思いますので
参考程度に読み進めるのが良いかと思います!!
自分の考え方とは違う考え方を学ぶのも、クリティカルシンキングを鍛えるには重要ですからね!!
それでは、最後までご覧頂き、ありがとうございました!!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
