
イスラム圏の戦争史を概観した『イスラムの戦争(Islam at War)』の文献紹介
21世紀に入ってからも、西アジアにおいては戦争が止むことはなく、各地で大小さまざまな戦いが続いています。この地域の戦争を理解するためには、歴史的なアプローチをとる必要があり、特にイスラム教の発達と関連付けた戦争史を知ることが効果的です。
研究者向けの専門書ではなく、一般向けの概説書として紹介することができるものに『イスラムの戦争(Islam at War: A History)』(2003)があります。これはイスラム教が創始された7世紀から米国が対テロ戦争へと乗り出した21世紀の初頭までの西アジアの戦争史を要約している軍事史の著作です。
Nafziger, George F., and Mark W. Walton. 2003. Islam at War: A History. Westport: Praeger.
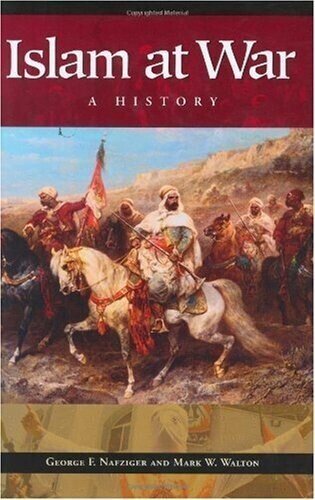
目次
イスラーム教の誕生:イスラーム教の拡大と戦場の指揮官としてのムハンマド
大征服
イスラーム教と十字軍
剣とインド:モンゴルの征服
イスラーム世界におけるエジプト
ムスリムの征服とスペインの喪失
オスマン帝国の勃興
ヨーロッパの病人:バルカン人とオスマン帝国の没落
剣と海上:ムスリムの海軍、レパント、マルタ
ムッラーと機関銃:中東における植民地戦争
ムッラーとミサイル:1945年以来のイスラームの戦争
イスラーム教とジハード:本来の自身に到達するために
神のために身を捧げる:暗殺の過去と現在
結論
7世紀に創始されたイスラム教は、西アジアを中心に独自の発展を遂げた世界宗教です。歴史学ではイスラム教が宗教にとどまらず、政治、経済、社会など幅広い影響を及ぼしたことが明らかにされていますが、著者らは特に戦争との関連に注目しています。
著者らはイスラム世界の軍事史は3期に大別できると述べています。第1期は大征服の時代であり、7世紀の創始された直後から始まっています。
預言者のムハンマド(Muhammad, 570?~632)は自らの教えを広める過程で、時の権力者から危険視されるようになり、最終的には武力闘争を指導しなければならなくなりました。ムハンマドの死後およそ1世紀の間にイスラムの勢力は大きく拡大し、一時は北アフリカ、スペイン、インドを征服するほどでしたが、やがて政治的分裂の時代に入ると、その勢力は少しずつ後退し、ヨーロッパの十字軍、そしてモンゴル帝国の侵攻を受けることになりました。
第2期はオスマン帝国の時代です。14世紀に台頭したオスマン帝国は長年にわたってイスラム教徒と戦ってきたビザンツ帝国の首都を攻め取り、その支配を安定させました。
オスマン帝国の下で政治的安定が確保されると、その勢力は地中海、バルカン半島を経てヨーロッパに及ぶようになり、特にオーストリアの何度もオスマン帝国の侵攻を受け、戦いが繰り返されました。しかし、相次ぐ敗戦と政治の腐敗などの要因が重なり、次第に軍隊の能力は低下していきました。
19世紀までには工業化を遂げたヨーロッパの列強に対抗することができなくなるほど衰退しており、第一次世界大戦で敗れたことが最後の打撃となりました。オスマン帝国の領土はイギリスやフランスによって分割され、現代の中東の国境が形作られることになりました。
第3期は第二次世界大戦以降の時代です。第二次世界大戦でイギリスやフランスの勢力が後退したことで数多くの独立国家が誕生しました。
しかし、ヨーロッパの列強に取って代わって台頭した米国とソ連がそれぞれの利害から中東各国を支配下に置くために競合し、特にアフガニスタンでは1979年以降に長期にわたって代理戦争が繰り広げられました(アフガニスタン紛争)。ユダヤ民族の国家としてイスラエルが建国され、アラブ諸国との長い戦いが始まった時代でもあります(中東戦争)。
著者らの議論は2001年のアフガニスタン侵攻、そして2003年のイラク戦争にまで及んでいますが、2003年の出版であるため、それより後に起きた戦争に関して言及はありません。また、それぞれの戦争の原因に関する記述はあまり充実しておらず、戦争の経過も概観するにとどまっています。
それでも、7世紀から21世紀までの長期にわたってイスラム圏の戦争史を一冊の書物にまとめるという無理難題に果敢に取り組んだ著作として評価することはできると思います。アラビア語の固有名詞には苦労するかもしれませんが、専門的な表現は避けられており、一般向けの書籍として書かれています。
関連記事
調査研究をサポートして頂ける場合は、ご希望の研究領域をご指定ください。その分野の図書費として使わせて頂きます。
