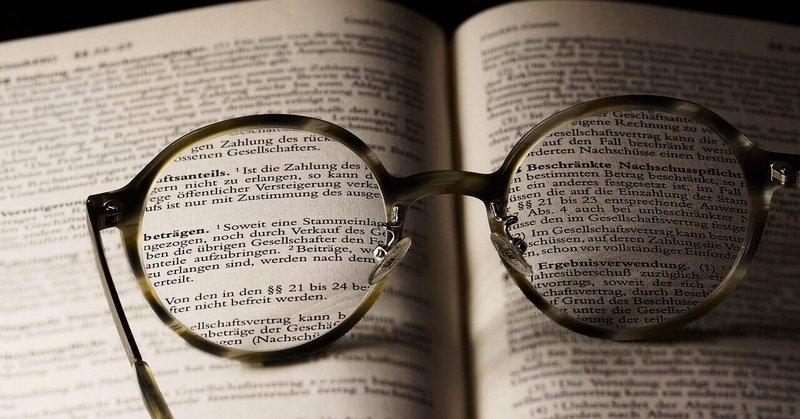
50年前の産業用ロボットの論文の指摘が心に染みる。
先日、何気なく目を通していたウェブニュース。
この記事は記事で、特に無料登録してから読める2ページ目以降が面白かったのですが、その中に以下のような文章がありました。
「自動化を実際に進めるか否かは管理者の自動化へのニーズ如何による。上記のように企業を取り巻く条件が急激に変化していくことに対する認識の問題である。目前の算盤勘定にのみ固執していると企業を過(あや)まることになりかねないということである」──これは1972年に発表された「自動化とロボット」という論文の一節である(注)。
注) 「自動化とロボット」『機械の研究』第24巻1号
ここでは、将来の倉庫や物流像を考えた上で、企業として何を差別化要素として設定するかをよく考えなさい、という指摘の文脈で産業用ロボットに関する論文が引用されていました。日本ロボット工業会がロボット産業の出発点となったとして「ロボット普及元年」に設定したのが、1980年です。その前の1972年にこんなことが指摘されていたのだなぁと感心しました。
この頃の歴史は、以下などを参考に頂けるとイメージが沸くかもしれません。
歴史そのものは一旦置いておいて、今回は、ロボット元年と呼ばれる1980年よりも前の時代に、ロボット研究者は何を感じ、どんなことを指摘していたのか調べてみます!!
というわけで、Google Scholarで「ロボット」をキーワードにして調べて見ると、1980年代:8550件、1970年代:1290件、1960年代:269件、1950年代:67件の論文や発表が引っかかりました。J-STAGEで検索してみても同じような傾向でした。学術面でも1980年代に一気に拡大したように見受けられます。もちろん、ほとんどの研究発表は純粋に工学的な内容だったのですが、いくつか業界を俯瞰した分析や課題について論じているものもありました。
すると、「今でも当てはまる・・・」というような内容や「昔はそうだったのか」と考えさせられる内容もありましたので、いくつか紹介したいと思います。
ざぁーーーっと見た中で、印象に残ったのは、
合田 周平, アメリカにおけるロボット研究の現状と今後の問題点, 計測と制御, 1968, 7 巻, 12 号, p. 859-870(論文)
梅谷 陽二, ヨーロッパにおける工業用ロボット研究のすう勢, 日本機械学会誌, 1977, 80 巻, 702 号, p. 420-423(論文)
という、いずれも海外の状況と比較をした上で現状や課題を論じていた内容。
特に印象に残った箇所を引用させて頂くと、
合田 周平, アメリカにおけるロボット研究の現状と今後の問題点, 計測と制御, 1968, 7 巻, 12 号, p. 859-870
今後これらをさらに開発するため,または,現在の工業用ロボットをさらに活躍させるためにも,つぎのようなアプローチが考案され開発されている.
3・4・1 ロボ ット・システムの開発
コ ンベアを中心とした現在の工程ラインに,これら工業用ロボットを活用するためには,工業用ロボットとコンベアとのシステ ムの研究が必要である.す なわち,・・・(中略)・・・
(c) コンベア 自体の開発,つまりコンベ ア上の部品を位置ぎめすることで,暗 中模索するロボ ットをたすけ活用する.
(d) 工程全体 のIntegrationをすすめる.このことは,エ レク トロニクスにおけ るIC回 路の思想を工場全体に適用 しよ うとす るもので,ロボットに都合のよいように工程システムを改良しそれをもとにロボットを考ようとするものである
今で言うところの、システム連携やロボットフレンドリーな環境整備、そして、全体最適化みたいなことでしょうか。
同じような内容として、以下のような指摘も書かれています。
とくに工業用 ロボットの場合,現在の人間の作業者を対象とした工程システムにそのまま合うようなロボットを開発することへの疑問である.さきにも述べたように,ロボットの開発はまず機械であるロボットに都合のよいような工程ラインの改善よりはじめるべきで,それとともにロボットがその機能を充分に発揮しうるような形態を考えるべきである.このことは,工程全体のIC化 にも通じるもので,現実の問題として,それぞれ機械化に都合のよいブロックごとに,こうした問題をとりあげることが,工業用ロボット開発にまず要求され ることである.このような意味で,バーサトランやユニメートなどの設計基準 となっている人間の作業者にすぐとって代わりうるという利点は,ロボット開発という大局的な立場にたつと,それはかえつて将来の発展のための欠点とな りうるものである.要するに,ロボット工学という新しい分野の研究にあたっては,まず目的とする作業についての手順や環境をよく分析し,基本的問題か らとりあげるべきで,いたずらに現存するシステムや技術にかなうロボットの開発にとりかかることはつつしむべきことである.
同じようなことの自分の日経クロステックの連載に書いたばかりなことが、こっぱずかしくなってきます。。。産業用ロボットの開発において昔、指摘されていたことが、今サービスロボットの開発においても目の前に出現してきているという解釈もできるかもしれません。
そして、極めつけは最後の締め方。1968年当時の話かと思いますが、頭にしっかり叩き込みます!
わが国のロボット研究はまだ日もあさく,そのことばのもつイメージから一般的な興味に流れやすいが,われわれ工学研究者は,その意義と目的を正しくつかんで工学的サイドか らロボットを考えることが第一で,そのためにも技術 の総点検とロボットの目標をまずかためることがたいせつである.
梅谷 陽二, ヨーロッパにおける工業用ロボット研究のすう勢, 日本機械学会誌, 1977, 80 巻, 702 号, p. 420-423
工業用ロボットは確かに自動機械ではあるが,通常の自動機械とはいささか 異なる側 面をもっている.すなわち通常の自動機械は,自動化と高速化に よる量産効果もしくはスケールメリットの獲得を目的とする生産手段と考 えられる.それゆえ自動機械を導入するかどうかは経済性(設備投資のそ ろばん勘定)だけで判断ができ,また何を導入すべきかは技術的な機種選 定の問題として解決できる.これに対して工業用ロボットは,これを単な る設備機械と見なして生産現場へ導入するには,余りにも問題が多すぎる ことはすでに識者の指摘するところである.工業用ロボットを特徴づける 側面は,つぎに示すいくつかの指摘から明らかになろう.
・一連の動作を繰返すハンドリングマシンである .
・人手不足を補うための省力機械である .
・低位作業や危険労働の解消に有効である(いわゆるQWLの問題 ).
・労働組合とのいざこざの種である .
・もっと人工知能化しなければ使いものにならない .
要するに工業用ロボットにっいては ,どんなタイプのロボットをどこへ何台備えっけるか,またどんな業種に適用されるべきか,などの解答は産業構造や労働市揚,さらには労働者の意識にまでさかのぼって考察せねば得られ ないのである .
工業用ロボットをサービスロボットに置き換えても、だいたい当てはまりますね。特に、最後の一文はごもっとも!という感じです。
工業用ロボットの効用は,どのような工程へ適用するかによって半分以上決まってしまう.逆に言えば,現在もっとも効果的に使われている生産現揚 を見れば,工業用ロボットの必要性,技術水準,使命が感知できる.
成功事例の研究が圧倒的に不足しているような気がしていますので、もっと勉強します!!
そして、結構ビックリしたのは、以下の図でした。

この図は、Proc. International Symposium on IndustrialRobots,1st−6thとProc. Conference on Industrial Robot Technology, 1st〜3rdでの発表を国別、そして内容別で分類したものなのですが、思ったより「調査・分析」の研究比率が多いのです。ここでの「調査・分析」は、『工業用ロボットに関する広義のIE(工業経営学)を行った論文をさし,また需要予測や技術アセスメ ントを包含している 』とされています。具体的にどんな発表がされていたのかは確認できていませんが、少なくとも現状国内・海外のカンファレンスでは基礎研究、開発研究がメインであり、IE的な内容が発表されていることはほぼ内容に感じます。
産業用ロボット元年を迎える前に、現場の分析やIEな取り組みについて非常に多くの発表がされ、多くの事例共有が行われているということは、今の段階においても非常に示唆に富んでいる内容です。
今回は、代表例として2つの論文から引用しましたが、この他、例えば、
森 政弘, ロボットの基本思想と構想, 計測と制御, 1968, 7 巻, 12 号, p. 871-880(論文)
などは、ロボット研究者として非常に勉強になるものでした。
というわけで、自分が生まれる前の論文や発表に、今回改めて目を通してみましたが、先人達の知見、視座は凄まじいなぁと思うとともに、まだまだ勉強が足りないなと再認識次第です。そして、今考えていること、感じていること、分っていることはしっかり纏めておく重要性についても教えられた気がします。
では、また来週〜。
「フォロー」や「ハートマーク(スキ)」を押して頂けると喜びます。笑
安藤健(@takecando)
==================
Twitterでは気になった「ロボット」や「Well-being」の関連ニュースなどを発信しています。よければ、フォローください。
頂いたサポートは記事作成のために活用させて頂きます。
