
【読書記録#11】「言語技術」が日本のサッカーを変える
スポーツ指導者の論理的に話す力が注目されています。
特にサッカーの場合は、唯一の正解がないスポーツです。
正解がない中でも、
最適な判断を相手に理解させ納得するように説明するには
コミュニケーション力が必要になります。
「あいまいな指導が多い」と
スポーツを長年やっていて僕も感じていました。
同時に、指導者をしていて、感覚的にプレーしていたものを
言語化する難しさをひしひしと実感していました。
「なぜ、この時はこうしないといけないのか?」
一時的に疑問を持つものの、
「そういうものだから」
で片づけてしまうことが日本人には多くある気がします。
そこで止まっていたら、進化は無い。
そのように本書を読んで再確認できました。
冒頭に書いてあった内容で印象に残っていることがあります。
それは、2006年W杯準決勝、イタリアが一人退場して10人になった時、出場プレーヤーの誰一人としてベンチを観なかったということ。
日本で考えられるでしょうか?
少年サッカーから高校サッカーを見ていて、トラブルが起こった時には必ずといっていいほど、ベンチを観ます。
目的は、
次どうしたらいいか、監督の意見に耳を傾ける為に。
そういった習慣があるからです。
イタリア代表がそうでなかったのには、
選手一人ひとりが
「考えるサッカー」を身に付けていたからだそうです。
欧米は選手が考える自ら考えてサッカーできるような
スタイルということです。
「考えるサッカー」ができる為には何が必要なのか。
それが論理的なことばを扱うスキル「言語技術」の習得に
他なりません。
まずは指導者が「言語技術」を磨くこと。
そして、選手に論理的な「ことば」を用いて接すること。
すると、選手たちの思考は論理的にサッカーを捉えることができるようになり、瞬時に解を出す力が養われます。
それが「考えるサッカー」に繋がるのではないでしょうか。
以下はメモ書き程度に
気付いたり、学んだり、上記のように考えたりした理由を
納めます。
・ドイツと日本の違い「自分の考えを言葉にする能力」
①言葉に出して明快に表現する力が身についていない。
「ただなんとなく」「あいまいなまま」で納得することが多く、
やがて平気になっているから。
②「論理」を求めると、1つの正解だけを探す。
心の中に「まちがってはいけない」という固定概念が
教育上身についている。
・サッカー指導者養成のためにディベートの講習を導入
(日本ディベート研究会 北岡俊明先生)。
サッカーは唯一の正解というものがないスポーツだからこそ、
監督は自分なりに論理的に考え抜いた上でこの方法が
一番いいのだという根拠(エビデンス)をもって
選手たちに納得させなくてはならない。
・言語技術の習得は子どもの方が早い。
大人は社会人としての経験が豊かな人ほど、
言語を直していくのが早い。
逆に、(学校の教員など)1つの立場で長く仕事をしていた人
は、言語についても固定的な習慣がついてしまっている傾向が
見え、修正に苦労する。
・「言語技術」とは、
情報を取り出し、解釈し、自分の考えを組み立て、判断する力
・日本人、論理的に突き詰めて考える習慣がない
その際のトレーニングのポイント
①たくさんの人と一緒に訓練する
②考え感じたことをことばにし、声にして出すこと
自分の考えたことや感じたことは、
ことばにして声を発した時点で、
やっと他者に伝わる条件を得ることになる。
・相手に確実に伝えるための条件
→誰からも正確に理解してもらえる言葉で話す
・バルセロナ、一流の建築家が講話している。
惜しげもなく教育現場に投入している。
・人間としての能力を磨き、自立した選手になる。
その土台の上に文化的素養(日本文化)を積み重ねなければ
本当の日本流サッカーは花開かない。
・1試合、ボールタッチの多い子だと約100回。
少ない選手は30回。
ボールコンタクトの機会に論理的に考えているかどうかに
よって、考える力は大きく変わる。
・こどもの自立に向けて準備するために大人がすべきこと、
サッシの悪い「大人」を演じること。
・指導者も論理力UPが求められる。
理由は指導者は素晴らしい理論を持っていたとしても、
それを正確に伝えることができなくては、
理論をもっていないと一緒であるから。
・野外教育を指導者養成で実施。
野外教育…元は軍隊の教育。
戦場は命がけであり、全ての指示は、曖昧さを排除し、
明確に、論理的に、スピードをもって出される必要がある。
それをサッカー指導者向けに開発。
(サッカーは戦況の移り変わりが激しい。戦場と似ている)
・指導者の意識次第で選手の伸び方が変わる
(取り組んでいる練習やどのように接するのかという
日常的な関わりまで)
・意味があるプレーに取り組むということは、
ひとつひとつのプレーが失敗したか成功したかを
その都度自分で考え、感じ、判断しながら理解していくことに
繋がる。
自分の意図通りにプレーできたかどうかという判断基準を
持ちながら、試合経験を積み重ねる。
・日本人の資質「阿吽の呼吸」と
論理的なコミュニケーションを使い分ける必要がある。
・欧米など外国との共存するグローバル化は進み、
国境は消えていく時代。
見識豊かな国際人として生きていくには欧米流の「言語技術」を
理解し、身に付ける。そんな時代である。
・「お前、そのプレーをしていたら、プロになれないぞ」。
指導者が「ここがプロのラインだ」とはっきりした言葉にだして
言える強さも大事。
・「お前に対する指導はこの目的のためだ」と毅然として語る
ことのできる「理論」と「ことば」を持つこと。
・リスペクトとは強制されるものではない。
自分が誰かをリスペクトするからこそ、
自分もリスペクトされる。
・Jリーグ発足当初、日本人監督は全体の2割。
理由は一流外国人プレーヤーに対して、
「日本人監督は、自分のチームの選手たちを自身の『論理』と
『ことば』によって説得しプレーさせる力が足りない」から。
選手「なぜ?」に対して、「なぜなら」と答えられずにいた。
・オシム監督のミーティング
「論理的に言うと」というフレーズが2時間に10回以上出る。
・「アピアランス」がいかに大事か。
言語技術以前の人間性の問題。
・少年指導は、ゲームの結果に拘るよりも、
「勝とうという努力をしたのか、しなかったのか」
というところに厳しくこだわるべき。
・Jリーグ百年構想の基本スローガン
「スポーツで、もっと、幸せな国へ」
・会津若松「ならぬことはならぬ(什の掟)」のように
裏付けのある掟で判断基準をもつことも重要である。
※われわれは子どもたちの未来に触れている
(アンディ・ロクスブルク)
※弱いものほど相手を許すことができない。
相手を許せる者ほど強いものだ。
(ガンジー)
※自分を信じて限界をクリアしたことで、
力を伸ばした選手たちが「皆のために」という精神をもつ。
これが1つにまとまった時、
チームを支えるたくさんの魂が選手のプレーに現れるから、
観客が感動するのだ。
(ジーコ)
※強い者ほど自分の運命を嘆かない。
(著者)
※失敗とは転ぶことではなく、起きあがらないことである
(メアリー・ピックフォード)
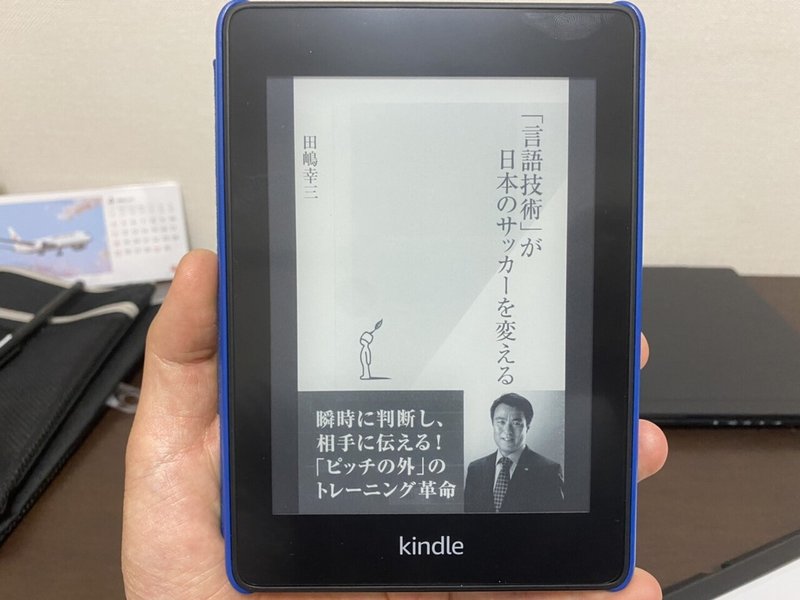
スポーツコミュニケーションアドバイザー&コーチ
田原直弥
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
