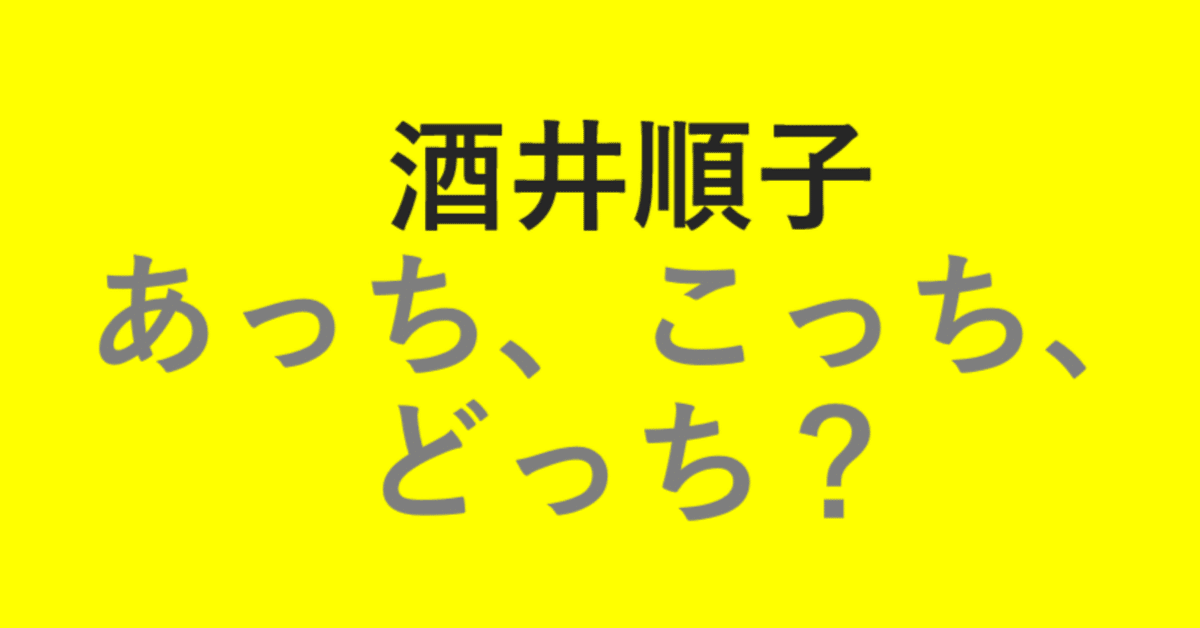
「自分は中身が薄い人間だ」と感じても、落ち込まなくていい
『築地本願寺新報』で連載中のエッセイストの酒井順子さんの「あっち、こっち、どっち?」。毎号、酒井さんが二つの異なる言葉を取り上げて紹介していきます。今回のテーマは「薄い」と「厚い」です(本記事は2024年3月に築地本願寺新報に掲載されたものを再掲載しています)。
かつて、会社員の友人と悩みを話し合ったことがあります。
「何だか自分が、ペラッペラな人間である気がして仕方がない。知識でも何でも、すべてが浅くて……」
「わかる! 私もそう!」
などと。
それはおそらく、中年期に人が抱きがちな悩みなのでしょう。ずっと仕事を続けてきたものの、ふと立ち止まってみると、日々の業務をこなすのに手一杯。自分自身に厚みをつけることを忘れていたのではないか、という不安に、我々は襲われたのです。
悩みを共に語り合った友人はその後、一念発起して難関大学の大学院に進み、博士号を取得。大学教授へと転身しました。彼女を「すごい!」と仰ぎ見ながら、では自分は……と我が身を省みると、いまだペラッペラなまま。人間性に厚みを持たせるにはどうしたらいいのか、悩む日々は続いています。
が、薄さもまた味わいなのかもしれない、という気がしたのは、ある日の夕餉においてでした。しゃぶしゃぶ用の牛肉が冷凍してあったのでその肉を使ってしまおうと思ったのですが、その時に食べたくなったのは、しゃぶしゃぶではなく、すき焼き。「しゃぶしゃぶ用のお肉だけど、まぁいいか」と極薄肉ですき焼きをしたところ、これが意外においしいではありませんか。薄い分、すき焼き肉よりもあっさりと食べることができて、中高年にはいい感じ。
肉をごく薄く切るというのは、外国ではあまりみられない手法です。が、薄切り肉というのは非常に汎用性が高く、我々は薄切り肉が大好き。
肉だけではありません。日本には、〝薄切り文化〟とでも言うべきものが存在する気がします。鰹節にせよおぼろ昆布にせよ、向こう側が透けそうなほど薄く削る超絶技巧は、器用な日本人ならではのものでしょう。ネギなどの野菜にしても、我々は極薄に切ってその風味と歯ざわりを楽しんでいます。
若い頃は、そんな薄切り文化があまり好きではありませんでした。何だかケチケチしているみたい、ペラッペラの肉ではなくて、厚い肉が食べたい! と思っていたのです。
しかし年をとってくると、わかります。極薄の鰹節やおぼろ昆布をひとひら舌に乗せた時の、じんわりとだしが染み出してくる感じは、ほのぼのとした幸福感をもたらしてくれます。また薄切り肉を口に含めば、すぐに溶けて広がる脂の風味は、薄切りなのに分厚い。
そして牛丼チェーン店の牛肉もどこもペラッペラだけれど、あれが厚い肉であったら、かえって人気はなくなるのではないか。‥‥というわけで、薄切りにしか出すことのできない味が、そこにはあるのです。
しゃぶしゃぶ肉によるすき焼きを堪能しながら、私は薄さには薄さの妙味があることを、実感していました。厚いステーキばかりが旨い肉ではない。薄い肉と春菊の食感と風味のコラボは我が国ならではのもの、などと。
では人間性は、と考えてみると、「薄っぺらい人」というのは、明らかに褒め言葉ではありません。人間性に急に厚みをもたらすことはできないけれど、せめて鰹節やおぼろ昆布のように、極薄のひとひらから、じんわりと味わいを滲み出させることができる人になりたいものよのぅ、とすき焼き鍋の前で私は思っていたのでした。
酒井順子(さかい・じゅんこ)
エッセイスト。1966年東京生まれ。大学卒業後、広告会社勤務を経てエッセイ執筆に専念。2003年に刊行した『負け犬の遠吠え』がベストセラーとなり、講談社エッセイ賞、婦人公論文芸賞を受賞。近著に『鉄道無常』(角川文庫)など。
