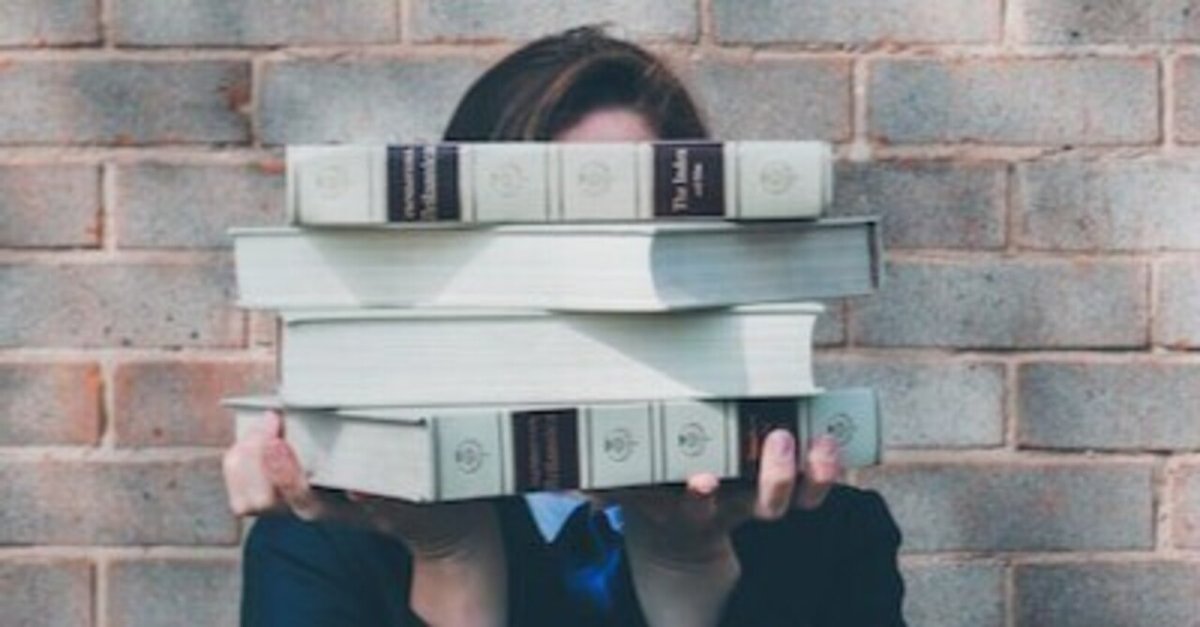
読書に数学が必要な理由
理系と文系という区分にはあまり意味がない
理系・文系の由来
「私は文系なので、数学は苦手なんです」
「僕は理系なので、読解力が弱いんです」
このような会話は、日本ならではのようです。
カナダでは、「あなたは文系?理系?」という会話は皆無だそうです。
これは、カナダに限ったことではなく、ヨーロッパをはじめ、アジア、アフリカ、オセアニアなど、世界各国の学生は、誰もそんなことは気にしていないそうです。
つまり、グローバルな視点からすると、「理系・文系」という区分にはあまり意味がないと言えそうです。
こうした違いが、世界との間に生まれたのは、歴史にあるようです。
現代の科学は、17世紀の科学革命をきっかけにしてヨーロッパで生まれた近代科学を礎にして育まれてきたものですが、日本はこれを明治時代にいきなり『完成形』で輸入しているという違いがあるのです。
ヨーロッパの文化が、古代ギリシャに源流を持つことは知られています。
一方、日本に特徴的な文系・理系にこだわった区分方法は、じつは明治政府が帝国大学をつくった際に、実験や実習で教育に金のかかる理系、医学、工学などを理系、金のかからない文学や法学などを文系と分け、大学生の予備軍である旧制高校の学生までも、入学時から理系と文系にコース分けしてしまったことが発端だと言われています。
日本では、文系・理系・芸術系・体育系・音楽系など、完全に分業制が確立されてしまったのです。
しかし欧米では、文学も数学も音楽もスポーツも一体で、「すべてに豊かな教養があってこその教養人」という『一般教養(リベラルアーツ)』重視意識が基本にあるのです。
理系は「まとめる」が好き
理系的な発想の一つに、「要点にまとめる」というものがあります。
かのガリレオは、地球誕生以来、数限りなく地上に落下し続けてきたあらゆる物体の動きを「落下の法則」にまとめてしまいました。
ニュートンは、「慣性の法則」「運動の法則」「作用反作用の法則」だけで、世界の物体のあらゆる動きをまとめられると説いています。
「抽象化」対「具体化」
「要点にまとめる」を別の言葉に置き換えれば、「抽象化」です。
まとめることが苦手な文系的な人も、がっかりすることはありません。
理系の抽象化に対して、文系の人は「具体化」が上手いはずです。
「理系」対「文系」の不毛な戦いの原因の大変は、ここに隠れていると考えています。
これは、「木を見て森を見ず」とも言えそうです。
目の前にあるのはサクラの木で、向こうに見えるのはウメの木だったとしても、理系の人は森全体を把握して「ここはヒノキの森だ」と、ヒノキを中心とした森作りを考えられます。
しかし、文系の人は、一本一本の木を見て、「そうとは言い切れない」となるのです。
抽象化と具体化の両者で差が大きいのは、抽象化の方が汎用性が高く、応用が効くのに対し、具体化はそれが難しく、局所的にしか使えないような特殊性が往々にしてある、ということです。
「木を見て森を見ず」も「神は細部に宿る」も、逆説的な視点ですが両方の視点が必要です。
つまり、抽象も具体も両方が大切なのです。
こうした理由を基に、理数センスの一端が見えて来たでしょうか。
カチコチな文系という逆説
相対性理論というものをご存知でしょうか。
名前だけなら知っているという方がほとんどであろうと思います。
相対性理論というものの内容はここでは割愛しますが、非常に奥行きのある理論であることは有名です。
相対性理論というのは、理系的な考え方を基に説かれたものですが、理系であっても数学や物理にはやや弱い化学や生物学を専攻している友人たちよりも、文系であっても哲学を学んでいる友人の方がよほど深いところまで相対性理論を理解できるということがありました。
つまり、相対性理論の理解には、厳密な論理的思考に長けていて、抽象的な議論に強い哲学科の友人の方が向いていたのです。
いわゆる理系の世界は、厳密な論理や数学という、いわばブレの無いルールで構成されているので、皆さんがイメージされているとおり、とっつきにくく、また堅苦しいところがあるのは確かです。
でも、そこから生み出される結果は、むしろ非常に多様で、また自由です。
量子力学や素粒子のように、従来の思考を打ち破る壮大で驚くべき理論が生まれたり、未知の世界から想像を絶する発見をもたらしたり、「こんな便利なものが!」といったあっと驚く新技術が産み出されたりもします。
逆に、いわゆる文系の世界の方は、入り口は多少アバウトなところもあり、なじみやすく、理解も進みやすいところがあるのですが、じつはそこからアウトプットされるものは意外に硬直化されていることが少なくありません。
議論が決まっている、とまでは言わないにしても、或る大枠から出られないようなことが多いように思われます。
「出ない」と心に決めているラインがあるようなイメージです。
一般社会における理系と文系には、
手続きが厳密な代わりにどんな結論を出すかは自由な理系
手続きにはあまりこだわらないけれど、結果や結論の出し方はかなり不自由な文系
そんな違いがあるようです。
自称文系の私も、自身の思考を多少なりとも厳密化していけば、その分だけ思考の過程やその結論にも自信が持てるようになり、これまでの硬直化した枠組みを捨て、堂々と自由な発想を表現することもできるようになるのかもしれません。
理系の人がときどき、「空気が読めていないなあ」と思わせるほどに力のある発言をするのは、この厳密な思考に沿っているがゆえの自分の結論に対する自信の表れなのです。
理系・文系という妙な意識の壁を捨ててしまえば、読書をして得られる『成果』も、より多様になり得ると言えそうですよね。
読書には、文系的要素だけではなく、理系的要素も必要だという理由が、少しはわかっていただけましたか?
もっと、詳しく知りたい方は、上記にあります書籍『文系のための理数センス養成講座』をお読みくださると、もっと理解が深まります。
因みに私は、この著者、竹内薫さんが、俳優の吉田鋼太郎さんに見えて仕方ありません(笑)
とっても嬉しいです!! いただいたサポートはクリエイターとしての活動に使わせていただきます! ありがとうございます!
