
介護労働Ⅱ 『マルクス解体 プロメテウスの夢とその先』(斎藤幸平2023.10.24)で読み解く介護

斉藤幸平さんの『マルクス解体 プロメテウスの夢とその先』(2023.10.24 講談社)はとても刺激的でした。この本を介護分野に引付けて読んでみるのも良いかも知れません。
(1)業務計画至上主義と実質的包摂
介護施設には多くの業務がり、この業務を効率的に遂行するための業務遂行計画が定められています。例えば、食事介助、入浴介助、排泄介助、着替え介助、移動・移乗介助など当事者に直接相対峙して行う介護業務。そして、配膳・下膳、義歯洗浄、歯ブラシや歯磨き用カップやストローの洗い・煮沸消毒、お茶の準備、配給、居室・トイレ・共同生活室・廊下などの掃除・施設内の整理整頓、エプロンや入居者の衣類の洗濯・乾燥・収納、ゴミ集めゴミ捨て、ベッドメイキング等々、さまざまで膨大で雑多な業務があります。
資本・経営側はこの膨大な量の業務をなるべく少人数の労働者で行わせることが利益確保のための絶対条件ですので、多少、かなり?無理があっても、生産効率の高い業務計画を作成するわけです。つまり、より少ない人数で、より多くの業務遂行を介護労働者に要求するのです。
ですから、普通の介護施設の介護労働者たちは、一日の勤務が終わると心身ともに疲弊しきってしまうのです。しかも、世間並以下の給料なのです。
この業務計画が介護現場の法律、規範となっていますので、労働者は入居者には目もくれず、この業務計画を遂行することが何よりも大切だと思うようになって行くのです。
このように介護現場において、規範化され、労働者に内面化されて、その業務計画を絶対視することを、私は「業務計画至上主義」と呼んでいます。
日本の介護施設に蔓延「業務計画至上主義」は資本主義社会における労働の「実質的包摂」そのものだと思うのです。
本来の労働は、知識と技術を持った労働者が「構想」(知的労働)と「実行」(肉体労働)を統合して行うものですが、資本主義社会ではこの「構想」は資本が行い、「実行」のみを労働者にさるようになってきたのです。「実質的包摂」とは資本増殖(儲けるため)のために資本自身のイニシアチブで労働者の具体的な業務に介入し、業務を再編成し、より生産的・効率的な方法を生み出し、労働者に従わせることです。
斎藤幸平さんは、このような実質的包摂により労働者に生じる問題点を次のように指摘しています。
「労働過程が資本のイニシアチブによって、組織、編成されていけば、労働者は労働過程全体に対する経験、知識、技能、洞察をますます失っていく。」
要するに、「業務計画至上主義」・「実質的包摂」によって労働者は労働を行うための主体的条件、すなわち労働の内容を「構想」する力さえも失うことになるのです。
(2)「魂の包摂」とマトリックス
斎藤幸平さんの次の文章は今の介護現場そのものではないでしょうか。
「資本が労働過程を分析し、単純で、反復的で、計算可能で、機械的なタスクからなる流れへと分割・再結合することで、熟練労働者は非熟練労働者に取って代われれる。その際、資本は、労働者がそれまで有していた経験や知識とは無関係に労働過程を独自の効率性やマネージメントの視点から再編するので、労働者は資本が押しつけてくる上からの命令に受動的に従わなければならなくなる。」
確かに、業務計画・業務日課に従い、またはマニュアルに従い、何も考えず、何も感じず、ただただ、淡々と、業務をしている介護労働者もいるでしょう。そもそも、忙し過ぎて、考える時間、感じる暇さえないように働かされているのですから。
「実質的包摂」により労働者は資本・経営側の定めた業務計画に嫌でも従わなければなりません。ある意味、資本に飼いならされていくことになるのです。斎藤幸平さんはこの辺の事情を次のように的確に指摘しています。
「資本の物象化された力が労働過程全体を貫くにつれて、社会的生産の増大は資本のイニシアチブによってのみ達成されるようになる。労働者の自律性と独立性は決定的に損なわれ、労働者はより容易に飼いならされ、規律づけられていく。」
介護労働者は資本に飼いならされ「実質的包摂」を具現する「業務計画至上主義」によって、身も心も包摂されてしまうのです。労働における「構想」だけでなく、労働者の感性、心までも資本に包摂されることを、政治学者の白井聡さんは「魂の包摂」と呼んでいます。
また、ミシェル・フーコーの生権力を思い出しますね。昔の権力は「従わなければ殺すぞ」でしたが近代の権力は、人々の生にむしろ積極的に介入し、生き方を調教管理するもの「規律権力」ともいえるものですからね。
いずれにしても、介護現場には、資本に魂までもが包摂され、調教された介護労働者(包摂組)と、調教されていない介護労働者(非包摂組)とが混在することになるのですが、圧倒的多数の包摂組が自ら考え、感じ、入居者に真摯に向き合おうとする非包摂組の労働者を非難、排斥するようになります。
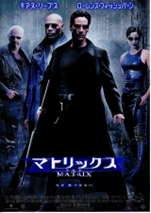
魂が包摂されていない介護労働者は映画の「マトリックス」(The Matrix 1999年)の主人公ネオのような存在なのかもしれません。映画マトリックスの設定は自我を持った人工知能が誕生し、人類は仮想現実システム「マトリックス」に幽閉され、動力源として利用されてるけれど、そのシステムから抜け出した人間たちは、脅威とみなされ、システムの内外で人工知能に追われるというストーリーです。
この映画で描かれているマトリックスは現実の資本制そのものでしょうね。
資本は介護労働者の魂までも包摂し搾取しますが、それに気づきそのシステムから抜け出し、自ら考え、感じ、真摯に入居者の現実に向き合い介護しようとする少数者たちを、必死に妨害、排除しようとするのです。
マトリックスの主人公・ネオがマトリックスを打ち破ることができたのはマトリックスのプログラムコードを解読、見れるようになったからですが、介護現場のネオたちも資本のコードを解読、読み取れるようになることが必要なのかもしれません。
(3)生産性向上は必ずサービスの低下を招く
介護保険法の一部改正(「全世代対応型の持続可能な社会保障性を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和5年法律第31号)」)が2023年5月12日の通常国会で成立し、5月19日に公布されています。
この改正の中で注目すべきことがあります。それは、都道府県に対して介護事業の生産性向上、業務の効率化の促進が努力義務とされたことです。
つまり、介護事業の生産性向上及び業務の効率化が介護保険法に明記され、生産性向上に錦の御旗が与えられたということなのです。もちろん、サービスの質の向上という文言もはりますが、これは単なる飾り、言い訳、アリバイ作りにすぎないと思います。
〔参考〕
改正介護保険法(新設)(国及び地方公共団体の責務)第5条
3 都道府県は、前項の助言及び援助をするに当たっては、介護サービスを提供する事業所又は施設における業務の効率化、介護サービスの質の向上その他の生産性の向上に資する取組が促進されるよう努めなければならない。⇒ https://www.zenhokan.or.jp/wp-content/uploads/tuuti1473.pdf
しかしながら、原理的に考えて、介護事業・介護産業における生産性の向上は可能なのでしょうか。斎藤幸平さんは、エッセンシャル・ワークは労働集約型産業であり、自動化に向かないと次のように指摘しています。
『そもそも、エッセンシャルな部門は生産性を向上させるのに必ずしも適していない。多くのエッセンシャル・ワークは自動化に向いておらず、労働集約的である。その結果、機械化によって資本集約的になっていく他の産業部門と比較して、「非生産的」なものとして扱われることが増えていく。』
そして、同氏はケア部門で無理に生産性を向上しようとすると使用価値を劣化させ、事故や虐待の原因になると危惧しています。
『新しい機械で生産量が2倍、3倍になっていく産業部門とは異なり、看護や教育などのケア労働の生産性は同じように上昇することはない。それどころか、これらのケア部門においては、使用価値を劣化させ、事故や虐待のリスクを増大させることなしには、生産性を高めることができないことが多々ある。』
さらに、同氏は「ケア労働の性質上、生産力の向上には大きな限界があり、これが、「ボーモル病」と呼ばれる問題を生み出してきた。」と指摘しています。
この「ボーモル病(Baumol's cost disease)」を調べてみたら面白かったです。
ボーモルとボーエンという経済学者は、ベートーベンの弦楽四重奏を演奏するのに必要な音楽家の数は1800年と現在とで変わっていない。また、看護師が包帯を交換する時間や、大学教授が学生の文章を添削する時間は1966年と2006年の間で短縮されていない。
要するに、ケア部門などの労働集約的な業態では、まったく生産性は向上していないけれど、自動車製造部門や小売部門のような商業部門では、機械や器具の技術革新によって絶えず生産性は上昇している、ということを指摘しているのです。
実演芸術や看護、教育のような労働集約的な部門では人的活動に大きく依存しているため、生産性はほとんど、あるいはまったく上昇しないというのです。当然と言えば当然ですが。
参照(ボーモル病) ⇒ https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9C%E3%83%BC%E3%83%A2%E3%83%AB%E3%81%AE%E3%82%B3%E3%82%B9%E3%83%88%E7%97%85 2023.11.06)
介護保険法に生産性向上を盛り込んだ政府の意図は、介護人材が足りないから、生産性を向上させ、少ない人数でも介護事業を行えるようにしたいということです。これは当然、資本の喜ぶことでもありますからね。ある意味、政府が音頭を取って介護事業者の生産性を向上させ、企業の資本蓄積、株価アップを支援していくということです。
生産性向上を声高に叫ぶ政府、大企業には、介護サービスの利用者、入居者の視点、介護労働者のことは眼中にないのでしょうね。生産性向上政策は、徹頭徹尾、資本の論理を貫徹するため、儲けるためなのでしょう。
介護労働現場にICT、AIを導入すれば生産性が上がり介護労働者を削減できると考えるのは、クラシックのライブ演奏会などで、AIを導入するから、ベートーベンの弦楽四重奏を2人で演奏しなさいというような、お粗末でおバカな考えです。しかし、今の政権、大企業は真面目にこのようなおバカなことを考えているようですね。
「馬鹿な大将、敵より恐い」と言いますが、介護の世界でも同じなんですね。
(4)気象危機時代の介護産業 ~脱成長コミュニズムに向けて~
斎藤幸平さんは『資本主義的生産に比べて、脱成長コミュニズムの方が、「物質代謝の亀裂」を修復する可能性を高めると考えられる理由は少なくとも5つある。』と記しています。
その第一番目の理由は、脱成長コミュニズムでは社会的生産の中心がエッセンシャル・ワークにシフトするからだとしております。
『社会的生産は無限の経済成長の恒常的圧力から解放され、その焦点をより使用価値の高い生産に移すことが可能』になります。
そして、『資本主義において、多くのエッセンシャルな部門が不十分な状態で放置されてきた以上、そうした分野はむしろ「成長」するだろう。より良い教育、ケア労働、芸術、スポーツ、公共交通、再エネを提供するために、資金と資源をより多く再配分することになるからである。』
もはや、気候危機を乗り越えるためには脱成長コミュニズムしかないように思いますが、この脱成長コミュニズムという観点から介護を捉えてみると良いように思います。もちろん、ケア労働はエッセンシャル・ワークを代表する労働です。
生産性が低くて何が悪い
候危機のこの時代、介護労働者は堂々と主張すべきです。「生産性が低くて何が悪い!」
斎藤幸平さん曰く・・・
「それゆえ、社会が基本的な使用価値の生産を重視したエッセンシャル・ワークにシフトすればするほど、経済成長は鈍化することになる。一方で、ケア労働に代表されるエッセンシャル・ワークは環境負荷が低い。したがって、使用価値経済は、脱成長と親和的であるとともに環境負荷も下がるはずだ。」
地球という惑星の危機の時代、介護産業は、低い生産性であっても環境負荷が低いのです。堂々と「生産性が低くて何が悪い」と胸を張るべきだと思います。介護労働者はすでに十分、働かされているのです。政府の役割はしっかり介護労働者の待遇(賃金と労働時間)をより高いレベルで保障することだと思います。
脱成長コミュニズに向けて介護労働者はもっともっと主張していくべきだと思います。私は次の4点は最低でもアピールすべきだと思っています。
① もっと時間を!労働時間を短縮せよ
脱成長コミュニズムを目指して、介護現場も労働時間の短縮を目指す必要があります。給与の改善も確かに大きな課題ですが、介護現場の人員配置の改善、労働時間の短縮も給与に改善以上に必要です。
介護労働者が、身体的、精神的に、ゆとりが持てるようになることはとても大切です。マルクスによると、人間の力の発展、真の自己実現のためには「労働時間の短縮が基本的な前提条件」だと言っているそうです。時間的な余裕がなければ、地域の活動、政治活動、文化活動、ボランティア活動等々ができないわけで、人生を楽しむことができません。
例えば、介護施設で、週休3日を実現し、夜勤帯の配置は10:1、日勤帯は3.3:1、年間10日間程度の有給完全消化を条件にすると、職員配置は1.1:1になります。最悪、夜勤帯を20:1にすると、1.4:1になります。この程度の人員配置を目指すべきだと私は思います。
② 「構想」を取り返そう
「業務計画至上主義」から脱して資本・経営側から「構想」を取り戻さなければなりません。
介護職が専門職だと言うのであれば、当然、それは単純労働で誰でもできる労働ではなく、熟練労働だということです。熟練労働者であれば「構想」(考えること)と「実行」(実施)が統一されていなければなりません。
この「構想」と「実行」を分離し、資本・経営側が労働者から「構想」を取り上げる仕組みが「業務計画至上主義」なのです。この資本・経営側が定めている業務計画を労働者自らが入居者の立場に立って、変更、改善していくことが大切だと思います。
③ 過度な分業は止めよう
そもそも、介護とは被介護者と介護者との相互行為であり、衣食住のみならず社会参加、人間関係の維持発展、文化的生活等々を含む総合的なものであるべきです。この総合的なものを分解し過度な分業体制で介護するということは介護の総合性、全体性を脅かすことになってしまいます。
例えば、入浴介助の大まかな流れは次のようなものでしょう。居室での離床→脱衣室への移動→衣類の脱衣→浴室への移動→洗身・洗髪→入浴(お湯に浸かる)→浴槽から脱衣室への移動→身体を拭く→着衣→頭髪の乾燥→居室・共同生活室への移動→爪切り・水分補給
極端な話ですが、このフローの各項目を全て違う労働者が行うとしたら入居者はどう思うでしょうか?自分がまるで工場のベルトコンベアーの乗せられた加工物にされていると感じるでしょう。これでは介護が相互行為だとは言えなくなってしまいます。過度な分業体制は介護そのものを破壊してしまうのです。
介護現場での分業体制については介護の相互行為を壊さないように、介護を単純労働にしないために、慎重に検討すべきだと思います。そして、この介護施設における分業体制等について、当然、介護労働者もその策定、更新について参画すべきでしょう。
④ 守れ!中小介護事業者~介護事業はコモン~
近年、介護事業所の大規模化が推奨されるようになってきています。2022年5月25日には財政制度等審議会は介護分野の大規模化を推進するよう提言してます。
「・・・介護サービスの経営主体は小規模な法人が多いことを踏まえ、今年度から施行される社会福祉連携推進法人制度の積極的な活用を推進していくことはもとより、経営の大規模化・協働化を図ることが不可欠である。」
大規模化するということは、要するに、大企業が市場競争で中小企業を淘汰しながら巨大化していくということになるのでしょう。淘汰の末、介護事業者で残るのは全国展開する幾つかの大企業だけになってしまう怖れもあるかも知れません。
しかし、介護事業は基本的には商圏の狭い地域に立脚した事業です。この介護事業が短期的な利潤を追求する大企業、お年寄りを食い物にする大企業に牛耳られてしまっては、地域のコモン(共有財産)である介護事業・介護ネットワークが衰退してしまう怖れがあります。
介護は地域社会にとってのコモン(共有財産)です。このコモンを守り育てていかなければなりません。
小規模であっても、利潤優先ではなく、心をこめて介護できる事業者こそ生き残れるよう、国及び地方自治体が支えなければならないと思うのですが・・・新自由主義思想に汚染された権力では無理でしょうね。
介護関係者と介護サービス利用者とその家族たちが、もっともっと声を上げ、訴えて行かなければならないと思います。
(参考:斎藤幸平2023「マルクス解体 プロメテウスの夢とその先」講談社 p358-365)
気候危機のこの時代、斎藤幸平さんのいうマルクスの環境思想は、人類の生き残りのための思想だと思います。そして、この思想の中で介護労働は大切な位置を占めるのではないでしょうか。
以下のnoteも併せてご笑覧願います。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
