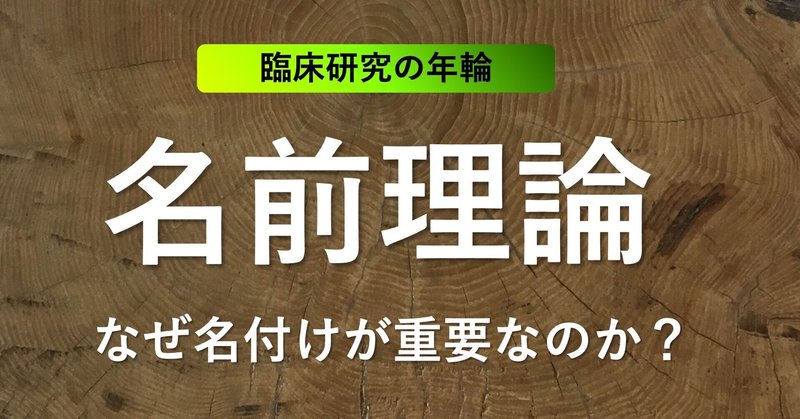
名前理論-なぜ名付けることが重要なのか?
子路が言った。
「衛の君が、先生をお迎えして政治を為すなら、先生はまず何を第一にしますか」
先生(孔子)がおっしゃった。
「必ずや名を正さんか(まず必ず物の名前を正すことから始めるだろう)」
臨床研究とは、個人の前進を、人類全体で共有する営みです。
そのなかで、大切な、大切なことがあります。
それは、「名前」「名付け」です。
これがあるから、「Aという現象」を、他者と「Aという現象」として共有することができるのです。
このnoteでは、改めて名前・名付けの機能を明らかにして、その意義を噛み締めてみたいと思います。
▶︎標本化・結晶化機能:標本化すること、結晶化して、永遠に無くさないものにする
真に独創的な人物とは何か
奇抜なことをして衆目を集めるのが独創的な人物ではない。
それは単なる目立ちたがり屋だ。
たとえば、独創的な人間の特徴の一つは、すでにみんなの目の前にあるのにまだ気づかれておらず名前さえ持たないものを見る視力を持ち、さらにそれに名称を新しく与えることができる、ということだ。
ニーチェ 『悦ばしき知識』
たとえば、以下のような現象があります。
【現象A】とある食べ物を食べた後に、腹痛、吐き気、嘔吐などの不快な経験をし、その食べ物を嫌いになった。
誰だって、こういう経験をしたことが、1回くらいありますよね。
大事なのは、道が分かれるのは、そのあとです。
その経験をしたあと、みなさん、どうしました?
「どうしましたと言われましても、普通に復活して、普通に生きて参りました」
違った道を開拓した、偉人がいました。
その偉人は、以下のような実験を行いました。
・ネズミを被験者とした実験
・甘味液を与えた後、胃の不調を生じさせる放射線を照射させると、甘味液の摂取を避けるようになった
・つまり、ある特定の味と放射線照射を対提示しただけで、その味に対する強い嫌悪が形成された
Garcia, et al. Science (1955) 122, 157–158.
この実験によって、はじめに紹介した【現象A】が一般的真理であることが明らかとなり、発見者の偉人の名前をとってガルシア効果と名付けられました。
このように、名前・名付けには、個々人が経験したことや発見したこと、あるいは「あるよね〜」と言われながらも存在が不明瞭な現象に、クッキリとした輪郭・形状を与え、標本化・結晶化する機能があります。
そして、名付けの過程には、その経験や現象が一般的真理であることを証明する「研究・実験」が欠かせない場合が多いです。
▶︎環世界拡大機能:名前が世界の新しい一部をつくる
名称が与えられて初めて、それが実際に存在していることに人間は気づくものなのだ。
そうして、世界の新しい一部分が誕生してくる。
ニーチェ 『悦ばしき知識』
2021年、日本から以下のような報告がされました。
名前がなかったベラの仲間にキツネオハグロベラと命名
飯野, 他. Ichthy, Natural History of Fishes of Japan, 9: 21-26

シンプルに、超珍しい対象・現象・経験に名付けること。
いま、僕は観察・発見したけど、これまでも、これからも、こうやって見つけられることがないかもしれない。
それに名前がつくことで、誰かがふたたびその事象に出会ったときに、「あ、キツネオハグロベラ!」と思えるのです。
「なにこれ、変な魚」とか「・・・(気づかない)」とかいうことではなく。
これが、ニーチェが述べた『名付けられることで、世界の新しい一部分が誕生してくる』ということなのかな、と思っています。
名前が明らかになっていることが、人類の環世界を拡大させるのです。
▶︎召喚機能:名前がその中身を連れてくる
千: これ、お別れにもらったカード。ちひろ?……千尋って……私の名だわ!
ハク: 湯婆婆は相手の名を奪って支配するんだ。いつもは千でいて、本当の名前はしっかり隠しておくんだよ。
千: 私、もう取られかけてた。千になりかけてたもん。
ハク: 名を奪われると、帰り道が分からなくなるんだよ。私はどうしても思い出せないんだ。
(中略)
でも、今思い出したの。その川の名は……その川はね、琥珀川。あなたの本当の名は、琥珀川……
"瞬間、白竜から輝く鱗が剥がれ落ち、ハクの姿になっていく。"
千: ああっ!
ハク: 千尋、ありがとう。私の本当の名は、ニギハヤミ コハクヌシだ。
「千と千尋の神隠し」より
不思議なものです。
名付けのプロセスは、「その人が、そのものが、その経験が、その現象が(中身)」あって、とある「名前」がつけられます。
その順番は、逆ではありません。 #そうですよね
ですが、いったん名前がつけられると、堀の中を水がどちらにも移動できるように、「中身」と「名前」が双方向の関係性になってしまうのです。
そして、そこにこそ!、名付けの重要性があります。
一旦明確に「中身」を囲ってしまえば、ファイナルファンタジーの召喚獣のように、その「名前」が、その存在・中身を一瞬で、呼び起こしてくれるのです。
それによって、ある人が血の滲むような努力の末、数年かけて名づけた中身を、誰でも一瞬で召喚できるようになるし、今までぼやっと通り過ぎていたものが、一個の存在として浮き彫りになって、そこから新しいストーリーが生まれたりするのです。
実際に、Nature Neuroscience誌において、脳内の視覚イメージと、視覚イメージに対応する言語表象が、脳の近接した領域で連合していることが明らかにされ、経験と意味がセットになってすぐに反応し合えるようにまとめられている可能性が示唆されています。
✅ Related research
Popham, et al. Nature Neuroscience 24.11 (2021): 1628-1636. >>> doi
▶︎ハイパーリンク機能:情報量の極限まで圧縮する
Less is more (少ないほど、豊かである)
ルートヴィヒ・ミース・ファン・デル・ローエ
おそらく、名前の一番大切な機能です。
名前は召喚機能を持ちますが、その際に注目すべきは、「情報量」です。
以下の関係性が成り立ちます。
中身:名前 = 巨大:極小
たとえば、標本化・結晶化機能で紹介した「ガルシア効果」。
「ガルシア効果」という名前(6文字程度)に対し、400文字の説明を費やしていますし、膨大な実験論文もあります。この場合、少なくとも66.7倍以上の圧縮力を示しているわけです。
名前には、このような極限の圧縮力があります。そう、極限です!
だって、そうでしょう!?日本という2文字で、世界という二文字で、宇宙という2文字で、なにを囲っていますか?
名前は、あらゆる大きさ、あらゆる複雑さをもつ中身を圧縮してリンクする機能があります。
この機能のことを、馴染みのある言葉を引用して『ハイパーリンク機能』と呼びたいと思います。
2021年には、脳活動を測定した研究において人間の作業記憶が実際に『圧縮』されることが示されました(Roumi, 2021)。
さて、
「So What ?、だからなに?。量が多かろうと、少なかろうと、関係ないじゃん。頑張れよ♪」と思われるかもしれません。
ですが、量が少ないということが、『創造にとって最良の土壌』なのです。
「マジカルナンバー7±2」という概念があります。
これは、人間が瞬間的に保持できる情報の限界値を示すものです(Miller, 1994)。
日本という名前で、日本の中身を囲っていなければどうなるでしょう?当然、7±2をオーバーします。アメリカだって、同等か、それ以上でしょう。
すなわち、ハイパーリンク機能がなければ、日本とアメリカを同時に頭のまな板の上に置くことができないのです。
同時に頭のまな板の上に日本とアメリカを置けることで、初めて「アメリカは日本と比べて・・・」「日本はアメリカより・・・」とか、「日本とアメリカの共通点は・・・」とかの思考が可能になります。
そして、この既知情報の比較や、組み合わせや、結合といったものが、「創造」の1形態です。つまり、「名前なくして創造なし」といえるほどには、創造にとって名前は重要です。
▶︎解決の呼び水機能・解決プライミング機能
〇〇問題と聞くと、人はつい解きたくなってしまう
電通Bチーム
2021年、電通Bチームがネーミングの効用として、「名もなき課題を課題化する」ことを論じました(電通Bチーム, 2021)。
これは、確かにそうなのです。
たとえば、「大腿骨頸部・転子部骨折に対する手術後のリハのときに、膝痛が出現することって、よくあるよね」と無意識下でずっと感じていました。ですが、「まぁまぁ、そんなものなのですかね」で、ぼやっと済ませていた問題です。
それに対し、2020-2021にかけて、「PHFKP:post hip fracture knee pain(股関節骨折後の膝疼痛)」というネーミングが報告されました(Kaizu, 2020, Kaizu, 2021)。
それによって、どうなったかといいますと、
「それ、あるよね!!!う〜ん、どうやって解決したら・・・」
と、いわれたわけでもないのに、「解決方法」を考えていたのです。
たずねよ、さらば与えられん
アンソニーロビンズ
ネーミングによって課題が明確化されること自体が、『たずねる』ことを含んでいるようです。
▶︎カメレオン機能:1つの名前 - いろんな想起
僕はきょうまで、だれもがいくつもの顔を持ち合わせていることに気がつかなかった。
何億という人間が生きているが、顔はそれよりもたくさんにある。
だれもがいくつもの顔を持っているからである。
リルケ
1つのものには、たくさんの価値の側面を持っています。
たとえば、「りんご」という1個のものに対しても、色、匂い、固さ、美味しさ、かっこよさ(apple)・・・etc。
そして、それらの価値の1つ1つを、逐一説明されたとしたら、どうでしょう?
「もういいよ」、と飽きてしまい、興味を持って聞いてもらえないと思います。
ところが、表現したい複数の価値を示すぴったりの「名前」が見つかれば、その一語で済むのです。
たとえば「運動スナック」という言葉があります。
✅ 運動スナックの定義
1日を通して定期的に行われる、1分以下の激しい運動を単独で行うこと。
詳細は以下noteを参照 ↓↓↓
『運動スナック』は、その一語で以下のような複数の価値を示しています。
・気軽さ(短時間)
・美味しさ(効果性)
・病みつきさ(中毒性)
複数の価値観を、いっぺんに伝えたい。
そんな時は、それらの色をすべて持つ1つの「名前」を逆算的に発掘 or 創造するといいかもしれません。
あたかも、さまざまな色に変化できるカメレオンのような名前を。
▶︎名前・ことばに関する名言
最後に、名前・名付け・ことばに関する、偉人の名言を載せて終わります。
「正しい言葉とほぼ正しい言葉の間には、稲妻と蛍火ほどの違いがある」
マーク・トウェイン
本当に人の心に届く言葉は、短くて、強い言葉よ
赤毛のアン
事実、言語は科学のための努力の第一段階である
ニーチェ
言葉の匂い
どんな一語にもそれ独特の匂いがある
様々な匂いの、したがって様々な言葉の1つの調和と不調和がある
ニーチェ
私たちの思考がとめどもなく発展するように、
それに見合うための「ことばの創造」を真剣に考えねばなるまい
うたかたのあぶくのように、現れては消えるようなことばではなく、
日本人として、地球人として正しく思考し、行為するための正しい言葉を!
【時実利彦】人間であること
言葉は意思であり、自分であり、力なのだ
宮﨑駿
あぁ、他の名前になって!
名前には、何があるというの? 私たちがバラと呼ぶものは、
他のどんな名前で呼んでも、同じように甘く香るわ
シェイクスピア(ロミオとジュリエット)
人間はただ、ことばによってのみ人間である
フンボルト
言葉によって表現された思想はすべて、限りなき働きを持つ力である
トルストイ
はじめにことばがあった。
ことばは神と共にあり、
ことばは神であった。
ヨハネによる福音書1:1
○●━━━━━━━━━━━・・・‥ ‥ ‥ ‥
臨床研究のつくり方を考え・つくり手を育てる
『僕らの臨床研究の年輪』
こちらから♪
↓↓↓

#理学療法 #臨床研究 #研究 #リハビリテーション #エビデンス #僕らの臨床研究の年輪 #研究方法
‥ ‥ ‥ ‥・・・━━━━━━━━━━━●○
