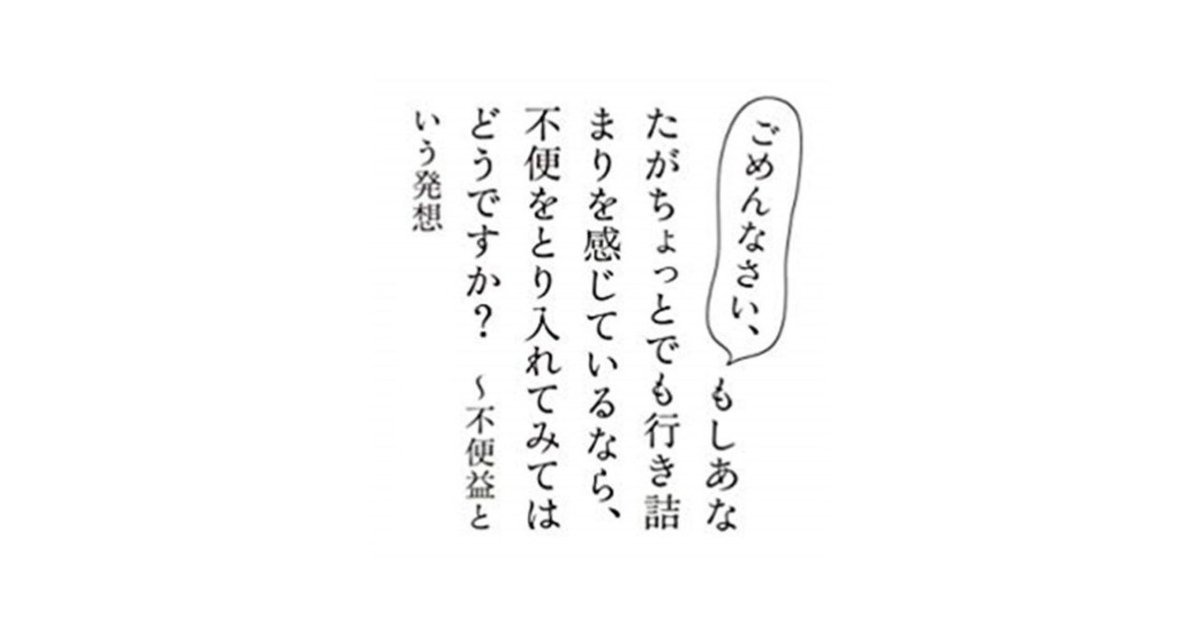
#3 非効率に生きるメリット:(書籍タイトル)※長すぎて略
こんにちは!スガッシュです。
「ビジネスガッシュ!」第3回は、
とってもタイトルの長い本を紹介致します!
「ごめんなさい、もしあなたがちょっとでも行き詰まりを感じているなら、不便を取り入れてみてはどうですか?~不便益という発想」
…長い。
とっても長いですよね。長すぎて、こうやって書評を書く時もタイトルを書くのが面倒くさい。不便です。
この本では、
そんな「不便」が、逆から見ればある種メリットがあるのではないか。
便利だから得られる便益はさることながら、不便から得られる「不便益」にスポットを当てよう。というような内容が語られていきます。
私は、タイトルが長すぎるのが気になって、つい手に取って購入してしまいました。これは著者からすれば、「不便だから」得られた益ですよね。
また、タイトルが本の内容をそのまま表しているので、「不便益」という考え方が濃く私の頭にインプットされているような気が。これも、著者からすれば「不便だから」得られたメリットです。
この本では、そんな「不便だから」良いこともある、
という考え方が紹介されていきます。
*不便益とは発想の転換法。懐古主義ではない!
この本の著者である京都大学の教授・川上浩司さんは、便益を得られる不便な物事・システムをデザインする方法を研究されています。
この方、携帯を持っていないのだそう。私としてはあり得ないのですが…
でも、この方は本中で「『いつでも好きな時に』連絡が取れないので、人とコミュニケーションを取れるありがたさを日々感じる」とのこと。
不便益ですね…
この方が強調しているのは、不便益という考え方は、昔を懐かしむ懐古主義ではない!ということ。確かに、携帯を持ってないと聞くと、「昔は皆携帯なんて持っていなったんだ!」とか言ってきそうですし、柔軟に世の中に合わせられないのかなぁ…と思いますよね。
でもそうではなく、あくまで発想の転換法として取り入れるべきだ、というのがこの本での前提。便利なものは便利だし、積極的に使えばいい。だけど、その便利の裏側で失われるものは何か?逆に不便だから得られるものは何か?気づけるようになれば、日々の生活やビジネスにおいて、何かヒントを与えてくれるのではないか?そう主張しているのです。
*「労力を省くこと」がゴールでいいのか?
本書では、様々な「不便益」の事例を取り上げながら、
不便のメリットとは何か?考えていきます。
例えば、旅行。旅行会社は様々なツアーを組み、集客をします。
確かにツアーであれば、申し込むだけで参加できるし、決められた旅程通りに観光すれば効率よく観光地を巡ることができて、とても便利です。
ですが、一方で弊害もあります。
例えば、その土地の隠れた魅力を知ることができない、ということ。例えば、観光地巡りではその土地の家庭料理は食べれません。道端で現地住民と仲良くなって、一緒にご飯を食べないとわかりませんよね。この家庭料理が他にはない特徴的なもので、美味しいのだとしたら、それを味わえないのは勿体ないですよね。これは便利であることの弊害です。
他にもあります。誰だってそのツアーに参加すれば、同じ体験ができるので、「自分だけの経験」という自分だけ感がない、ということです。
地域住民と仲良くなって、一緒にご飯を食べて、連絡先を交換して、また遊ぶ約束をする。こういう体験は「自分だけの経験」として、とても誇らしくなるし、つい自慢したくなりますよね。
旅行ツアーは確かに便利だけど、一方で弊害もある。であれば、面倒だけど自分で余裕のある旅程を組んで、冒険してみるのもアリだな、と思えるのではないでしょうか?これも不便益の考え方です。
*便利になれば仕事が奪われる、は本当?
AI、ビッグデータ、IoT…テクノロジーによって現代社会はますます便利になりつつあります。その中で、「便利になれば、テクノロジーが仕事を代替するから、多くの人は今の仕事を失う」と言われています。
創造性や社会性が求められる、クリエイティブな仕事しか生き残らない、とよく言われていますよね。
ですが、これは本当でしょうか?
この本では面白い小噺が紹介されています。
-あるパイロット仲間同士の会話-
【副操縦士】
自動航行のほうが安全なら、人間はやることなしですね。
私は降ります。代わりに犬を乗せておきます。
【機長】
犬、必要?
【副操縦士】
あなたが自動航行装置を解除しようとしたら、咬みつく係です。
【機長】
そんなに信用ないなら、私も乗ってる必要ないやん。
【副操縦士】
あなたは犬のエサ係です。
もはや、別の仕事になっているという。笑
でもこれ、案外確信をついてる話だと思うんですよね。
他にも似たような話がコレ。
機械トラブルは0.1%でも起こり得る。だから、操縦士・副操縦士の仕事は操縦することではなく、目の前の計器をチェックすることになる。
すると操縦士・副操縦士に必要になるスキルは、操縦スキルではない。
「密閉された空間の中で、二人きり、
英語で10時間以上場を持たせるスキル」だ。
つまり、仕事がなくなるのではなく、別の仕事になるのではないか?ということ。便利になると、ただの作業がなくなっていく、とよく言われていますが、作業がなくなるのではなく、別の作業になるのではないか?
案外そうかもなぁ…と私は思いました。
便利なのはいいことだけど、
ただ便利を追い求めても、新たな作業が生まれるだけなのでしょうか…?
もしそうだとしたら、
不便益の考え方を取り入れることが、そんな未来を生き抜く1つのヒントになるのかなぁ…と、この本を読んで考えさせられました。
*「非効率に生きる」ということ
私は、個人的に、「非効率に生きる」重要性を主張しています!笑
その心はというと、効率的にやろうとする(=便利を追い求める)と、
確かにゴールまでの道のりを早く駆け上がることはできるけど、
そのせいで、得られたであろう経験値を取りこぼしてしまうのではないか?ということ。
例えば、プロサッカー選手になりたい!とします。
確かに「効率」を考えれば、毎日ボールを蹴れば良いはず。
ですが、効率を意識しすぎてしまうと、学校で授業を受ける時間も、
彼女とデートする時間も、文化祭の準備をする時間も、
ボールを蹴る時間に費やしてしまう。
すると、勉強や恋愛など、青春時代に得られたはずの経験値を、
全部取りこぼしてしまいます。私はこれ、とっても危険だと思っていて。
例えば、プロサッカー選手になれなかった場合。サッカー以外の経験値がないところから、再スタートを切らなければなりません。
逆に、プロサッカー選手になれた場合。確かに夢を叶えるのは素晴らしいことですが、年を取り、引退後、どうすればいいかわからなくなります。
もし恋愛の経験値を貯めていれば、紆余曲折ありながらも大事な人ができて、その人の存在が人生を支えてくれたかもしれません。
あるいは、もし文化祭で演劇の経験値を貯めていれば、物語や文章を書くのが好きだ、と気づけたかもしれない。ライターや作家という道に興味を持てたかもしれない。
経験値の幅を狭めることは、とっても危険なんです。
人生の可能性を狭めてしまう。
だから、今興味があることにチャレンジするのは素晴らしいのですが、
今興味がなくても、「まずやってみよう!」というポジティブな気持ちで、
色々と手を出してみることも大事なのではないか?と思うのです。
これが「非効率に生きる」という考え方。
人生経験は、「幅」と「深さ」で表せるのでは、と。
1つのことに対して、「効率的」に極めるということは、「深さ」を作るとは思います。プロサッカー選手にしか、プロのピッチ上の雰囲気はわからないし、スポーツの駆け引きの深さはプロ選手だけ体感できるものだし、プロの世界だからこそ、スポーツビジネスの汚い裏まで、知ることができる。
ですが、「効率」は「幅」を作ることはできない。決めたことじゃなくて、ふいに目の前に現れた機会に対しても、柔軟にチャレンジしてみること。
「非効率」こそが経験値を広げ、人生の「幅」を作るのでは、と思います。
この「不便益」という考え方は、まさしく「幅」を意識する考え方だなぁ
と思いました。手作り旅程だからこそ、自分だけの旅行の思い出ができるんですよね。
ビジネスだってそう。外注すれば、自分の仕事がなくなり、便利。
だけど、自分でその仕事をする能力は育たなくなるし、
その仕事をしたことで得られた経験値を、得る機会は失われる。
日々の生活やビジネス、色んなところで、意識してみてください。
そういう「不便益」について、考えさせられる本でした。
以上、「ビジネスガッシュ!」第3回
「ごめんなさい、もしあなたがちょっとでも行き詰まりを感じているなら、不便を取り入れてみてはどうですか?~不便益という発想」
でした。なげぇ。
ではまた!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
