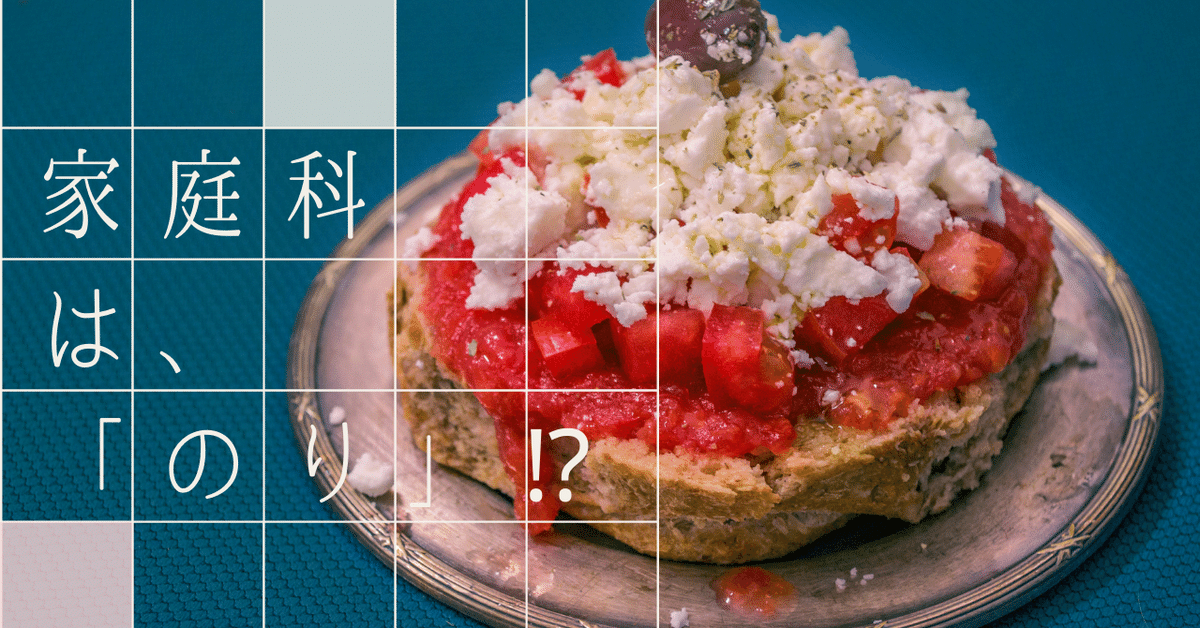
(続)どうして家庭科を学ぶんですか?
つづきです!
前の記事で家庭科の目的・目標を、
学習指導要領の目標を参考に考えてみました。
学習指導要領は私的には、
・実践的で体験的な活動をする
・日常に関わる知識技能を身につける
・課題解決学習をする
・構成員(小学校では家族、中高に従って社会)として生きるために学ぶ
といったことを目標として掲げていると解釈しました。
自分の中の目的・目標をしっかり考え直すために、
もう一つ、
『教科の本質が分かる授業』シリーズ総論編
教科の本質と授業-民間教育研究運動のあゆみと実践
-柴田義松編著(2009.8)
を参考にしてみたいと思いました。
今回の課題は教科の目的・目標、ですが、
別の授業でこの本を読む機会があり、
よさそう!と思って引っ張ってきました。
余談ですが、この本、
総論編ではなく、家庭科として別に3冊でてるんですね!
そして、私が先生になろうと思ったきっかけである鶴田敦子先生が編著してます!
私が初任の時はこの本をなめるように読んでました(関係ないけど、つい、笑)
さて、では総論編に戻って、
2.家庭科教育研究者連盟がまとめた目標
この本に、
1987年家庭科教育研究者連盟がまとめた家庭科の目標が書かれていました。
家教連については以下のように紹介されていました↓
学習指導要領「家庭」に縛られずに、子どもの学習欲求と家庭と地域の実態にもとづいた自主的編成の家庭科教育の実践を考えた家庭科教員達は、1966年、家庭科教育研究者連盟(略称「家教連」を結成し、毎年夏に研究大会を開催し、研究と実践を重ねていった。
以下に引用する教育課程案がつくられた経緯については家庭科の教授に聞いたのですが、
1960年代から新設が噂されていた総合学習について、
実施されれば家庭科が総合と合併されて無くなるという議論が行われていたらしい。
これに危機感を覚えた家庭科教師たちが、
家庭科の存在意義を示すために作成した、とのこと。
家庭科教育の目標は憲法に定める「健康で文化的な最低限度の生活」(第二五条)と「個人の尊厳と両性の本質的平等」(第二四条)の規定の、生活上での現実を目指し、生命と生活の再生産にかかわる家庭の営みとそのしくみを家庭科の独自の対象として抑える。「生命と生活の再生産」とは、一方では、生活手段、すなわち衣、食、住などの生活資料の生産とそれに必要な道具の生産とかかわり、他方では人間それ自身の生産、すなわち種の繁栄とかかわるというように広範な内容を含んでいる。さらに、学習過程は、
(1) 技能の伝承と原理の感性的認識(やり方を知る)
(2) 自然科学的な認識(なぜそのようにするのかを知る)
(3) 生活の現実認識(現状はどうなっているのかを把握する)
(4) 現実の社会科学的認識(なぜそうなっているかがわかる)
(5) 政治的自覚(主権者としての自覚を持ち、これからどうしたらよいかがわかる)
これらは、子どもの生活経験や他教科、特に、自然、社会、保健、教科外活動などの学習と深いかかわりがあるので、段階は固定的なものではなく、相互に絡み合いながら発展していくものと捉える。
家庭科の先生が作ったということで背筋が伸びますね。
そうなんです。家庭科の先生たちが、頭を寄せ合って家庭科の本質を協議したという事実に畏敬の念を覚えます。今後家庭科不要論が再発したら、私たち同じことできるのかな。、
内容としては、
・人としてよりよく生きるため内容
・課題解決学習をする
・政治的自覚としっかり明記し、民主主義的な主体を育てる
・家庭科を通して他教科を統合し、生活に落とし込む
といった感じでしょうか。
ちょっと難しい表現(教授曰く民間団体っぽい表現)もありましたが、
「再生産」とは、私たちの生活には家庭という場所があり、
また生きるために労働という場があることを示しているのかなと思います。
(「再生産」という言葉は家政学や家庭科で昔よく使われていたようです。)
家庭と労働は相互に影響していて、
「よりよい生活」を送るためには「よりよい社会」が基盤となる。
そしてその社会をつくる担い手は私たちである。
つまり、私たちはより「よい社会」をつくる個人であり、
よって政治的自覚をもちましょう。というところでしょうか。
教員は政治と聞くと触れてはいけないと感じますが、
ここでいう政治は民主主義の考えであり、むしろ
学校教育で取り上げるべき部分だなと最近別の授業を受けて
考えが変わりました。
補足ですが、
「家庭の営みとそのしくみ」は、
科学的な仕組みを学んでいくことを示しています。
そして、
(1)~(5)に特徴がありますよね!
この本を取り上げた授業の中で、家庭科の教授が教えてくださったのですが、小学校の教科書にセロハンテープでごみを集めるというトライをこの学習過程に当てはめてみると、
(1)場所によって掃除の仕方が違うことを知る
(2)セロハンテープで教室や自分の部屋など気になる場所のごみを集めてみる
(3)場所によってごみの種類が異なることを把握する
(4)ごみには意図的に出るごみと、意図的ではなく自然に出るごみがあると判断する
(5)自分が快適だと思う生活のためにどうしたらよいかわかる
のような流れにできます。
このセロハンテープの実践は飯野こうさんという方が行っていたらしいのですが、
現在も、この実践は複数の教科書に掲載されています。
教科書は家庭科教師が書いているものも多いので、
このような良い実践が残り続けているのかもしれませんね。
政治的な、という部分で同じように考えてみました。
例えば中学技術・家庭の悪質商法のところなど、
(1) 悪質商法の手口を知る
(2) 高齢者や若者は被害にあいやすい
(3) 成人年齢が引き下げられたから騙されないように気を付けなさい!
Aさん:なんでこんなひどいやり方で騙す人がいるんですか?
(4)騙さないと生きていけないからです
Bさん:えぇ、どゆこと、僕たちの中にもそういった仕事をする人が出るのかな?日本はそんな社会なんですか?
(5)社会的格差や貧困について調べてみる
こんな感じでしょうか。
ちなみに、騙されないと生きていけない人、について、個人的に面白かったYouTubeを載せておきます。( 映画『ギャングース』presents 実録!!振り込め詐欺のしくみ )
個人的にはこのような実際にある社会について、
児童生徒という社会的責任が無い立場で議論する面白さを感じます。
大人が言えないことも子どもは言ってくれますから笑。
さて、
ここまで学習指導要領と家庭科教育研究者連盟の2つの目標をみてきました。
なんで家庭科を教えるの?と聞かれたらなんて答えよう?
10年に一度改訂されるため、学習指導要領は完璧とは言えません。
完璧なものではないからこそ、学習指導要領に則った授業を行いつつも、
自分が教えたい事はどんなことか、
家庭科教師として教科の本質に迫っていくことも大事なのだと思いました。
私は今まで、自分や自分の家庭を俯瞰し、
生活と社会や世界の繋がりを知って、
自分の生活を豊かに創造するために家庭科があると思っていました。
しかしその豊かさとはどのような豊かさか、?
誰のために創造するのか、?
今後研究を行う過程で、自分が思う家庭科の本質をもっと深く考えてみる必要があるんじゃない?と教授からもアドバイスいただいたので、
家庭科の歴史や先人が大事にしてきたこと、海外との比較、など視野を広げて、引き続き考えていきたいです。
最後に、
前回noteの冒頭である先生の言葉を載せました。
この言葉の後半、
「自分が生きていく上で何が必要なのかっていうことが分かっていくためにも、まあ、家庭科があって、それはつなぐ、のりみたいなね、役割をしていく教科があれば、非常にいいと思いますね。」
が、じんわり心に残っていたので、載せました。
この先生は総合的な学習という言葉もない時代に家庭科を教えていて、
その実践の過程で家庭科の本質を自分なりに導き出していました。
それが他教科を統合して自分がよりよく生きるために必要なことを見つける家庭科。
社会の構成員になるために学ぶより、
自分らしく、自分を人生の主人公にしてあげる方法を学ぶ教科、
という考え方が今の私にはしっくりくるような気がします。
長くなってしましましたが、
読んでくださってありがとうございます!
※勉強不足ですが、学びの過程としてnoteにしています。
間違っている部分があれば、教えていただけるとありがたいです。
#日記#自分#大学#教師#自信#徒然#授業#大学院#生徒#授業づくり#家庭科#大学院進学#家庭科の先生#高校家庭科
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
