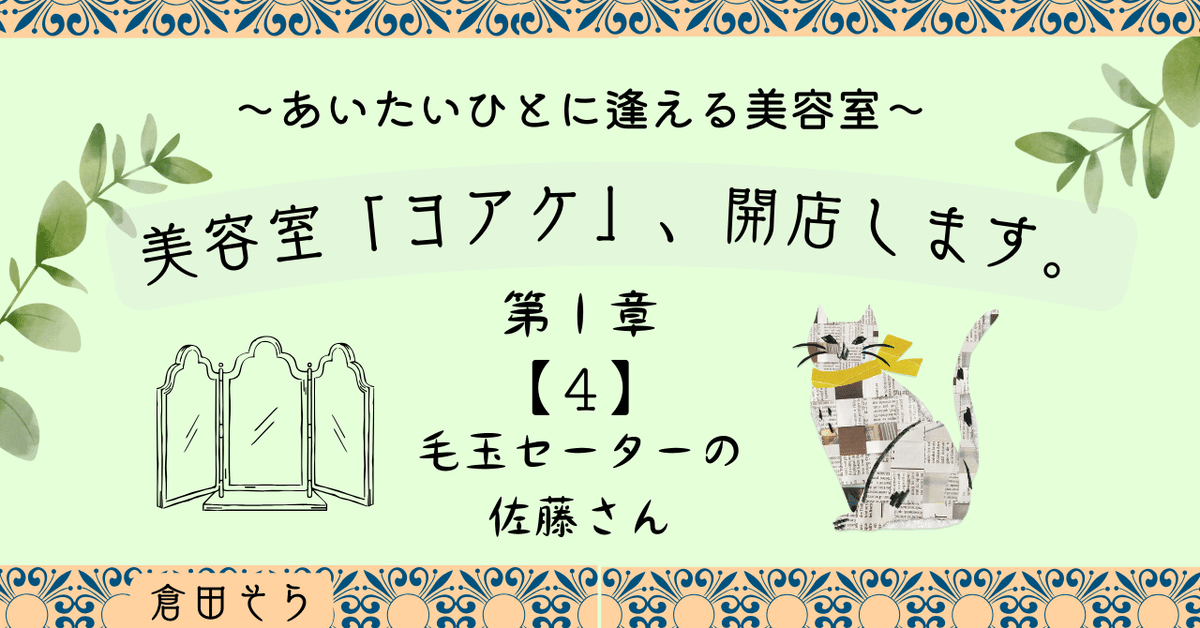
【#4】 連載小説 『 美容室「ヨアケ」、開店します。』 (第1章 「毛玉セーターの佐藤さん」第4話)
あらすじと前回までの話はこちらです。
理恵との約束の日。
麻衣はひとり、午後三時頃から自主練に来ていた。もともと店の鍵は持たされていたので、店長には、
「火曜日に休日出勤して自主練します。友達をカットモデルで呼ぶかもしれません」
とだけ報告した。あれこれ佐藤さんのことを詮索されたくなかったからだった。
青空が広がり空気はひんやりしていて、外に出ると気持ちがスッと引き締まるような日だった。
麻衣は地元の長野県を思い出していた。
(久しぶりに帰りたいなぁ。この辺にある細くて汚い、川なんだかよく分かんないようなのじゃなくて、透明で底まで見える川が見たい…)
そんなことを考えながら、シザー(ハサミ)をワゴンの上に並べ、手入れをしているときだった。
「おーい田辺~。ちゃんとやってっかぁ~」
先輩の男性スタイリスト、新城の声だった。
新城は店の近くに住んでいるので、出掛けたついでに麻衣の姿を外から見て、ふらっと立ち寄ったようだった。
「あっ、えっ?あれ?新城さん!お疲れ様です…」
「見に来てやったぞ」
いつもならアドバイスをもらえるので喜ぶところだったが、今日は、あーあタイミングが悪いなあ、と麻衣は思った。
「すみません、ありがとうございます」
「そんじゃあ、今日は俺の頭、切ってもらおうかな。あ、でもほんとに頭切んじゃねえぞ、髪切んだぞ」
新城が小学生みたいなノリつっこみをして笑った。
「はい…よろしくお願いします…」
練習にはなるし、特に断る理由も見つからなかったので、麻衣は新城の髪を切ることにした。
新城にもし今日のことが知られたとしても、怒られるとか、店長に言いつけるとかはしないだろう。
しかし、今日は麻衣ひとりじゃなきゃだめだ、と感じていたので、内心は焦っていた。
「田辺は彼氏とかできても仕事優先しそうだからさ。ちゃんと遊んでるか?…うわっ!?そこハゲ作ってない?…って、ああ、気のせいだった」
新城が冗談交じりに言った。
「めっちゃびっくりしたじゃないですか!手がすべってほんとにハゲ作っちゃいますよ、もう…。それに彼氏は今いないですし。やっとスタイリストになれたんだから、上手くなって顧客を増やさないと」
「おっ。俺のお客さん取る気か。でも無駄だからな。どんな手を使ってでも引き留めるから」
「どんな手、って何ですか…!」
麻衣は笑った。
「田辺はちょっとまじめすぎるところあるからさ~。まあ、適当に手を抜いて、それも仕事のうち。遊んで休めよ」
麻衣がつい色々やりすぎてしまう性格なのを知っている新城は、ときどきさりげなくサポートしてくれる。
その優しさが、麻衣は嬉しかった。
六時過ぎ頃、新城のカットが終わった。
「ありがとうございました。勉強になりました」
麻衣は言った。
「襟足のところとか、だいぶ上手くなったじゃん。うん、あとはどんどん経験を積むことだな…ところでさ、これから誰か来んの?」
「…えっ!何でですか?!」
麻衣は突然言われたので、声が上ずってしまうのを感じた。新城はすかさず言った。
「おおっ?やっぱり!俺ってカンいいよなー。だれだれ、彼氏出来た?」
「いえ、だから彼氏はいないですってば」
麻衣は慌てて言った。新城は特にそういうことには勘が鋭いタイプだった。
しかし、麻衣の彼氏でも来て二人きりでカットするんじゃないか、くらいに考えているようだった。
「ほんとかー?あやしいなあ~」
「本当です、誰も来ませんよ。今日はもう帰ります」
しかし新城は、麻衣の態度でいつもと違う何かを感じたらしく、何かと理由をつけて六時半をまわっても残っていた。
仕方なく麻衣は、片付けて帰り支度を始めるふりをした。それで新城もようやく諦めたらしく、じゃあ気をつけて帰れよ、と言って出て行った。
七時を少し過ぎた頃だった。入り口のドアがチリンと鳴った。
麻衣は弾けるように立ち上がり、階段を駆け降りた。
カウンターの前に、理恵が立っていた。
「ああ、来てくれたー!よかったぁ!ありがとう」
ジャージ姿しか見たことがなかったのだが、フリースの下に今日はきれいな花柄のワンピースを着ていたので、だいぶ印象が違って見えた。
ジャージ姿のときよりも自分に似ているような気がする、と麻衣は思った。
麻衣はフリースを預かり、カウンター奥のクローゼットに仕舞うと、
「お二階、ご案内しますね」
と声をかけた。理恵は小さくうなずいた。
カウンセリングするために一度席に案内し、麻衣は改めて
「スタイリストの田辺麻衣です」
と自己紹介した。
鏡越しに目が合うと、理恵ははにかんだように下を向いてしまった。
理恵の金髪はかなり傷んでいて、水分が抜けてパサパサになっていた。
「ずいぶん傷んでるよー。トリートメントしたほうが良さそう。それから、ついでにカラーする?」
「え、いいんですか?」
理恵は、ぱっと顔を上げて言った。
「うん、もちろん!トリートメント成分が入ったカラー剤あるから、それにするね。あ、もちろん無料ね、私の練習だから。色はどうしたい?」
「えっと…」
「あ、カラーチャート見てみる?」
麻衣は、カラーリングの見本の髪が、少量ずつ何種類も貼り付けてあるボードを持ってきた。
「どんな感じになりたいかな?」
「えーと…」
麻衣はヘアカタログも持ってきて、一緒に見ながら色々な提案をした。理恵はしばらく迷っていたが、思いついたように言った。
「…あっ、田辺さんみたいな色がかわいい」
麻衣はどちらかと言えば黒に近いような、落ち着いた茶色だった。
「じゃあそうするね。カラーの調合頑張るけど、もともとの髪質もあるから、全く同じ色にはならないかも…。もちろんなるべく近づけるけど、それで大丈夫?」
「はい、全然…」
「ありがとう!だいたい同じようにはなるかなって思うから、理恵ちゃんにきっと似合うよ」
「えーそうですかねー」
理恵は笑った。表情が一気に幼い感じになった。
シャンプーをしながら、麻衣は聞いてみた。
「かわいいワンピースだね。めっちゃ似合ってるよ」
「そうかな…でもさアタシ、あれからすぐ彼氏と別れたんだ」
「えっそうなんだ!でも心配してたからほんと良かった!」
「うん…ちょっとキツイけどさ、まあ、大丈夫だよ。それからさ……こないだは、えっと、話しかけてくれてありがと」
ヤンキー風だったのは彼氏の影響で、本当は歳相応な女の子なんだな、と麻衣は思った。
「そういえばさ、えと…」
理恵が小さな声で言った。
「なあに?」
「………は……の?」
「え?ごめん、シャワーの音で…」
「あ…あの…あのさ、えっと……うちのお父さん、…来てないの?」
そう言うと理恵は慌てて、「あ、別にどうでもいいんだけど」と付け加えた。
「うん。来てくれなくなっちゃった」
「そっか。アタシもあれからすぐ彼氏んち出ちゃったからさ、お父さんどこにいるか、わかんないんだよね」
「そっか…で、彼は大丈夫?追いかけて来ない?」
「来ない来ない。もう新しい女いるみたいだし。ってか、もともと二股?三股?だったみたい」
「そうなんだ…」
理恵のカラーをしながら、麻衣はガラス越しに外を何回も眺めた。夜なのであまり見えないのだが、それでもチラチラと見ずにはいられなかった。
「外、どうかしたんですか?」
麻衣の様子をみて、理恵が言った。
「あ、ううん、何でもないよ。…あ、雑誌、なんか違うの読む?」
「ああ、じゃあ今度はセブンティーン見たい」
「うん、じゃ、持ってくるね」
カラー剤を塗り終わり時間を置いている間、麻衣は休憩室でペットボトルのお茶を飲んだ。
「あーあ、ちょっと疲れたな…」
椅子から立ち上がって、小窓を手でこすってから顔を寄せた。外が暗いので、こうしないとあまり見えないからだった。道には人影はまばらだった。
そのとき、手元のタイマーがピピ、ピピ…と鳴った。カラー剤を流す時間だった。
麻衣はもう一度外を眺めてから、休憩室を出た。
「はい、じゃあ流しますねー」
理恵をシャンプー台に案内すると、椅子を寝かせ、シャワーを出した。
(まだ八時だし…。でも理恵ちゃんの連絡先は書いてもらったから、これからは連絡取れるから大丈夫かな…)
理恵のシャンプーをしながら、麻衣は思いを巡らせた。
シャンプー台に当たるシャワーの音は大きいので、そのとき入口のドアが開いた音に気付かなかった。
誰かが階段を上がってくる音で、麻衣はようやく手を止めた。
「あ…!!良かった!来て下さったんですね!」
麻衣は言った。理恵はシャンプーをしていて顔に布を掛けられているので、くぐもった声で「どうしたの?誰?」と聞いた。
「佐藤さん…あ、えっとね、お父さんだよ」
「え?お父さん?!」
理恵がシャンプー途中なのに起き上がったので、周りがびしょ濡れになってしまった。
「おう…」
佐藤さんはひとこと言って、麻衣が案内した椅子にさっさと座ってしまった。
「なんでお父さんが来んだよ?!」
「ごめん、私が呼んだのよ」
理恵と話した夜、麻衣は佐藤さんに手紙を書いたのだった。
佐藤さんは理恵のことを心配して、アパート近くの公園にきっとまた来るだろう、そうしたらもしかしてこの手紙を見てくれるかも知れない、そう思ったのだった。
一か八か、ダメもとだった。
麻衣はコンビニで買った便箋に、理恵が「ヨアケ」に来ることと、今日の日付と時間を書くと、名刺と一緒に封筒に入れ、宛名には、
『理恵さんのお父さん、佐藤さんへ 美容室ヨアケ 田辺より』
と大きく書いた。それからそれをジッパー付きのビニール袋に入れると、ベンチの上に置き、手ごろな大きさの石を持ってきて重石として置いた。
「上手くいくかなあ…上手くいくといいな…」
余計なお世話かもしれない、でもやっぱり…。そう思いながらやったことだった。
理恵はそれきり黙ってしまった。
気まずい雰囲気のまま、理恵のシャンプーが終わった。
「お疲れ様でしたー」
麻衣は理恵を起こし、頭にタオルを巻くと、佐藤さんの隣の椅子に案内した。親子が鏡に向かって横に並んで座った。
(やっぱり、余計なことしちゃったかな…)
麻衣は衝動的に自分がしてしまったことを、今になって後悔し始めた。
美容室の客の人生にまで口を出す権利は、自分にはない。
これで親子関係が余計にこじれてしまうかもしれない。
そのとき、静かな夜の美容室の空気を裂くように、理恵のスマホが鳴った。
無言のまま理恵は、目の前の台に置いたバッグを引き寄せ、キティちゃんの大きなストラップがついたピンクのスマホを取り出した。
「あ…」
そのとき、隣の佐藤さんが小さく言った。視線の先には理恵のトートバッグがあった。口が大きく開き、中が丸見えだった。
その中にキティちゃんの顔型のポーチが見えた。麻衣が公園で初めて佐藤さんを見た時、理恵に投げ返されていたものだった。麻衣は、拾って公園のベンチに置いてきたのを思い出した。
理恵も父親の視線に気付いたようだった。しかし、画面を食い入るように見つめていて、一言もしゃべらなかった。麻衣が理恵の濡れた髪をとかす音だけが、シュッ、シュッ…と小さく聞こえていた。
麻衣が「何か雑誌でも見ますか?」と二人に聞こうと、口を開きかけたときだった。
「…公園に戻ったらさ、なんかこれまだあったから」
理恵はスマホから目を離さずに、ぶっきらぼうに言った。
しばらくの沈黙の後、佐藤さんは、「うん」とも「ふむ」ともつかないような声を出した。
そのとき、送信したラインの返事が来たようで、シュポッという音がした。理恵は画面から目を離さず、カチカチと長い爪の音を立てながら、両手で何かを打ち込んでいた。
佐藤さんはキティちゃんのポーチを、じっと見つめていた。
「さあ!」
麻衣がいきなりパン、と手を叩いたので、二人は同時に顔を上げた。
「それじゃあ次はカットしますね!佐藤さんは久しぶりでずいぶん伸びたようなので、理恵ちゃんが終わったらカットしますから、しばらく待ってて下さいねー!」
麻衣は元気良く言った。
「でも…僕は今日は客じゃないし…しばらく来てなくてね、申し訳ないから…」
佐藤さんは遠慮したが、麻衣は遮るようにして言った。
「私、やっとスタイリスト試験に合格したんです。佐藤さんが指名してくれて、すごく勉強になりました。ありがとうございました。
だから今日はカットモデルとして、私の練習台になって下さい。お願いします!」
佐藤さんは少しの間だまっていたが、麻衣に丁寧にお辞儀をして、
「じゃ、お言葉に甘えて…」
と、嬉しそうに言った。
ヨアケの中でしゃべっているのは、ほとんど麻衣一人だったが、麻衣はよく笑った。つられて理恵や、佐藤さんも笑った。
結局二人のカットやカラーが全て終わったのは、十時近かった。
「前と全然違う…!めっちゃ嬉しい!」
理恵が嬉しそうに言った。ツヤツヤの髪で、来た時とは別人のようだった。
傷んだ部分をカットしたので、セミロングから肩の上くらいのボブになっていた。
「気に入ってくれて私も嬉しいよ!…遅くなってしまって、申し訳ありません」
「いえ、とんでもない、こちらこそ、今日は本当にありがとう」
佐藤さんはポケットから小銭入れを出したが、麻衣は辞退した。
「今日は私の練習で、カットモデルとして来て頂いたので頂けません。それより、またいつでも来て下さいね。もちろん、理恵ちゃんもね。あ、でも今度はカットモデルじゃダメかも…ごめんね。そのかわりお友達価格で安くするからね」
「ありがとうございます!」
理恵は嬉しそうに笑った。
麻衣はドアを開け、二人を送り出した。
佐藤さんは店を出ると、振り返って麻衣に向かって深々と頭を下げた。それを後ろから見ていた理恵の表情が、少し泣きそうに歪んだようにみえた。
「ありがとうございましたー!」
麻衣は大きな声で言って、頭を下げた。
その時、佐藤さんが、
「あ、オーナーさんにもよろしくお伝え下さい」
と言ったので、麻衣は驚いた。
「えっ?お知り合いだったんですか?」
「いえ、知り合いってわけでは…あ、それからあのネコちゃんにも」
「え?ネコ??」
麻衣が聞き返したとき、先に歩き出した理恵を追うように、佐藤さんも歩き出した。
「理恵、金髪より、そっちのが似合うぞ」
「…」
「今日はもう遅いから、送っていくから」
「…うん」
二人は連れ立って駅の方に向かって歩いて行った。
外は雪でも降りそうに寒かった。クリスマスが近いので、往来にはイルミネーションが多く、曇ったガラスに色とりどりの光が反射していた。
レジカウンターに並べてある名刺立てには、坂本や新城、荒井のものと共に、麻衣の名刺も置かれていた。麻衣は真新しい名刺を一枚手に取り、『スタイリスト 田辺麻衣』の文字を見つめた。
「さ、片付けて私も帰ろっと」
麻衣は大きな声で言うと、名刺をそっと元に戻し、きれいに揃えた。
火曜定休日を返上したので、明日からまた一週間休みは無い。
しかしそれでも麻衣の身体は軽く、二階に上がる階段を、一段抜かしで駆け上がっていった。
(第二章 「サスペンス小学生」に続く)
この記事が参加している募集
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?

