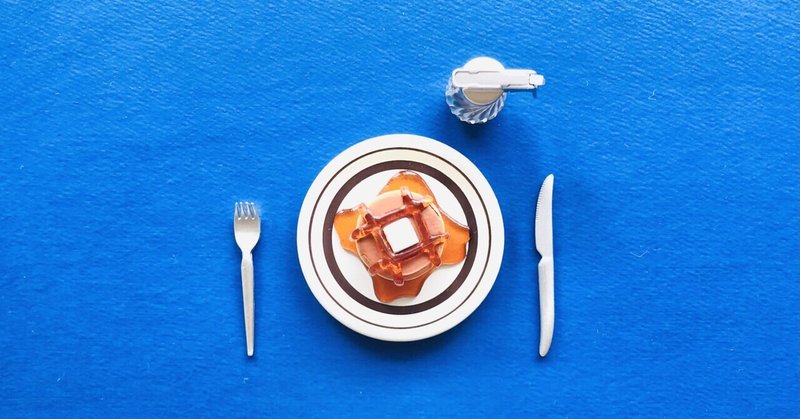
創作|⑤そらいろホットケーキ
そらいろホットケーキ
前回までのお話
前回までのお話は、下記リンクでお読みいただけます。
9.メープルシロップをどうぞ
未来は変えられる。いつでも。何回でも。
まず、卵をわって、よく混ぜる。
これは得意だ。毎朝やっていたから。
それから、さとうとミルク、バターをまぜる。
ほどよいところで、ふるっておいた薄力粉とベーキングパウダーを合わせ、バニラエッセンスをちょっぴりたらす。
フライパンをあたためて、たねを流しいれようとして、ハッと気が付く。
ぬれぶきん、ぬれぶきん。これをいつも忘れてしまう。
一度火を止めて、フライパンをぬれぶきんでサッとさまし、それからもう一度弱火にかけて、おたまですくったクリームいろのたねを、そうっとそうっとフライパンの真ん中から流しいれる。
『うまく焼こうとか焦がしちゃいけないとか考えないで、ただそこにあるホットケーキと無心で向かい合うの』
頭の中で、前に話していたおばさんの声がきこえる。
『そうすれば、自然とどうすればいいか分かる。強火にすればいいのか、弱火にすればいいのか。そろそろひっくり返した方がいいのか、まだもう少しあとなのか』
今、おばさん本人はお母さんといっしょにテーブル席に座って、カウンターの中でホットケーキを焼くわたしをじっと見ている。振り向かなくてもわかる。
まるくひろがったクリーム色のたねの表面にぷつぷつと空気の穴があきはじめる。
はしっこがカリカリになってきたところで、ぐるりとひとまわり、フライ返しのはじっこで外側をすこしだけ、持ち上げてみる。
いいかんじだ。そうっとフライ返しをホットケーキの下にすべりこませる。
フライ返しが完全にホットケーキの下に入ったのを確認してから、そっと持ち上げる。
反対の手でフライパンも宙にうかせて、フライパンの面とぷつぷつしているホットケーキの面を、両手のひらをあわせるみたいに、ぱっ、と合わせて、そのまますばやくフライパンをコンロの上へ。
ふーっと息がもれた。成功だ。
ホットケーキの裏側は、焦げもせず変なもようもできず、きれいにまるく、すべすべに焼けていた。
ふーっともう一度息がもれる。汗が落ちないように、首にかけていたタオルでおでこをふく。どこかで扇風機がぶーんとまわっている。
反対側も焼けたようで、いい匂いがしてくる。
またそっと、フライ返しをすべりこませてみる。
くっつかない。少しだけ持ち上げてのぞく。
いいかんじだ。そうっとお皿にとる。
そんなわけでわたしは、三人分のホットケーキが焼きあがった時は、もうくたくただった。
切っておいたバターをのせ、ハチミツと白砂糖、メープルシロップと一緒にテーブルに運ぶ。
お母さんとおばさんは、まじめな顔をしている。
「お待たせしました」
おばさんの真似をしてわたしは言ってみる。
「シロップとお砂糖は、お好みでどうぞ」
二人とも、お皿を見たまましーんとしている。
(焼きかげん、だめだったのかな?)
わたしはおばさんの顔をじっと見る。
「いただきます」
突然ぱんと両手を合わせて、おばさんが言った。
メープルシロップをさっととり、バターの上からたっぷりかけた。
おもむろにナイフとフォークをかまえ、ざくざくと切ってゆく。
切り口にとろけたバターとシロップがしみて金色にひかり、湯気がもわもわと立ちのぼった。
「いただきます」
つられたようにお母さんも両手を合わせ、そう言った。
お母さんはメープルシロップもハチミツもかけない。バターをぬりひろげてホットケーキにナイフを入れる。
「おいしい」
「おいしい」
一口食べて、二人が同時にそう言ってくれたとき、わたしはちょっとだけ、むねのあたりがきゅっとした。全然ちがう二人が、そっくりだったから。小さな姉妹がフォークをにぎってホットケーキをほおばっているのを見ているような、そんな不思議な気持ちになった。
わたしは椅子をすべりおりて、床にすっくと立った。
「お母さん、おばさん」
わたしは言った。二人の目がこっちを見た。お母さんは少し心配そうに、おばさんはいつものように、じっとわたしを見た。
落ち着いて、息をすって、わたしは言った。
「わたしは、おばさんがだいすきです。おばさんと暮らしたいです」
「未来!」
カチャンとフォークをお皿に落とし、お母さんが大きな声を上げた。そしてそれから、続きの声が出ないようだった。
「それで?」
静かな声でおばさんが言った。お母さんもこっちを見ている。わたしは足に力をいれて、続けた。
「お母さんに小さい時においていかれて、とっても悲しかったです。親がいないからって友達にからかわれたりしてくやしかった。急に帰ってきてまたいっしょに暮らそうなんて、お母さんは勝手です。わたしは、お母さんが好きかどうか、わからない。またお母さんと暮らしたいかどうか、わからない」
お母さんは泣き出したみたいだった。わたしはこわくて、お母さんの顔を見られなかった。まっすぐ前を見てるつもりが、いつのまにか自分のサンダルを見ていた。
わたしは両手をぎゅっとにぎった。どう続けたらいいのか分からなくなって、頭がぼうっとしてしまった。
「それで?」
もう一度、おばさんが言った。それはわたしには、
『うまくやろうなんて考えちゃだめ』
と聞こえた。
『余計なことを考えずに、ただ無心で向かい合うの』
いつもおばさんが言っていたこと。
『たとえば誰かと仲良くなりたいときとか、反対にけんかのときとか、もっと他の、思いがけない何かがおこったときとか』
わたしは体の力をぬいて、息をすった。ホットケーキのふんわり甘いにおいをすいこんで、わたしは前を向くことができた。
「でも、だから、わたしは、お母さんと行きます」
お母さんが目を丸くした。
「もう一度いっしょに行って、お母さんとの悲しかった思い出とかくやしかった時間とかを、今はちがう、今はいいんだっていうように、変えたいから」
わたしはじっとお母さんの顔を見た。
お母さんの目にみるみる新しい涙がもりあがって、それからお母さんは、わーんと机につっぷして泣きはじめた。
お母さんは、まるで子どもみたいだった。三歳みたいだった。あの朝お母さんにしがみついて泣いた、わたしみたいだった。
「よく自分で決められたね」
おばさんがわたしを見ていた。わたしはおばさんを向いてもう一度ホットケーキのにおいをすいこんだ。
「おばさん、今まで本当にありがとう。ずっとわたしのおばさんでいてくれてありがとう。時々遊びにきてもいいですか。それから大人になったら、いっしょにホットケーキのお店をやってもいいですか」
そのときわたしは初めて見た。おばさんの目から涙がこぼれたのを。
「おばさん」
びっくりしてわたしはおばさんにかけよった。
「汗よ」
私をおしやり、おばさんは机に置いてあった台ふきんで顔をごしごしふいた。それからそのふきんをお母さんに投げつけた。
「ほら、まりちゃんも顔ふきなさい。みっともない」
わんわん泣いていたお母さんが顔を上げた。きれいなお化粧がどろどろになっていて、わたしたちは笑った。
笑っていると、おばさんの手が伸びてきて、首にかけたタオルでわたしの顔をぐるりとふいてくれた。わたしの顔も知らない間に、涙と鼻水でぐちゃぐちゃなのだった。
わたしたちはみんなげらげら笑った。ばかみたいに笑った。
「まったく」
と、おばさんが言った。
「このあついのに、ホットケーキなんて」
それから、わたしたちはそろってホットケーキをほおばった。
夕日が店の中いっぱいにさして、お皿の上のホットケーキが金色にひかった。夏の夕方の空みたいに。
そらいろホットケーキ。
了
お読みくださり、ありがとうございました。
この作品は、14年ほど前に書いたものです。
長らくパソコンの中に眠っていましたが、このたびnoteという場に出させていただくことにしました。
そんなに長いものではないので、全5回に振り分けて、下記マガジンにまとめました。
いつもの生活エッセイとは異なりますが、皆様にひととき物語の世界をお届けできていましたら幸いです。
お読みくださり、本当にありがとうございました。
2024年は団地の暮らしエッセイから創作小説など、いろいろ掲載して行きたいと思います。サポートよろしくお願いします!
