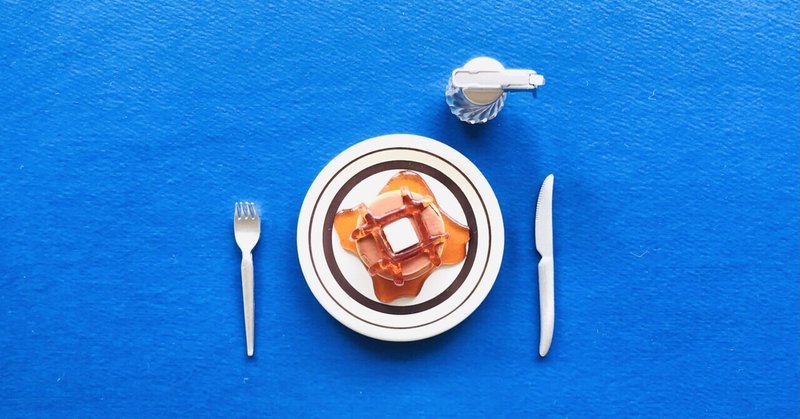
創作|④そらいろホットケーキ
そらいろホットケーキ
前回までのお話
前回までのお話は、下記リンクでお読みいただけます。
7.まほうのことば、ひとつ
この世には、分からないことがいっぱいある。
宇宙の外側はどうなってるの? とか、死んだらどうなっちゃうの? とか、わたしはどうして生まれてきたの? とか。
夜に考えると胸の奥がひゅーとするようなことたち。心臓がドキドキして、足が冷たくなり、頭があつくなる。ふとんの中でずっと眠れず、目がぱっちり開いてしまうようなことたち。
ふすまの向こうから、おばさんが電卓をたたく音がする。お店の帳簿をつけているのだ。いつもはその音を聞いているうちに眠ってしまうのに、たまに、おばさんがすべて後片付けを終え、電気を消し、となりにしいたふとんに入るまで、ずっと眠れないことがある。
わたしは、眠れないでいることをおばさんに気づいてほしくて、わざともぞもぞしてみる。おばさんは隣のふとんからわたしを見て、
「未来、眠れないの」
と、言う。
「何か考えているんでしょう」
と。そこでわたしは聞いてみる。
「宇宙の外側はどうなってるの?」
とか、
「死んだらどうなっちゃうの?」
とか、
「わたしはどうして生まれてきたの?」
とか。
おばさんはしばらく考え、
「わからない」
と、言う。大人にもわからないのか、と思って、わたしはまたひゅーとした気持ちになる。おばさんはふとんをめくると、わたしの足にさわり、
「やっぱりね」
と、言って立ってゆく。しばらくすると、湯たんぽを持ってきてわたしのふとんにいれる。
「足が冷たいから眠れないのよ、これでもう大丈夫」
夏でもおばさんはいつもそうする。あついなあ、と思いながら、それでもわたしはようやく眠ることができる。
カレンダーの日めくりが一まい一まいちぎられて、夏休みまでもうすぐになった。
わたしは久しぶりにお店でホットケーキを食べながら宿題をやっている。
お客さんは誰もいない。扇風機がぶうーんとまわっている。暑い時期のホットケーキ屋はひまだ。
「楽なもんよ」
と、おばさんは言う。
あれからお母さんからの連絡はない。あるのかもしれないけれどわたしには知らされてない。……と、思っていたら、本当に連絡がないのだと、おばさんは言う。
「こっちから電話をかけてもいつも留守番電話なの」
と。
あの日のことは夢だったんじゃないかな、と思うことがある。突然あらわれたお母さん。昔と変わらなすぎたお母さん。そこで、おばさんにそう言ってみたら、
「現実だよ、しっかり考えなさい」
と言われた。
「未来が決めなきゃ」
と。
「ここにいてもいいの?」
と、わたしは聞いてみる。どきどきしながら。
「未来が本当にそう決めたならね」
と、おばさんはじっとわたしの顔を見る。
わたしはうつむいてホットケーキを口におしこむ。
お母さん、と心の中でよんでみる。
お母さん、お母さん、泣いてしがみついたのにわたしを置いて行ったお母さん。
でもわたしを迎えに来てくれた。またいっしょに暮らせる。今行けばまたいっしょに暮らせる。お母さん。
「まあ、勝手だね」
と、おばさんが突然言ったので、わたしは飛びあがった。
「まりちゃんは、勝手だよ」
おばさんはゆっくり、もう一度言った。まりちゃんというのはお母さんのことだ。
「未来を置いて行く時も、急に電話して来て、明日出て行くからしばらくあずかってくれない? って」
そうだったのか、とわたしは思う。おばさんは続ける。
「犬や猫の子じゃあるまいし。それでまた急に帰ってきて、未来は引き取るから今までありがとう、って何なの?」
何なの? と言われてもわたしもこまる。
「未来」
おばさんはじっとわたしを見た。
「決めたの? そろそろ」
「決められない」
正直にわたしは言った。
「そろそろ決めなきゃ」
おばさんはじっとわたしを見たまま言った。
「お母さんは」
わたしはあわてて、関係のないことを言ってしまった。
「お母さんはやさしいよ」
おばさんはじっと私を見ている。
「お母さんが出て行く日に、わたしわんわん泣いて、ずーっと泣いてて、そしたらお母さんは、『ホットケーキを焼きましょう』って」
「それで?」
「……それで、お母さんは出て行っちゃったけど、だから勝手かもしれないけど、お母さんはわたしには、やさしかった」
そこまで一気に言って、わたしはだまった。扇風機のぶうーんという音だけが、お店の中にひびいていた。
「ふうん」
やがておばさんはそう言って、ひたいの汗をぬぐった。
「そんな昔のこと、よくおぼえてるのね」
そう言うとおばさんは、どこかさみしそうに笑った。
「……未来、まりちゃんと行きなさい」
西側のガラス戸から、オレンジ色の光がお店いっぱいにさしこんでいた。
8.こんがりふんわり焼けたなら
わたしはずっと、さびしくなんかなかった。
それからの二週間はあっという間にすぎた。お母さんからようやく何度か電話がかかってきて、わたしもしゃべった。電話ごしのお母さんの声は、びっくりするほどおばさんに似ていた。
「もうこっちに何もかも用意してあるから」
と、お母さんは言った。
「ようやく一緒に暮らせるね、ずっとさびしい思いさせてごめんね」
と。
「うん、わかった、ありがとう」
と言って、わたしはおばさんに電話をかわる。かわったあと、ちょっとだけ不思議な気持ちになる。わたしはずっと、さびしくなんかなかったのに。
終業式、色紙と手紙をたくさんもらって、わたしは転校のあいさつをした。今までありがとうございました。みんな元気でいてください。泣いている子が何人かいた。航太はそっぽをむいていた。
帰り道、
「おまえほんとに転校すんだ」
と、石をけりながら航太は言った。
「うん」
と、わたしは言いながら、辺りをきょろきょろと見回す。わたしにも、けとばす石があったらいいのに。
「じゃ、夏休みの宿題は?」
と、航太が聞き、
「へっ?」
思いがけない質問に、わたしは声がうらがえる。
「転校したら、夏休みの宿題はどうなんの?」
「わからないけど、二学期からその学校の生徒になるんだから、夏休みの宿題は無しかも」
ふうん、と航太は重々しくうなずいた。
「それ、いいな。おれも転校しよっかなあ」
「……となりの県だもん、すぐ遊びに来るよ」
わたしが言うと、
「そんなこと言ってねーだろ、バーカ」
と言って、航太は力強く石をけとばした。
「ただいま」
うちに帰ってお店のガラス戸をあけると、おばさんが一人でホットケーキを焼いていた。
「おかえり。暑かった?」
うん、とうなずき、わたしはカルピスをつくるために冷蔵庫をあける。おばさんが
「私にも」
と、言うので、コップを二つ出した。
氷をたくさんいれて、わたしはこいめ、おばさんはうすめでカルピスをつくる。
「氷をカラカラいわせながら少しずつのむのがいいよね」
と、おばさんは言う。
カルピスを飲みながら、おばさんはどんどんホットケーキを焼いて行く。どんどん、どんどん。いつか絵本のさし絵で見たみたいに、ホットケーキが高くつみあがる。
「ずいぶんたくさん焼くんだね」
おばさんの背中を見ながらわたしは言う。
「たねをつくりすぎちゃったの」
とおばさんは言う。
一心不乱におばさんはホットケーキを焼いている。
へたくそなはなうた、ぬれぶきんでフライパンをさますジュッという音、そしてホットケーキの焼けるふんわり甘い匂いがしてきた時……わたしの目からとつぜん、涙がこぼれた。
なぜか、とても、なつかしい気持ちになったのだった。
「はい、どうぞ」
コトン、とテーブルにお皿が置かれた。ほかほかのホットケーキの上で、四角いバターがとけかかり、おばさんはその上からメープルシロップをたっぷりかけた。
(あれっ?)
その時、わかった。思い出と今が、パズルがぴったり合うように、わたしの中で、パチリとつながった。
(あの朝ホットケーキを焼いていたのは、お母さんじゃなかった。お母さんが出て行った後で、わたしを迎えに来た、おばさんだったんだ!)
to be continued
次回、最終回です
この作品は、14年ほど前に書いたものです。
長らくパソコンの中に眠っていましたが、このたびnoteという場に出させていただくことにしました。
そんなに長いものではないので、数回(全5回を予定)に振り分けて、下記マガジンにまとめて参ります。
いつもの生活エッセイとは異なりますが、どうぞこちらもお付き合いいただけましたら幸いです。
2024年は団地の暮らしエッセイから創作小説など、いろいろ掲載して行きたいと思います。サポートよろしくお願いします!
