
防災の知識を、子どもに伝えたい。歴史家 磯田道史が新刊にかける思い【大垣書店イベントまとめ】
2021年2月20日、大垣書店の主催により「マンガでわかる災害の日本史」(池田書店)の発売記念オンライントークイベントが行われました。歴史学者としてテレビなどで活躍し、多くの著書を持つ磯田道史氏がライフワークといているのが災害史の研究。東日本大震災から10年。最新作をマンガで出版した意図と、制作の舞台裏を語ってくれました。
話を聞いて感じたのは、磯田氏が新刊にかける思いの強さ、そして、凝縮された情報を届けたいという、制作における強いこだわりでした。

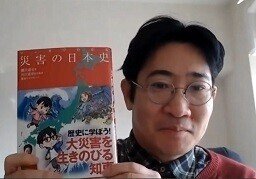
磯田道史(いそだみちふみ)1970年岡山県生まれ。歴史家。国際日本文化研究センター准教授。慶應義塾大学大学院文学研究科博士課程修了。『武士の家計簿』(新潮新書、新潮ドキュメント賞受賞)、『天災から日本史を読みなおす』(中公新書、日本エッセイスト・クラブ賞受賞)『感染症の日本史』(文春新書)など著書多数。
「なぜ、マンガで出版することになったか?」
磯田 なぜ、「マンガでわかる災害の日本史」を出すことになったか。それは、防災に関する情報は、子どもが知っているべきだからです。子どもから知らせるのが、一番、将来にわたって、減災効果が大きいからです。今生まれた子どもたちは、これから100年近く生きるので、なるべく若い世代に向けた本が作りたかった。また、活字が苦手だ、本を読むのが嫌いだという人がいるのでマンガがいいなと思ったのです。
私は自分自身を“歴史の救急車”だと思っています。たとえば、地震や津波が起こったらそれに関する歴史の知識を提供する。コロナ禍の現在であれば、「感染症の日本史」(文春新書)のように感染症に関する情報を提供する、そういうことを考えているんです。
たとえば、東日本大震災であれば、一番近いのが410年前(1611年)の東北の地震「慶長三陸地震」です(下の画像参照)。そのときには、8年後の1619年に熊本地震「肥後八代地震」が起きました。あるいは、これは単なる偶然かもしれません。しかし、東日本大震災の後も、5年後の2016年に熊本の地震が起きてしまったのです。過去の出来事と似た現象が起きたのは、まぎれもない事実です。歴史は知識として知っておく必要があるのです。

マンガで出版することになった背景には、編集者の熱心なアプローチがあった。ちなみにマンガには磯田氏も出演。こんなにイケメンじゃないと謙遜するが、情熱的なキャラクターは本人そのものだ。
「どのようにマンガの本をつくったのか?」
磯田 私は、絵は描けないので、キャラ設定とストーリーとセリフを細かく考えました。登場するのは、「ミチ君」という歴史オタクの少年、幼馴染でしっかりものの「マリちゃん」という女の子、「頼母(たのも)先生」という理科の先生です。
この三人が、災害時にどうするか?というケーススタディをしていく。
起きるかどうかわからないことに対処するケーススタディを、戦国時代以来よくやっていたのは薩摩藩士でした。ここから、上野の西郷隆盛像が連れている犬「ツン」が先生役で出てきてタイプスリップする設定を思いつきました。
このツンが三人を災害の場面に連れて行き、そして「もしこうならば」という問いかけをする。その問いに正解すると犬からカードのようなものがもらえてクエスト達成、現実の世界に帰ってこれる。こんなプロットなら、子どもにも興味をもってもらえるでしょう、と提案し、制作がスタートしました。


主人公たちを歴史的な災害の場面に連れていくツンは「現代で災害にあったら?」という問題も出してくれる。防災の情報は、数多くの防災・減災の著書、論考をもつ河田惠昭氏が監修。子どもはもちろん、大人にとってもサバイバルに役立つ知識が満載だ。
「マンガで印象的な津波のシーン」
――磯田氏は、マンガでとくに思い入れがあるシーンを見せながら、歴史から得られる教訓を紹介してくれました。

磯田 南北朝時代の記録では、(上のマンガのように)津波による引き波で海が陸になると、貝や魚がぴちぴちと地面をはねるので、それを人々が獲りに走ったという記録があります。しかし、江戸時代にはものすごい津波がくることがわかっているからやめるようになりました。
マンガでは、主人公のミチ君は、避難をすることができました。しかし、魚を獲りにいった当時の人々は津波に飲まれてしまいます。このように、小さいころから「もし災害がきたらこうするんだ」という心づもりをして、行動パターンを理解しておくことが大事です。
このシーンは、感情表現が巧みで素晴らしいと磯田氏。正面からではなく横向きで、つらそうに目に涙を溜めている。ここに、津波に飲まれた人々を目撃してしまった頼母先生の感情が見事に込められている。この本は、備前やすのり氏の作画によってよいものになったという。
「コンデンスミルクのような凝縮された本を作ろう」
――この本のこだわりのポイントはマンガだけではないようです。
磯田 昔の学習マンガのように、マンガの下の欄に豆のような小さな文字で「マメ知識」を入れてもらいました。子どもは文字が小さければ小さいほど読みたくなる。子どもは一個ずつ読んで、知識がひとつずつ入っていくのが楽しいわけです。
でも、大変なんですよ、豆知識を加えるっていうのは。この本を手に取るとわかると思いますが、情報量が多い。普通の本の3倍か4倍くらいはある。私は、そういうものでないと本じゃないと思っています。制作スタッフには、そういう知識のコンデンスミルクのような、濃縮された本にしようということを伝えました。
豆つぶのような文字の「マメ知識」がこちら。これら本書の情報は、優秀なライターと編集者の苦労によって、ページ内に凝縮されていると磯田氏。
「総合学習、生存に役立つ本」
磯田 「マンガでわかる災害の日本史」は、これまでお話ししたような志と方法でつくりました。学校の図書館に入れていただけるとありがたいですし、子どもたちの総合学習に最適です。医学、地学、理科、歴史、生活、全部を総合した情報です。サバイバルに役立つ。ぜひ、子どもたちや、学校の先生にも読んでほしいと思います。
お子さんや、親戚のプレゼントにもぜひ。実は私の子どもや、そのいとこたちにプレゼントしたのですが、一日手から離さずに読んでくれたそうです。私の本で、子どもが一日で読んじゃったというものはありません笑。
――残念ながらここでは紹介できませんが、ほかにも京都に本店を置く大垣書店のお客様に向けて京都の災害についての話がありました(応仁の乱などの戦乱による火災の話、京都に定期的に起こる地震の話など)。最後に磯田氏はこう締めくくりました。
磯田 コロナ禍で家に閉じこもらなければならず、皆さんに直接お会いできず残念です。ただ、家に閉じ込められても、本は読める。知識を増やして、有意義に楽しく生きていけるように、私はしていきたいと思います。皆さんもそうしてみてはいかがでしょうか。
本日はありがとうございました。
(文/高橋ピクト)
実用書の編集者。スポーツ、健康書を中心に、囲碁、麻雀、競馬、アウトドア、雑学などを担当することが多い。ワクワクする実用書をつくるのが目標。町中のピクトグラムが好きで、見たことがないトイレのピクトグラムを発見することに幸せを感じる。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?

