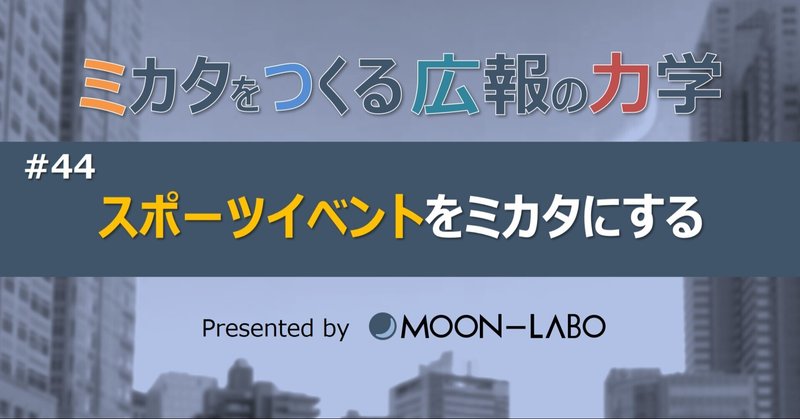
【ミカタをつくる広報の力学】 #44 スポーツイベントをミカタにする
今回は「イベント協賛」の話。夏から秋にかけて、競技大会や野外フェスなど様々なイベントが盛り上がってきます。
今はコロナの影響で残念な状況が続いていますが、こうしたイベントはPRの絶好の機会になりますので、協賛のメリットや提供先の探し方などについて書いていきたいと思います。
※初めての方は、「#00 イントロダクション」をお読みいただくと、コンセプトがわかりやすいかと思います。
イベント協賛のメリット
イベントといっても、スポーツ競技大会や野外フェス、フードフェスや美術展など、そのジャンルは多種多様。近ごろでは、夏季休暇の後にも秋のシルバーウィークがあって、イベントの機会はかなり増加しています。
今はコロナ禍で自粛傾向にはあるものの、いざ開催となれば多くの人が集まるのは想像に難くないでしょう。
コンテンツは様々ですが、そのイベントに集まる大勢の来場者に向けてPRするのがイベント協賛です。
イベント主催者と契約して協賛金を支払うと、協賛企業(オフィシャルスポンサー)になれます。
公式スポンサーになると、スポンサークレジットに名前が載るほか、コンテンツの著作権を得たり、チケットがもらえたり、広告枠がもらえたり、様々な特典が付いてきますが、一番のメリットは「協賛している」というファクトを広報活動に利用できることではないでしょうか。
自社の広告や名刺、パンフレット、ホームページ、あるいは商品パッケージなどにも、イベントロゴとともに「当社は○○大会を応援しています」と表明することができるのですから、イベント開催期間に限られてはいますが、短期集中でボリューム感のあるPRが可能になります。
ただし、目的とターゲットを間違えると失敗するので注意が必要です。
例えば、オリンピックやワールドカップのような国際大会は、いくら有名なイベントだとしても、海外展開している企業でなければとてもコスパの悪い施策になってしまいます。
自社の特徴と戦略を考えて協賛することが重要です。
オフィシャルパートナーの仕組み
イベントの協賛方法として最もシンプルなのは、上記のように協賛金を支払ってオフィシャルスポンサーになることですが、協賛には他にもいろいろな方法があって、オフィシャルサプライヤーもその一つです。
「オフィシャルスポンサー」と「オフィシャルサプライヤー」はどう違うのか。
「スポンサー」というのは基本的に「お金」を出す人のこと。
これに対して「サプライヤー」というのは「モノ」を提供する人のことを差します。
つまり、イベントにおいて使用する物品を無償または低価格で提供する代わりに、協賛企業を名乗らせてもらうということ。
言い換えると「物協賛」のことです。
コンテンツをつくったり、イベントを開催したりするのは、莫大な資金が必要なのはもちろんですが、場所や機材、消費財など、様々な物資も必要になるので、金銭以外の資材を提供することでも協賛企業となりうるのです。
テレビ番組や映画のクレジットでは、「衣裳協力」とか「撮影協力」と記載されているものがありますが、あれのイベント版と考えると分かりやすいかもしれません。
オフィシャルスポンサーとオフィシャルサプライヤー、どちらの立場も持つ場合には、「オフィシャルパートナー」と呼ばれることが多いようです。
国際的なスポーツ競技大会は、自社が誇る最新の技術を世界中に披露する場でもあるため、会場に設置される大型ビジョンや撮影機材、計測機器、選手のウェアなど、多くの資材が協賛企業から納入されています。
こういった場合は物協賛ではなく、むしろ納入業者となる権利も含めてパートナーとなるケースが多々あり、納入業者としてのビジネスチャンスを目的として協賛金を支払う企業も少なくないのです。
オフィシャルパートナーのケースが多いのは、万博のような比較的長期にわたるイベントや、テーマパークのような常設の場合。万博ではパビリオン、テーマパークではアトラクションの出展企業として参画します。
パートナー企業の業種も様々で、施設内で販売される飲料や食品、グッズ関連の他、警備や保険に関する企業、会場の通信や制御機器の関連企業、コンテンツに関わるメディア、施設近隣の交通機関、決済システムなど。
施設内で消費される資材の売上が確保できるわけですから、協賛が付くのも頷けます。
直接の売上目当てだけでなく、もちろんPRの場としても優れています。
神戸のコーヒー会社が1970年の大阪万博で世界初の缶コーヒーを販売して、それを機に多くの認知を得た話は有名ですね。
どんなイベントに協賛すべきか
では、どんなイベントに協賛すれば良いか。
「協賛」というのは本来、上記のようなビジネスライクなものではなく、「賛同して協力する」意味合いがあるので、そのイベントの趣旨に対して賛同できるかどうかが一番の争点になってきます。
現実的には、大人の事情やお付き合いの出資も多いですが、PRにおいてはストーリーがつくれる根拠が欲しいところ。
最近増えているのは、ピンクリボンなどのリボン運動や、LGBTQをはじめとするダイバーシティの推進活動など、社会課題に関する運動のオフィシャルパートナー。
昨今のESGの流れの中で、企業の考えやスタンスを表明するのにふさわしい場といえます。
そこまで大上段なステートメントではなく、もう少しカジュアルに応援したいという場合には、やっぱりスポーツや文化といったエンタテインメントが良いのではないでしょうか。
それでも自社事業と関係のあるコンテンツでないとストーリーづくりに苦労するので、企業理念やミッション、パーパス、クレド、事業内容などと照らし合わせながら選ぶと良いでしょう。
私が所属していた印刷会社は教育や出版関連が多かったため、美術展やミュージアムへの協賛が多かったのですが、得意先の新聞社から、共催している市民マラソンのオフィシャルサプライヤーのお話をいただいたこともありました。
そういう意味では、スポーツは協賛する企業を選ばない、万人受けするコンテンツかもしれません。一般的に「スポーツイベントの協賛金は高い」と思われていますが、探せば手頃な協賛メニューも存在します。
例えば野球のゲームスポンサー。
野球の試合というのは、どこの球場でもシーズン中であれば何かしらの試合をしているもので、その個別の1試合に限り、冠スポンサーになれるのが「ゲームスポンサー」です。
「ワンデースポンサー」と呼ぶ球団もありますね。
試合のランクによって金額は異なるのですが、数百万円程度で冠スポンサーになれてしまいます。
ゴルフの「○○カップ」のように、当日のゲームタイトルに企業名や商品名が入ります。他にも、球場内に広告が流れたり、商品サンプリングをしたり、始球式に参加したり、マスコットキャラクターと絡んだり。
場所も期間もターゲットもピンポイントですが、雑誌広告レベルの金額でこれだけ様々なファクトがつくれるなら、一考の価値があるのではないでしょうか。
もちろんスポーツイベントの中には、もっと低価格なものも、もっとユニークなものもあると思いますので、いろいろ探してみることをお勧めします。意外な掘り出し物が見つかるかもしれません。
おわりに
今回はスポーツイベントを中心にイベント協賛の話を書きました。協賛というシステムは、広告権の売買を超えて、とても柔軟に設計されています。
主催者側はなんとか資金を集めようとしているので、メリットも多彩にユニークに提案されます。考えてみたら「ふるさと納税」も一種の協賛。実に奥が深くて勉強になります。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
共感してもらえましたら、スキやフォローをいただけると励みになります。
ではまた次回お会いしましょう。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
