
3-3-1-1. モンゴル帝国後の西アジア・南アジア ティムールとは何者か? 新科目「世界史探究」をよむ
14世紀にモンゴル帝国が解体すると、その後の展開は一気に「いかにしてヨーロッパが経済的発展を遂げたか?」という内容一色となりがちだ。
しかし、それではいけない。
まずもって、この男、ティムール(1336〜1405)を忘れてはなるまい。
彼は14世紀末から15世紀初めにかけて、遊牧エリアと農耕エリアを一体として統治したモンゴル帝国の栄光の再現をめざし、トルコ系、モンゴル系の諸部族軍をとりまとめた指揮官である。
戦闘で右腿・右肩・右腕に矢傷を負い、右手・右足が不自由となったことから「ティムーリ・ラング」(片足が不自由なティムール)とよばれ、これが西洋における「タメルラン」(英語でタマレイン)の呼称のもととなる。
だが、現代のわたしたちにとって、ティムールという人をとらえるのは、なかなか難しい。
だがこの難しさ、よくわからなさそのものを、逃さず扱っていくことが大切だとおもうのだ。
ティムールを扱うことの難しさ。
理由その1。
まずもって彼の活躍した範囲が、現代の国境を越え出てしまっていることにあろう。
たとえば彼は、ウズベク人が多数を占めるウズベキスタンの紙幣にもなっている。
だが、実は彼自身はウズベク人ではないのだ。
ではどうしてウズベク人ではないティムールが、ウズベク人のシンボルとして讃えられるにいたったのだろうか?
そういった取り上げ方が考えられる。
【スタッフ】駐日ウズベキスタン大使館の客間にはティムールが鎮座しています。ティムールは、ウズベキスタンで未だに人気が高く、レギスタン広場のプロジェクションマッピングでは大歓声がおこるほどです。
— 嶌 信彦 (@shima_nobuhiko) August 26, 2021
俳優の鈴木亮平さんは #せかほし でティムール愛を熱く語られていました。#ウズベキスタン pic.twitter.com/OJaSdsb4rX

いまひとつの理由は、ティムール帝国の台頭が、世界史における時代の過渡期にあたることにある。
ティムールが亡くなる15世紀初めの時代は、東アジアでは明がユーラシア規模の商業ネットワークに見切りをつけ、ミニ中国を志向する一方で、鄭和がインド洋に繰り出し、マラッカ王国、アユタヤ朝、マジャパヒト王国、ヴィジャヤナガル王国といった諸国が貿易の利をめぐり角逐する「海の時代」の幕開けにあたる。
アジアの繁栄に誘引されるのが、ポルトガルという新参者。銃砲で武装した彼らも倭寇に加わり、交易のおこぼれにあずかろうと必死だ。
そのような時代にあって、かつてのモンゴル帝国の築いた、ユーラシアの草原と定住民の世界をつなぐ経済圏(森安孝夫氏のいうところの前近代世界システム)を復興させようとしたティムール朝は、どうしても前時代的にうつってしまう。
これがティムール朝がわかりにくい2点目の理由だ。
しかし、ティムール朝がその後の西南アジア・中央アジアにのこした影響は、実際には計り知れない。
こうした扱いの難しさを踏まえつつ、簡単ではあるが、ティムール朝の動向をたどってみることにしよう。
急拡大したティムール朝
シルクロードの幹線が走る中央アジアを支配していた中央アジアのチャガタイ・ハン国は、14世紀なかばのペスト(黒死病)の流行もあり政情不安定となり、東西に分裂していた。
チンギス・ハンがモンゴル帝国を築いたのが13世紀前半。
そしてユーラシア大陸の広域にひろがったモンゴル帝国が解体に向かうのが、14世紀なかば以降。
このうち西チャガタイ・ハン国の軍人であったのティムールが登場するのが、14世紀末のことだ。
14世紀半ばは、世界的に天変地異の相次いだ時期にあたる。
たとえば世紀末にかけて中国では元が滅び明に交代。朝鮮半島では高麗が滅び朝鮮が建国、日本でも長引いた南北朝時代が長引いている。
彼はすでに解体していたイル・ハン国なきあとのイランやイラクを制圧し、さらには北インドのデリー・スルタン朝や、エジプトのマムルーク朝にも侵入。そして現在のトルコからバルカン半島にかけてを支配していたオスマン朝にも挑み、アンカラの戦いでこれを破った。
彼の夢はモンゴル帝国を再現すること。
明をめざして遠征するも、夢半ばで病死してしまう。
歴代君主はイラン系のイスラーム教徒定住民の経済力や文化を認め、学芸や
商工業が発達した。
チンギス・ハンの征服以降破壊されたサマルカンドも、壮麗な大都市に蘇った。
歴史教育の世界では、一部の民族に植え付けられていたイメージを払拭しようとするあまり、かえって白か黒かの評価を植え付け直してしまう傾向がある。「モンゴルが残忍な虐殺をおこなったわけではない」という判官びいき的な言説もそのひとつだ。
もちろんモンゴルが常に殺戮ばかりをおこなっていたわけではないが、彼らの侵入により中央アジアの人々は、実際に甚大な被害を被ったのである。
1221年サマルカンドを訪れた長春真人一行は「城内〔すなわち市壁内〕の戸数」が四分の一に減ったと聞かされている。
モンゴルの侵入によって、中央アジアのほとんどすべての都市は破壊され、住民は殺された。サマルカンドの住民は、1500年以上も自分たちの町のあったところに、町を復興することはできなかった。新しい町ができたのは現在のサマルカンドの地で、古い町は放棄され荒廃し、アフラシアブとよばれる廃墟になった。モンゴル人は中央アジアの灌漑施設の大部分を破壊した。そのために、中央アジアの住民が2000年間につくりあげたオアシスは、砂漠の砂に埋もれてしまった。
(中略)
しかし、まもなく、旧サマルカンド(アフラシアブ)の南に新たにサマルカンドの町がつくられたらしい。13世紀後半に、サマルカンドに来たマルコ・ポーロは、サマルカンドのことを大きな有名な都会だといっている。
このサマルカンドの城壁を修復したのがティムールであった。
ティムール時代の歴史家は、「かつてサマルカンドのすべての建物は泥と木であったが、この強国の時代には、多くの建物が焼いたレンガでつくられた」と伝えている。
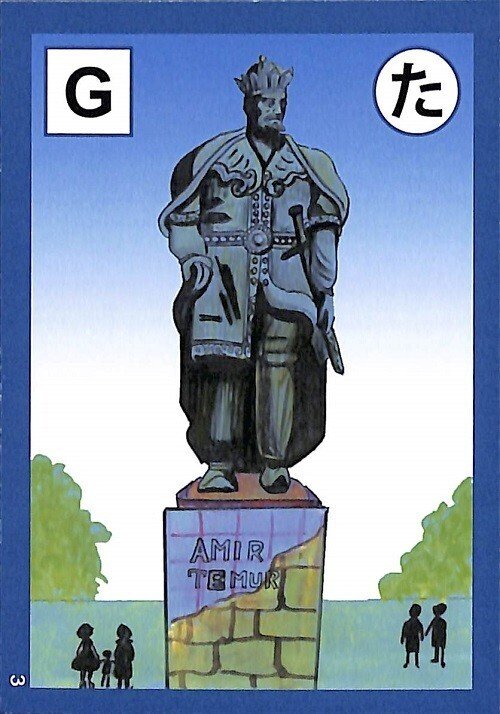


またティムールのもとでは、交易の発展を促すべく交通路が整備され、駅逓制度も十分に整えられていた。道中の治安の良さについて、一人の寡婦が二人のインド人奴隷のみをともなって、カンダハールからはるかディヤールバクル(現トルコ共和国東南部)まで商用旅行を成しとげた、という逸話を紹介するだけで十分であろう。ティムール最晩年の1404年、クラヴィホによれば、中国の明朝、エジプトのマムルーク朝、アナトリア諸侯、そしてはるかイベリア半島のカスティリャの使節が、ティムール帝国の首都サマルカンドを訪れていた。まさに”すべての道はサマルカンドに通ず”とでもいうべき状況が生じていたのである。
また、第4代のウルグ・ベク(1394〜1449)はサマルカンドの郊外に最新鋭の天文台を構え、正確な暦を作成した。
ティムール帝国の文化は、教科書的には「イラン・イスラーム的な都市文化と、トルコ・モンゴル的な遊牧文化が混じり合い、トルコ・イスラーム文化(ティムール朝文化)が花開いた」と説明されるが、これまたピンとこない。
そもそもチャガタイ・ハン国の時代に、中央アジアに移り住んだモンゴル人たちは、特に言語面でトルコ人たちに同化する傾向があった。
彼らは遊牧民としての気風を重視し、定住して宮殿を立てようとした君主に対しては、「定住民になるとは何事だ!」と非難の声があがるほどだった。
しかし、都市の商業を保護し、農耕民の領域を支配しようとするならば、定住民の発達させてきた文書行政を受け入れる必要があるのはいうまでもない。イラン高原からアム川流域にかけての地域では、ペルシア語を話す定住民の強力が不可欠だ。
そこで両者が学び合う中で、独特なティムール朝文化が生み出されていったわけである。
ティムール朝の滅亡―ウズベキスタンとティムール
15世紀後半にティムールの王朝は分裂し、トルコ系のウズベク人に滅ぼされた。ここが後にロシアに支配され、現在のウズベキスタンにつながる。
ティムールへの憧憬や畏敬の念は、ウズベキスタンをはじめ現代アジアにおいても非常に根強く、それゆえ20世紀末、この地がソビエト史観・大ロシア主義のくびき[くびきに傍点]から解放されたときには、人々のティムールへの思いがあふれかえった。いま彼らの偉大なる祖先は自らの誇りと威厳を取り戻し、その巨大な銅像やその名を冠した建造物が、この地を訪れる人々を迎えてくれる。
モンゴル帝国を継承しようとしたティムール。
彼は、現在ウズベキスタンの人々にとっては、ロシア以前の支配者ということで、民族的な英雄として讃えられるようにもなっているのだ。
インドとティムール
インドには、16世紀にムガル帝国という王朝ができる。
ムガル帝国の后の墓であるタージ・マハルのポスターが、よくインドカレー屋に貼られていることから、ムガル帝国はインドにもともと住んでいた人たちのつくった国であると思うかもしれないが、それは大間違いだ。
ムガル帝国は、中央アジアからやってきたティムール朝がつくった、「第二次ティムール朝」とでもいうべき王朝なのである(そもそも「ムガル」という通称も、「モンゴル」の訛ったものである)。
(前略)アフガニスタンでは、ティムール朝の生き残りであるバーブルがティムール帝国の再興をめざしてカーブルを拠点に活動していた。かれはウズ・ベグに対して何度も反攻に出るが成功せず、ついに中央アジアをあきらめ、新天地を求めてアフガニスタンから北インドに進出する。こうして、1526年、バーブルはムガル帝国(1526〜1858)を創建し、かれの子孫が帝国に降臨した。このような経緯から、ムガル帝国を「第二次ティムール帝国」「インドのティムール帝国」と呼ぶこともできよう。こうして、それまでティムール帝国により統合されていた中央アジアから西アジアにかけての広大な地域は北インドを巻き込んでいくつかの大勢力により再編される時代を迎えたのである。
バーブルの評伝にも、つぎのような解説がある。
なお、「ティムール朝の滅亡」といっても、バーブルがインドに創設したムガル朝は、バーブルをはじめティムールの子孫たちが君臨した王朝がある。それゆえ、ムガル朝を「インドのティムール朝」ないし「後期ティムール朝」と呼ぶこともできる。そのように見るならば、ティムール朝は16〜19世紀、新天地インドでなおもその命運を長らえたともいえる。ムガル朝の君主たちも自らがティムールの子孫であることをなによりも誇りにしていた。
バーブルは本当はサマルカンドをとりかえしたかった。
そのことは、彼の、つぎのような記述からもうかがえる。
――サマルカンドは驚くほど美しい都会である。そこには、他の多くの都会では見られない一つの特徴がある。すなわち、各種の商業や工業は、それぞれ定まった街区でおこなわれ、入りまじっていない。習俗は美しい。良いパン工場や酒場がある。世界で最上の紙はサマルカンドでつくられる……サマルカンドのもう一つの製品は、イチゴ色のビロードで、それはあらゆる国に輸出される……サマルカンドはブドウ、ウリ、リンゴ、イチジクなどの見事な果実を多量に産する。また他のあらゆるくだものもよろしい。とくに、サマルカンドのリンゴと〈サヒビ〉(ブドウの一種)は有名である。
このたびはお読みくださり、どうもありがとうございます😊
