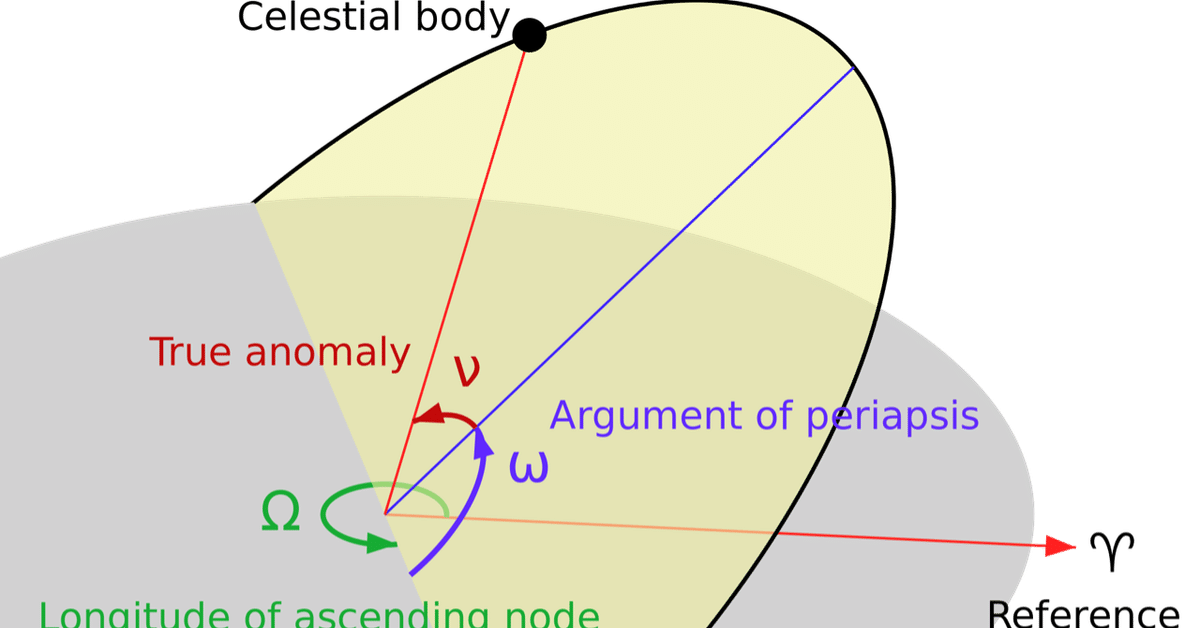
9.2.4 科学革命と近代的世界観 世界史の教科書を最初から最後まで
16世紀にアジア・アメリカに乗り出し“視野”をひろげたヨーロッパ世界は、17世紀になると「科学革命」と呼ばれる時代を迎える。
“わけがわからない”ことを“わけがわからない”ままにするのではなく、“キッチリわかるところまで、理詰めや観察で突き詰める”考え方(近代合理主義)が確立されていったのだ。
天体の動きを観測し、すべての物体の間には、その質量に応じて引き合う力が働いているのだという「万有引力(ばんゆういんりょく)の法則」を導いたイギリスのニュートン(1642〜1727年)は代表的な自然科学者。

中世以来の研究の進んでいた錬金術(れんきんじゅつ)にも手を出していたものの、観察した結果を「数式」で表すことで、目には見えない力の存在を導き出した点は、斬新だった。
一定の条件におけるさまざまなケースを観察し、そこから法則を導き出す方法を「帰納法」(ディダクション)という。
世界の物事を認識するためには、なにより世界の物事についていろんなかたちで経験することが重要だとしたイギリスのフランシス=ベーコン(1561〜1626年)の発想は、ニュートンをはじめ多くの人々に影響を与えた。

その一方、「とはいえ経験が必ずしも当てになるとは限らない。人間の感覚というのは、不正確なことも多い」と指摘したのはフランス人のデカルト(1596〜1650年)。
「じゃあどうすれば真理に迫ることができるのか?」ということを考えたときに、彼は「われ思う、ゆえにわれあり」(いま自分が頭を使って考えている。考えている自分がいるということ自体は、少なくとも疑うことはできない。この考えている私こそが、真理に至る出発点だ)ととらえた。
「なーんだ当たり前のことじゃないか」と思うかもしれないけれど、『聖書』の記述や信仰、迷信や悪弊などにとらわれず、「頭を使って合理的に考える方法を考えよう!」というのは、当時の人々にとっては、まさに“革命的”だったのだ。
この時代の人々の好奇心は、人間社会そのものにも向かう。
ヨーロッパ人がアメリカやアジアで出会ったのは、常識を超越するような人々。

とても同じ人間のようには見えないときもあったけれど、よくよくみてみるとまぎれもなく同じ人間だ。
ライフスタイルも価値観も違う人間同士に、共通の「決まり」があるとしたら、それはいったいどんなものなのだろう?
「人間なら、いつの時代もどんな場所でも、守るべき不変のきまり」(自然法)というものはどんなものだろう?
そんな議論が盛り上がっていく。
もうひとつ、この時期に流行った学説に、社会契約説がある。
「国の統一的な支配を進めようとするヨーロッパの君主に対し、個人の自由はどこまで守られるべきか?」などといった問題が浮上する中、「そもそも国というものは、どういう事情から生まれたものなのだろうか?」「どのような国家のあり方が望ましいのだろうか? その成立の事情から考えてみよう」と思索する学者が現れたのだ。
もちろん、はるか昔の時代のことなんてわからないからフィクションではあるんだけれど、さまざまな人が「自然状態」(国がまだなかったころの人間たちの状態)を想定した。
そんな状態、どうやったらわかるのだろう?
たとえばイングランドのホッブズ(1588〜1679年)という人は、冒頭に挙げたように、人間の社会を合理主義的にとらえ、 その謎を解き明かそうとする。
史料 ホッブズ『リヴァイアサン』冒頭(光文社新訳文庫より引用)
自然とは、天地を創造し支配するために、神が用いる技のことである。人間の技術はさまざまな事柄において自然を真似る。そうした模倣によって人工的な動物を作ることもできる。「人工的な動物」という言い方は奇異に聞こえるかもしれない。だが、生命とは四肢の運動のことであり、その運動は内部の中心的な部分から起こる。それを踏まえるなら、「すべての自動機械(たとえば、腕時計のように発条と歯車によって自動的に動く機械)は、人工的な生命を持っている」と説明したからといって、何の差し障りがあろうか。なにしろ、心臓、神経、関節に代わるものとしてそれぞれ発条、線条、歯車があり、それらのおかげで全体が制作者の意図したとおりに動くのだから。 人間の技術はそれにとどまらない。模倣の対象は、理性をそなえた被造物、すなわち自然の最高傑作とも言うべき人間にも及ぶのである。実例を挙げよう。まさに人間の技術によって創造されたものに、彼の偉大なるリヴァイアサンがある。リヴァイアサンは国家と呼ばれている(英語ではコモンウェルスまたはステイト、ラテン語でキウィタス)が、実は一種の人造人間にほかならない。自然の人間よりも巨大かつ強力であり、自然の人間を守ることを任務としているところに特徴がある。
この人造人間は主権を人工の生命としている。それは全身の活力と運動の源泉である。為政者や司法・行政を担当する官吏は、人工の関節である。賞罰は、関節や器官を一つひとつ主権という中枢部に結びつけ、それぞれの義務を遂行させるので、神経に相当する。その働きは人体における神経と同じである。個々の構成員が蓄える富や財宝は、生身の人間であれば体力に相当し、人民の安全を図ることは、人間で言うなら職務に相当する。国家にとって知る必要のある事柄を漏れなく教えてくれる顧問団は、[脳内の]記憶装置の役割を果たしている。公平と法律は、いわば人工的な理性と意志である。国内の調和は人体の健康、騒乱は病気、そして内戦は死に相当する。
どうだろうか。
人間社会ってのは機械みたいなもんであり、その運動によって成り立っているのが国家だ。
つまり、国家を理解するには、その“部品”たる人間とは何かが分かればよい。
…というわけで、ホッブズの考察は、人間の心理へと進んでいく。
おもしろいのは、ホッブズが「人間の思考や感情は相互に似かよっている」と言っていることだ。
人間ってのは、だいたいみんな似たようなものだから、難しく考える必要はない。自分自身を知ろうとすれば、それがほかの人々を知ることにつながるというわけである。心の作用が国家というよくわからない人工物を生み出すのだとすれば、そのメカニズムを深掘りしよう。ホッブズはそのようにアタリをつけた。
すなわち、まず自分自身の内面を見つめることである。そして、自分自身の思考・推論・期待・恐怖が究極的に何を意味しているのか、また、何に根ざしているのか、それを考察するがよい。そうすれば、自分と同じ状況にある人間の胸中を読み取り、知ることができよう」。 念のために言っておくが、私が述べているのは、欲求・恐怖・希望など万人に共通する感情の仕組みが似かよっているということであって、感情の対象──平たく言えば、何に欲求・恐怖・希望を感じるのか──が似かよっているということではない。
こうしてホッブズは、自然状態を「国がなかった頃の人間たちは、自分や味方ことばかりを考え、限られた富を奪い合う状態(万人の万人による闘争)だった」との推論に至る。でも、それじゃあ怖い。だから人間はその状態を避けようとする。そうして自主的に自分が生まれつき持っている権利を「ひとつの存在(主権者)」に委ねる形で、「国家」があらわれてくる。

ようするに「国家」というのは、個々にバラバラな「個人」という要素が集まってできたものなんだという発想だ。

ホッブズの『リヴァイアサン』の表紙には、たくさんの人々が集まって「リヴァイアサン」という強大なパワーを持つ怪物(たった一人の主権者)を構成しているイメージ図が掲載されている。
ホッブズの世界観は突飛に聞こえるが、機械論的に世界をみようとする当時の潮流に根差したものだったといえるだろう(2022/12/28追記)。
一方、違った方向から国家の成り立ちについて考えた思想家もいる。
イングランドで名誉革命が起きた時に活動したロック(1632〜1704年)だ。

彼は、「もともと人々は、自分たちの自由や財産を守るため、それを保護してくれる政府に支配を“任せる”契約を結んだのだ。でも政府が勝手なマネをして、約束を守らない状態であれば、人々には政府を倒す権利(革命権;抵抗権)がある」と主張した。
その後のヨーロッパ諸国において、商工業で富を増やす資本家の影響力が強まると、「自由に競争することを良しとする社会」が、どのような決まりに基づいて運営されるべきかという議論も高まっていった。
「自由に競争することを良しとする社会」というのは、固定的で落ち着いた身分制の社会とは打って変わって、流動的で落ち着きのない社会だからね。
その中で、「市民中心の新たな時代を生きるために必要な道徳」について主張したのが、ドイツの哲学者カント(1724〜1804年)だ。

彼は、固定的な価値観が揺らぎ激しく変化する社会の中で、経験論のように感覚だけを重んじるのでもなく、合理論のように知性のみを重視するのでもなく、両者をドッキングさせようと試みた。
そのためにまず、「人間というものは、自分や世界について、どの程度まで正しく認識できるのだろうか? 認識できない部分があるとしたら、それはどこまでだろうか?」といった根本的なところを、突き詰めていく。
伝統的な秩序が崩れ、みんなが共有していた常識が崩れたとき、果たして人間は「正しい判断」を下せるのだろうか。
利益を追求し合い、互いに弱肉強食を繰り広げる資本主義的な競争の中で、守るべきルールとは何なのだろうか、と。
彼の結論はこうだ。
人間には、生まれたときから備わっている「認識の枠組み」のようなものがある。形とか、大きさとか、属性や形式を表すための枠組みだ。
人間はこの「認識の枠組み」を通して、外界の事物を認識する。
逆に言えば、あらゆる事物は、人間の「認識の枠組み」を通してしか、認識することはできない。
つまり、「認識の枠組み」を通過する前の “事物そのもの”(カントは「物自体」と呼ぶ)に直接ふれることはできないし、そもそも「認識の枠組み」の対象外のものについては認識すらできないということになる。
ということは、あらゆる事物は、それを認識する人間の「判断枠組み」によって決まるということになる。
つまり、「事物というのは、認識されることによって、構成される。まあ、ひとまずそういうことにしましょうや」というわけだ。
これは大変な発想の転換だったわけなので、天文学におけるコペルニクスの地動説になぞらえて、「コペルニクス的転回」とも呼ばれるよ。
この転回がもとになって、この世のすべての事物は “認識される限りにおいて” 人間の記述の対象範囲に含まれることになっていくわけだ。
このたびはお読みくださり、どうもありがとうございます😊
