
【ニッポンの世界史】#36 世界史が語る国際政治や文明の衰亡:高坂正堯と塩野七生
世界史化する時事論壇
1980年代以降、論壇誌や政府関係の刊行物、ビジネス系の雑誌に引っ張りだことなった女性がいます。
小説家・塩野七生(1937〜)です。

たとえば1989年に安田信託銀行調査部の発行した刊行物に塩野のインタビューが載っています。
一口に云って、EC統合というのは既に歴史的に確立あれているヨーロッパを守ろうとする、防衛的な動きなのです。古代ローっまは現在のヨーロッパの領域に中近東や北アフリカも加えて、次々に拡大して行ったのですが、ECはこれとは逆に16世紀に国境線によって解体されて行ったヨーロッパを、もう一度元の姿に戻そうとするもので、日本や米国との経済競争に生き残ることがその狙いです。古代ローマ滅亡後の、中世と呼ばれる1000年間、ヨーロッパには今日のような国境はなく、ヒト、モノ、カネが自由に行き来していました。ベネチアの商人がシャンパーニュの市場に物を売りこむようなことが極く[ママ]自然に行なわれていましたし、レオナルド・ダビンチがフランスの王侯のもとで死ぬなどということも、決して奇異なことではありませんでした。ラテン語という共通語も大いに役立っておりました。ところが16世紀になって、勃興するオリエントの強大な国家にこの体制では対応できなくなり、それぞれ国境線を明確にし互いに鎬を削りながら、近代国家群が興隆して行くことになるわけです。しかしこの近代国家群も、今や衰退しつつあり、外からの新たな挑戦に対応して行くためには、もう一度元のボーダーレスの体制に戻す必要が出て来たのです。
もちろん塩野は国際政治の専門家ではありませんし、歴史学を修めたわけでもありません(先行は池田理代子とおなじく哲学)。本人がアイデンティティとするように、彼女は西洋をモチーフとする物語を編む作家です。
少し前の時代なら、こういうところにわざわざ塩野のような人物は呼ばれません。歴史といっても人々の関心は西洋史よりも日本史、あるいは中国史(→#25 越境する中国史:陳舜臣のユーラシア的想像力)にあった時代です。
もちろん1970年代には『背教者ユリアヌス』(1974)やルネサンス時代のフィレンツェを舞台とする『春の戴冠』(1977)を送り出した辻邦夫(1925〜1999)のような作家も現れてはいますが、塩野のようなポジションではありません。
じつは塩野自身、作品と時事的な論評を安易に結びつけるのはお門違いであって、作品を現実世界とつなげようというつもりはまったくないと、さまざまな作品のなかで語っています。
にもかかわらずその素ぶりとは裏腹に、塩野は多くの作品のなかで頻繁に現代の日本や世界の事象とのアナロジーを示しています。
たとえば『海の都の物語:ヴェネツィア共和国の一千年』(1980〜81年)では、一見はるか遠いヴェネツィアが日本に、オスマン帝国がアメリカであるかのように論じられます。そういった作風は同じ資料を読んでいても歴史学者だったらできない芸当であるとして、読者を増やしていきました(実際には塩野の解釈には数々の問題があるわけですが、現在にいたるまでそのこと自体ほぼ等閑視されています)。
***
以前ふれたように、歴史小説をよむ読者層の多くはサラリーマンでした。もちろん従前のように歴史を人間的修養ととらえる向きや、エンターテイメントとして消費する向きもあったでしょう。他方で、特に司馬遼太郎の築いた歴史小説の市場は、歴史を総合的な「教養」として吸収し職業人・組織人としてのキャリアに活かそうとする読者を育てていきました。
そもそもそれ以前の時代小説の多くは忍者ものや剣客もののような架空の設定がほとんどで、史実に迫る点を売りにした作品は珍しかったわけです。そうした素地がなければ、歴史ファンの厚みもふくらむことはなく、西洋史を舞台とする歴史小説が大衆的にすんなり受け入れられることはなかったでしょう。
しかし、なぜ1980年代にかけて「西洋」に関する作品への注目があつまったのでしょうか。
そして塩野はなぜ、みずからの物語が時事論評に結び付けられることを嫌いながら、同時に時事論評の場に顔を出して「歴史」を語ろうとしたのでしょうか。
今回はこれらの問いを通して、現在の「ニッポンの世界史」に連なる水脈を掘り下げてみようと思います。
文明に対する関心の高まりと、高坂正堯の活躍
大きな要因は、1980年代の日本で「文明」の興亡に対する関心が高まったことにあります。
敗戦から復興を経て、1968年にはGNPが西ドイツを抜いて世界第2位となり、短期間で経済大国にのぼりつめたことは、文明の浮沈を日本人に強く意識させることとなりました。同時に1970年代には石油危機や高度経済成長の歪みがあらわとなった時代です。成長の限界や終末論が叫ばれる中、超長期的な視野のもとで文明の成り行きを見定めようとする想像力も育っていました。
そして世界に目をやれば、超大国アメリカのドルの覇権にヒビが入り、ベトナムも泥沼化している。他方、ユートピアと思われた社会主義国の内実も、はなはだもって理想との落差がある。
そんな中、NHK教育テレビの番組で1985年3月18日に「新・文明が衰亡するとき」というスペシャル番組が制作・放映されました。
出演者は第1〜3回を通して国際政治学者の高坂正堯(1934〜96)。共演者は以下の通り。内容は確認できませんが、なんとウィリアム・マクニールも出演しています。
1985年03月12(火) 午後08:00 〜 午後09:00
「(1) 「繁栄の条件」―ヴェネツィアそして日本―」
高坂正堯、塩野七生、ウィリアム・マクニール1985年03月13(水) 午後08:00 〜 午後08:50
「(2) 「安定の落とし穴」―イギリスそして日本―」
高坂正堯、アンソニー・サンプソン1985年03月14(木) 午後08:00 〜 午後08:50
「(3) 「巨大なるものの崩壊」―ローマ帝国そしてアメリカ」
高坂正堯

いまと比較すれば比べものにならないほど学者に対するリスペクトが高かった時代。そんななか高坂は積極的にメディアに出演し、この番組でも体を張ったロケをし、わかりやすく説明をし、与えられた役をこなそうとしました(森田吉彦がNHKのライブラリーをもとに高坂のテレビ出演の変遷を論じている)。
***
ところで高坂と共演した塩野七生は、このときのことを財務省の広報誌のエッセイに綴っています。
台本をわたされた私は、まず苦笑してしまった。私が書いたヴェネツィアが見事に切りきざまれて、エッセンスだけ随所に点在していたからである。
しかし、こんなことはどうでもよい。あくまでもベースにされているのは高坂さんの著作で、私のものではないのだから。
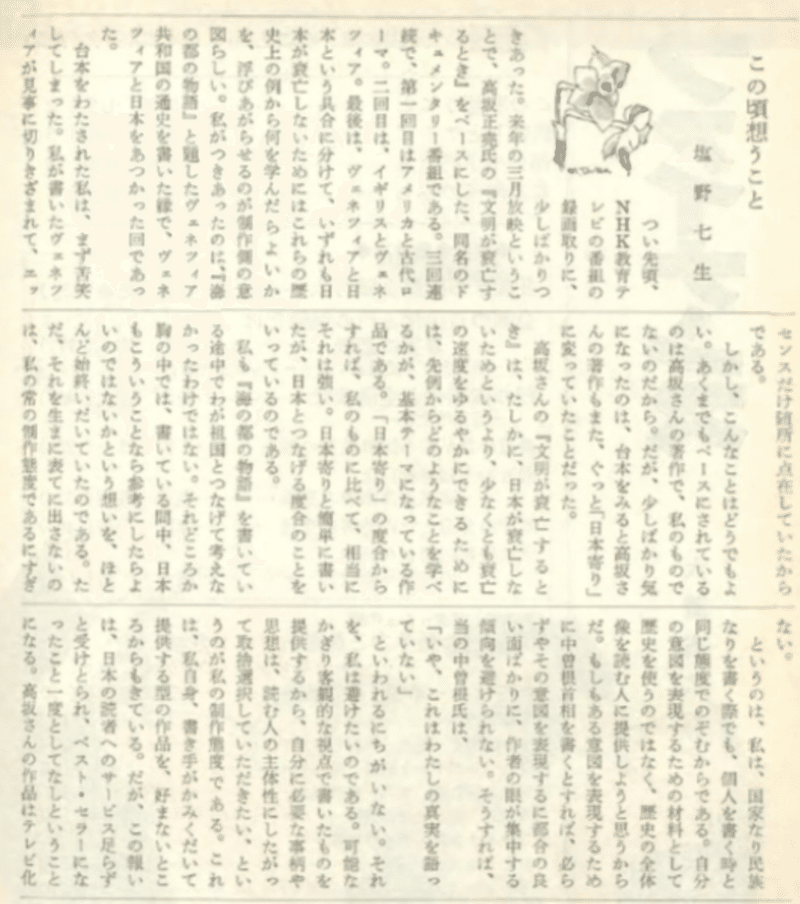
ここでいう「高坂さんの著作」とは『文明が衰亡するとき』(初版1981年)のことだ。
高坂の著作のなかで、塩野の『海の都の物語』は、ほかの歴史学の文献とほぼ同列に複数の箇所で引用され、論に組み込まれている。高坂の番組に呼ばれたのも偶然ではありません。
ですが、先ほどのエッセイからもわかるように、塩野は作品を時事論評にひきつけられるのをひどく嫌います。
朝日新聞の書評で憧れの文学者・篠田一士(1927〜89)に「きわめてアクチュアルな現在性」があるとされたとき、これに感謝しつつも「今日的意義」など意識して書いてはいないし、これから書くつもりもないと愚痴をこぼしています。
ビジネスマン必読の書に、一時にしてもなったのはけっこうだったが、これは、衰亡論流行と時を同じくしていたためであろう。「通商国家日本の将来」とか、「転換期に強い組織」なんて企画があると、必ずと言ってよいくらいにお座敷がかかってくる。
「経済界財界のVIP」賞賛を前に、なぜ書いたかと問われれば、こんなふうに答えて来たということです(具体的には通産官僚の天谷直弘(1925〜94)と対談し、英語版『通産ジャーナル』を通して海外からも声がかかったという)。
「国体を変えないで、あれほど長続きした国は他にないからです」
盛者必衰は、歴史の理(ことわり)である。現代に至るまで、一例も例外を見なかった、歴史の理である。
それを防ぐ道はない。人智によって可能なのは、ただ、衰退の速度をなるべくゆるやかにし、なるべく先にのばすことだけである。
本人が言うにはこれは「本心」ではない。物語を通して「教訓」めいたことを訴えるつもりはない、といいます。
ただ、おそらくそれは正確ではありません。
そもそも『海の都の物語』を読んで、「資源にめぐまれなかった島国」ヴェネツィアが大国に揉まれながら戦略的に発展していく様をみて、日本のアナロジーとして読めないことのほうが難しい(たとえば上巻257頁)。
つまり塩野が嫌うのは、物語に今日的意義を与えることではありません。作者自身がわかりやすい形で与えているわけですから。
では彼女がほんとうに嫌うものは何か。それは、物語になにか別の権威(それはたとえば朝日新聞であったり文学者であったり通産官僚であったり、歴史学者であったりする)が勝手に今日的意義を与えること、これです。
歴史は「物語」であるという姿勢
1980年代の塩野の話はこれくらいにしておきますが、周知の通り、最大のヒット作『ローマ人の物語』(1992〜2006年)が、まさに日本という文明が下降線を描くなかで著されることになります。
これを通して塩野は、かつてのように時事論評と距離を置くのではなく、積極的に「文明」について語るようになっていきます。刊行の終盤に同時多発テロがあり、アメリカを帝国のアナロジーで見る向きが強まったことも関係しているでしょう。
同時に注目されるのは、塩野が「歴史=物語」をいわば聖域化する姿勢も強めていくことです。たしかにその姿勢は初期の頃からみられます。たとえば『海の都の物語』の単行本刊行に際して、次のように述べていた。
第一作を書いた当時から、一貫して私の制作態度の根底をなしてきた考えは、歴史は娯楽である、ということにつきる。なにもわざと面白い事象ばかり取りあげなくても、それ自体ですでに面白いのが歴史である。教訓を得る人は、それでよい。しかし、歴史から学ぶことになど無関心で、ただそれを愉しむために読む人も、私にとって大切な読者であることには変りはない。いや、そのような人を満足させえてはじめて、真にためになる教訓を与えることも可能なのだと信じているくらいだ。
それからおよそ30年、2007年の対談における発言では、次のような発言がみられます。
「学者の歴史研究は大勢の方々がそれぞれの専門分野別で書き分ける場合が多いですが、私はなぜローマ史を一人で書いたのかと聞かれれば、一人の見方で一貫しないと、歴史の複雑な現象は描ききれないと思うからです。トインビーは、「不完全であるかもしれない。しかし、通史は一人で書いた方がいい」と言っています。」
「私は一度たりとも学者に挑戦したことはないんですよ。私が書いたのは、あくまで作家が書いた歴史です。学者が書く歴史と作家が書く歴史のどこが違うかといえば、人間に対する興味が作家の方が断じて強い。ですから作家が書いた歴史作品では、登場する人間たちが生きてくるということはありえます。」
これまでの塩野の発言を総合すると、次のように成立することができるでしょう。
歴史は本来、人物を生かす物語であるが、歴史学者にはそれができない(たとえばマルクス主義的な歴史学は人物を活写しない)。
作家が書いた歴史は、歴史のもつ本来の娯楽性を守り、多くの人に届けることができる。
それを受け取った人は、あるいは楽しみ、あるいはおのおの教訓を感じることができる。
だが、読者がどのような教訓を得るべきかは、なにか外的な権威が決めることではない。
1980年代にはマルクス主義への批判から、理想主義に代わり現実主義への傾斜がみられるようになりました。前々回みたように、その一旦が国家や文明の衰亡を説く地政学でした。
塩野の作品は、小さな海洋国家と大きな大陸国家の歴史を、人物を通して描くことで、本人の意図とはかかわりなく結果として、高坂の言論活動とともに人々の地政学的想像力を受け止める作品を世に表しました。
そうして人々が、たとえばヴェネツィアを日本と読み替え、日本の運命をヴェネツィアに重ねる物語を「歴史」として受け取る方法を学習し、おなじく経営者や政治家が、物語や作者の主張と渾然一体となった「歴史」を通して国際政治や政策を語ろうとする様子は、まさしく今日の日本の世界史受容ともよく似ています。
世界史がわかれば未来がわかる。
世界史がわかれば日本がわかる。
「国際化」のなかで、世界史がわからなければ、とりのこされてしまう。
1980年代は、そういった需要が前景化していくことになる時代なのです。
このたびはお読みくださり、どうもありがとうございます😊
