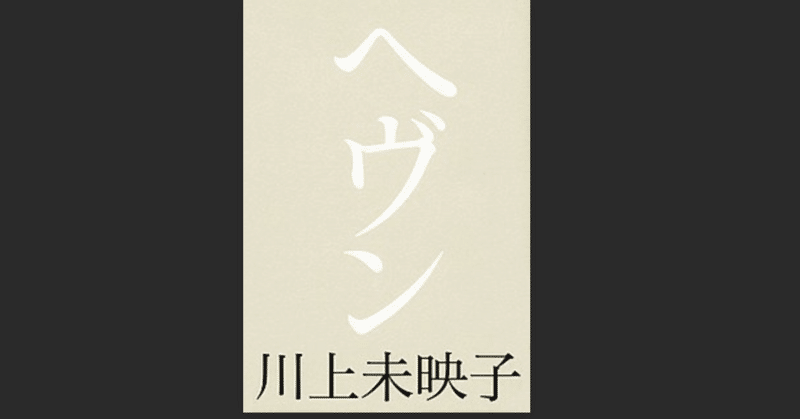
弱者をいじめる理論
「いじめられ、暴力をふるわれ、なぜ僕はそれに従うことしかできないのだろう ー 善悪の根源を問う、著者初の長編小説」。Amazonでそう説明されていた『ヘヴン』は読み応えのある小説だった。
この小説で最も印象的だったのは、いじめを行う側の論理で、百瀬という少年が述べる事柄だ。率直に言って、百瀬はいじめによって人を傷つけることには多少の罪悪感も持ち合わせていない。「たまたま」そういう欲求があっていじめただけで、そこにはいじめられる相手が「斜視」であろうとなかろうと、別に理由などないと言う。
どれだけ他人を引き刷り込むことができるか、圧倒的に有無を言わさず、自分の枠の中に取り込むことができるかが問題であって、それが気に入らないならば、自分で自分を護るしかないという理論が百瀬の言葉に現れる。
「いいとかわるいとかじゃなくてさ」と彼は言う。「そういうのってあらかじめ区切られたことなんだよ。都合よくね。相手の立場に立って行動しろなんてことが言えるのはそういう区別のない人間、矛盾のない人間だけだ。でもそんな人間がどこにいる?いないだろ?」
自分でものを考えることもできない、自分で自分を護ることもできない、そんな人間につべこべ文句を言う資格はないと言うことを百瀬は言う。
それを聞いて、そんな言葉をいろいろな国で聞いたことを思い出した。これまで旅したいろいろな国で。そしてその多くは、開発途上国とか第三世界とか呼ばれている国で、そこには少数の支配者がいて、支配される者たちとの間に一線を引いている。
「お前たちが自分で自分を護れないから、国が護ってやってるんだ」と支配者たちは言う。もちろん国は護ってなどいない。一部の人間たちが弱者から搾取するそんな構造があるだけだ。
『ヘヴン』のAmazonレビューでは、このような強者の論理に対して「たわごと」だと述べているものがある。「よく読んでいる哲学者の言葉がそのまま出ているだけの幼稚なたわごとにすぎない」のだと。
けれど本当にそうだろうか?このような理論をあたりまえに振りかざす支配者は多くいる。そしてこの百瀬の言葉を借りるなら、商売女を買う男たちは、その女たちの父親の身になって考えることなどしない。つまり自分がされて嫌なことを人にはしないという論理は成立しないのだと指摘する。
人間とその行為の善悪についての奥深い問題を、この小説は問い続ける。
そして人の弱さについて、あきらめるのではなく自ら「受け入れる」という言葉が登場する。
主人公が虐待を受けて、それでもその拳に掴んだ石を相手にぶつけなかったという選択にも、読者は考えさせられるだろう。善とは。悪とは。そして勇気とは何なのかを問いかける力強い作品だ。
サポートは株式会社スクーンジャパンおよび米国スクーン社が乳がんのNPO団体(LBBC)に寄付する資金に利用させていただきます。
