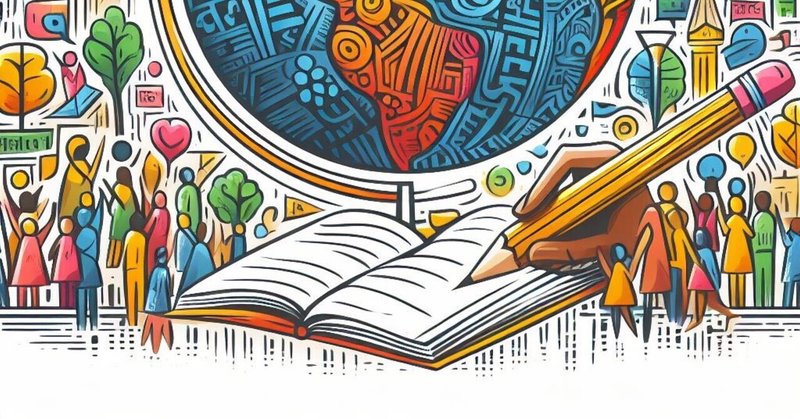
ナラティブとクリティシズム(4)(2023)
5 物語の誘惑
先の大戦をめぐる「わかりやすい物語」に共感しない人であっても、「陳腐な物語」の魅惑に抗いきれないことも少なくない。そうした物語化への誘惑がいかに根強いかを物語る具体例を紹介しよう。2023年10月11日、藤井聡太棋士が第71期王座戦五番勝負の第4局で勝利、史上初の8冠を達成する。『東京新聞』や『朝日新聞』、『毎日新聞』の看板の連載コラムがこの出来事を取り上げている。3紙はいずれもリベラル系と言われ、先に引用した奥泉のインタビュー記事を『朝日』が掲載しているように、「わかりやすい物語」に警鐘を鳴らしている。
2023年10月12日付『東京新聞』の連載コラム「筆先」は、藤井8冠の快挙をめぐり、彼を物語にすることが難しいと次のように述べている。
大リーグの大谷さんとこの若者について書くことは小欄、正直、気が重い。前人未到、歴史的快挙…。いかに賛辞を重ねようとその人や、成し遂げた偉業の大きさを十分に伝える自信がない。若者とは将棋の藤井聡太さん▼本日は書かねばなるまい。第71期王座戦を制し、「前人未到」の八冠を達成した。「快挙」である。笑われても不十分な賛辞しか浮かばない▼藤井さんの話をためらう理由はそれだけではない。強すぎるのである。無論、ご本人は人知れぬ努力と研究を重ねて、高き山を征服したのではあるが、傍目(はため)には、なにやら藤井さんがひょいひょいと頂点に駆け上がったように見えてしまうところもある▼強すぎてドラマがない、少なくとも見えない。人間ならスランプや将棋への迷いに苦しむ日があっても不思議ではないだろう。が、藤井さんには挫折はおろか、心の乱れさえ見えぬ。見えるのはただただ強いその人が脇目も振らず、栄光の道を静かに歩む姿のみである▼恋に将棋を忘れ、あるいは燃え尽き、そこから再びはい上がる青年のドラマは藤井さんには決して起きまい。落ち着いた棋風と勝利への強い意志がその道を迷わせぬ▼ドラマが起こるとすれば、新たな強力な好敵手の登場か。「八冠」はその人にとって偉業であってもライバルたちには屈辱だろう。打倒、藤井に奮起せよ。物語の新展開に期待する。
筆者は、藤井8冠に内面のドラマが見えないので、コラムに書きにくいと明かしている。「人間ならスランプや将棋への迷いに苦しむ日があっても不思議ではない」。このコラムニストは8冠を等身大の人間として扱い、内面に共感の入口を見出そうとしている。その上で、「恋に将棋を忘れ、あるいは燃え尽き、そこから再びはい上がる青年のドラマ」を期待する。これはまったく「陳腐な物語」でしかない。「見えるのはただただ強いその人が脇目も振らず、栄光の道を静かに歩む姿のみである」としたら、それを書くべきだろう。史上初のタイトルホルダーに既存の物語を当てはめること自体が矛盾している。結局、筆者はそうしたチャレンジをせず、凡庸な態度を最後まで崩さない。「『八冠』はその人にとって偉業であってもライバルたちには屈辱だろう」。8冠に内面のドラマが見えないとして、ライバルの方にそれを認める。筆者はどこまでも内面のドラマを見ようとする。
確かに、新聞記者は高踏的に当為を語るのではなく、取材や談話取りをして記事を書く。「1日だけのベストセラー」と呼ばれるように、読者層の幅は広く、そのため、わかりやすい文章を執筆することが必須である。しかし、それは前例泣き天才を扱う際に人間ドラマを正当化するものではない。
この筆者は大谷翔平にも触れている。実は、スポーツ報道に人間ドラマが氾濫するようになった発端はMLBの事情である。1950年代、大リーグはナイトゲーム中心のスケジュールに切り替え、テレビによる生中継も本格化する。従来はデーゲームがほとんどだったので、試合終了から翌日の朝刊の締め切りまで時間の余裕があり、記者たちは練りに練った記事を執筆している。ところが、ナイターではゲームセットが夜遅くなり、手早く記事を仕上げる必要がある。しかも、試合の様子はテレビが放映している。こうした事情により、記者たちはテレビが映さないロッカールームの選手の姿を伝えるようになる。それは1960年代に勃興するニュージャーナリズムの手法と親和性があり、スポーツ報道に人間ドラマが氾濫していく。
しかし、すでに述べた通り、心理描写は近代文学が等身大の人物を主人公とするために考案した方法である。英雄でもない平凡な人物が主人公たり得るのは、一見さもないように思えてもその内面にはドラマがあるからだ。これをよく示しているのがヘンリー・ジェイムズの作品である。彼の小説にはこれと言った出来事など起きない。けれども、登場人物の内面は激しいドラマに満ちている。
ただ、コラムニストの藤井8冠に求める心理描写はこれと異なっている。類稀な天才であっても、その内面には等身大の人々と同じであることを期待している。見たいのは自分と同じようなルサンチマンに悩まされる普通の人としての姿である。しかし、重要なのは藤井8冠が前人未到のことを達成したことであって、それについて考察すべきだ。。文にも書けない凄さは表現に値しない。
しかし、この人間ドラマ傾向は他の連載コラムでも認められる。達成の翌々日、『朝日新聞』の「天声人語」と『毎日新聞』の「余録」もこのニュースを扱い、しかも、いずれもAIに触れている。
『朝日新聞DIGITAL』2023年10月13日5時00分配信「棋士も人間だった」は8冠達成をめぐって次のように述べている。
「極端に言えば、将棋は『終盤で相手に一回間違えさせたら自分の勝ち』」。棋士の杉本昌隆さんが、自著『悔しがる力』で将棋の面白さをそう書いている。一昨日の王座戦第4局は、まさにそんな激戦だった。藤井聡太さんが永瀬拓矢さんに勝ち、八冠を達成した▼最終盤では双方が、一手60秒未満で指す「1分将棋」に突入した。どちらが完璧に読み切れるか。どちらかが間違えるのか。息詰まる緊張のなか、123手目を指した永瀬さんが突然、頭をかきむしった。ため息をつき、天を仰いだ▼明らかにミスをしたとわかるしぐさに、驚いた。血の気が引いたか、悔しさが出たのだろうか。藤井さんは表情を変えず、盤上を見つめたままだ。直前まで優勢でも一手で変わる。将棋の怖さを見た思いがした▼無表情で隠し通す人もいる。谷川浩司さんは40年前、初めて名人位を得た対局で「おやつとして出ていたイチゴにフォークを刺した瞬間」にミスをしたことに気づいたという。「何食わぬ顔でイチゴを口に入れたが、まったく味はしなかった」(『藤井聡太論』)▼今回の対局にこれほど引きつけられたのは、棋士の魅力によるところが大きい。どんなにAI技術が進歩しても、全力で対峙(たいじ)する人間のようには、見る者の心は打てない▼トップ棋士たちも間違い、落ち込むのだ。5連覇を目前にした永瀬さんの重圧はいかほどだったか。そして、あの指し手の応酬を乗り切った挑戦者の心技体の充実ぶり。恐るべき21歳である。
確かに、将棋をはじめボードゲームは対局者の技量が拮抗している場合、心理戦の要素を無視できない。居合わせるだけでも疲れてしまう緊張感の中で棋士が思わずミスをしてしまい、それが勝負を決定づけることも少なくない。そのため、しまったと思っても、それを悟られないようにやり過ごす態度も必要だ。なるほど、こうした心理戦もボードゲームの魅力の一つである。だが、すべてではない。「棋士も人間だった」のタイトルが示している通り、この筆者も、「筆先」同様、トップ棋士たちに等身大の姿を見ようとしている。そのため、藤井8冠の強さの秘訣は「心技体の充実ぶり」という「陳腐な物語」に堕してしまう。技量が拮抗した棋士の対局では「心技体の充実ぶり」が勝敗を決するのは後知恵でしかない。
また、2023年10月13日付『毎日新聞』の「88年前に始まった将棋の実力名人戦は…」は8冠快挙について次のように述べている。
88年前に始まった将棋の実力名人戦は江戸以来の終生名人制に終止符を打った初のタイトル戦である。「あゝその日は来た‼」。主催者の大阪毎日新聞記者が執筆したリーグ戦初戦の観戦記は近代将棋幕開けへの感動の言葉で始まった▲同じ表現を使いたくなった。藤井聡太(ふじい・そうた)名人の8冠制覇。初タイトルの棋聖獲得以来、いずれその日が来ると期待していた。だが、登場したタイトル戦を全て制し、ほぼ最短ルートで前人未到の高みに達したのは驚異だ▲史上最年少でプロ入りした天才棋士の実力を強く印象づけたのがデビュー以来の29連勝途上に行われた非公式戦「炎の七番勝負」。永世7冠の羽生善治(はぶ・よしはる)九段ら実力者を次々に撃破した。唯一、敗れたのが永瀬拓矢(ながせ・たくや)九段だ▲それ以来、研究会で切磋琢磨(せっさたくま)を続けてきた2人がぶつかった8冠目の王座戦。実力は拮抗(きっこう)していたのだろう。藤井名人は「非常に苦しい将棋で、逆のスコアでもおかしくなかった」と語った▲形勢判断が難しい終盤にも優劣を数字で示す人工知能(AI)判定は観戦の新たな魅力だ。王座戦でも一手で数値が大きく変わる局面が続いた。だが、失着を含め、天才たちが頭脳の限りを尽くすギリギリの攻防こそ人間ドラマではないか▲「伸び代というか、改善の余地は多い」。さらなる高みを目指す姿勢が「8冠」の真骨頂か。「誰にでも全盛期はある。問題はどれだけ長く続けられるかだ」。初の名人戦を勝ち抜き、戦後まで通算8期を獲得した木村義雄(きむら・よしお)十四世名人の言葉である。
戦前、坂口安吾が1949年5月29日付『毎日新聞 大阪版』に発表した「碁にも名人戦つくれ」によると、将棋より囲碁の方が人気は上回っている。「十何年前のことだが本因坊秀哉《しゅうさい》名人と呉清源(当時五段ぐらいだったと思う)が争碁を打ったころは碁の人気は頂点だった。当時の将棋は木村と金子が争っていたが、人気はなかった。近ごろの将棋名人戦のすごい人気に比べて碁の方は忘れ去られた淋しさである。将棋の人気はいうまでもなく実力第一人者を争う名人戦の人気である。昨日の名人もひとたび棋力衰えるや平八段となり時にBC級へ落ちることもなきにしもあらずである。実力だけで争う勝負というものは残酷きわまるものである。その激しさ、必死の力闘が人気を生むのである」。実際、石橋湛山は、『天分の認識』において、明治以来、政界では碁を打って親睦を深める習慣があったと証言している。
この筆者は、先の『筆洗』や『天声人語』と比べて、内面のドラマへの関心が抑制的である。けれども、「人間ドラマ」への期待は同様である。それは木村14世名人の引用から教養小説と理解できる。このジャンルは人間の心理的成長を描くもので、ヨハン・ヴォルフガング・フォン・ゲーテの『ヴィルヘルム・マイスターの修業時代』・『ヴィルヘルム・マイスターの遍歴時代』やゴットフリート・ケラーの『緑のハインリヒ』がその代表である。この成長過程を歴史の変動の中で描くジャンルを「大河小説」と言い、ロジェ・マルタン・デュ・ガールの『チボー家の人々』がよく知られている。教養小説の物語構造は成長過程にある若年層を主な読者とするマンガにおいて根強い人気がある。『あしたのジョー』を始めとする梶原一騎原作の劇画はこの代表である。ただ、それだけなじんでいるだけに、「陳腐な物語」でもある。
しかも、そのために、『天声人語』と同じく、AIを引き合いに出している。2022年11月30日にオープンAI社が公開したチャットGPTをきっかけに、爆発的にAIへの関心が一般の間でも高まり、多くの分野で利用が広がっている。反面、それに対する器具や反発も大きい。『天声人語』と『余禄』ののAIについての言及もそうした声の一つと理解できる。
ボードゲームは形式が明確であるため、歴史的に言って、AI開発の際に利用されている。基本的ルールが簡単で、過去から蓄積されてきた定石がゲームでは利活用される。データ学習のAIと相性がいい。今日、進歩したAIは対局したトップ棋士を破る能力を有している。より強くなるために、アマチュアのみならず、プロの棋士もAIを相手に訓練を積んでいる。
そういう状況だからこそ、人間同士の対局の魅力を強調しようとAIに触れるレトリックを筆者が用いていると理解できる。しかし、人間とAIの対局であっても、お互いに「頭脳の限りを尽くす」ことに違いはない。意地や自尊心といった我欲に囚われた人間同士がタイトルをかけて緊張感漂う真剣勝負に筆者が惹かれることは、コラムの前半からわかる。だが、勝負にかける執念のぶつかり合いの魅力を語る際に、AIに言及して「頭脳」を持ち出す必要などない。
将棋ではなく、囲碁であるが、AIとの興味深い対局に関する『朝日新聞』の記事がある。それは人間対AIの戦いが「頭脳の限りを尽くす」ことを明らかにしている。囲碁はAIの深化が最も遅いボードゲームの一つと言われてきたが、近年では人間を凌駕している。
2016年、韓国のイセドル九段がグーグル傘下のディープマインド社が開発した「アルファ碁」に1勝4敗と完敗する。3年後に引退した彼は「自分が1位になったとしても、勝てない存在がいる」と語っている。また、アルファ碁引退後の最強AIとされる中国テンセントの「絶芸」は、トッププロにも二子置かせて打つ。対局サイト「野狐」に「絶芸指導F」の名で常駐し、ハンディを対戦者に与えて99%近く勝っている。
ところが、2023年2月、『フィナンシャル・タイムズ』は、米国のアマチュア有段者が超人AIと15回対戦し、14勝したと報じる。当地の調査会社が徹底的に調べ上げたAIの弱点を突いたと言う。このニュースを受けて、日本の芝野龍之介二段は、2月21日、超人AIに対局を挑む。
大出公二記者は、『朝日新聞DIGITAL』2023年9月25日16時30分配信「超人囲碁AI、まさかの弱点 芝野龍之介二段、あえての悪手次々と ――気づいたときには死んでいた」において、その模様を次のように伝えている。
■「まじめに打て」騒ぐチャット欄
日本の芝野龍之介二段は、FT発のニュースを知った直後の2月21日、その手法を絶芸に試し、勝った。
芝野二段は二子置いたが、置き石のアドバンテージを最初から放棄している。人間相手なら絶対に打たない悪手のオンパレードなのだ。
まず黒2、4。自陣にわざわざ自石を埋め込むのは碁の法にない。黒18は不要の一手。打たずとも隅の黒の一団はすでに生きている。これらも対AIの作戦というが、極めつきは黒20だ。白21と換わって敵の弱点を消すお手伝いにすぎないではないか。チャット欄では「まじめに打て」と観戦者が騒ぎだした。だが芝野二段はまじめだった。黒20は、AI相手の本局では「自慢の一手」という。
囲碁は石と石のつながりが大事だ。切断されると一方あるいは両方の石が攻めの標的になりかねない。しかしあえてAIに石をつながらせるのが芝野二段の作戦だった。そして黒22と廃石に等しい黒20にヒモをつける。白23と左下に3連打した盤上は、白ばかりが好点を占めて手合違いの様相だ。だが、ここから黒の狙いが徐々に明らかになる。
廃石を担ぎだした黒の一団は二眼つくって最低限の生きを得たものの、ぐるりと囲んだ白の外壁は周囲を圧する。人間相手なら最悪の図を芝野二段は選んだ。ひとつながりになった石を、AIは完全無欠の生きと勘違いする欠陥があるらしいのだ。
白は左辺から延びる黒の一団を追いかけ回し、白63まで外回りに大勢力を築いた。圧勝の勢いだが、黒も66まで左上の白の一団を逆包囲した。芝野二段は、この大石の死命を制する一点狙いで打ち進めてきた。とはいえ、大石は懐が広く、とても死ぬ石ではない。しかし、このあと異変が起きる。黒が白の大石にいくら迫っても、AIはすでに生きていると判断しているのか、生きようとしないのだ。気づいたときには死んでいた。
■劣る部分も発見、人間にも可能性
この一局を最後に、絶芸はサイト上から1週間姿を消した。欠陥を修正するメンテナンスに励んでいたのだろう。3月1日に復帰したが翌日、芝野二段にまたも敗れ、今度は3カ月入院した。6月6日に復帰してからは、芝野二段の作戦にハマらなくなったという。
「基本的にAIの能力は人間より上。でも劣っている部分もあることを示せた。人間が露骨に弱点を狙えばぶっ壊せるという可能性は、今後もあり続けると思う」と芝野二段。今月6日には絶芸とは別の超人AI「KataGo」を互先で破った。
このように、人間とAIの対局もお互いに「頭脳の限りを尽くす」。AIに内面はない。しかし、プログラム設計上の弱点がある。定石に杓子定規に従うのなら、人間相手では使わないような「悪手」を打てばよい。開発者もそれに気がつき、対応策を考え、プログラムを修正する。AIにはなくとも、開発者には意地やプライドがある。棋士もそれに対抗して弱点を探し、対策を練る。双方共に「頭脳の限りを尽くす」戦いが続く。内面のないAIであっても、これだけ興味深い記事を書くことができる。
AIは文脈を理解できない。学習したデータに基づき、一般的に最適と推測できる手を打っているだけである。しかし、人間は石の意味をわかっているので、個別の対応が可能である。相手のクセに合わせて臨機応変できるから、あえて握手を選べる。
3人のコラムニストにかけているのは抽象化である。そのため、「陳腐な物語」に誘われてしまう。対象を抽象化してそれが関連する体系に位置づけて一般化し、その意味を論じる。藤井8冠の場合、着目するのは彼の行動であって、心理ではない。行動が歴史的快挙と評価されているのであって、内面ではないからだ。抽象化をしていないので、存在が具体性にとどまり、それを理解するために、藤井8冠を登場人物とする物語を探し求める。史上初の快挙であるにもかかわらず、ルサンチマンを晴らすための既存の「陳腐な物語」に依存することになる。
こうした物語の誘惑に抗うために、批評が必要である。その好例を紹介しよう。
1928年、囲碁の神童と呼ばれた14歳の中国人少年が母と兄と共に来日する。それが呉清源である。後に、彼は木谷實と並んで「新布石」を創始、その他にも数々の新手法を生み出している。十番碁における圧倒的な成績から「昭和の棋聖」と呼ばれる。
坂口安吾は、その天才ぶりに衝撃を受け、観戦記を含め呉清源に関するエッセイをいくつか書いている。安吾は、『呉清源』において、彼の強さについて次のように述べている。
呉清源は、勝負をすてるということがない。最後のトコトンまで、勝負に、くいついて、はなれない。この対局の第一日目、第二日目、いずれも先番の本因坊に有利というのが専門家の評で、第一局は本因坊の勝というのが、すでに絶対のように思われていた。三日目の午前中まで、まだ、そうだったが、呉氏はあくまで勝負をすてず、本因坊がジリジリと悪手をうって、最後の数時間のうちに、自滅してしまったのである。
もとより、勝負師は誰しも勝負に執着するのが当然だが、呉氏の場合は情緒的なものがないから、その執着には、いつも充足した逞しさがある。坂田七段は呉清源に気分的に敗北し、勝っている碁を、気分によって自滅している。呉清源には、気分や情緒の気おくれがない。自滅するということがない。
将棋の升田は勝負の鬼と云われても、やっぱり自滅する脆さがある。人間的であり、情緒的なものがある。大豪木村前名人ですら、屡々自滅するのである。木村の如き鬼ですら、気分的に自滅する脆さがあるのだ。
それらの日本的な勝負の鬼どもに比べて、なんとまア呉清源は、完全なる鬼であり、そして、完全に人間ではないことよ。それは、もう、勝負するための機械の如き冷たさが全てゞあり、機械の正確さと、又、無限軌道の無限に進むが如き執念の迫力が全てなのである。彼の勝負にこもる非人間性と、非人情の執念に、日本の鬼どもが、みんな自滅してしまうのである。
この対局のあと、酒にほろ酔いの本因坊が私に言った。
「呉さんの手は、当り前の手ばかりです。気分的な妙手らしい手や、シャレたような手は打ちません。たゞ、正確で、当り前なんです」
本因坊が、現に、日本の碁打ちとしては、最も地味な、当り前な、正確な手を打つ人なのであるが、呉清源に比べると、気分的、情緒的、浪漫的であり、結局、呉清源の勝負にこもる非人間性、非人情の正確さに、くいこまれてしまうらしい。
結局は、呉清源の勝負にこもる非人間性、これが克服すべき問題なのだ。坂田七段の場合にしても、本因坊の第一局にしても、勝っていた碁が、結局、呉清源の非人間性に対して、彼らの人間の甘さが、圧迫され、自滅せしめられているのである。
中国と日本の性格の相違であろうか。そうではなかろう。織田信長などは、呉清源的な非人間性によって大成した大将だった。結局、この非人間性が、勝負師の天分というのかも知れない。それだけに、彼らの魂は、勝負の鬼の魂であり、人間的な甘さの中で休養をとり、まぎらす余地がないのである。家庭的な甘い安住、女房、子供への人情などで、その魂をまぎらす余地がないのだ。
しかも、彼らほどの鬼の心、勝負にこもる非人間性をもってしても、自己の力の限界、自己の限界、このことに就てのみは、機械の如く、鬼の如く、非人間的に処理はできない。否、その自らの内奥に於て、最大の振幅に於て、苦闘、混乱せざるを得ないのである。むしろ彼らの魂が完全な鬼の魂であるために、内奥の苦闘は、たゞ、永遠の嵐自体に外ならない。
呉清源がジコーサマに入門せざるを得なかったのも、天才の悲劇的な宿命であったろうと私は思う。
これは新聞コラムではない。1948年に『文学界』に発表したエッセイである。しかし、先の3つのコラムと異なり、「陳腐な物語」に依存しない批評である。
安吾は、対局の観戦を含め取材や談話取りをしてこの作品を欠いている。新聞記者と同じ姿勢であるが、先のコラムニストたちと違い、人間ドラマを期待していない。呉清源の強さの理由を考察し、それを「勝負にこもる非人間性」に見出す。「勝負するための機械の如き冷たさが全てゞあり、機械の正確さと、又、無限軌道の無限に進むが如き執念の迫力が全てなのである」。ここまで彼ほどそれを徹底した棋士はいない。だから強い。先のコラムニストたちが藤井8冠の強さをめぐり人間ドラマを探しているのとは逆である。安吾はルサンチマンを晴らすための物語を欲しない。強者を強者として語る。
安吾とコラムニストたちとの違いは抽象化にある。安吾は呉清源を抽象化して棋士という勝負師の体系に位置付けてその強さを論じている。他方、コラムニストたちは藤井8冠を具体的な存在のままで捉えるので、既存の物語の登場人物として理解しようとする。適当な物語が見つからないと、執筆しにくいと音を上げてしまう。
このように物語は人間を誘惑する。それは具体的・個別的な出来事を抽象化・一般化しないまま理解を与える。しかし、そのドラマは特定の価値観を自明視させる。そこで示される登場人物の行動が倫理的であるとされ、それを実践することを求める。近代は個人に価値観の選択の自由を保障している。ところが、選んだはずの物語に依存してしまう。物語が人間にとって不可避であるとしても、それに依存するのは自由で平等、自立した個人であることを放棄するものだ。その物語に誘惑されている自分自身の暗黙の前提を明示化するために、批評を必要とする。
I like criticism. It makes you strong.
(LeBron James)
〈了〉
参照文献
石橋湛山、『石橋湛山著作集4』、東洋経済新報社、1995年
大治朋子、『人を動かすナラティブ なぜ、あの「語り」に惑わされるのか』、毎日新聞出版、2023年
小栗康平、『映画を見る眼』、日本放送協会出版、2005年
坂口安吾、『坂口安吾全集17』、ちくま文庫、1990年
寺山修司、『人生処方詩集』、立風書房、1993年
戸ヶ里泰典、『〔新訂〕健康と社会』、放送大学教育振興会、2023年
常盤新平編、『アメリカ情報コレクション』、講談社現代新書、1984年
ノースロップ フライ、『批評の解剖〈新装版〉』、海老根宏他訳、–法政大学出版局、 2013年
ジャン=フランソワ・リオタール、『ポスト・モダンの条件―知・社会・言語ゲーム』、小林 康夫訳、 水声社、1989年
大治朋子、「人を動かすナラティブ」、『毎日新聞』、2023年6月27日配信
https://mainichi.jp/articles/20230627/ddm/002/070/035000c
同、「集合的で支配的な物語」、『毎日新聞』、 2023年7月11日配信
https://mainichi.jp/articles/20230711/ddm/002/070/148000c
石川智也、「「新しい戦前」の今こそ、加害の歴史忘れず「経験化」を 奥泉光さん」、
『朝日新聞DIGITAL』、2023年8月15日 6時30分配信
https://www.asahi.com/articles/ASR854G4FR83UPQJ014.html
大出公二、「超人囲碁AI、まさかの弱点 芝野龍之介二段、あえての悪手次々と ――気づいたときには死んでいた」、『朝日新聞DIGITAL』、2023年9月25日 16時30分配信
https://www.asahi.com/articles/DA3S15751389.html
「大リーグの大谷さんとこの若者について書くことは小欄、正直、…」、『東京新聞』、2023年10月12日 06時39分配信
https://www.tokyo-np.co.jp/article/283140
「棋士も人間だった」、『朝日新聞DIGITAL』、2023年10月13日 5時00分配信
https://www.asahi.com/articles/DA3S15765416.html
「88年前に始まった将棋の実力名人戦は…」、『毎日新聞』、2023年10月13日配信
https://mainichi.jp/articles/20231013/ddm/001/070/092000
c
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
