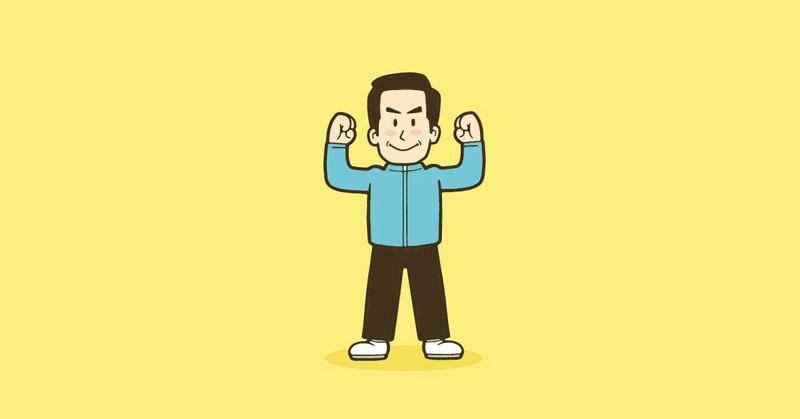
新年度。
ご無沙汰しております。
2月-3月は、そこそこ業務に勤しんでおりました。今週は久々に土日ともプライベートにあてて過ごせたように思います。
昨日から新年度が始まりましたね。新社会人の皆さま、明日に備えて今日は早めに寝ましょう。平日5勤は体力勝負です。
僕は2015年4月から新社会人になりましたので、今年で社会人9年目になるのかな。来年でようやく10年選手となるわけですね。あっという間に20代が過ぎていったなと、冒頭の文章を書いて感じました。
昨年に30歳を迎え、徐々に健康面への意識も気にしなければと考えているところです。今までなんとも無かった花粉の影響が、今年ついに開花してしまったみたいですし(鼻水出る、鼻が詰まる、目の内側に痒みを感じる)、脂っこいものなんて食べた日には、吐き気との闘いになることもあります。
人生100年時代とか言われている昨今にありながら、3分の1にも満たないところで胃もたれとか歯茎下がっていくとか、「ヒトの身体もう少し頑張ってくれよ」と突っ込みたいところ。今の技術では再生が難しいものに縋っていても時間は止まってくれないので、使える機能を駆使しして人生を謳歌するのみよ。と思うようにしています。
相変わらず積読はあるものの、普段の業務でタスクを捌くスピードが関係しているのか、読書スピードも上がったように思います。が、実際のところは「一言一句じっくり読み眺める」ことを止めて、「サッと目を通して淡々と情報を拾っていく」読み方になっていることが、主な変化かなと思っています。
身体という点で、最近読み終えた↓の本は読んでいて勉強になったと言いますか、ヒトが見ている世界には様々な解釈の仕方があるんだなと感じました。
大学時代に義足を使用している方々と一緒に、陸上競技の練習をしたことがあります。卒論のテーマを障害者スポーツとしていたので、実際の練習会に参加させていただいたり、インタビューをさせていただいたりしました。当時はまだ現役で陸上選手をしていた僕ですが、とても勉強になった一時だったと今でも記憶しています。
コンマ1秒でも速く走りたいと考える皆さんは熱心に「速く走るポイント」を尋ねてこられたのですが、僕は皆さんに「正確に走るポイント」を教えてもらいました。例えば、膝関節機能を持たない人は義足が膝の部分まで機能を担っているのですが、どの角度から接地してもしっかりと上半身を支えてくれるわけではなく、正しく地面に力を与えないと、膝折れという現象が起こるそうです(今の義足がどうなっているかは収集不足で分からずですが、当時伺った際は、膝にあたる部分のパーツは固定でも半固定でもありませんでした。固定していると、膝下の動きがぎこちなくなってしまうのだとか)。そうなると、走るどころか身体を支え切れずに転倒してしまうと。
なので、義足で走れている人はまず、地面への力の伝え方が上手いと捉えることができます。多少フォームが荒くても、筋力や関節機能でいわゆる「ゴリ押し」ができる自分とは違い、この点は当時すごくハッとさせられました。いかに効率よく正しく力を使うか。筋力だなんだの前に、まず基礎を学びなおすという体験をしたというのが、当時の感想でした。
障害者スポーツは、福祉の視点で健常者から指導を施すような矢印がパッと見の印象として感じる一面がありますが、実際は健常者が障害者から身体の扱い方を教わる方が、機会としてはとても有意義ではないかと、この本を読んで改めて思いました(本の内容は、視覚障害が主たるテーマです)。世間ではバブルちっくにメタバースへの投資に各社奮起していますが、デジタルとアナログが相互的にかかわり続けていくこれからの時代において、自分たちの身体が持つ可能性(進化を含めて)を追究することは、より一層大事なアクションになるのではと感じています。
健康第一を意識していく一方で、いずれ衰え上手く機能しなくなっていく箇所も出てくるであろう、自分の身体。今一度、「俺も老けたなあ・・・」としみじみ思わず、「今この身体で、どんなことが感じられるだろう」という前向きな変化思考を、楽しんでいくようにしたいなと思いました。
