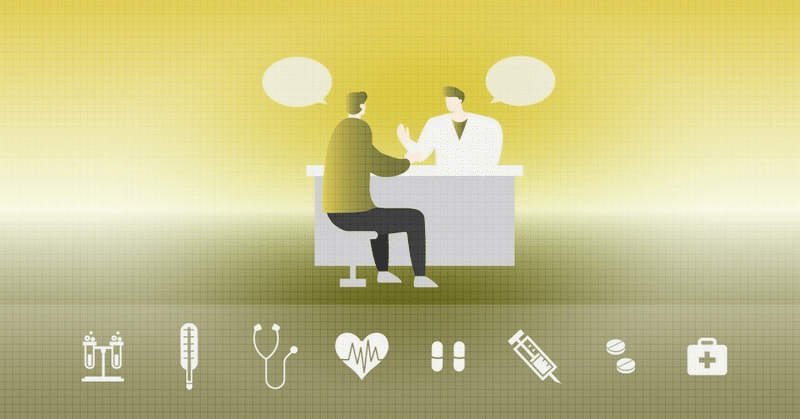
発達障害者の職業として医療系専門職が向いている理由
発達障害を持っている人は、一般的に社会に馴染むことが難しい。その理由の一つとしては発達障害者に向いている仕事がなかなかないということが挙げられる。しかし、私は発達障害者には医療系の専門職が向いているのではないかと思う。そこで今回の記事では発達障害者の仕事として医療系の専門職が向いている理由について書いていきたいと思う。
社会に出るまでの訓練プログラムがしっかりと用意されている
まず医療職と言ってもかなりいろいろな種類があるので、ここでは薬剤師を一つの例に挙げて書こうと思う。薬剤師は6年制の薬学部薬学科を出る必要がある。その6年制のプログラムの中で、社会に出てから活躍できる薬剤師になれるような様々な訓練プログラムが用意されている。
例えば5年次の薬学実習である。約5ヶ月間にわたって薬局と病院それぞれ2ヶ月半ずつ実習を受ける。薬剤師が働く場所としては薬局と病院が主に挙げられるので、それぞれで働く前に事前に実習するわけだ。一般に発達障害者は社会に出てから仕事に慣れるのが難しいとされている。仕事を覚えるのが遅かったり、ミスが多かったりするからだ。しかし、薬剤師の実習訓練のように、社会に出る前の訓練がしっかりとしていればいくら発達障害者でも社会に出てから仕事で行き詰まる可能性を低く抑えることができるだろう。
ではなぜ医療系の専門職は社会に出るまでの訓練が充実しているのか。それは、医療系は仕事でミスすると人の命に関わる可能性が高いからである。例えば薬剤師の仕事の場合、同じような名前の薬がたくさんあり、患者に間違った薬を渡してしまう可能性がある。それを防ぐために薬学実習を始めたとした様々な訓練プログラムが用意されているわけだ。また医者の場合も同じように医師免許取得後に初期研修期間が2年、後期研修期間が3年もある。それは医者は医療においてリーダー的な役割を果たし、医者のミスがそのまま患者の命に関わる可能性が高いからだ。そのミスを防ぐために訓練プログラムが長い期間にわたって用意されており、発達障害者でも社会に適応できるレベルまで引き上げてくれるだろう。実際、医者の発達障害を持っている率はかなり高いらしい。
働き方が自由である
発達障害者の職業として医療系専門職が向いていると思う理由の二つ目は、資格さえとってしまえば後の働き方が比較的自由である点だ。ここでも薬剤師を例に挙げて説明しようと思うが、薬剤師はパート、派遣、正社員と働く時間や労働形態に応じて様々な働き方がある。また、正社員として働く場合に様々な職場を選ぶことができる。主な職場として薬局やドラッグストア、病院の他に、物流倉庫や製薬会社などがある。つまり、自分の適性に応じて働く職場を自由に選ぶことができるのだ。
また、資格職ということで転職もしやすい。もし自分に合わない職場に就職してしまった場合も転職すれば自分に合った職場に巡り会える可能性が高いのだ。例えば、新卒で薬局に就職したけど、少人数の職場が自分に合わなかったとしよう。その場合は大人数が働いている病院などに転職すればよく、自分に合わない職場で無理して働く必要がないわけだ。
仕事内容が専門的でありジェネラリスト的な仕事を求められることが少ない
また、理由の3つ目としては、仕事内容が専門的であり決まりきった仕事さえすれば良いということが挙げられる。ここでも薬剤師の仕事を例に挙げると、薬剤師の主な仕事は調剤といって医者が出した処方箋に応じて薬を患者に渡すことである。他にも細かい仕事はあるかもしれないが、主な仕事は調剤であり、それ以外の仕事は覚える必要がない。
では逆に医療系の専門職以外の職を見てみよう。例えば事務職の公務員を考えてみると、定型的な仕事はほとんどなく、様々な仕事を任せられることになる。しかも2〜3年というスパンで部署異動があり、その度に新しい仕事を覚える必要がある。つまり、ジェネラリスト(悪く言えば便利屋)的な仕事を任せられることが多いのである。またこれは公務員の場合だけでなく、文系の総合職はほとんど同じであり、便利屋として本当に色々な仕事に器用に適応していかなければいけない。
発達障害者には不器用な人が多い。逆に言えば決まっている仕事を淡々と行うことであれば得意な人が多いということだ。これは発達障害の中でもASD的な特徴を持つ人に多いと思う。医療系の専門職はスペシャリストであり、決まりきった仕事を淡々と行う仕事が本当に多い。実際に、薬剤師、放射線技師、医者、理学療法士、作業療法士などは決まった業務を淡々とこなしていれば良い職業だ。例外として看護師はジェネラリスト的な役割が求められるので発達障害者には向いていないといえるが、ほとんどの医療系専門職は発達障害者に向いていると言えるだろう。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
