
2022.8.13 【全文無料(投げ銭記事)】神社でこんな間違いしていませんか?
お正月に神社に初詣に行く人も多いと思いますが、何をお祈りするでしょうか。
私は昔から神社で個人的なお願いをするのは、よくないのではないかと考えていました。
例えば、偶にしか会わない相手が、貴方に会うたびに、
「あれをしてください」
「これを頼みます」
と、お願いするばかりだったら、神様だって、
「いい加減にしてくれよ」
と、思うでしょう。
それよりは、会うたびに、
「お陰様で元気でやってます」
などと感謝されたら、
「これからも色々面倒をみてやろう」
と思うはずです。
だから、神社とは、お願いをする場所ではなくて、感謝をする場所ではないかと考えていました。
身体のどこかに多少の不調があっても、まずまず元気で毎日を過ごしていけること。
名声や富とは縁遠くとも、張り合いをもって日々の仕事や家事、育児に取り組める。
そうしたことを神様に感謝するのです。
しかし、最近読んだ本で、それも不十分だということを知りました。
「ありがとうございます」
と言うのも、自分に関することで感謝しているだけでは、まだまだ自分本位だとその本は言います。
白駒妃登美著の『幸せの神様に愛される生き方』です。
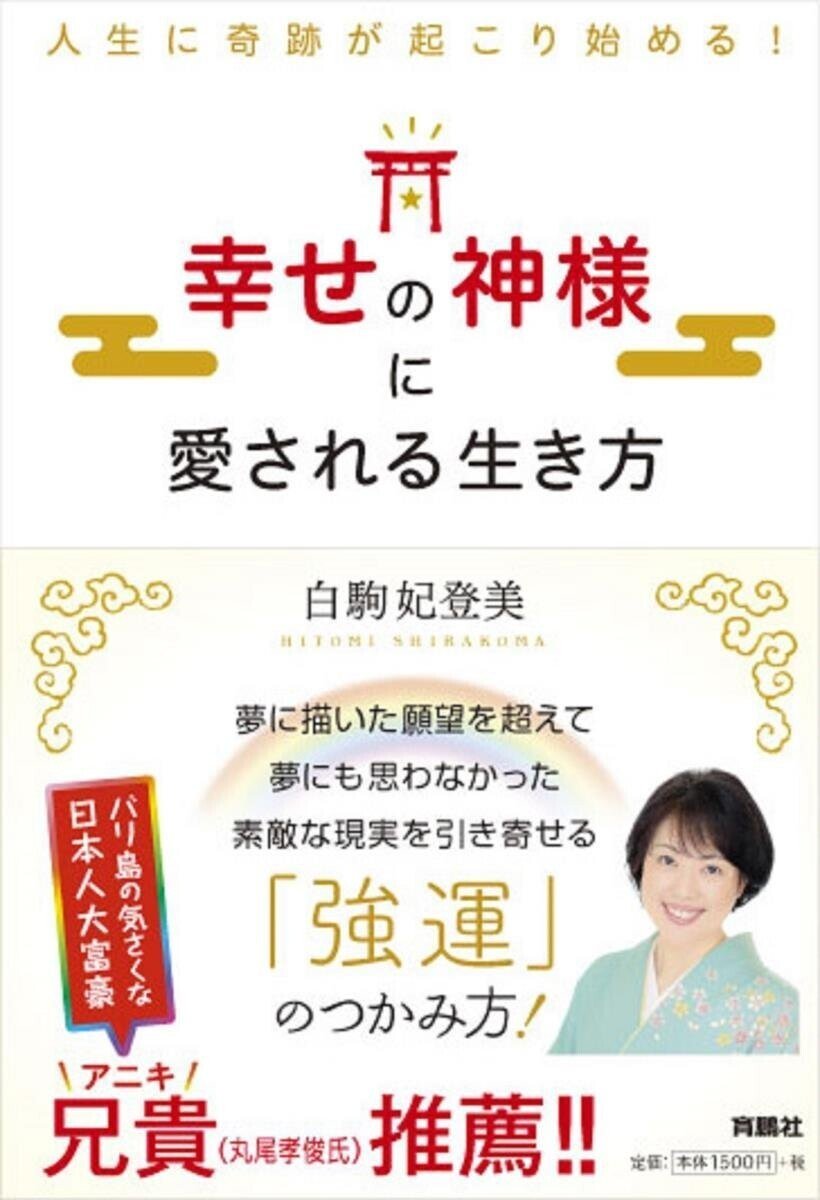
この書籍にはこう書かれています。
<「願い」というのは、自分のために叶えたいもの。
それに対し、世のため人のため、自分を超えた存在のために叶えたいものが
「祈り」なのだよと、ある方が教えてくださいました。
・・・
日本人の誇りを育むためにも、神社は、「願う」場所ではなく「祈る」場所でありたいなと思います。>
江戸時代の経営者は『商売繁盛』とは祈らなかった
商売人や経営者は、神社にお参りして『商売繁盛』を願う人が多いでしょう。
ところが、江戸時代の経営者は、『諸国客衆繁盛』を祈ったといわれています。
<「諸国」は「全国」、「衆」には「すべての」と言う意味があります。
自分の店に商品を買いに来てくれる人だけではなく、仕入先や取引先も含めて、広い意味で、「すべてのお客様」、それが「客衆」です。
「商売繁盛」は、「自分の商売がうまくいきますように」と言う願いです。
それに対して「諸国客衆繁盛」というのは、「自分につながるすべてのお客様の商売がうまくいきますように」と、すべてのお客様の繁栄を祈るものなのです。>

伊勢雅臣著の『世界が称賛する日本の経営』でも、“売り手良し、買い手良し、世間良し”の『三方良し』が伝統的な日本の経営の理想であることを述べていますが、この『諸国客衆繁盛』こそ、その『三方良し』への祈りだったのでしょう。
<「商売繁盛」は、自分が幸福であるために、自分で自分に鞭打って頑張る感覚です。
でも、「諸国客衆繁盛」の世界では、自分以外の全ての人が、自分を応援してくれる人なのです。
これならば、絶対商売がうまくいきますよね。>
地獄と極楽の違い
この道理を子供にも分かるように説いた譬え話があります。
<私は以前、子供向けに描かれた仏教の絵本を見て、驚いたことがあります。
その絵本によると、地獄も極楽も、人々を取り巻く環境は、なんと同じなのです。
どちらも、目の前に、素晴らしいご馳走が並んでいます。
そして地獄も極楽も、人々は三メートルぐらいある長い箸を使って、そのご馳走を食べなければいけません。
地獄はみな、その長い箸を使って自分で食べようとするので、うまく食べられません。
みな、カリカリ、イライラしているのが地獄です。>
しかし、極楽では同じ環境なのに、皆がとても上手に食べて、皆満ち足りていて、ニコニコとびっきりの笑顔で過ごしています。
白駒氏は、小学校入学前の息子さんに、
「どうやって上手に食べているのか」
を尋ねました。
「わかった、手で食べるんだ」
「箸がぐにゃと曲がるんだ」
と、最初は答えていましたが、
「違う」
と言われると、しばらく考えてから、突然、瞳がキラキラっと輝きました。
<「わかった!隣の人に「あーん」ってしてあげるんだよ。
そうしたら、その隣の人が次の隣の人に「あーん」ってしてあげて、また次の人が「あーん」。
最後は僕が誰かに「あーん」ってしてもらえるから、皆が食べられるんだね」
と言ったのです。>
皆が自分だけの事を願うよりも、皆が他者のために祈っている方が、遥かに社会全体が幸せになると言うごく簡単な原理を、この譬え話は説いています。
人間は本能的に、人のために生きることを喜びとする
白駒氏と息子さんの会話の部分で感銘深い一節があります。
<私は、そうやって人々と助け合う姿を思い浮かべた時の、息子の瞳の輝きが尋常ではなかったので、人間は本能的に、人のために生きることを喜びとするという一面を持っているのだなと、とても驚き、感銘を受けたことを覚えています。>

2018年の1月末に発行された、伊勢雅臣著の『日本人として知っておきたい皇室の祈り』のあとがきには、こう書かれています。
<利他心とは人間の本能に備わった特質なのではないか、と私は考えています。
・・・
人間が群れをなして暮らす動物であった以上、利他心はグループ全体の生存のために必要なことです。
それゆえに進化の過程で、利他心が人間の本能にビルトインされたと考えれば、極めて合理的な仮説のように思えます。
とすれば、利他心を発達させることは自己実現の一つのステップとして、幸福に至る道なのではないかと考えられます。>
息子さんの“瞳の輝き”は、『利他心は人間の本能の一部』という仮説のもう一つの例証でしょう。
『夢』と『志』の違い
冒頭で引用した『願い』と『祈り』の違いを説明したところでは省略しましたが、下のような一文が挟まれていました。
<「願い」と「祈り」の違いは、「夢」と「志」の違いと重なります。
夢以上に志を大切にしてきた日本人は、「祈り」の民族でもあるのですね。>
『夢』と『志』の違いを、白駒氏は以下のように説明しています。
<「夢」は、自分が叶えたいもの。
言ってみれば「for me」の思いが「夢」なのだと思います。
でも「志」は、自分が叶えなくても他の誰かが叶えてくれたらそれでいいと思えるような、我を超えた、我を手放した、もう一段高いレベルの思い、言ってみれば「for you」の思いが「志」なのではないかと思うのです。
そして私は、「志」を持った時に、私たち日本人のDNAがオンになるのではないかと感じています。>
アメリカ人の『目標達成型』、日本人の『天命追求型』
『夢』を実現する方法論として、アメリカ流の『成功哲学』があります。
白駒氏も、かつては成功哲学の信奉者だったといいます。
<私は、今でこそ日本が大好きで、その歴史や文化を語ることが何よりの喜びですが、実は若い頃は、日本が嫌いでした。
欧米に憧れていて、生き方でも、例えば『マーフィーの法則』やナポレオン・ヒル、カーネギーといった、アメリカ型の成功哲学にどっぷりつかっていて、常に目標を持ち、それを追いかけてきました。
アメリカ型の成功哲学は、まず夢を持つことから始まります。
その夢に期限をつけて目標とし、その目標を達成するために計画を作るのです。>
10年後の目標のために、5年後、3年後、1年後の目標を逆算し、そのために今月、今週、今日やるべき事を考えていく。
『今』は『未来』のための1ステップなのです。
しかし、白駒氏は日本の歴史、日本人の生き方を改めて振り返ったとき、アメリカ型の成功哲学を実践して幸せになった日本人はいないのではないか、と言うことに気がついたといいます。
そして“今、ここに”全力投球した時に道が開ける。
それを積み重ねる事で、天命によって運ばれていくというのが、日本人の生き方なのではないかと言います。
アメリカ型の成功哲学が『目標達成型』の生き方だとしたら、日本人が歴史に刻んできたのは、『天命追求型』の生き方と言えるのではないかと白駒氏は考えます。
ノーベル賞に至った志

伊勢雅臣著の『世界が称賛する国際派日本人』で、国際社会から称賛された日本人十数人を取り上げていますが、確かにこれらの人々全てが『天命追求型』の生き方をしていました。
例えば、ノーベル生理学・医学賞を受賞した北里大学の大村智特別栄誉教授。
大村教授の開発したメクチザンによって、WHO(世界保健機関)の発表では、西アフリカ諸国で約4000万人がオンコセルカ症の感染から逃れ、60万人が失明から救われました。
そのきっかけは、大村教授が夜間高校の先生をしていた時、昼間は油にまみれて働き、夜は学校で必死に勉強に取り組んでいる生徒たちの姿を見て、「自分も学び直そう」と思った事でした。
そこから猛勉強を始め、東京理科大学の大学院修士課程に入学すると、夜は高校の教師、週一日の高校の研究日を金曜日として、金土日の三日間は大学で実験に打ち込むという生活を送りました。
その姿に心打たれた大学の先生方、更にはアメリカの一流教授たちも大村教授を指導し、協力し、遂にはノーベル賞に受賞に至りました。
伊勢氏はこう結んでいます。
<大村の偉業は、多くの人々に導かれ、助けられ、支えられて、成し遂げられた。
まさに「一期一会」の精神で、多くの人々との出会いを大切にしてきたからだろうが、その姿勢も「自分はもっと何かをしなければ済まない」という初志に支えられていたのだろう。
そういう志を持っていればこそ「袖振り合う縁」を生かせる。
そして、そういう人には世間も助力を惜しまないし、天も必要な時に必要な人に出会わせてくれるのだろう。>
『夢』は自分の限界を作ってしまう
『夢』と『志』には、もう一つ大事な違いがあります。
<アメリカ型の成功哲学を追求し、強い心を持ってチャレンジしている間は、夢は叶いますが、逆に言えば、夢しかかなわないのです。
「夢が叶ばいいじゃないか」と多くの人はおっしゃるでしょう。
でも、自分が描いた夢が最高の人生であるということは、
・・・
自分の限界を自分で作っていることになるのではないでしょうか。
人間の可能性は、そんなもんじゃない、私たちが描く夢よりも、私たちの潜在能力は、可能性は、もっと大きいと思うのです。>
夜間高校の先生を出ている頃の大村教授は、大学院修士課程の入学を目指して、猛勉強していました。
その時に、アメリカ型の成功哲学によって目標を描いたとすれば、一流の研究者になるという程度の夢だったでしょう。
しかし、大村教授は、色々な人々とのご縁を得て、親切な助言や指導に一生懸命応え、そのご恩に報いようと努力する過程で、一段一段と活動の舞台が広がり、微生物の力を使って人類を救うという天命が少しずつ明らかになり、ついには4000万人もの人々を救うに至りました。
夜間高校の先生だった頃には、『夢』にも思わぬ偉業でした。
日本人の遺伝子
『目標達成型』の生き方は、自分のための『夢』を抱き、その『未来』のための準備として『今』を捉えます。
その生き方では、現在、偶々出会った人々とのご縁を大事にしようとか、頂いたご恩に報いようと言う心掛けとは、すぐには結びつきません。
一方、『天命追求型』の生き方では、今の一瞬一瞬を他者のために懸命に生きます。
偶々出会った人々とのご縁を大切にし、また頂いた恩になんとか報いようと更に努力します。
その結果、自分では思いもよらなかった偉大な功績に繋がる事があります。
これこそ、私たちのご先祖様が、『祈り』『志』『ご縁』『ご恩』『お陰様』『天命』などの言葉によって、子孫に伝えてきた日本人の生き方でしょう。
貴方が、これらの言葉を懐かしいと思えるなら、それは貴方自身の心に潜む日本人の遺伝子が反応しているのです。
白駒氏の言うように、私たち日本人は『祈りの民族』です。
『天命追求型』の生き方を大切にしてきました。
だからこそ、神社では、他者のための『祈り』を捧げるのが良いのです。
その『祈り』によって、貴方の心の中にある日本人の遺伝子が目覚めていきます。
そのような人にこそ、神様も3mの長い箸で、
「あーん」
っと、幸せを運んでくれるのではないでしょうか。
記事が良かったと納得して頂いた上で、投げ銭して頂けると大変嬉しいです。
今回も最後までお読み頂きまして有り難うございました。
ここから先は
¥ 149
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
