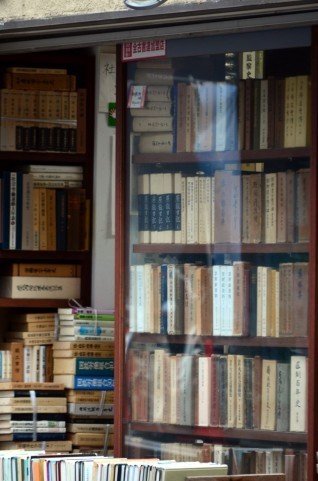
聖書や日本書紀、平家物語などを読みながら、「日本」について外国人に説明するにはどうしたらいいかとか、農村部の論理と都会人の論理がどう違うかと言ったことについてのヒントを考えていま…
- 運営しているクリエイター
2023年4月の記事一覧
「周の禾」は「稲」なのか?他
史記の鄭世家に鄭が「周の禾を取る」と言う表現が出てきます。
この「禾」について、現代語訳は「稲」としています。注釈には、左伝に秋に周の禾を取ったと言う記載があると書かれています。どうやら、左伝のこの記載を元に史記が書かれ、秋に取ったものだから「稲」と訳した模様です。
「禾」は例えば「秋」や「種」などに使われている「ノギヘン」、それ自体だけの漢字です。漢字としては穀物の総称で必ずしも「稲」を意味
「なぜ勉強をしなければならないか」への答えは「人間らしく生きるため」他
子どもの頃、よく、「ひょっこりひょうたん島」を見ていました。
あの中に「勉強なさい」と言う歌が出てきました。
子どもたちが勉強なんかしなくたっていいじゃないかと言うと、お返事が人間らしくなるためだと言うやり取りが、子ども心に印象に残った記憶があります。
今聞いてみると、ちょっとズレてるかなぁと感じる点はあるのですが、ただ、勉強する根拠=人間らしくなると言うのは、この歌の論旨とは別に「あってい
毛皮が「商品」になった事と日本の開国の関係など
アダム・スミスの国富論にこんな一節があります。
「人間が最初に衣服の材料として用いたのは、比較的大きい動物の皮であった。それゆえ、この動物の肉を主食としている狩猟民族や牧畜民族の間では、食料を自給することによって、各人の必要以上の衣料の材料を自給する事が出来る。
外国との貿易が全然なかったなら、この材料の多くは無価値なものとして捨てられたことであろう。
北アメリカの狩猟民族の間では、かれらが







