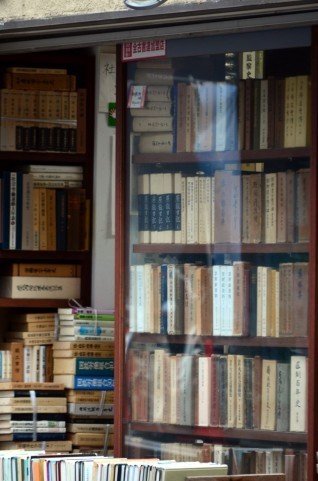
聖書や日本書紀、平家物語などを読みながら、「日本」について外国人に説明するにはどうしたらいいかとか、農村部の論理と都会人の論理がどう違うかと言ったことについてのヒントを考えていま…
- 運営しているクリエイター
2018年11月の記事一覧
「往来」が途絶えた先にあるもの
食物、女性、子供、財産、護符、土地、労働、奉仕、宗教的役割、位階など全てのものは譲渡され、返還される物体であると言うことである。
人と物を含む霊的な物体の永続的交換が位階、性、世帯に分かれたいくつものクランや個々人の間にあるかのように、あらゆるものが往来するのである。(マルセル・モース 贈与論 ちくま学芸文庫)
ポリネシアなどで「ポトラッチ」と呼ばれる全体的給付制度について、モースはこう述べてい
「贈与」経済の限界・・・文明化
「ダヤク族(ボルネオ)は、よそで食事に居合わせたり、食事の準備をしているところを見たりした時は、必ずその食事に加わらなければならないと言う義務に基づいた法と道徳の全体系を発展させさえした」
(マルセル・モース「贈与論」ちくま学芸文庫)
この件については、同書の注釈の中で、制度の比較研究のために「正しく確認すること」が難しいとしています。
例えば、「ボルネオのブルネイ国における強制的取引と言う
モノがやり取りされる時、モノの「霊」もやり取りされていると言う思想は現代社会でも生きている
「ハウは生まれたところ、森やクランの聖地、あるいはその所有者のところに帰りたがるのである。タオンガないしハウはそれ自体一種の個体であり、一連の保有者が祝宴、祝祭、贈与によって、同等あるいはそれ以上の価値の財産、タオンガ、所有物、労働、交易をお返ししない限り、彼らにつきまとう。
そうしたお返しによって、その贈与者は、最後の受贈者になる最初の贈与者に対して権威と力を持つようになる」
(マルセル・モ

