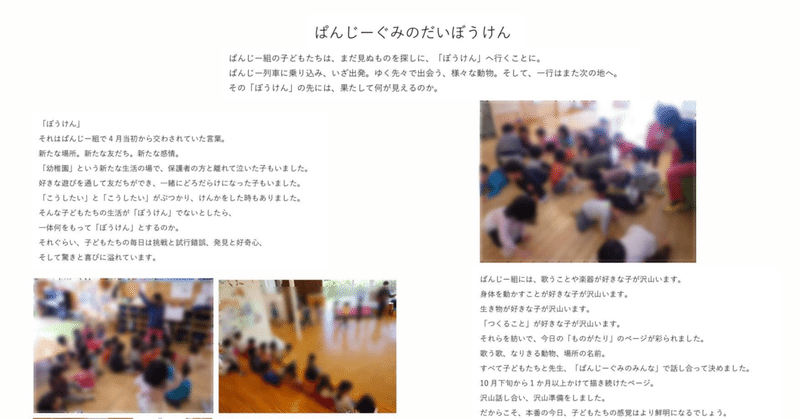
【幼児教育】いろんな楽しさ、大きな楽しさ
今日は幼稚園の行事「しぜんものがたり」でした。
最高に楽しかった。
子どもたちも今日が一番楽しそうだった。動物になりきっていない子も、友だちの様子を見たり、笑顔を見せていた。これまで床にびろーんとなっていた子が列車の先頭に立ち、大きな声で歌っていた。
行事のコンセプトは、普段子どもたちがしていることや好きなことを紡いで「ものがたり」とし、保護者の方々に見てもらったり一緒に楽しむこと。
振付などが決まっているお遊戯会ではなありません。何をするか、何の動物になるか、何を歌うか、などなど、全て子どもたちと話し合って決めました。タイトルは「ぱんじーのだいぼうけん」か「ぱんじーぐみのだいぼうけん」かというところまで決めました。
地図も自分たちで作りました。地図の場所の名前を決める話し合いでは「いるかのうみ」(そこでなりきる動物はイルカではなくワニ(笑))「がちゃがちゃこんこん」など僕にはとても思いつかないアイデアも飛び出しました。
昨晩、僕はそわそわしていました。
緊張と言うよりも「そわそわ」。
どうしてかと考え、たどり着いた結論は、
「自分ではどうにもできない」
から。
でもそれは、子どもたちに自分の理想を押し付けようとしている心の現れ。
身体を動かしてほしい。大きな声で歌ってほしい。ぐちゃぐちゃにならないでほしい。
これまで子どもたちと一緒に話し合うこと、作り上げることを徹底してきました。子どもたちにとって大切な経験を常に重視してきました。緊張して固まってしまうのもいい、走り回りたくなってしまうのも気持ち。それが子どもたちの正直な姿。
そう考えるのと同時に、心のどこかで、「保護者の方にまとまりのないクラスだと思われたら嫌だな」と、そんな思いがありました。
その相対する気持ち。しかし子どもたちがどう動き、感じるかは自分ではどうにもできない。こうして昨晩の「そわそわ」につながっていたのだと思います。
今日、そんな「そわそわ」は子どもたちが吹き飛ばしてくれました。
笑顔、不安、恥ずかしさ。
これまで自分たちで決めてきたからこそ鮮明に映る、偽りのない表情。
いろいろな気持ちが混ざってできる「楽しさ」。
子ども26人それぞれの楽しみ方。
ワニになって床をはう楽しさ。そんな友だちを見つめる楽しさ。初めて感じるどきどきに耳を傾ける楽しさ。
そしてそれらが重なって、みんなと一緒にいることでの大きな楽しさも生まれていた気がします。楽しさが重なり合って、新たな楽しさへ。
僕もカホンを置き、動物に変身しました。楽しかった。
「子どもたちと」をやり続けていてよかった。
夕方のお迎え時、お母さんがお子さんに「お家でもものがたりやってね」と。
するとその子が「いやだ!」
「だってぱんじーのおともだちがいないといやだから」。
よかったよ、本当に。


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
